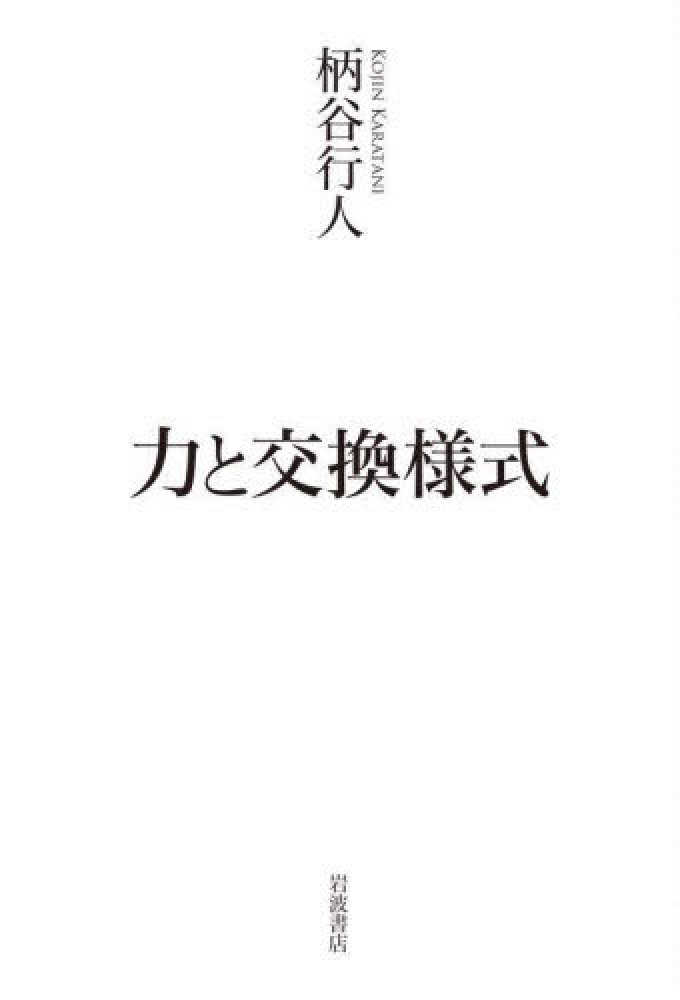グイド・レーニ『キリストの洗礼』1622年。美術史美術館、ウィーン。
【73】 「交換様式D」の先駆者たち――時系列
さて、柄谷氏が「D」の現出として述べていることがらを時系列に振ってみると、次のようになります:
- c.875-c.850 BC エリヤ
- 750?-721? BC ホセア
- c.787-c.687 BC イザヤ
- c.630~? BC ゾロアスター〔ザラスシュトラ〕
- 前7C末~前6C前半 エレミヤ,エゼキエル
- 〔c.530 BC ユダヤ人、「バビロン捕囚」から帰還〕
- c.470-399 BC ソクラテス
- c.470-c.390 BC 墨子〔墨翟〕
- 460s?-380s? BC ブッダ
- c.6 BC-30 AD イエス
- 後1C後半 パトモスのヨハネ
紫字は『旧約聖書』の預言者。主な人物を表示しています。彼らも、「D」現出のほかの体現者も、年代の決定は難しいのですが、柄谷氏の引用文献と Wiki を見て、できるだけ最新の有力説に揃えました。
これを見ると、『旧約』の預言者は、ゾロアスターの前後にわたっています。イスラエル国家建設期のエリヤなどは、明らかにゾロアスターより前です。もっとも、『旧約』の諸書が最終的に文書化されたのは、ユダヤ教の司祭たちが「バビロン捕囚」から解放されてパレスティナに帰還した前6世紀以後です。そこで、柄谷氏は、『旧約』預言者における「D」現出の時期を、ゾロアスターより後に置いているようです。つまり、世界最初の「D」の出現を「ゾロアスター教」に置き、ユダヤ人は、「捕囚」からの帰還後に、ペルシャ帝国を通じて「ゾロアスター教」の影響を全面的に受けることによって「D」を引き継いだ、と考えることになります。
しかし、歴史的な「D」現出の時期は、それが文書化された時点よりも、じっさいにその体現者たちが生きた時代に置いたほうがよいと思われます。そこで、モーセのように実在したかどうかはっきりしない人物は別として、エリヤ以下の預言者は、各生存年代を基準にしてみます。
そうすると、「D」が最初に出現したのは、カナン(パレスティナ)に定住したイスラエル人の間においてだった。それが、前9~8世紀。そのあと、それとは独立に、前7世紀の東イランでゾロアスターに「D」が現出したことになります。そして、前6世紀後半に至って、ペルシャ帝国の仲立ちで両「D」が出会い、パレスティナにおいて『旧約聖書』という形で、かなり高度な「D」文献を成立させた。それが、のちの紀元1世紀に現れるイエス教団の下地となります。
もちろん、「帝国」時代のゾロアスター教にしろ、イスラエル古代の慣習法や族長・王の事績と混じって伝えられてきた旧約預言者にしろ、雑多なA,Bの要素を含んでいましたから、それらから、祭司の手によってまとめられた『旧約聖書』も、純粋な「D」ではありえませんでした。後のイエス教団による「D」の再登場が、過激な暴挙として大衆の非難を浴びることとなった理由が、そこにあるのです。
アンリ・レーマン「若者に預言を書き取らせるエレミヤ」1842年。
ゾロアスターとイスラエル預言者群という・この2つの出現は独立に起きていますが、関連がないわけではありません。交換様式Aの優位が崩れて、B,Cにドミナントの座を明け渡しつつある社会、という歴史的段階の共通性があるからです。
しかし、これを地理的に見ると、共通点はさらにはっきりします。どちらも、メソポタミアを “中心部” とするオリエント「帝国」文明の “周辺部” に位置しています。「帝国」の「世界宗教」に対抗する「普遍宗教」すなわち「D」は、「帝国」の影響力が圧倒的な “中心部” ではなく、“周辺部” に興るのです。
つぎに、ソクラテス、墨子、ブッダの3人は、生存年代が驚くほど一致しています。何か理由があるのでしょうか?‥のちほど考えてみたいと思います。
ソクラテスとブッダは、「帝国」のさらに外延、つまり「亜周辺」に出現しています〔「亜周辺」というウィットフォーゲルの用語は解りにくいですが、「周辺」のさらに外側という意味です〕。墨子は、かなり離れていますが、中国でも「帝国」が形成されつつありました。墨子がいたのは山東省(一説には湖南省)ですから、中国「帝国」域の「周辺」と言えるかもしれません。
紀元後1世紀にも、イエスという大きな「D」の出現があります。ほぼ同時の「パトモスのヨハネ」は、『新約』に収録された「ヨハネの黙示録」の著者です。イエスは、福音書を見るかぎり《終末論》についてはほとんど語っていません〔例外:マタイ 24:29-44 等〕。が、《終末論》は「D」の重要な要素ですから、ヨハネについても、そこで見ておきたいと思います。
このイエスの同時代に、東のほうでは何も起きなかったのでしょうか? ひとつ考えられるのは、インドで『法華経』が成立していることです〔紀元1世紀以降か〕。『法華経』は、「国家」のもとで祭司化した仏教僧侶団・に対抗する在家信徒教団の経典で、その中には、‥信仰者は、王臣王子と交わってはならない、山林に隠棲する修業僧団とも一線を画せ、等々述べたクダリがあります。中国については、「国家」内部で批判精神を保持することに努めた史官・司馬遷〔前145?-前86?〕が注目されます。しかし、これらについては、柄谷氏は触れていませんしレヴューの範囲を越えてしまいますので、これ以上は述べません。
【74】 「交換様式D」の先駆者たち
――預言者イエス:「D」の本質内容の開示
イエスとソクラテスほか2名は、ソクラテスらのほうが時系列では先なのですが、『旧約』預言者との関連があるので、柄谷氏の叙述はイエスが先になります。
ジョン・エヴァレット・ミレー『両親の家のキリスト』1849-1850.
大工であった父ヨハネの仕事場での情景。少年イエスが、
“神の子” ではない生身の人間として描かれている。©Wikimedia.
『新約聖書』収録の4つの福音書のなかで最初に書かれたのは「マルコによる福音書」です。それは紀元後 70年ころ、つまりイエスのタヒから 40年ほどたったころと推定されています。
『今日主流の説では、「マルコによる福音書」と共通資料(Q資料)をもとにして、「マタイによる福音書」、さらに「ルカによる福音書」が書かれた。〔…〕しかし、「マルコによる福音書」はその後のものとは異質である。一言でいえば、その他の福音書ではイエスが神格化されているのに対して、そこでは、預言者としてのイエスの言動が浮き彫りにされている。
「マルコによる福音書」によれば、イエスを信じ、その奇跡にすがった群衆たちは、最後には「十字架につけろ」と罵声を浴びせた。また弟子たちが、イエスを誤解し裏切る姿は、ここに最も生々しく描き出されている。したがって、預言者としてのイエスを考えるのに、「マルコによる福音書」が最もふさわしい、〔…〕「マルコ」の場合、イエスはみじめな生身の人間として描かれ、』『旧約』の預言を成就するメシア、といった『意味づけをほとんど与えられていない。そして、ここにこそ、普遍宗教をもたらすにふさわしい預言者の姿が描かれていると言える。』
柄谷行人『力と交換様式』,2022,岩波書店,p.175.
じつは、この節で初めて、柄谷氏は「D」の具体的内容を叙述しています。それは、氏が勿体ぶって内容の説明を先延ばしにしていたわけではなく、「福音書」就中 なかんづ く「マルコ福音書」で初めて「D」の具体的内容が記録されるからなのです。
おそらく、『旧約』の預言者たちも、ゾロアスターも、彼ら自身はイエスと同様に、「D」を具体的に語っていたはずです。しかし彼ら自身は文字を知らなかったし、文字能力のある者も文書を残しませんでした。信徒や代筆者によって伝えられた言行録や伝承は、彼らの「D」の語りを十分に伝えてはいないのです。なぜなら、「D」の語りは、伝統的な「A」の宗教とは異なって、一般人には理解しがたい異常なものであったからです。福音記者(おそらくイエス生前の弟子のひとり)マルコによって、それは初めて記録された。というのは、その紀元後 70年ころにローマに対するユダヤ民族の反抗が最終的に撃滅され(ユダヤ戦争)、「D」の理解と継承を邪魔していた伝統的宗教の抑圧から、原始キリスト教団は一時的に解放されたからです。
もっとも、まもなく原始キリスト教団は、教団としての体制と教義を整えてゆくにつれ、伝統的な『旧約』の思想で理論装備を固めるようになり、イエスの「D」は薄められてゆくことになります。それが、「マタイ/ルカ福音書」の成立です。
原始キリスト教は、もともと「ユダヤ教の〔ギトン註――革新〕運動の一派であった。」それは先ず、都市下層に流れこんだ人びとの「遊動的な共同体として広がった。それは当初、都市の周縁部で下層階級の人々の間にあった」。「それをキリスト教という宗教に仕立て上げたのは」オリエント世界の中心からは外れた「亜周辺のローマ的な世界である。」「そして、幾度も弾圧されながら、4世紀にはローマ帝国の国教となった〔…〕その時キリスト教は “世界宗教” となったが、同時にそれによって、普遍宗教的な部分、すなわち交換様式〔…〕Dを無くしてしまった。
普遍宗教は本来国家を否定するものであり、だからこそ弾圧されたのだが、それが国教となると、国家を支えるBを肯定することになる。これは、ゾロアスター教や仏教がたどったのと同じ道である。」(柄谷,p.203.)
ともかく、本節は、柄谷氏が「D」について具体的に語っている稀有な箇所であり、本書の “隠れたマスター・キー” と言ってよい枢要部分です。
ムンカーチ・ミハーイ『この人を見よ』1896年。ユダヤの議会と民衆はイエスの
処刑を強硬に主張したので、ローマ総督ピラトはイエスを逮捕して鞭打たせた上
傷だらけのイエスを人びとに示して納得させ、無罪放免しようとした。ところが
民衆は、「十字架につけろ!十字架につけろ!」と叫んだ〔ヨハネ 19:1-6〕
『イエスは人々に食べ物を与え、病を癒やした。これは人並み外れた力を示すことである。しかし、それはむしろ王の仕事であり、人々は、そのようなことができる王が到来し、ローマの支配から解放してくれることを期待していた。したがって、イエスも「王」として期待されたのだが、彼は一貫してそれを拒絶した。〔…〕
異邦人の間では、支配者と見なされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力をふるっている。しかし、あなたがたの間ではそうではない。あなたがたのなかで偉くなりたい者は、皆に仕える者になり、いちばん上になりたい者は、すべての人の僕 しもべ になりなさい。人の子〔ギトン註――わたし〕は仕えられるためでなく仕えるために、また、多くの人の身代金として自分の命を献げるために来たのである。〔マルコ 10:42-45〕
イエスは、このような「王」を斥けた。というより、「国家」を斥けた。交換様式で言えば、それはBを斥けることである。たとえば、彼がいたころ、イスラエルではローマからの独立をはかる熱心党(zealot)が強かった。が、イエスは彼らに同調しなかった。ローマによる支配を支持したからではない。同一民族が支配者になろうと、国家は国家だ、と考えていたからだ。〔…〕
ホッブズ』によれば、『イエスは、〔…〕いかなる強制とも支配とも無縁であり、それらを意図的に退けた。』
柄谷行人『力と交換様式』,pp.175-176,404(6).
「マルコ福音書」によって柄谷氏が明らかにする「D」の主要点は:①王と国家を斥ける、②家族と共同体を斥ける、③商業と致富を斥ける、④「隣人愛」と「神の国の到来」を説く、の諸点に要約されます。①②③は、いわばネガティヴな規定であり、④はポジティヴな言説による規定です。↑上で引用したのは①の部分で、次↓は、②です。
『さらに、イエスは家族・共同体を斥けた。それはAを斥けることである。《21 身内の人たちはイエスのことを聞いて取り押さえに来た。「あの男は気が変になっている」と言われていたからである。〔…〕31 イエスの母と兄弟たちが来て外に立ち、人をやってイエスを呼ばせた。32 大勢の人が、イエスの周りに座っていた。「御覧なさい。母上と兄弟姉妹がたが外であなたを捜しておられます」と知らされると、33 イエスは、「わたしの母、わたしの兄弟とはだれか」と答え、34 周りに座っている人々を見回して言われた。「見なさい。ここにわたしの母、わたしの兄弟がいる。35 神の御心を行う人こそ、わたしの兄弟、姉妹、また母なのだ。」》※〔マルコ 10:31-35〕』
柄谷行人『力と交換様式』,pp.176-177.
註※ 引用は前後を補充し、また「新共同訳」に替えた。
カラヴァッジョ『この人を見よ』1605年 .
この箇所は、「マタイ伝」では、《わたしは…人をその父に、娘を母に、嫁を姑に…争わせるために来た》というイエスの有名な発言に変っています。しかし、これは「十二使徒」を送り出す場面での訓示の一部です。イエスは、あなたがたは迫害を受けるだろう、と予告したうえ、また布教によって信者の家族を分裂させることになろう。しかし、それを恐れてはならない、と言っているのです:
『1 イエスは十二人の弟子を呼び寄せ、〔…〕5 イエスはこの十二人を派遣するにあたり、次のように命じられた。
「〔…〕21 兄弟は兄弟を、父は子をタヒに追いやり、子は親に反抗して刹すだろう。 22 また、わたしの名のために、あなたがたはすべての人に憎まれる。しかし、最後まで耐え忍ぶ者は救われる。〔…〕
34 わたしが来たのは地上に平和をもたらすためだ、と思ってはならない。平和ではなく、剣をもたらすために来たのだ。 35 わたしは敵対させるために来たからである。
人をその父に、
娘を母に、
嫁をしゅうとめに。
36 こうして、自分の家族の者が敵となる。 37 わたしよりも父や母を愛する者は、わたしにふさわしくない。わたしよりも息子や娘を愛する者も、わたしにふさわしくない。」』〔マタイ 10:1-37〕
マルコ,マタイともに、特別な事情のなかでの発言として伝えています。とくにマタイのほうは、教団の宗教闘争の一環として解釈できるように、「十二使徒」への訓示に組み込んでしまっています。おそらくは、自分の家族をも冷たくあしらうようなイエスの言動は、どの福音記者にもショッキングだったのでしょう。
しかし、のちに引用する④↓との関係で見ると、イエスの言動は単なる状況発言ではなく、「家族・共同体の無化」という彼の根本思想にもとづくものであったことが理解できます。
↓つぎは、③。
『さらにまた、イエスはCを斥けたといってよい。たとえば彼は、「祈りの家を強盗の巣にしてしまった」と言って、神殿から商人を追い出した。また彼は、「皇帝に税金を払うことは律法にかなうか」という問いに対して、「皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい」と言った〔マルコ 12:13-17〕。これは王の権威を認めることではなく、むしろ貨幣の権威を認めないことである。イエスは弟子たちにこう言った。「財産のある者が神の国に入るのは、なんと難しいことか」。彼は金持ちの男に次のように言った。《「あなたに欠けるものが一つある。行って、持っている物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。〔…〕それから、私に従いなさい」。その人はこの言葉に気を落とし、悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。》〔マルコ 10:21-23〕』
柄谷行人『力と交換様式』,2022,岩波書店,p.177.
「皇帝〔ローマ皇帝〕のものは皇帝に」のクダリは、ちょっと注釈が必要でしょう。マルコ伝12章を見ると、この時、パリサイ派・ヘロデ派の人びとは、イエスを引っかけようとしてこの質問をした。「皇帝(ローマの総督府)に税金を払うべきでない」とイエスに言わせて、彼を当局に告発しようとしたが、イエスはこの策略を上手にかわした、というわけです。あるいは逆に、ローマの植民地支配に抵抗する勢力から同じ質問をされたとしても、イエスは同じように答えたでしょう。その理由は↑①で述べました。
ですから、この「皇帝のものは皇帝に」のエピソードは、「C」よりも「B」に関わると言ったほうがいいかもしれません。
アブラハム・ヤンセンス〔1567-1632〕『この人を見よ』。
「C」に関して柄谷氏の指摘に付け加えるとしたら、「マタイ伝」の有名な「タラントン」の喩え話〔マタイ 25:14-30〕が、「マルコ伝」には無いことが挙げられます。主人から預かった貨幣を、商売で殖やした僕 しもべ は褒められ、穴に埋めておいてそのまま返した僕は叱られた、というクダリです。このような利殖の思想――のちに「プロテスタンティズムの倫理」として近代資本主義の精神を形づくったとされる――は、イエスの本来の教えには無かったわけです。
ともかく、「C」との関わりについては難しい問題があります。古代の経済現象と経済思想の理解が関わってくるからです。ここではあまり深入りしないでおきたいと思います。
④に移ります。これまで↑は、~を斥ける、という消極的なかたちで「D」の諸点が述べられていました。それらをまとめて言えば、「交換様式A,B,C」を斥ける、ということになります。柄谷氏の言う「DはA,B,Cを無化する」とは、こういうことなのでしょう。
「無化」したうえで、どんな社会を建設するのか?……それを④で見てみましょう:
『イエスが唱えた「最も重要な掟」は、次の言葉に要約される:《隣人を自分のように愛しなさい》〔マルコ 12:31〕。隣人とは仲間のことではない。たとえば、イエスはすすんで徴税人や罪人と食事をした。《医者を必要とするのは、丈夫な人ではなく病人である。わたしが来たのは、正しい人を招くためではなく、罪人を招くためである》〔マルコ 2:17〕。つまり、彼にとって隣人とは、社会的諸関係を超えて見いだされるような他者のことである。いいかえれば、彼が示唆するのは交換様式A・B・Cを超えて人と交わることだ。
それがDの到来であり、「神の国」の到来である。それは、天国や極楽のような、この世界の外、彼岸に想定されるようなものではない。イエスの語る「終末」は、この世界の問題でもある。〔ギトン註――「終末」ののちも〕この世界はそのままにとどまる。ただ、何かが変わるのだ。そのとき交換様式が変わる、といってよい。《ファリサイ派の人々が、神の国はいつ来るのかと尋ねたので、イエスは答えて言われた。「神の国は、見える形では来ない。[ここにある][あそこにある]と言えるものでもない。実に、神の国はあなたがたの間にあるのだ」》〔ルカ 17:20-21〕。つまり、人と人の「間」、いいかえれば交換の形態が変わる。すなわち、交換様式Dが到来する。そしてそれは原遊動性の回帰であるがゆえに、反復強迫的である。イエスをせきたてる終末論的衝迫は、そこから来る。』
柄谷行人『力と交換様式』,pp.177-178.
柄谷氏は、これまでは一種 “神秘主義” 的な言い方でしか述べなかった「交換様式D」について、ここで↑、かなり解りやすく書いています。「D」が到来して「交換様式A,B,Cを無化する」ということを、マルクス/エンゲルスが描いたような社会革命ないし急激な社会変革のように考える必要は、かならずしも無いのです。それはたとえば、「仲間」でも家族でも上司でも取引相手でもない人を「隣人」として遇し交わる、という「倫理」が広がることによっても可能なのです。「D」は、人が “来させる” ものではなく到来するものである以上、革命運動や民主的政治運動のような意識的な集団的活動ではありえない。が、おそらくは、自然発生的な暴動のようなものでもないのです。
たしかに、倫理の実践――「人と交わること」――ならば、個人でもできます。
Niccolo Tornioli:"Vocación de San Mateo", 1635-37, MBA Rouen.
イエスは取税所にいた徴税人マタイを手招きし、「私に付いて来なさい」と
言った。マタイはイエスの弟子になったことを喜んで、自宅で盛大な宴会を催す。
そこにはマタイの仲間の徴税人や罪人,サイコロ師などが大勢集まり、イエスと
弟子たちと酒を飲んで騒いだので、パリサイ人らは非難した〔マタイ 9:9-13〕
ただ、そうした・いわば個人の “こころがけ” だけで、社会を変えられるとは思えません。「隣人」倫理の実践のみによって、「D」が社会においてドミナントになることは、おそらく無いでしょう。イエス自身、それを宗教的教団活動として展開しようとして、12人の「使徒」をユダヤの各地に送り……失敗しています。
のちほど見るように、イエスの創始した宗派は、彼の死後に「キリスト教」として教勢を広げてゆく過程で、共同体とも統治権力とも商人・富者とも妥協してA,B,Cの要素を帯びるようになり、変質していきました。最終的には、ローマ帝国の国教となった段階で、決定的に「B」の宗教、すなわち「世界宗教」に転化しています。
歴史上「D」は幾度となく出現したが、それが、社会において一時的にもドミナントとなるには障碍が大きすぎるのです。たとえ障碍を乗り越えて広がることができたとしても、その場合には「D」じたいが変質してしまう――というのが、現在までの人類史の到達点なのではないでしょうか。
私たちは、柄谷氏の言説の先を見て、そう言う必要がある;そこからあらためて考えてゆく必要があると思います。
ところで、イエスの「D」に関しては、次のような点も指摘されます。
「マルコ伝」からは、イエスの本職は、父ヨセフとともに大工だったことが読みとれます。「彼らは祭司でも農民でもない。遊動的工芸人であった。」また、イエスが最初に弟子にしたペトロらは、「ガリラヤ湖で網を打っていた4人の漁師」でした。「漁師は多くの点で遊牧民と類似する。モーセが遊牧民を率いたように、イエスは漁師を率いたのである。〔…〕イエスと弟子(使徒)たちが遊動的であったことは言うまでもない。」彼らは、ユダヤの地を遊動して「人間をとる漁師」でした。「したがって、原始キリスト教は」、のみならず一般にDは、「原遊動性とその回帰(終末)・という問題と切り離すことができないのである。」(柄谷,p.178.)
この指摘は、私たちが「交換様式D」を理解し、いつかその到来を迎えて活かすためには、重要なヒントとなるものでしょう。
それとともに、以前に (14)【44】で見た、キリスト教の「隣人」倫理に対するフロイトの批判についても、あらためて想起しておく必要があると思います。
フロイトは、人間の攻撃性が内向的に折り返して「超自我」を形成するのと並行して、人間の集団である文化共同体にも、個々の人間の自我を規制するような「超自我」が形成されると考えていました。集団的文化の超自我は、個人に対して、他律的に自我を抑圧することとなります。「超自我」本来の、……個人の自律性の核心として自我の自立を援助するという「超自我」本来の性格……からは、懸け離れてしまっているわけです。過度の理想を個人に押し付ける〔ギトン註――教権成立以後の〕キリスト教倫理や共産主義が、その典型例として挙げられていました。
フロイトのこの批判を踏まえるならば、「D」を実践倫理として進める場合には、それが「超自我」の対自攻撃性のみを強めることによって、かえって「自由」を抑圧してはいないかどうか。原遊動性の回帰という「D」本来の性格・志向から離れてしまってはいないか、つねに反省してみる必要があると言えるでしょう。
ハンス・メムリング『パトモス島でヨハネが黙示を幻視する』
1479年、祭壇画。©Wikimedia.
【75】 「交換様式D」の先駆者たち
――「パトモスのヨハネ」と「黙示録」
『新約聖書』の末尾に収録された「ヨハネの黙示録」は、キリスト教会では永いあいだ、「ヨハネによる福音書」「ヨハネの手紙1・2・3」と同じく「使徒ヨハネ」が書いたものだと信じられてきました。しかし、近代になって、古代ギリシャ語に関する知見と『新約』テクストの言語的/思想的解析が進むにしたがって、この伝統的見解は疑われるようになりました。とくに「ヨハネの黙示録」は、他の「ヨハネ文書」とは、言語的にも思想的にも異質であることが明らかにされ、その著者「ヨハネ」は、他の文書の著者とは別人だとするのが、現在主流の見解となっています。(Wiki「ヨハネ文書」「ヨハネの黙示録」)
その「黙示録」著者のヨハネは、自著の冒頭で、つぎのように自己紹介しています:
『9 わたしは、あなたがたの兄弟であり、共にイエスと結ばれて、その苦難、支配、忍耐にあずかっているヨハネである。わたしは、神の言葉とイエスの証しのゆえに、パトモスと呼ばれる島にいた。 10 ある主の日のこと、わたしは “霊” に満たされていたが、後ろの方でラッパのように響く大声を聞いた。 11 その声はこう言った。「あなたの見ていることを巻物に書いて、エフェソ、スミルナ、ペルガモン、ティアティラ、サルディス、フィラデルフィア、ラオディキアの七つの教会に送れ。」 12 わたしは、語りかける声の主を見ようとして振り向いた。振り向くと、……〔ヨハネ黙 17:9-12〕』
この記述を信ずるならば、著者ヨハネはパトモス島の住人か、もしくは「黙示録」の啓示を受けた時にパトモス島にいたことになります。
パトモス島・スカラ港。©Wikimedia.
パトモス島は、エーゲ海に浮かぶトルコ沿岸の島です。この島には、ヨハネを記念して 11世紀に建てられた「神学者聖ヨハネ修道院」が現在もあり、ヨハネが「黙示」を受けた場所と伝えられる洞窟があります。これらは世界遺産に登録されています。
なお、「ヨハネの黙示録」の内容については、こちらで「交換様式D」の観点から詳述していますので、読み返していただければ幸いです。
『終末論には、今の世を悪とし、新しい世を善とする二元論が存在する。さらに重要なのは、今の世と新しい世の転換点には、神の審判があるとする思想である。〔…〕この時、地震や大災害によるパニックが出現し、タヒ者の復活が起こる。〔…〕
「ヨハネの黙示録」は、この世の終末に行なわれる神と悪魔の決戦、ハルマゲドンを説く。その情景は、ゾロアスター教の終末論を説く・『アヴェスタ』の「ザームヤズド・ヤシュト」や、中世ペルシャ語の『ブンダヒシュン』の記事と驚くほど似ている。「ヨハネの黙示録」〔…〕が、グノーシス思想の影響下に成立したものであるなら、それは当然と言える。なぜなら、グノーシスとは、イラン思想のヘレニズム的形態にほかならず、とくにその二元論は、ゾロアスター教に源泉があるのは確実だからである。』
岡田明憲『ゾロアスターの神秘思想』,1988,講談社現代新書,pp.114-116.
よかったらギトンのブログへ⇒:
ギトンのあ~いえばこーゆー記
こちらはひみつの一次創作⇒:
ギトンの秘密部屋!