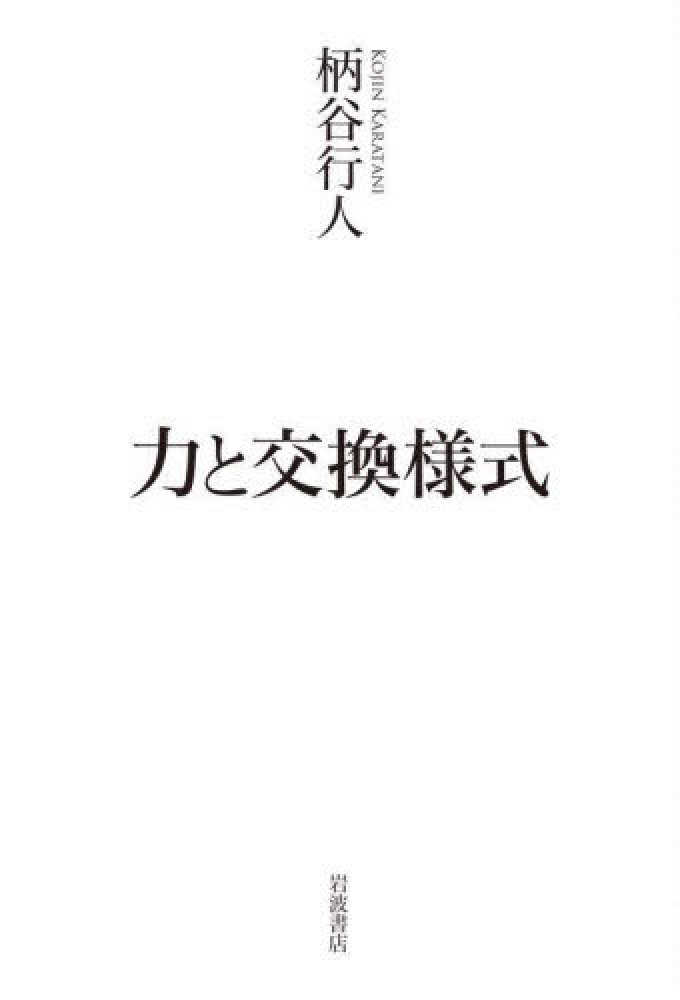ヨゼフ・ハスルワンダー〔1812-78〕「アジール権」。ベルヴェデーレ・オースト
リア絵画館。ヨーロッパでは教会が「駆け込み寺」の役割をした。©Wikimedia.
【67】 「交換様式D」――「A」の回帰か?
『社会構成体は、A、B、Cの交換様式の結合体としてあり、どれがドミナントであるかによって、歴史的段階が区別される。そして、Dは、Cが支配的となる資本主義社会・のあとで出現するような社会の原理だといってよい。しかし、それはたんに、生産力が進んだ段階で出現する、というようなものではない。Dはいわば、BとCが発展を遂げた後、その下で無力化したAが “高次元” で回帰したものだ。注目すべきなのは、それがすでに古代において出現したということである。』
柄谷行人『力と交換様式』,2022,岩波書店,p.159.
柄谷氏は、ここで本書の総論を再説しています。そこで私たちも改めて、この「交換様式A・B・C・D」の理論を再検討しておきたいと思います。ここで注目されるのは、「D」の出現とは、資本主義によって「生産力」が発展すれば、やがて「D」の社会になる、というような単純なことではない、としている点です。
「史的唯物論」の考え方では、共産主義ないし社会主義は、資本主義発展によって高められた「高度な生産力」のもとで実現する、とされます。しかし、「交換様式D」は、ユダヤ教、キリスト教などの形で、すでに古代において――ピンポイントでの噴出ではあれ――出現しているのです。したがって、「交換様式D」は、生産力とはあまり関係が無い。それでは、「D」の出現は、何と関係しているのか?
柄谷氏によれば、「D」は、「交換様式A」「B」「C」のあいだの相互関係の展開から生じてくるのです。
かつて「交換様式A」がドミナントだった氏族社会は、B〔国家〕とC〔商品経済〕の発展のもとで崩壊し、「A」は、それらの力に抑えられて「無力化して」いるのが、中世から近現代までの文明社会の歴史です。その無力化したAが、「 “高次元” で回帰して」「D」となって出現する、というのです。「高次元で回帰」とは、どういうことなのか? Aの単なる再出現ではないとすれば、「D」は、Aとどう違うのか?‥
柄谷氏は「序論」のはじめで、次のように述べていました:
『マルクス主義の標準的な理論では、社会構成体の歴史』について、『生産様式が経済的なベース(土台)にあり、政治的・観念的な上部構造がそれによって規定されているということになっている。私は、〔…〕そのベースは生産様式だけではなく、むしろ交換様式にあると考えたのである。交換様式にはつぎの4つがある。
A 互酬(贈与と返礼)
B 服従と保護(略取と再分配)
C 商品交換(貨幣と商品)
D Aの高次元での回復』
柄谷行人『力と交換様式』,pp.1-2.
( )内は、交換様式の物質面を述べているようです。交換様式Bも、ここでは「略取」――収奪・徴税――と「再分配」として、物質面がきちんと捉えられています。ただ、その後の本書の叙述では、もっぱら「服従と保護」という観念的な面だけが述べられていて、不十分な印象を与えているのが残念ですが。
他方、「D」については、「Aの高次元での回復」としか述べられておらず、内容が明確ではありません。
「序論」の少し先では、次のように述べられています:
『Dは厳密にいえば、交換様式というよりも、交換様式A・B・Cのいずれをも無化するような力としてあるものだ。またDは「Aの高次元での回復」として生じる。〔…〕重要なのは、Dが人間の意志や企画によって生じるものではない、むしろ、それに反してあらわれる、ということである。それは、観念的な力、いいかえれば、「神の力」としてあらわれるのだから。』
柄谷行人『力と交換様式』,p.35.
「D」は、「交換様式というよりも」、交換様式とは少し違うものだ、というのです。
そして、「D」は、それが出現することによって「交換様式A・B・Cを無化する」力だ、というのです。そういう「観念的な力」だ、ということのようです。
発展した「B・C」の下で無力化していたAが、力を盛り返して「回帰」してくる――それが「D」の出現――ということは、「B・C」は「D」に抑え込まれることになります。それが、「B・Cを無化する」ということなのでしょうか。
しかし、「B・C」だけでなく、「A」も「無化」されてしまう、というのがよくわかりません。
資本主義の後で、人類社会の「交換様式」はどうなってしまうのか? 物質交換のない社会になるわけではないとすると、「交換様式A・B・C」のどれとも異なる交換様式が現出するのか?‥ あるいは、「D」という「観念的な力」がドミナントになって、「A・B・C」を規整するのか? ‥‥「無化する」というコトバの意味がよくわかりません。
もしかすると、柄谷氏は「DはAの…回復として生じる」という言い方をするので、よけいに解りにくいのかもしれません。この言い方を延長すると、「Aが回復すると、Aが無化する」ということになり、自己矛盾に陥ってしまうからです。
これまでに読んできたところからすると、実は「A」じたいが「原遊動U」の「回帰」と考えられるのでした。だとすると、「D」は、「Aの回復」というより、むしろ「原遊動Uの回帰」だ、としたほうが解りやすいのではないか? ‥その点を検証してみましょう。
『交換様式Aは、人類が定住した時点で生じた。そのとき人々は、太古の遊動段階にあったような在り方ができなくなった〔…〕つまり、定住を強いられた諸個人は、定住共同体の掟に自発的に従うようになったが、同時に、遊動的な段階にあった個体性・独立性を保持したのである。それが氏族社会である。』
柄谷行人『力と交換様式』,p.389.
『人類社会の初期は、遊動民の社会であった。それは、フロイトの言い方でいえば、原遊動民の「無機質」の状態である。私はそれを原遊動性(U)と呼ぶことにする。
だが、人類が定住したのち、さまざまな葛藤と対立が生じた。それを解消したのが、交換様式Aである。それは、フロイトの言葉でいえば、「忘却されたものの回帰」として生じた。それは反復強迫的である。ただし、「忘却されたもの」とは、〔…〕原遊動性(U)である。それは定住後に失われたが、消滅したのではない。それは、贈与交換を命じる霊として現れた。〔…〕
その意味で、氏族社会やその拡大としての首長制社会は、たんに禁忌によって縛られた抑圧的な社会なのではない。そこにはいわば、ユーモアに見られるような高貴な自律性もまた存するというべきである。』
柄谷行人『力と交換様式』,2022,岩波書店,pp.95-96.
『交換様式の観点から言えば、首長制社会は交換様式A、そしてそこから生じる力によって支えられている。この “力” は、定住化によって抑えられた原遊動性(U)の強迫的な回帰にもとづくものだ。そのため、Aを通して、原遊動性がある程度保持される。具体的に言えば、氏族社会・部族社会の人々は集団を形成しその中での規律に従いながらも、平等性と独立性(自由)を維持している。したがって、不満があれば出て行ってしまうし、また、首長といえども、失敗すれば解任されたり刹されたりする。』
柄谷行人『力と交換様式』,2022,岩波書店,pp.123-124.
このように、「交換様式A」がドミナントな「氏族制社会」とは、一面では共同体の掟や禁忌に縛られた社会ですが、成員はそれに従いつつも、遊動段階にあった平等性と自由・自律性を保持しているのです。なぜなら、「交換様式A」は「原遊動性U」の回帰だからです。
そこで、「交換様式D」とは、この「交換様式A」がそのまま――「掟」や禁忌もろとも――回復するのではなく、むしろ「原遊動性U」が、「交換様式A」とは異なる形で回帰してくる。それが「交換様式D」である、と言ったほうがよくないでしょうか? ‥また、そういう言い方のほうが、「D」に関する柄谷氏の具体的叙述には、よりよく適合するようにも思われるのです。この最後の点は、今後「D」に関する叙述を追うなかで検証していきたいと思います。
【68】 「交換様式A」の回帰
――「アジール」と遊牧民・漁民
「アジール」とは、「国家」成立後も「統治権力が(全面的または部分的に)及ばない地域」として残された場所で、西欧中世の「教会」「市場」「自治都市」などが挙げられます。日本中世でも、神社、仏閣、市場、港などの一部が、公権力の捜査検索を拒否する特権を認められていました。戦国時代の「堺」・近江「堅田」などの自治都市もアジールと言えます。日本のアジール(「無縁所」といいます)については、こちらで詳しくレヴューしていますので、参照いただければ幸いです。
江戸時代になると、幕府の政策で「無縁所」は大部分が消滅し、わずかに将軍家とゆかりの深い寺院いくつかが「駆け込み寺」として残されました。
浄発願寺。神奈川県伊勢原市日向。
『世界史において、AからB、そしてCへの発展の過程で、そのような発展に対抗しようとする動きが常にあったことを指摘しておきたい。ピエール・クラストルは『国家に抗する社会』において、人々が定住し国家を形成するようになったあとも、氏族社会にあった、生産物の共有という平等主義と、個人の自由独立性という観念が、さまざまなかたちで残った、という。交換様式の観点から言えば、それは、氏族社会にあった交換様式Aの名残り、あるいはその回帰があったということである。
その一例として、アジール(Asylum)と呼ばれる聖域を取り上げよう。
そこに入ると、人々はそれまでの社会的拘束や制約から解放された。たとえば、奴隷・債務者・犯罪者などが制裁を免れた。アジールは、どんな国家社会』に『でも局所的に存在してきたといえる。オルトヴィン・ヘンスラーは、アジールは元来、呪術的な起源をもつもので、倫理的な〔社会的・政治的な――ギトン註〕意味をもっていなかったと言う〔舟木徹男・訳『アジール――その歴史と諸形態』,2010,国書刊行会.〕。
では、なぜそれが倫理的な意義をもつにいたったのか。私の考えでは、国家成立後に残存する呪術性は、Bを支援するものとして働く。しかし、そこには同時に、Bを拒み、Aにあった互酬性をとりもどす衝迫が残っていたのである。その点から見ると、アジールは、氏族社会が国家社会に転じたのちに、抑圧された交換様式Aが局所的に回帰したものだと言ってよい。
ゆえに、それは呪術的であると同時に、倫理的な〔「超自我」的・自律的な――ギトン註〕意義、つまり反国家的な動機をはらむ。国家体制の側もそのような「力」(呪力)を恐れて、アジールに逃げ込んだ者には手を出せなかった。ここに、Bの優位に抗する運動の原型があると言ってもよい。
しかし、アジールあるいは盟約共同体※を支える霊的な力は、概して弱く、国家の末端、あるいは周辺にとどまるほかなかった。』
柄谷行人『力と交換様式』,pp.159-161.
註※「盟約共同体 Eidgenossenschaft」:西欧中世都市の自治を支える原理。都市自治への参加資格を認められた市民の「盟約(宣誓)」によって、内部統制を固めるとともに、外部に対する独立性を保持した。
「アジール」は、「交換様式D」のような「高次元での回復」ではなく、「交換様式A」がそのまま局所的に残ったような・「A」の「名残り」というべきものです。なぜなら、そこには、「自由・平等」の精神だけでなく、「氏族社会」にあったような厳しい「共同体の掟」もあるからです。むしろそうした厳しい拘束によって結束を固め、外部の国家社会に対抗して「自治」を守っていたと言えます。
たとえば、「縁切り寺」として有名な北鎌倉の「東慶寺」では、駆け込んで匿われている女子の間に厳しい序列があったといいます。自治都市でも、資格市民と劣格市民の間には厳然たる差別がありました。
東慶寺。神奈川県鎌倉市山ノ内。
しかし、他方で、「遊牧民」「漁民」のような非農業民は、遊動性を保持しながら、その交易活動によって「帝国」の形成を助ける役割をしました。これは、日本中世の「無縁所」寺社が、朝廷とのつながりによって特権を保持し、武士政権に対して自治・独立を主張する根拠としたことと平行する現象です。
『帝国をもたらしたのは、むしろ共同体と共同体、あるいは国家と国家の間にいた人たちである。すなわち、共同体や国家の「間」での交換を担った遊牧民や漁民である。彼らはいずれも、定住的でない仕事に従事したがゆえに、遊動民段階の慣習を維持していた。〔…〕
遊牧民〔…〕は、交易にも従事した。それは、国家の官僚が行なう交易とは別であった。〔…〕農耕民が忠実な「臣民」となったのに対して、遊牧民は国家に全面的に服属することがなかった。国家と国家の「間」にとどまったからだ。そのため、遊牧民は原遊動民とは異なるが、後者にあった重要な側面、すなわち自由独立性と平等性を保持したのである。つまり、遊牧民は “原遊動性” の記憶を保持した、と言ってもよい。
その点では漁民も同様であった。彼らも漁業だけではなく、海上交易に従事した。〔…〕
こうして、遊牧民や漁民は、農耕民を組織した専制国家の周辺や間で、それとは異質な空間を形成した。したがって、それは広域国家、すなわち帝国の形成を助けたが、帝国が成立するにつれて、その中に吸収されてしまった。
それと同時に、国家に対抗して、原遊動性に由来する何か、すなわちAの “高次元での回復”〔つまりD――ギトン註〕を企てる者が〔ギトン註――遊牧民のなかから〕出現した。それを典型的に示すのが、預言者ゾロアスターやモーセである。』
柄谷行人『力と交換様式』,pp.161-162.
東慶寺。神奈川県鎌倉市山ノ内。境内撮影禁止のため公道から撮影。
【69】 「交換様式D」の先駆者たち――序
『世界宗教とは、エジプトのイクナトンや、オリエントのハムラビ王がもたらしたような、帝国を支える一神教である。多数の地域社会を統合した帝国では、統治のために、新たな世界神が不可欠であった。つまり、このような神は、交換様式でいえば、Bの極大化によって生じたものである。
一方、普遍宗教〔ゾロアスター教,ユダヤ教,原始キリスト教,原始仏教,‥――ギトン註〕とは、帝国の中心ではなく周辺部に現れたものであり、帝国に対抗するものであった。“Aの高次元での回帰” を通して、BやCを超克しようとするものである。すなわち、Dの出現である。
このような宗教的集団は当初、少数であり、また無力であった。その後、世界帝国によって受け入れられるようになると、変容した。つまり、世界宗教と類似するようになったのだ。〔…〕
普遍宗教が出現するには、複数の異なる契機が必要なのだ。そして、それらの契機は互いに矛盾するので、普遍宗教もまた、たえず矛盾にさらされる。また、それはいつのまにか、共同体の宗教(偶像崇拝)、民族の宗教、帝国の宗教に戻って〔なって――ギトン註〕しまう。
〔…〕旧約聖書にも、そうした出来事が無数に描かれている。それに対して異議を唱えたのが、預言者たちである。彼らが唱えたのは、要約すれば、荒野に帰れ、ということである。それは、原遊動性の回帰にほかならない。そして、それが交換様式Dの到来であるといってよい。
しかし、原遊動性への回帰を志向したのは、イスラエルの預言者たちだけではない。またそれは宗教的な人物に限らない。Dは、いわゆる「宗教」とは異なる次元にあり、したがって、見たところ非宗教的な場合も少なくない〔イオニア自然哲学,墨家など――ギトン註〕。』
柄谷行人『力と交換様式』,pp.162-163.
そこで、以下、古代世界の「普遍宗教」その他に見られる「交換様式D」の事例を見ていくことになります。
最初に取りあげるのは、ペルシャのゾロアスター教ですが、ここで回を改めて始めることとしましょう。
よかったらギトンのブログへ⇒:
ギトンのあ~いえばこーゆー記
こちらはひみつの一次創作⇒:
ギトンの秘密部屋!