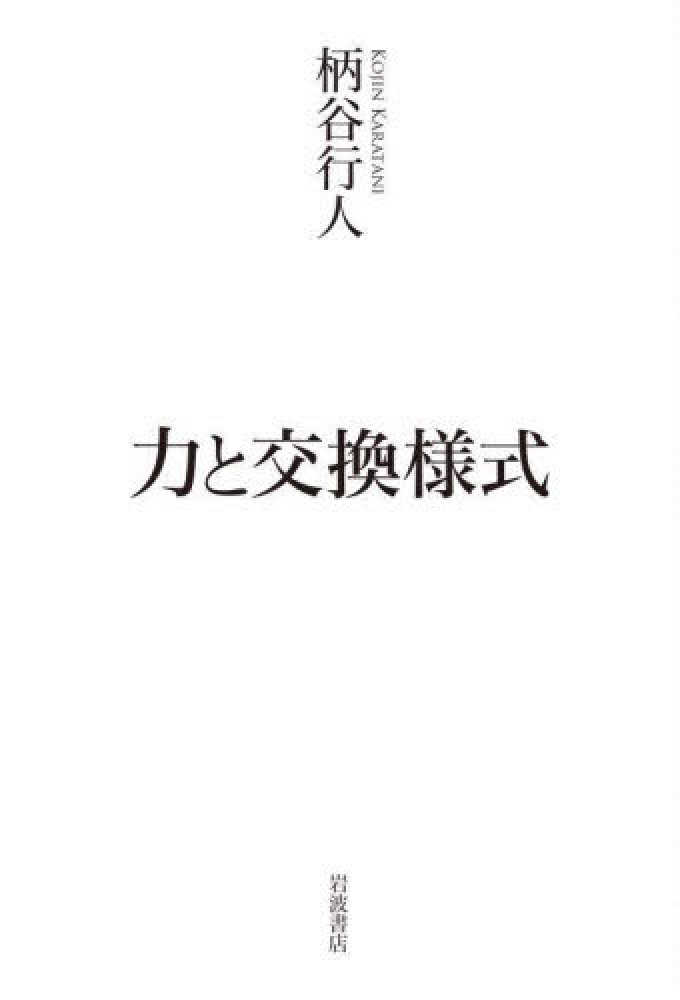吉野ヶ里遺跡「北内郭」、佐賀県。吉野ヶ里遺跡は、弥生時代後期(紀元1-3世紀)
・環濠集落の典型とされ、土塁・柵を伴う二重の「環濠」(からぼり)で囲まれ、
物見櫓で防禦された約 40ha の中に、祭殿・祠堂・市楼と見られる楼閣、
高床式倉庫群、竪穴式の住居・集会所・作業場・厨房が密集する集落、墳丘墓
などが検出されている。集落間の戦争が常態であったと考えられる。
【60】 柄谷行人――
「原遊動U」の強迫的回帰
マルクスは『晩年にいたって、未来の共産主義を、「古代社会」にあったものの “高次元での回復” と見なした。だが、“高次元” とは何を意味するのか。通常、これは「生産様式」(生産力と生産関係)の観点から〔…〕生産力が高度になった段階において、太古にあった共産主義を取り戻すことだと見られる。しかし、交換様式の観点から見ると、そうではない。共産主義とは、太古にあった交換様式Aの高次元での回復である。すなわち交換様式Dの出現である。』
柄谷行人『力と交換様式』,2022,岩波書店,pp.388-389.
柄谷氏はここで、交換様式Dは交換様式Aの「高次元での回復」である、というような書き方をしています。しかし、ここから、「D」は「A」と同じもので、ただ現れる社会ないし時代が異なるだけだ、と表面的に読んでしまうと、大きく間違えると思います。
氏の他処での議論を見ても、「交換様式D」はAとは、現出のしかたが著しく違います。「A」は、ある意味で自然な現れです。移動生活から遠ざかるとともに廃れつつあった「原遊動」の心性と伝統原則を維持し回復しようとする、人間社会としてはある意味自然な保守的傾向とも言えます。しかし、「D」のほうは、人びとの意識と志向を裏切るかのように、突然に思わぬほうから到来してくる現象です。「D」の出現をいち早く予感し説き広めようとする者があれば、社会の常識を破壊する過激な扇動家として指弾されるほかありません。ソクラテス、墨子、ブッダ、イエス、ミュンツァーら千年王国派、そしてトマス・モアからマルクス,エンゲルスまでのユートピアン。柄谷氏が「D」の体現者として挙げている人びとは、みなそうした運命を負いました。
「D」は、「原遊動」を回復しようとする点は「A」と同じであっても、再現の現れ方は「A」と異なるのです。私はやはり、遊動時代から「狩猟定住」にかけての時代――原初の「自由・平等」がなお維持されていた時代――と、近現代とでは、生産力の相違があることは無視できないと思います。生産力と言うと狭すぎるかもしれない。より広く、複雑化し巨大な能力を具えるにいたった社会、という条件の違いを無視できない、‥と言ったほうがよいでしょう。↑前段の人名録を見ると、これら「D」の反復的現れを体現した先駆者たちはみな、「穀物定住」以後、あるいは「国家」成立以後に登場しています。つまり、「D」は、もはや「原遊動」の時代の記憶がはるかかなたに沈み、社会の実情は大きく隔たってしまったあとで、原遊動の回復という「太古の道」が、なお無意識から衝迫されるようなかたちで、突発的に噴き出してくるものなのではないでしょうか。
ジャック=ルイ・ダヴィッド「ソクラテスのタヒ」
交換様式Aは、原遊動の・いわば「低次の再現」です。その意味は、原遊動以来の「平等化の縛り」を “掟” として維持し、社会が物質的・文化的に発展(変化)するのを抑えることで、原初の「自由・平等」を維持しようとする、ということです。「低次」とは、「文明」社会と比べて文化的に低いレベルの社会にある、というような意味ではありません。むしろ、狩猟採集民は、自然との物質交換の面でも、人間関係の面でも、「文明」人よりも複雑ですぐれた知識や技能・習慣を駆使して生活しているのです。
ただ、そこには発展した強大な生産力も、われわれの持つ科学・芸術のような、いわゆる「高度な」文化もありません。それらを手放すことなく、原初の「自由・平等」を再実現すること、それができれば、それこそが原遊動の「高次の再現」であり、交換様式Dなのです。
『交換様式Aは、人類が定住した時点で生じた。そのとき人々は、太古の遊動段階にあったような在り方ができなくなった〔…〕つまり、定住を強いられた諸個人は、定住共同体の掟に自発的に従うようになったが、同時に、遊動的な段階にあった個体性・独立性を保持したのである。それが氏族社会である。』
柄谷行人『力と交換様式』,p.389.
つまり、交換様式Aは、モースらが考えた《集団間》の交換ではなく、《集団内》、共同体内部の諸個人のあいだの交換なのです。また、交換様式Aが維持しようとする原初的「自由・平等」は、「個体性」の主張と尊重を含んでいます。それを経済面から言えば、「私有財産」は原初からある、原初の人間社会は絶対的「共有」の社会ではない(つまり、狭い意味での「共産主義」ではない)、と考えられます。柄谷氏は、この箇所では交換様式Aについて正確な議論をしています。
『しかし、国家の出現とともに、事態が変わった。氏族社会が終っても、人々は国家の下で村落共同体を維持したが、それまであった個体性・独立性を失った。交換様式でいえば、そのときAがBに抑えこまれたのである。
その後、近代国家・資本主義の発展、つまり、BとCの拡大とともに、村落共同体Aは解体されていった。しかし、それはある意味で回復された。〔…〕資本主義経済の下で、ネーション(想像の共同体)が形成されたからである。とはいえ、それはAの “低次元での回復” にすぎない。その結果として成立したのが、資本=ネーション=国家である。〔…〕それが最初に出現したのは、ヨーロッパにおける 1848年の革命〔のナポレオン3世らによる圧服過程――ギトン註〕を通してであった。マルクスとエンゲルスはそのとき、資本=ネーション=国家の出現、すなわちCの下でのA・Bの結合という大事件に立ち会ったのである。』
柄谷行人『力と交換様式』,p.389.
これに対して、「交換様式D」は、「“Aの高次元での回帰” を通してBやCを超克しようとするものである。」それはしばしば、原始仏教、原始キリスト教のように「普遍宗教」のかたちをとって現れた。(柄谷,p.162)
普仏戦争(1870年)後のナポレオンⅢ世とビスマルク。©Wikimedia commons.
【61】 トマス・ホッブズ――
「国家」とは、人間たちが形造るロボットである。
『ホッブズの考えでは、自然状態では、すべての人間は自由で平等な自然権をもつ。だが、それは「万人の万人による闘争状態」を招くことになる。そのとき、人々が自然権を一人の者に譲渡することによって、そこから脱した。このような社会契約がなされたとき主権者が成立した〔つまり国家が成立した――ギトン註〕と、彼は言う。そして、それを「リヴァイアサン」(海の怪獣)と呼んだ。』
柄谷行人『力と交換様式』,p.101.
ホッブズ(『リヴァイアサン』)によれば、「国家」以前の社会では「万人の万人に対する闘い」が常態だった。すべての人間が、自分以外のすべての人間と闘争しあっていた、というのです。
しかし、縄文時代の遺跡を見るかぎり、そのような「闘争」の痕跡は見出せません。どころか、集落・対・集落の戦争が行なわれた証拠さえ、いまのところ見つかっていないのです。ホッブズの想像とは違って、「狩猟定住」は、めだった争いのない社会だったと考えざるをえません。
なぜ、「狩猟定住」の人びとは互いに争わなかったのか? 柄谷氏は、交換様式Aが、人びとの攻撃衝動を抑えこんでいたからだ、と考えるのです:
『氏族社会でも、つねに物理的な力による衝突がありえたのだが、それは交換様式Aから来る霊的な力によって抑えられていた。それが氏族社会を支えていたのだ。』
柄谷行人『力と交換様式』,2022,岩波書店,p.106.
もっとも、「狩猟定住」社会は、世界中どこでも平和だったわけではありません。モーガンが『古代社会』に描いた北米イロコイ族の氏族社会では、氏族間の戦争がありました。次節で見るように、ホッブズが「万人の闘争」の「自然状態」を着想したのは、じつは、植民者から伝え聞いた「アメリカの野蛮人」の抗争状態がもとになっていたのです。
しかし、それでも「アメリカの野蛮人」のあいだにも交換様式Aの融和力は働いており、それゆえに社会が内部闘争で崩壊してしまうことはなく、むしろ「イロコイ連邦」のような水平的な部族連合体を結成しえたのです。
つまり、国家以前の社会では、交換様式Aの融和作用によって、闘争が過度に激化しないようにして、人間社会が瓦解してしまうのを防いでいた、と言ってよいと思います。
「審判の日」に海から現れたリヴァイアサン(七頭の竜)©Jamin Bradley.
他方、国家成立以後の「国家」社会における平和維持の原理は、それとは異なります。この「国家」における原理が、ホッブズによれば「社会契約」であり、柄谷氏の言い方では、交換様式Bなのです。ホッブズが、人びとが意識的に「万人の闘い」をやめるために契約を結んだと仮想するのに対し、柄谷氏は、もっと無意識の次元で、同様のことが起こって「国家」が成立したと見るのです:
『国家という制度は、〔…〕人々の意志を超えた、何か観念的な力にもとづくのであり、そして、その「力」はAとは別のタイプの交換様式、すなわちBから来たのである。
交換様式B』もまた『交換である。というのは、それは、服従すれば保護されるという関係、あるいは、保護されるのでなければ服従しないという双務的な関係だからだ。その意味で、BはAとは異なるにもかかわらず、Aと類似する。Aの互酬性が水平的なものであるとしたら、それを垂直的な上下の関係にしたものがBである。〔…〕交換様式Bはある意味でAの変形であり、また、それ〔A――ギトン註〕によって支えられるのである。
氏族社会から国家が出現するまでの過程は、交換様式から見れば、AからBへの移行にほかならない。』
柄谷行人『力と交換様式』,2022,岩波書店,pp.106-107.
柄谷氏によれば、「国家」の成立は、人間の自由意思による事業でも、たんなる暴力による征服でもありません。そこには、「何か観念的な力」が働いていると言うのです。というのは、それ以前の氏族社会(狩猟定住と穀物定住)と、「国家」成立とのあいだには、大きな断絶があるからです。
たしかに、「穀物定住」ともなれば、氏族社会の内部でも階層分化と分業が起き、「首長・司祭」が誕生します。しかし、「首長・司祭」は「王」ではなく、「国家」の支配者とはなりえないのです。「首長」が他の「首長」たちを従えると「王」になる――というわけではない。なぜなら、氏族間の戦争は、次節で見るように、他の氏族を服属させるためではなく、自己の正当性を認めさせ、優越と名誉を得るためにのみなされるからです。勝利しても敗北しても、氏族間の関係は対等なまま。氏族社会とは、“たがいに侵 おか しあわない” 社会なのです:
『祀 まつ られざるも神には神の身土 みつち があると
あざけるやうなうつろな声で
さう云ったのはいったい誰だ〔…〕
さういふことを考へさせる
背後の力はいったい何だ
……雨がどこかでにはかに鳴り
西があやしくあかるくなる……
あゝ誰か来て私に云へ億の天才ならんで生れ
しかも互ひに相犯さない
あかるい世界はかならず来ると』
宮沢賢治「産業組合青年会」〔下書稿㈡第1形態〕,『春と修羅・第2集』#313.
東北の農村詩人が、「村々の気鋭な同志の会合」のさなかに、ふと「縄文」の神々にまで退いて行くかの想念に襲われたのは、偶然ではありません。「産業組合」の青年たちの自力更生の熱意に、原初の「対等・平等」が回帰してくるのを〔交換様式Dの噴出を〕感じたのです。
しかし、それは「国家」に服属する意識とは、究極において反することとなる。詩人はその矛盾を、鋭敏に感知しているのです。
五郎沼、岩手県紫波郡紫波町南日詰。1924年10月、宮澤賢治が夜半の雨の中
彷徨しつつ「産業組合青年会」ほかの詩篇を着想したのは、この沼畔だった。
『ここで重要なのは、このような怪獣〔リヴァイアサン,つまり国家――ギトン註〕が〔…〕人間と人間の「契約」によって形成されるということである。〔…〕
完全な自然状態のもとで恐怖から結ばれた契約は拘束力を持つ。たとえば、もしも私が敵にたいして、自分の生命の代わりに身代金とか労働を支払うという契約を結ぶならば、私はそれによって拘束される。というのは、それは一方は生命を得、他方は金または労働を得るという契約〔contract〕だからである。〔永井道雄・他訳『リヴァイアサン』,Ⅰ,2009,中公クラシックス,p.191.〕※
つまり、このような契約は、服従すれば保護されるという関係を含意するものであり、一種の交換である。私はそれを交換様式Bと呼ぶ。〔…〕
自発的隷従こそが国家を可能にすると言える。〔…〕私は、権力とはそもそも “自発的な服従” にもとづくものだ、と考える。人が自発的に服従するのは、それによって保護が得られるからである。つまり、それが「交換」となっているからだ。そして、そのことを最初に明示したのがホッブズである。
彼は「力」を、社会契約、つまり交換において見ようとした。その場合、主権者は誰でもよい。主権とは、〔…〕人がそこに置かれるような場である。その場に立つ者が「力」を持つ。いいかえれば、〔ギトン註――「服従」⇔「保護」という〕ある種の交換こそが「力」をもたらすのである。それは主権者に、命令する権利を与えるだけでなく、臣民の要求に応じる義務を課する。私はこの種の交換様式をBと呼び、商品の交換様式Cや贈与の交換様式Aから区別する。』
国家は、『支配階級と被支配階級の「交換」、つまり、被支配階級の「自発的服従」によって生じたのだ。』
柄谷行人『力と交換様式』,pp.102-103,105.
註※ 以下、柄谷氏は『リヴァイアサン』を、岩波文庫版(水田洋訳)と中公版(永井道雄ほか訳)の2種から引用しているが、中公版に統一し、また、柄谷氏の引用箇所の前後を含めて引用する。
このようなホッブズと柄谷氏の「国家」観は、王ないし「主権者」に「国家」の本質を見るものです。臣民が自分の自然権を「主権者」に譲渡する「社会契約」ないし「交換」契約、臣民の「主権者」への「自発的服従」が、「国家」を成り立たせると考えるのです。
これは、スコットのように、王よりも「官僚組織」の存在に「国家」の本質を見る「徴税国家」の考え方とは対照的であるように見えます。
『リヴァイアサン』1651年版の口絵(部分)。Abraham Bosse 画。
王笏と剣を掲げるリヴァイアサンの身体は、多数の人間で構成されている
しかし、『リヴァイアサン』の「序説」の冒頭で、ホッブズは次のように述べているのです:
『人間はその技術によって人工的動物をもつくることができる。』その『「自動機械」(腕時計のようにぜんまいと歯車によって動く機械装置)』にあっては、動物の『「心臓」とは「ぜんまい」、〔…〕「関節」は「歯車」のことであって、これらのものが全身に、製作者〔人間――ギトン註〕によって意図された運動を与えている〔…〕
技術は〔…〕「人間」さえも模倣する。すなわち、《コモンウェルス》ないし《国家〔STATE〕》と呼ばれる偉大な《リヴァイアサン》を創造するが、それは疑いなく一箇の人工人間にほかならない。ただ、この人工人間は、〔…〕自然人〔個人のこと――ギトン註〕を保護し防衛することを意図している。
また、人工人間にあっては、「主権〔Soveraignty〕」が人工の魂であり、それが全身に生命と運動を与える。「施政官〔Magistrates〕」とその他の司法・行政上の「役人たち」は人工の「関節」である。また「賞罰」(これによって、あらゆる関節や器官が主権の座に結びつけられ、それぞれの義務を遂行させられる)は「神経」であり、それは自然的肉体における神経と同じ働きをする。また個々の成員が所有する「富」と「財宝」は「体力」であり、〔…〕
この人工人間の性質を述べるにあたって、私はつぎの諸点を考察しようと思う。
第一に、その「素材」と「製作者」。それはともに人間であるということ。
第二に、「どのようにして」、またどのような「契約」によって、人工人間はつくられるか。』
ホッブズ,永井道雄・他訳『リヴァイアサン』,Ⅰ,2009,中公クラシックス,pp.7-8.
つまり、ホッブズによれば、「国家」とは一種の巨きな「自動機械」ないしロボットである。おおぜいの人間が結合しあって、巨大な「人工人間(ロボット)」となっている。「主権」と呼ばれる・「人工人間」の頭脳の位置にいるのが「主権者」=王である。手足の位置にいるのが、「施政官」と、その下で命令を遂行する「司法行政上の役人たち」つまり官僚である。彼らは「賞罰」で制御されて自動機械のように動く、というのです。ホッブズも、一面では、官僚制を必須の構成要素とする「徴税国家」の本質をとらえていたと言えます。
【62】 「交換様式A」の二面性――「友好」と「戦争」
「ホッブズは国家の成立を万人と万人が争うような[自然状態]から考えようとしたが」、その時彼の念頭にあったのは、北米先住民の社会だった。彼らは「まったく統治をもたず、……残忍なやりかたで生活している」とホッブズは言う(柄谷,pp.110-111;リヴァイアサン,中公版,Ⅰ,pp.172-175)。つまり、ホッブズが「万人の万人に対する闘争」状態と見なしたのは、じつは、モーガンがその「自由・平等」を称賛した・同じ北米先住民の「氏族社会」にほかならなかったのです。
北米先住民社会の『この状態は、交換様式Aにもとづくものであり、戦争状態もそれによってもたらされていた。氏族社会がもたらす絶え間ない戦争こそ、国家形成を妨げたというべきである。』
柄谷行人『力と交換様式』,p.111.
いくさに出ようとしているイロコイ族の氏族。
つまり、「交換様式A」(互酬・贈与交換)は、氏族社会の人びとに融和をもたらすだけでなく、戦争状態をももたらすのです。そしてこれら両面は、それぞれが「国家」の成立を妨げることになります。
そうすると、「縄文人」社会のような場合には、交換様式Aの「超自我」的な「自律」作用が強くはたらいて〈融和〉の局面が圧倒していたのに対し、西洋人がやってきた頃の北米先住民の場合には、〈戦争〉の局面が強く現れていたと見ることができるでしょう。しかし、後者のような「たえまない氏族間闘争」は、「氏族」内に階層分化が進展した後の、つまり「首長・祭司」が発生した後の現象ではないでしょうか。
『氏族社会は交換様式Aにもとづき、国家は交換様式Bにもとづくのである。そして、Bが出現したのは、Aが十分に機能しえなくなった時点においてである。
ホッブズが言う「自然状態」とは、互酬交換Aの原理が強く残っている社会の状態を意味するというべきである。〔…〕主権者が成立するためには、Aとは異なる交換様式Bが確立されねばならない。それが国家をもたらす「社会契約」にほかならない。
通常は、こう考えられている。贈与の互酬交換は、他の共同体との関係において友好的関係を築く〔…〕したがって、氏族間で戦争は起こりえない、と。しかし、じつは、そこでは、しばしば戦争状態が生じた。それは、贈与の互酬交換が必ずしも友好的・平和的なものではないからだ。それはしばしば競合的であり、戦争に転化する可能性があった。贈与は〔…〕、返済できないほど過度の贈与によって相手を圧服させる手段となる。しかも、それは相手を支配するためではなく、自らの威信を守り誇示するためになされる。
したがって、互酬交換は一般に平和をつくりだすものと見なされるけれども、戦争をもたらす場合が少なくない。〔…〕ピエール・クラストル〔『国家に抗する社会』――ギトン註〕は、〔…〕アマゾン奥地のヤノマミ族がたえず戦争していることを指摘し、〔…〕贈与は、〔ギトン註――和平のためではなく〕むしろ戦争のための同盟をつくるためになされるのだ、という。彼の考えでは、部族間の戦争は、〔ギトン註――他部族を服属させて統一する目的も、効果もなく、むしろ逆に〕部族を越える大きな組織、つまり集権的な国家の形成を不可能にする。すなわち、部族間のたえまない戦争こそ、それ〔諸部族――ギトン註〕が国家に転嫁しない原因だ、というのである。
〔…〕部族社会の内部におけるたえまない戦争は、交換様式Aによるものであり、〔…〕彼らは戦争によって相手を屈服させようとするのだが、それは相手を征服し従属させるためではない。戦争は自らの「威信」のためになされる、一種の供犠である。したがって、戦争は、それぞれの共同体に凝集性・同一性をもたらすが、他の氏族・部族を征服し支配する、つまり国家を形成する、ということにはならない。〔…〕
この意味で、互酬交換すなわち交換様式Aは、そのポジティヴな性質(友好)によって国家の形成を妨げるだけではなく、同時に、ネガティヴな性質(戦争)によって、国家の形成を妨げる。それが権力の集中、ハイアラーキー〔ヒエラルヒー,位階序列――ギトン註〕の形成を妨げるからだ。サーリンズは贈与が果たすこのような両義的な役割について、次のように述べている。
まことに、贈与は、〔…〕個々に分離した一群の人々を、いっそう高度な統一体に溶解するのではなくて、まったく反対に、対立を相互に関係づけることで、対立を永続化させているのである。贈与は、契約する人々の個別的利害のはるか上空にそびえたつ第三者〔絶対的支配者,リヴァイアサン,王,国家――ギトン註〕を、けっして必要条件とするものではない。〔…〕贈与は平等を犠牲にすることもなければ、自由を決して犠牲にすることもない。交換によって盟約を結んだ集団は、〔…〕いつまでもその力を保持できるのである。〔マーシャル・サーリンズ,山内昶・訳『石器時代の経済学』,1964,法政大学出版局,pp.203-204.〕
〔…〕首長制社会では、人々は首長に従うとしても、それによって「自由」も「平等」も失うことはない。〔…〕
国家が成立するのは、Aとは異なる交換様式が成立する時、つまり、ある者が絶対的に支配し、他の者がすべて自発的に服従するという関係が成立する時、いいかえれば、首長が王となる時である。それが、交換様式Bにほかならない。〔…〕自発的に服従すること〔…〕を可能にするのは、物理的な力ではなく、交換様式Aに伴なう霊的な力をさらに上まわるような霊的な力である。それは交換様式Bによってもたらされる。それのみが、王に、首長を超える力を付与する。真に「聖なる王権」〔ホカート『王権』〕が出現するのは、そのときである。』
柄谷行人『力と交換様式』,pp.112-116.
纏向古墳群、茅原大墓、奈良県桜井市。纏向古墳群は、のちの巨大前方後円墳
時代に先立つ 3-4世紀の古墳群で、まだ前方部が小さいのが特徴だが、この
「茅原大墓」で観察できるように、前方部・後円部ともに段築されている。
銅鏡なども出土しており、前方部を祭祀場として、鏡の反射光を利用した
荘厳な儀式を行なっていたことが想像できる。
柄谷氏の言うB出現の契機、すなわち「Aが十分に機能しえなくなった時点」とは、氏族内部の階層分化と「首長・祭司」層の権力掌握が進んで、氏族社会で保たれていた “治者と被治者の同一性” が、もはや成り立たなくなった時点ではないでしょうか。集団内部での “支配・被支配” 関係の成立は、外部の集団を服属させ支配する能力の獲得をも意味します。
これは、日本の古代でも同様で、たとえば、ヤマト・纏向地方〔奈良県桜井市北部~天理市南部〕では、紀元3世紀頃、それまで数多くあった環濠集落の環濠(防禦施設)が埋め立てられ、古墳造営・水路建設等を組織する “神政王権”(卑弥呼一族か? 初期の天皇家か?) による一円的支配が成立しています。
それでは、首長性を超えて「国家」が出現するのは、どんな時なのか?「外部の集団を服属させ支配する能力」とは、どんな「力」なのか? ‥‥柄谷氏によれば、それは、王の支配が宗教的次元を伴なった時、すなわち、人びとをして自発的に服従させる宗教的「力」を持った「神聖王」が出現した時なのです。
よかったらギトンのブログへ⇒:
ギトンのあ~いえばこーゆー記
こちらはひみつの一次創作⇒:
ギトンの秘密部屋!
Jocke Åkerblom (1906-1972) :SITTING YOUNG MAN.