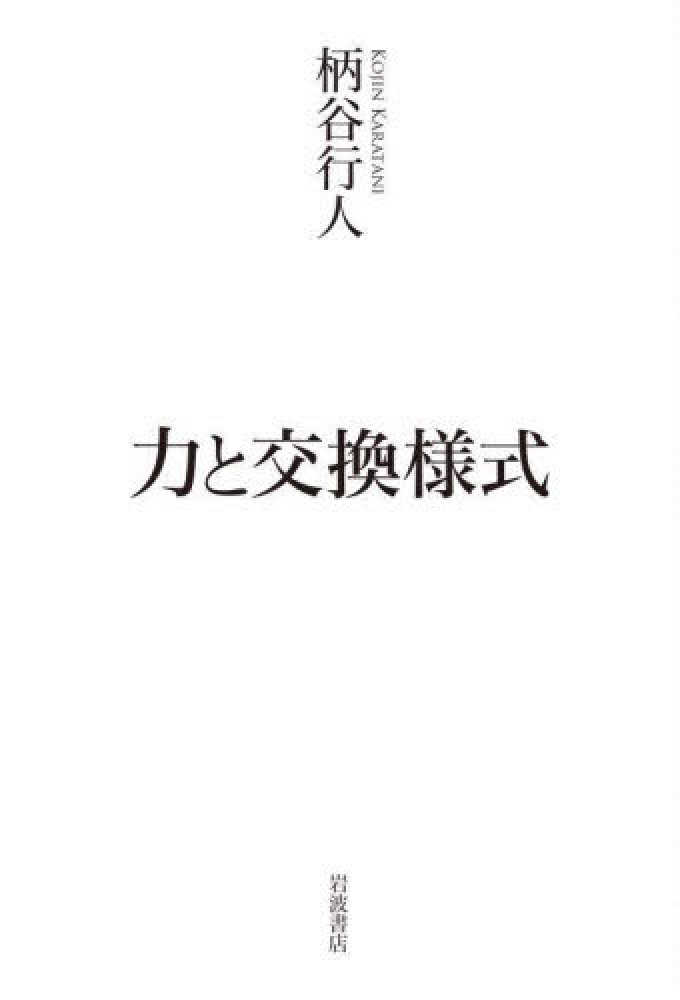「第3回モスクワ裁判」1938年。法廷に向う被告人ブハーリン(中央)とルイコフ。
スターリン執権下、共産党幹部の粛清とその国際的正当化を狙った公開法廷茶番劇。
【13】 漂流するブロッホ――
ユダヤ人迫害から逃れて
『彼〔エルンスト・ブロッホ――ギトン註〕は人間の社会史に関して、史的唯物論にも神学にもないような観点を導入しようとした。それは、彼独自のレトリックによって示される。
たとえば、彼は、資本と国家を揚棄する可能性を「希望」と名づけた。この場合、希望は願望ではない。つまり、人の主観によって招来するものではない。「希望」とは、「中断された未成のもの」が、おのずから回帰することである。〔…〕
しかし、このように、「中断され、おしとどめられている未成のもの」の回帰、あるいは反復という問題を考えたのは、ブロッホが最初ではない。たとえば、〔…〕キルケゴールが「反復」を論じた。〔…〕
「反復」とはそもそも、聖書に書かれた主題である。〔…〕アダムとイヴは〔…〕元の楽園に戻ることはできない。楽園は前方に、すなわち「未来」に見いだされなければならない。そして、それがキルケゴールの言う「反復」なのだが、ブロッホが言う「希望」も、それと同じである。〔…〕ブロッホは〔…〕それを社会主義に見出そうとしたのである。むろん、それは通常の社会主義ではない。〔…〕
キリスト教にかぎらず「世界宗教」の根底にある「希望」は、〔…〕社会主義の中でこそ実現される、とブロッホは考えた。過去に中断されおしとどめられた「太古」の道が回復されることによって「未来」の道を開く。すなわち、「太古の道」が、向こうから到来する。ゆえに、彼はいう。《マルクス主義哲学は未来の哲学であり、したがってまた、過去のなかの未来・についての哲学でもある》〔山下肇・他訳『希望の原理』,第1巻,1982,白水社,p.25.〕
〔…〕共産主義は、資本主義の破綻によって必然的に生じるものではないし、また、たんに人間の認識と意志によって実現されるものでもない。そこには、人間の意志を越えた何かが働いている。神学であれば、それは、神の約束、あるいはイエスの再臨として語られるだろう。が、ブロッホは、未来の共産主義を、「太古」からあり且つ中断されていた道が回復されることだと考えた。
では、この・過去に中断されたものが、なぜいかにして回復し「未来」の道を作りだす力をもつのか。ブロッホは、この問いに答えていない。そのような「力」があるというだけだ。彼はそれを「希望」と呼び、その痕跡を人類史における各所に探究するような仕事を続けたのである。なかでも、大著『希望の原理』では、世界史的に宗教、哲学、文芸、サブカルチャーなどを通して、多種多様な「希望」の痕跡を追求した。』
柄谷行人『力と交換様式』,2022,岩波書店,pp.380-382.
プラハのヨゼフォフ(ユダヤ人街)
ナチス・ドイツがオーストリアを併合し、チェコからズデーテン(対独国境地域)を奪い取り、ポーランド侵攻の準備を進めていた 1938年、ブロッホは、アメリカに移住し亡命します。このタイミングは危機一髪でした。ユダヤ人であるブロッホが、難を避けて滞在していたプラハには、ブロッホの渡米と入れ違いにドイツ軍が進駐し、ユダヤ人は絶滅収容所に送られたからです。
その一方で、ソ連では「モスクワ粛清裁判」が行なわれ、ロシア革命以来の功労者たちが次々に陰謀の罪で逮捕され処刑されて行きましたが、それが虚構のでっち上げだということは、知りようがありませんでした。西ヨーロッパの知識人たちも、不審の点を指摘する以上のことはできず、ボルシェヴィズム(レーニン主義)そのものを疑うには至りませんでした。ブロッホもまた、ナチスとスターリンの狭間で揺れるほかはなかったのです。
『象徴的なのは、彼がこの〔ギトン註――『希望の原理』執筆の〕仕事を、1938年アメリカに亡命する時期に開始したことである。それは、通常の意味ではまったく希望のない時期であった。〔…〕しかし、ブロッホのいう「希望」はむしろ、そのような時にこそ見いだされるものであった。
「希望」とは、人が未来に意識的に望むことではない。また、実現すべき何かでもない。それは、いやおうなく、向こうから来る。つまり、むしろ希望がないように見える時にこそ、「中断され、おしとどめられている未来の道」としての希望が到来する。つまり、共産主義は、むしろその実現がとうていありそうもないような状況においてこそ到来する。』
柄谷行人『力と交換様式』,pp.382-383.
亡命したアメリカ合州国で、ブロッホは、ほかのドイツ・ユダヤ人亡命者よりもはるかに苦労しました。彼の名はドイツ以外では知られていなかったうえ、彼の学風はアメリカでは理解されなかったからです。建築士の免許を持っていた妻がウェイトレスで稼いで生活を支え、ブロッホ自身も皿洗いをしていたとの記事があります(本人は否定)。
『ブロッホは、「具体的なユートピア」の、昼の夢の、希望の原理の哲学者であった。彼の思考の中心には、自らを通過して先まで思考する人間がいる。人間の意識は彼の存在の生産物であるだけではない。それはむしろ「余剰 Überschuß」を具 そな えているのだ。この「余剰」はその表現を、社会的,経済的および宗教的な諸ユートピアに、造形芸術に、音楽に、そして昼の夢に見出す。
マルクス主義者として、ブロッホは、社会主義と共産主義に、この「余剰」を実現する道具を見ている。マルクス主義としては特異なのが、彼の形而上学への強い志向である。そのさい、彼の考察の中心に立つのは、「未成のもの das Noch-Nicht-Gewordene」である。それは、われわれの「いま」を特徴づけている。人間が、社会が、「自身の満足できるものになっていない ist noch nicht bei sich angekommen」のは、われわれが未だ欠乏に悩んでいるからである。ところが、その・まだ実現されていない可能性の「意味の宮庭 Bedeutungshof」は、周りをあらゆる存在者が取り囲んでいる。その「宮庭」こそは、われわれをして、「未所有 das Noch-Nicht-Haben」を所有 Haben に、「未存在 das Noch-Nicht-Sein」を存在 Sein に、そして「未だ意識されないもの das Noch-Nicht-Bewußte」を意識されたもの Bewußtes に変換する「道に就かせる」ことができるのだが。』
独語版 Wikipedia「エルンスト・ブロッホ」.

1936年タイ刑執行直前のジノヴィエフのマグショット。拷問のせいで
やつれているのが分かる。ジノヴィエフはレーニンの側近で、レーニン
とともに亡命先スイスから革命中のロシアに帰国、コミンテルン議長等
要職を歴任したが、「第1回モスクワ裁判」で粛清された。
【14】 漂流するブロッホ――
社会主義に「希望の痕跡」を求めて
戦後、ブロッホは東ドイツに迎えられて、ライプチヒ大学正教授の職に就きます。しかし、それが良かったのかどうかわかりません。ブロッホは、『希望の原理』全3巻の刊行を始めますが、第2巻まででストップしてしまいます。ブロッホの「希望の原理」は、「正統マルクス主義」を奉ずる東独当局には、とうてい許容できない異端であったからです。けっきょくブロッホは、1961年「ベルリンの壁」ができる直前に西ドイツに移り、定住します(76歳)。『希望の原理』も、改めて西ドイツの書店から全巻を刊行しています。
『希望の原理』の「まえがき」↓を見ると、あちこちで、ブロッホが東ドイツ当局に迎合したかと思われる記述に出会います。以下では省略しましたが、レーニンから無理な引用をして「正統」を装った箇所もあります。
ブロッホの抑圧された理不尽な思いをしのびながらも、――おそらくは不本意であった――迎合箇所には注意を払いつつ、以下、「まえがき」を読んでいきたいと思います。
『たいせつなのは希望を学ぶことである。〔…〕希望という情動は、自分の外に出ていって、人間を、狭めるどころか広々とひろげていき、内側で、人間をめざす方向に向けさせるものが何なのか、外側で、人間と同盟してくれるものが何であるのか・について知ろうとして、飽くことがない。この情動の仕事は、生成するもの――人間もそれに属している――のなかにとびこんで働く人間を求めている。〔…〕生の不安と恐怖の策動に抗するこの仕事は、それらの〔…〕元凶どもに抵抗する仕事であり、この世界のために役立つものを世界そのもののなかに求めようとする。それはたしかに見つかるのだから。
いつの時代にも、人びとの見た夢はなんと豊かなものだったろう、〔…〕あらゆる人間の生活には、すみずみまで昼の夢が浸透している。そこでは、ある部分はほんの薄っぺらな、無気力な逃避にしかすぎず、詐欺師の餌食ともなるものでしかないが、しかし、もうひとつ別の部分は人をけしかけ、挑発し、現にある悪しき存在に妥協させず、まさに諦めさせることをしない。このもうひとつの部分の核に希望がある。そして、この部分は教えることのできるものである。それは、不規則きわまりない昼の夢からでも、またその夢の狡猾な濫用からでも、取りだすことができるし、埃 ほこり を払って活性化できるのである。〔…〕
考えるとは、踏み越えることである。そうは言っても、現にあるものが隠されたり、見落とされたりしてはならない。それゆえ、本当に踏み越えるということは、けっして前方(Vor-uns)というただの真空状態にただ夢中になって、ただ抽象的に思い描くだけで、はいっていくことではない。踏み越えることは、現に存在し動いているもののなかに媒介されているひとつのものとして、新しいものを把握することである。その新しいものは、解き放たれようとして、新しいものへ向かう意志を極度に要求するけれども。〔…〕来たるべき未来は、恐れられ、あるいは期待されているものを含む。人間の志向にしたがえば、つまり挫折がなければ、それはもっぱら期待を内容とする。希望の機能と内容は、たえずやむことなく体験されている。〔…〕
人間がむちゃくちゃな状態におかれているかぎり、その生活は公私ともに、昼の夢、これまであったよりもよい生活の夢が、隅々まで浸透している。すべての人間の志向は、偽りの状態では、まして本物の状態であればなおのこと、この基盤の上に盛られていく。〔…〕
考えるとは、踏み越えることである。〔…〕具体的に踏み越えることを意識化したことで、マルクスが展開点を画す。しかしその展開点〔つまり、マルクス自身――ギトン註〕には、頑固に染みついた思考の習慣〔既成品だけを考察の対象とする古い哲学の思考――ギトン註〕が、最前線(フロント)のない世界にへばりついている。ここでは、人間ばかりではなく、その人間の希望にたいする洞察も、むちゃくちゃな状態にある。〔…〕あらゆる人間の唯一の率直な特性である願望が、探究されていないのである。いまだ意識されないもの(das Noch-Nicht-Bewußte)、いまだ成らざるもの(das Noch-Nicht-Gewordene)は、すべての人間の感官とすべての存在の地平にいっぱいになっているにもかかわらず、言葉としてすらも、いわんや概念としては一貫して見通されたことがない。
この花盛りな問題領域〔「未意識」「未成」の領域――ギトン註〕が、従来の哲学ではほとんど口もきけないでいる状態である。〔…〕そのあげくに、おそろしく静的な思考が、〔…〕ただくり返し既成のものの話をつけることばかりに終始する。それは〔…〕観察的な知として、もっぱら観察可能なもの、つまり過去』にかんする知であって、それらの過去知が、『成らざるもの(das Ungewordene)の上に、既製品完結篇の〔…〕被いを張りめぐらす。おかげでこの世界は、〔…〕一貫して反復の世界〔…〕となる。それはライプニッツが名づけた〔…〕宿命の宮殿である。〔…〕
カントの道徳意識の要請(Postulat)においては、希望が無媒介に作用するし、ヘーゲルの史的弁証法においては、それが世界を媒介として作用する。それにしても、〔…〕彼らすべてには、ある中断されたもの、まさに省察によって中断されてしまったものがある。〔…〕つまり、既存のものが昇りくるものを圧倒し、既成性の集合体が、未来、最前線、新事象といったカテゴリーを完全に妨害している。
したがってユートピアの原理は、古代的神話的世界においてもそこからの脱出(Exodus)にもかかわらず、また都市的合理主義的世界においても爆発的な弁証法にもかかわらず、ついに突き破って出現するまでには至らなかった。』
ブロッホ,山下肇・他訳『希望の原理』第1巻,1982,白水社,pp.17-23.
ブロッホは、「ユートピアの原理」という新機軸を導入して、従来の哲学を大きく塗り替えようとしているのですが、そのさい、「正統マルクス主義」哲学(けっきょくはヘーゲル哲学の亜流)もまた、従来の固定的哲学の一翼としてブロッホの前に立ちはだかることになります。そこでブロッホは、自分の志向する哲学こそが「マルクス主義哲学」にふさわしいと主張することになりますが、その急進姿勢を進めていくと、かえって「マルクス主義」の教条に、みずから同化してしまうことになる。
そういうジレンマを抱えています。
『ただ世界を変えることをめざし、変革の意志を告知する思考だけが、未来(われわれの前方にあって閉ざされていない成立〔ギトン註――しつつある〕空間)に、当惑としてでなくかかわり、過去に、呪縛としてでなくかかわる。だから決定的なことは、意識的な理論-実践としての知だけが、生成するものにかかわり、そのなかで決定しうるものにかかわるのであり、反対に、観念的な知は、定義通り(per definitionem)既成のものにしかかかずりあいえない、ということである。
マルクスがはじめて〔…〕変革のパトスを、観察と解釈をあきらめない理論の第一歩としたのである。未来と過去のあいだを頑固に区別することは、かくしておのずから崩れ去り、未成の未来が過去のなかに見えるようになり、復讐され継承され、媒介され実現された過去が、未来のなかに見えてくる。
孤立的にとらえられ固定された過去は、〔…〕物象化された事実でしかない。〔…〕そこには、事実が生成するものでありたえず走り続けている過程であるという意識が欠けている。〔…〕
マルクス主義哲学は、生成することと昇りくるものについにふさわしく対応する哲学として、過去の全体をもその創造的広がりにおいて知っている。〔…〕なお生動して、まだ清算されていない過去のほかには、およそ過去を知らないからである。マルクス主義哲学は未来の哲学であり、したがってまた過去のなかの未来についての哲学でもある。』
山下肇・他訳『希望の原理』第1巻,pp.24-25.
【15】 エルンスト・ブロッホ――
「ユートピア的機能」の系譜
「まえがき」のなかで、この著全体の構想を述べているのが、↓つぎの部分です。話はやや具体的になるので、これまでよりもイメージを持ちやすいかもしれません。
『この書物が取り扱うのは、既成の日を乗り越えていく希望にほかならない。この著作の5つの部分のテーマは〔…〕よりよい生活についての夢である。それらの夢の無媒介な〔…〕特徴と内容が、広範囲に取りあげられ、探究され、吟味される。そしてその道は、小さな白日夢(Wachtraum)を越えて強力な白日夢へ、動揺し悪用されやすい白日夢を越えて、しっかりと厳密な白日夢へ、移ろいゆく空中楼閣を越えて、まだ欠けているが必ず現れずにはいない唯一のものへと通じていく。したがって、まず平均的な昼の夢から始められ、青年期から老年にいたるまでの夢が任意に無造作に選び出される。それが第1部。〔…〕
第2部のテーマはユートピア的機能とその内容である。論述は、このユートピア的機能とイデオロギーとの関係、祖型との関係、理想や象徴や、最前線および新事象(Novum)、無および故郷というカテゴリーとの関係、〈いま・ここ〉という根源的問題との関係、を探究する。』
山下肇・他訳『希望の原理』第1巻,pp.27,29.
「いま」という瞬間は、意識したときにはすでに過ぎ去っています。この「いま」という・とらえどころのないものを捉えること。「ユートピア」は、そこに関わっているというのです。
『人間の中の未だ意識されないものは、こうしてどこまでも世界のなかの未だ成らざるもの、未開発のもの、未だ顕在していないものに属する。未だ意識されないものは、未だ成らざるものと連絡し、相互作用をおこなう。より特殊的には、歴史と世界のなかに浮上しつつあるものと連絡し、作用しあう。そのばあい、先取りする意識の探究は、原則的には、願望され先取りされるよりよき生活の、本来的な相次いで生じる鏡像、さらには模写が、心的・実体的に理解できるものとなるように役立たなければならない。〔…〕
第3部の移行は鏡の中の願望像を示す。その鏡は、ある種の美化を行なう鏡であり、往々にして支配者が、弱者の抱く願望を、どのように願望するかを再現するにすぎない〔「弱者はこのように願望してほしい」と支配者が望むような・従順な願望を表現していることがしばしばだ――ギトン註〕。しかし、その鏡が民衆に由来するものであれば、童話〔=「メールヒェン」。訳語の違い――ギトン註〕でははっきり見えて素晴らしいように、事情はたちまち完全にすっきりしたものになる。鏡に映った・しばしば規格型となった願望が、本書ではこの第3部をなしている。
これらの願望のすべてに共通なのは、〔…〕華美なものへの欲動である。衣裳の魅力、まばゆい陳列品がこれに属する。しかしまた、さらに、童話の世界、旅における美化された遠方、舞踏、映画という夢の工場、範例提示の演劇がある。これらはたとえば娯楽産業のように、よりよい生活を現前して見せたり、エッセンスとして示す生活をありありと目前に描きだす。
ところで、こうした・眼前に描きだすことが、自由な・考えぬいた構想へと移行するとき、はじめて人は本来の、つまり計画あるいは見取図としての・ユートピアに至ることになる。これが第4部の構成であり、歴史的に豊富な・単に歴史的にとどまらない内容でみたされる。この部は、医学的、社会的、技術的、建築的、地理的ユートピアにまで、絵画と文学の願望風景にまで、拡大される。〔…〕ここには、先取り的に形成され、美的・宗教的に実験された本質への眺望が、かわるがわる片鱗を見せる。〔…〕その眺望は、それぞれの階級的制約に応じてさまざまに具体的であるが、いわゆる様式のなかにあらわれるそれぞれの〔…〕ユートピア的根本目標、この・イデオロギーを超えた「剰余」は必ずしも常にその社会もろとも没落することはない。〔…〕すべての芸術は、完成性のシンボルへ、ユートピア的本質をもった終局へとかりたてられる現象に満ちみちた姿をみせる。』
山下肇・他訳『希望の原理』第1巻,pp.30-31.
以上が「第4部」。つぎは、最終の「第5部」を解説します。予告されていた〈いま・ここ〉への大胆な歩みが遂行されます。
『たとえば技術的な願望像や計画においては、ユートピア的な思念に値するものはほとんど注意されることがなかった。』ユートピア的志向が存在するのに、それが見過ごされてきた重要分野が、『建築の領域である。』そこでは、『より美しい空間を形づくり、模写し、予示する』という・まさにユートピア的活動が行なわれてきた。『ユートピア的なものは、〔…〕絵画や詩文の情景や風景においても、未発見のままにとどまっていた。〔…〕
けれども、これらすべての分野において、内容は変ってもユートピア的機能はまさに活動している。〔…〕人間のファンタジーの充溢こそまさしく、世界じゅうのその相関物もろとも〔…〕、ユートピア的機能によるよりほかにはまったく探究も明細目録作成もできないのである。同様にまた、弁証法的唯物論なくしては精査吟味することもできない。〔…〕すべての芸術作品に刻みこまれた、この人物や状況〔典型的人物と極限的状況――ギトン註〕についての本質的洞察は、〔…〕いずれも既存の現実を越える可能性を前提としている。〔…〕
究極の意志は、真に現在的でありたいという意志である。すなわち、生きられている瞬間がわれわれのものとなり、われわれがその瞬間のものとなって、〔…〕人間は人間そのものとして〈いま・ここ〉の中へ入ろうと望み、一刻の猶予もなく、疎隔もなしに、みずからの十全な生活へ入っていこうとする。真のユートピア的な意志は、はてしない努力ではまったくなくて、むしろ、おのれの情態と現-存在のむきだしの直接的なもの、したがって何ものにも煩わされぬありのままのものが、最後的に媒介され、照らし出され、実現され、幸福かつ適切に実現されたものとしてあることを欲する。これこそが、ファウスト構想の「待てしばし。おまえ〔=「いま」という瞬間――ギトン註〕はいかにも美しい」で考えられているユートピア的極限内容である。構成の部〔第4部――ギトン註〕における客観的な希望の諸像は、実現された人間そのものの像、そうした人間と完全に媒介された環境世界、すなわち故郷の像に向って、不可避的に突き進む。この志向の測量を試みるのが、最後の第5部、同一性である。〔…〕そこで、人間的に限界を踏み越えていく文学上の諸人物が登場する。ドン・ジョバンニ、オデュッセウス、ファウスト。このファウストは、世界遍歴のユートピアの中でまさしく完全な瞬間への途上にある人物である。ドン・キホーテは、夢のモノマニア、夢の深みの中で警告し要求する。さらには音楽が、きわめて直接的な、きわめて遠いかなたにまで触れていく表現線の呼びかけ、描出として、浮かび出てくる。』
山下肇・他訳『希望の原理』第1巻,pp.32-34.
【16】 エルンスト・ブロッホ――
「童話」「冒険物語」「盗賊小説」
以上、「まえがき」を見てきましたが、最後まで話は抽象的で、隔靴掻痒の感が否めません。本文に移って、私たちになじみのある「童話(メールヒェン)」や「悪漢小説」の考察を、少し覗いておきたいと思います。
『童話〔=「メールヒェン」――ギトン註〕の主人公は、幸せな生活をひたすらじっと待っているほど大人しい者ばかりではない。彼らは幸せを見つけるために旅に出て、野蛮にたいして知恵で立ち向かう。勇気と計略が彼らの身を守る楯であり、知力が攻撃の槍である。〔…〕
知力をはたらかせた計略は、弱者に与えられた人間らしい部分である。童話は〔…〕、困難の克服においてはいつも賢明である。同時に、童話のなかで勇気と計略が成功するしかたは、実生活のばあいとまったくちがっている。〔…〕このばあい所与の桎梏を超えて虚構を語るものは、つねに、すでに存在する革命分子なのである。農民がまだ農奴の身分におかれていたときには、このようにして、童話の世界の貧しい若者は王さまの娘を征服した。〔…〕
しかし童話は、今日の世界の楽園所有者〔支配者・有産者――ギトン註〕が楽園とはこんなところだと言っても、けっして受けつけない。だから童話は反抗的であり、火傷を負った子供のように用心深く、抜け目がない。豆の木をつたって空へ登ることはできるが、そこに見られるのは、天使たちがお金を臼で挽いている姿である。〔…〕
大入道が片手で石を握りしめると、水がぽたぽた滴り落ち、また、石を放り投げると、ほとんど見えなくなる〔…〕しかし、仕立屋は大入道に負けていない。石のかわりにチーズを握りつぶしてぐしゃぐしゃにし、それから小鳥を空中高く放り上げる〔…〕童話のなかでは悪魔自身が騙される。〔…〕
童話は行為の代償をなすものではない〔正義の味方が超人的な力を発揮する・支配者お薦めのドラマとは、そこが違う――ギトン註〕。むしろ、童話のりこう者は、自分を偉そうに見せない術を心得ている。大入道たちの力はどこかに穴のあいた力として描かれ、その穴を通り抜けて弱者が勝利できるしかけである。〔…〕
願いごとをかなえてくれるきわめて便利な道具が、弱者に魔法の力を貸している。グリム童話の『食卓よ、ごちそうを出せ』と『金貨を産むロバ』と『棒よ袋から出よ』〔…〕『アラジンと不思議なランプ』こそ、手もとにないものを手に入れる〔…〕点で、もっとも特徴的である。〔…〕ランプは、主人の欲するものならどんな物でも無限定に運んでくる。〔…〕
遊戯や魔法は童話の世界ではこのようにことごとく自由自在であり、願望は命令になり、労せずして物事がなしとげられ、時間のへだたりも空間のへだたりもなくなる。〔…〕
このようにして、技術や魔法を用いた童話は、〔…〕必要やむをえないときにのみ所有にかかわりをもつのであり、通常は、物を・いつでも手近に存在している実用品に変えることを目的としている。』
山下肇・他訳『希望の原理』第1巻,pp.473-477.
「打ち出の小槌」のような・童話に出てくる魔法の道具は、一見すると、金持ちになりたい願望を表現しているかのように見えます。しかし、もしそうなら一寸法師は、ほかの願い事をせずに、ただひたすら「カネを出せ」と言って振りつづければ、たちまち億万長者になるはずです。しかし、童話の主人公は、決してそういうことをしません。童話の主人公が望むのは、金持ちになることではなく、必要なものをいつでも労せずして手近に調達すること、つまり、貧乏なままで満ち足りた生活をすることなのです。これは、《致富》とは正反対の理想です。むしろ、「誰もが必要に応じて取る」という共産主義の理想に近い。
そして、まったく努力しないで手に入れる・という点で、二宮金次郎のような、あるいはプロテスタントのような《致富》の勤勉倫理とも正反対です。
これは、西洋の言い方でいえば「愚者の楽園 paradise of fools」です。「愚者の楽園」とは、地獄の処罰も効かず、天国に入れるわけにもいかない愚者を死後に行かせる場所という否定的な意味で・ふつうは言われるのですが、ブロッホは、これを肯定的な意味で使っています。童話のめざす理想は「愚者の楽園」だというのです。
『こうした童話の志向するところ〔…〕それは愚者の楽園である。そこでは丸焼きの鳩が、いつでも手に入る。そうなると、もはやたんなる童話をこえて、〔…〕よりよい社会や国家についてのお伽話の領域に入りこんでいるようにも思われてくる。』
山下肇・他訳『希望の原理』第1巻,p.478.
「童話」に続いて、もっと野性味のある「悪漢小説」や「冒険譚」の類いに眼を向けます。
『めったに童話のたぐいとは見なされない一種の童話、いわば波瀾万丈の無法者童話がある。それはほとんど評価されていないが、その理由は〔…〕支配階級が入れ墨をしたヘンゼルとグレーテルなど好まないからである。波瀾万丈の童話とは、すなわち冒険物語であり、冒険物語は今日、民衆小説としてもっともよく生命を保っている。〔…〕
民衆小説は例外なく童話的特徴を示している。すなわち、民衆小説の主人公は、〔…〕幸せが自分のふところに転がりこんでくるまでじっと待ってはしないし、また、〔…〕投げ与えられた財布を拾うように幸せをつかんだりもしないのである。〔…〕彼らはいつも、民話の貧乏人や勇敢な人物の仲間であり、〔…〕読者と同じで何も失うもののない民衆小説の主人公には勇気がある。そして、ブルジョワのろくでなしの肯定的な話〔金持ちの放蕩息子が冒険のすえ成功する話――ギトン註〕が人気を集める。彼は家出しても途中で横死することなく、帰国する時には、勝利の印の棕櫚の葉や刀剣をもち、人間のうじゃうじゃしているアジアの町々の匂いをあたりにふりまく。民衆小説の夢は、二度とふたたび日常生活へ戻らないということであり、めざすところは、幸福、愛、勝利である。
冒険小説がめざす栄光は、〔…〕金持ちとの結婚などによって獲得されるものでなく、夢のオリエントへと積極的に船出していくことによって獲得される。〔…〕俗物に反抗するパトス、20歳にしてすでに墓碑銘のきまるような人生に抵抗し、暖炉の片隅や中庸主義に抵抗するパトスもまた生まれてくる。こうして、無法者童話の真のアウラ、たとえば「暑さと寒さ、嵐と貿易風、船や島々といろんな冒険、置き去り人に宝物そして海賊」のスティーヴンスンの世界のアウラが成立する。
そしてこのジャンル全体には、〔…〕文学的にデリケートな表現など伴わずに現れてくる場合にはいつも、ならず者の匂いがする。この匂いには二重の意味がある。ひとつはクー・クラックス・クランやファシストの匂いであり、彼らにとってこの匂いは特別な刺激剤になることさえある。
だが同時に、このならず者の匂いは、安逸をむさぼるブルジョワジーが、貧民の焚くあまりにも多くのかがり火に〔…〕抱く不審の種でもある。すべての冒険物語は、「祈れ、そして働け」という道徳を打ち破る。祈りのかわりに呪いが横行し、労働のかわりに海賊船、すなわち権力者』から『給料など貰っていない狙撃兵が現れる。盗賊たちのロマンティシズムは、かくしてもうひとつの顔、むかしから貧しい民衆に受けている顔をあらわす。〔…〕賊とは、支配者と相容れない者のことであった。しばしば賊の敵と民衆の敵は共通していたし、賊はまた農民のなかに拠点を持っていた。それゆえイタリア,セルビア,とくにロシアの民間伝承が、盗賊について官憲の報告とは違った評価を伝えている〔…〕シラーの『群盗』〔…〕には、未熟ではあるが嘘偽りのない革命の代替物がある。そしてそれは、民衆小説以外のどこにも表現されえないのである。〔…〕シラーという民衆小説の真の天才が、』もっと『民衆小説を書き続けていてくれたらと思う。
クー・クラックス・クランとファシズムは、民衆小説を短絡的にとらえて、犯罪と野蛮だけをよみがえらせる。しかし、野蛮な無法のなかにある非凡な目標、すなわち投獄と解放、竜退治、乙女の救出、巧みな術策、突破、復讐――これらすべては、自由とその背後にある栄光のためにこそあるものなのだ。ファシズムではなく、まだロマン主義的であったころの革命的行為が、この種の生き生きした民衆小説となったのである。
したがって 1789年〔フランス大革命の勃発年――ギトン註〕の直前直後には、シラーの『群盗』のほかにも、救出童話ともいうべき救出劇が現れた。〔ギトン註――スティーヴンスンの冒険小説『宝島』の〕洞窟の中の宝物のように、囚人が掘り起こされた。〔…〕『フィデリオ』の原作とトランペットの合図は、それらを描く民衆小説がなければ存在しないだろう〔…〕『フィデリオ』の筋書きは、〔…〕きわめて尖鋭な爆発的な民衆小説であり、〔…〕深い地下牢、ピストル、合図、救出、これらはその後の高級文学では決してこのような形では〔…〕現れないが、この世に存在する緊張のなかで最も強烈なもののひとつ、闇と光の緊張を生み出しているのである。〔…〕
童話も民衆小説もすぐれて空中楼閣的であるが、しかし条件の良い空中に立つ楼閣なのであり、〔…〕空中楼閣は正しいのである。』
山下肇・他訳『希望の原理』第1巻,pp.490-493.
ベートーヴェンのオペラ『フィデリオ』の「トランペットの合図」というのは、↓こちらの演奏を聴いてみてください。「序曲」冒頭の躍動的なテーマのあとで、トランペットの和音が、静かにゆっくりと鳴り渡る。夜明けの空を思わせる透明な描写です。ブロッホはこれを、「ユートピア志向」の表現として、とりわけ好んで聴いたそうです。
よかったらギトンのブログへ⇒:
ギトンのあ~いえばこーゆー記
こちらはひみつの一次創作⇒:
ギトンの秘密部屋!