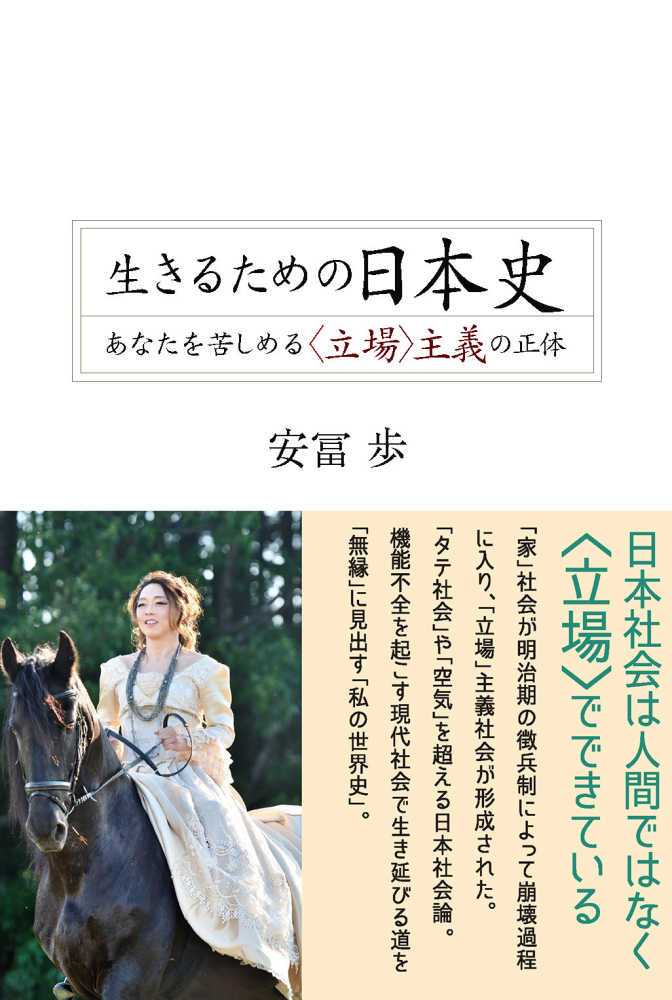『伴大納言絵詞』(1177年?) 〔上〕炎上する応天門
〔下〕驚いて見上げる見物人
【38】武装する中世の村
前回に引きつづいて、勝俣鎮夫氏の論文から、中世の人びとの生き方を取り上げます。人びとと言っても、武将や教祖や有名な文化人ではなく、なんでもない農民や下級武士が中心になります。というのは、時代の人びとの心性の「基層」は、その人たちにこそあるからです。
『鎌倉時代のなかごろの 14世紀ごろ、近畿地方を中心に、「惣(そう)」とか「惣村」とよばれる、農民が共同して生活する非常に強い結束をほこる村が各地にあらわれてきます。
それ以前は、農民たちの生活を守る力は主として親類などの血縁的なつながりであったのですが、その血縁社会の結合をこえて、同じ地域で共同生活をするつながりの場としての「村」がつくられたのです。
そして、15世紀から 16世紀の戦国時代には、このような村が、都市で町人たちがつくった〔…〕「町」とともに全国的にひろがっていきました。』
勝俣鎮夫『戦国時代の村の生活』,1988,岩波書店, p.48.
『中世成立期から始まった大規模開墾が鎌倉後期にはだいたい落ち着いて人々の定住性が高まり、南北朝・室町時代には近世、近代にまで続く集落が誕生していたことが明らかになっている。』
榎原雅治『室町幕府と地方の社会』,2016,岩波新書, pp.iii-iv.
16世紀初めの「入山田村」。 「惣村」と言っても、町のようにぎっしりと家が
立ち並んでいるわけではない。数軒の家がまとまって柵で囲まれた「垣内(かいと)」
をつくり、「垣内」のあいだには畑があった。村の最高所には惣鎮守の「滝宮」
がある。日常の農作業は「垣内」の共同で営み、田植え、灌漑などは村総出で
行なった。 勝俣鎮夫・文,宮下実・絵『戦国時代の村の生活』
『日本の村は、その4分の3ぐらいが室町時代に出発点をもっている。〔…〕現在われわれが見ている普通の集落のあり方、多くの家が集まって集落を形成しているような「集村」ともいうべきタイプの村は、 12世紀あるいは 13世紀のはじめのころの集落の発掘では確認できないのだそうです。
そのころの集落を〔…〕あえていえば「散村」とでもいえるような形態で、現在の集落の形態とはだいぶちがう〔…〕
近世の村につながる、いわゆる「惣村」といわれる集村が生まれてくるのは、14世紀後半から 15世紀と考えられています。』
網野善彦『日本の歴史をよみなおす(全)』,2005,ちくま学芸文庫, pp.15-16.
このように、地域的なまとまりとして成立した中世の「村」は、どのように運営されていたのでしょうか? 「惣村」を特徴づけているのは、村人の固い結束と独立性、そして自ら武装して治安と防衛にあたる自力救済の精神です。崩壊しつつある朝廷・公家の権威と、アナーキーな新興武士の権力が争い合うはざまにあって、農民たちが村の生活を維持するには、自分たちも武装して対処するほかはなかったのです。
竹槍で守護大名の軍勢と戦う村人たち 宮下実・絵『戦国時代の村の生活』
『惣村は宮座と呼ばれる、その地域の神社の祭りなどに奉仕する集団が中心となって成立しました。〔…〕村の惣鎮守(村全体のための神社)〔…〕は、村人たちの寄合(よりあい)〔…〕が開かれる場であり、〔…〕境内は村の広場の役割をはたしていました。
村の〔公的な――ギトン註〕仕事をする村人は〔…〕15歳から 60歳の成年男子にかぎられていました。〔…〕宮座に加入して仕事をした年限の長さによって、老(おとな)・中老・若衆(わかしゅう)にわけられていました。老(おとな)は、村の指導者の地位にあり、村の運営〔…〕にあたり、〔…〕若衆は、村の力仕事〔用水の修理など――ギトン註〕をまかされて、祭りをとりしきったり、村の治安をまもったりしましたが、そのほか重要な役割として外から侵略してくる勢力から村を防衛する役割をつとめていました。
〔…〕この村は、江戸時代の村や現代の村のように行政単位としての村ではなくて、農民たちが自分の生活を守るために自分たちでつくりあげた共同の集団であり、集団としての独立性と自治性が特徴でした。村の重要な問題はすべて、村人の参加する村の寄合〔…〕にかけられて決定し、その決定にもとづいて、村人たちが共同で行動したのです。』
勝俣鎮夫『戦国時代の村の生活』,1988,岩波書店, pp.48-51.
勝俣氏が企画し、文章を書いた・この歴史絵本は、戦国時代の惣村、和泉国日根野荘日根野・入山田村(現・大阪府泉佐野市)の1年間を、荘園領主の日記にもとづいて描いたものです。そのなかに、村で起きた犯罪の処罰を書いている箇所があります。
当時、この村では、村が備蓄している宮座のコメなどが盗まれた場合、疑いのある村人を、「盟神探湯(くがたち)」という古墳時代と同じ神判にかけて犯人を決めていました。煮え立った湯に手を入れて、やけどすれば犯人、しなければ無罪。しかも処罰はたいへん厳しく、盗んだものの量・価値にかかわりなく死刑でした。
「クガタチ」 宮下実・絵『戦国時代の村の生活』
『このごろ川にさらしてある村の人たちの大せつなワラビ粉が夜中にときどきぬすまれるので、若衆が見張りをしていると、千代ちゃんのお母さんがぬすむところを見つけた。おこった村の人たちが、みんなで家におしかけて、千代ちゃんのお母さんと兄さんを殺してしまった。〔…〕
むかしから、日本人は他の民族の人びとより、ぬすみをひどくきらって、ぬすびとに対してきびしい罰をくわえました。戦国時代に来日したキリスト教の宣教師も〔…〕おどろいています。〔…〕
この時代、村人たちが村内の秩序をまもるため、村のなかでおこった犯罪を自分たちで処罰することがおおく、この場合、ぬすびとに対しては死刑が一般的でした。
ききんで、食べるものがなくなった入山田村の村人は、最後の食べ物であるワラビの粉を川でさらして、これを少しずつ食べて生きていましたが、そのワラビ粉もない人びとが、夜中にこれをぬすむ事件がしばしばおこりました。自分たちの最後の食べ物をぬすまれた人びとの怒りははげしく、そのぬすびとだけでなく、その家族も殺すという制裁をくわえました。』
勝俣鎮夫『戦国時代の村の生活』,1988,岩波書店, pp.40-41,55.
山でワラビの根を掘る。 ワラビの根を掘り起こして、長時間、水に晒すと、デンプン
の粉が取れる。ワラビ粉(わらび餅)は、とても腹の足しになる代物ではないが、
飢饉時の救荒食としては重要だった。 宮下実・絵『戦国時代の村の生活』
勝俣氏は、「むかしから、日本人は他の民族の人びとより、ぬすみをひどくきらって、ぬすびとに対してきびしい罰をくわえました。」と書いておられますが、この点については私は疑問です。というのは、古代、あるいは古墳時代にまで遡ると、つぎのような史料があるからです:
『其の法を犯すや、軽き者は其の妻子を没し〔奴隷とし〕、重き者は其の門戸及び宗族を滅す。』
『魏志倭人伝』
『其の俗、殺人・強盗及び姦は皆、死。盗は贓〔盗品〕を計りて物を酬(むく)ひ、財無くば身を没して奴となす。』
『隋書倭国伝』
『魏志倭人伝』は3世紀、『隋書倭国伝』は7世紀初めの日本の状況を述べています。『魏志倭人伝』は、魏の使節が北九州まで来て視察した報告をもとにしていると思われ、『隋書』のほうは、半年以上にわたって北九州~瀬戸内を視察し、ヤマトに赴いて聖徳太子と推古天皇に謁見した裴世清の報告書に基づいていますから、いずれも信憑性が高いのです。3世紀の処罰は、軽罪ならば妻子を奴隷とする。7世紀には、殺人などは死刑にするが、窃盗は、盗品の価値に相当する物を返させる。返す資力がない場合には本人を奴隷とする、とあります。盗人は、死刑ではなかったのです。
そればかりか、この室町末期~戦国時代になっても、殺さないで奴隷にする処罰や、罰金として布を徴収する処罰は、各地の古文書で実証されています。殺人犯を、奴隷にする処罰で済ましているものもあります〔石井進「身曳きと “いましめ”」, in:網野善彦 et al.『中世の罪と罰』,2019,講談社学術文庫,pp.176-188.〕。それらはあくまでも、領主の行なった「検断」(処罰)の文書ですが、村農民の「自検断」の場合も、勝俣氏が考えるほど厳しかっただろうか?‥死刑以外の、罰金(罰物)や奴隷化の刑罰もあったのではないか、という気がします。
キリシタン版『どちりいな きりしたん』 東洋文庫・蔵
宣教師の報告書は、犯罪を憎む気持ちが強いイエズス会の神父たちですし、日本人を、布教の対象にふさわしい善良な人びととして法王庁に印象づける意図があったかもしれません。アフリカ、アジアに進出した初期のヨーロッパ人には、現地人を、文明の堕落に染まっていない無垢の野蛮人として理想化する風潮がありました。
ですから、宣教師の報告書が、そのまま当時の日本の一般的な状況だったとは言えないかもしれないのです。
だとすると、「日根野荘」で行なわれていた厳しい処罰は、戦乱と近畿農村の「惣村」化のためにそうなっていたとも考えられます。「惣村」化によって、村人の団結は固くなると同時に、内部統制は、これまでになく厳しいものになっていたのではないでしょうか。
それにしても悲惨なのは、両親と成人した兄弟が、全員「連座」で処刑された場合に、後に残された幼い子どもたちです。次節で説明するように、盗みにしろほかの犯罪にしろ、村から犯人が出たときは、犯人が住んでいた家を、「穢(けが)れたもの」として必ず焼き払いました。家族も家も失った子どもたちは、誰にも引き取ってもらえず、泣き叫びながら餓死したり、獣の餌食になるのがふつうだったと思われます。
『親も兄も殺されてしまい、家も焼かれてしまった姉と弟は、寝るところもなく、夜じゅう泣きさけんで村じゅうを歩きまわり、人々の助けを求めました。しかし、この時代、犯罪をおかすと、〔…〕親類なども責任をかぶせられる縁座、近所の人も責任をかぶせられる連座というきまりがあり、人びとは、縁座・連座〔…〕をおそれて、このきょうだいを助けませんでした。
〔…〕弟をつれた千代ちゃんは、今日一日じゅう泣きながら、親類の家をまわっていた。村のきまりで、〔…〕みんな引き取ってやれないのだ、とぼくのお母さんが言った。夜になって、うちにもやってきたけれど、お母さんはふたりを入れなかった。お母さんも泣いていた。ぼくは、千代ちゃんたちの泣き声が耳にのこって、いつまでも眠れなかった。』
勝俣鎮夫『戦国時代の村の生活』,1988,岩波書店, pp.55,42-43.
この絵本のケースでは、見かねた領主の九条政基が、千代の親戚の家に口をきいて、引き取らせています。九条政基は、関白(従一位)まで勤めた当代最高位の公家でしたが、戦乱で領地が近隣武士に取られてゆくので、領地の「日根野荘」に移住して直接、所領経営をして守っていたのです。千代姉弟は、たまたま政基のような教養ある公家が近くにいたので救われた、珍しいケースだったかもしれません。
しかし、一般には、このような問題は村人たちには解決する手立てがなく、領主のような、「村のおきて」を恐れなくてよい “支配階級” が介入してはじめて救われた――ということには、注意してよいと思います。支配階級は民衆を抑圧する;救済する場合があるとしても欺瞞だ、というような見方は、けっして万能な歴史観ではありません。
泣き叫ぶ みなしご 宮下実・絵『戦国時代の村の生活』
【39】「家」の処罰――「住宅検断」
「入山田村」のように、村の中で起きた犯罪は、事実上「惣村」の自治によって処罰されることが多かったと思われますが、公の法体系の上では、「検断権」(犯罪を捜査し裁判・処罰する権限)を持っていたのは領主でした。
とはいえ、一般に中世の領主は、自分が被害を受けた場合を除けば、犯罪の捜査・処罰には不熱心でした。領主による処罰は追放刑が多く、殺人犯人であっても、他の領主の領地に逃げこんでしまえば、追いかけていくことはありません。そもそも領主の屋敷には、犯人を捕らえておく牢屋などなかったのです。
「惣村」の村人による処罰が、基本的に死刑であったのとは対照的です。
しかし、どんなに不熱心な領主であっても、かならず行なったのが、「家の検断」でした。この場合の「家」とは、家族でも、一族の「お家」でもありません。犯人の住んでいた建物と、垣根で囲まれたその付属地を合わせた家宅が、処罰の対象となって焼き払われたのです。人的な「お家」と区別するために、日本史学者は「住宅検断」と呼んだりします。
犯人の住居ばかりではありません。他の領地から逃げてきた犯人が、たまたま居留した「家」も、「寄宿の咎(とが)」として「検断」の対象になりました。また、犯人だけでなく、被害者の「家」も「検断」されたのです。他領で殴られた被害者が逃げてきて死亡した茶屋が、略式で「検断」された例もあります。
「検断」の方法は、火を放って焼き払うのが本来のやり方であったと思われ、多くの場合に、家が垣のうちもろともに焼かれています。後代(戦国時代)になると、事情によっては、取り壊すだけ、あるいは、竹葉などで囲んで立入禁止にする、という形式的な方法もとられました。
犯人が、みずから自分の住居に火をつけて境外に退去してゆく「自焼没落」を行なった場合には、「検断」(処罰)は完了したと見なされました。
逆に、「検断」の対象である「家」と見なされるには、条件がありました。地方によって多少違いますが、「かまど」「(屋根の頂上の)棟(むね)」「門」「垣(かき)」「壁」を備えていなければ「家」とは見なされない。なかでも「かまど」は「家」の必須要素でした。これらが無い「ワラ屋」などに犯人が住んでいた場合には、無関係な他の家を買い取って、その家を代わりに燃やしたり、地域によっては(法隆寺門前など)、犯人の居た場所で法螺貝を鳴らして「検断」としています。
これらの事実から見ると、住宅の「検断」は、犯罪によって生じた「穢(けが)れ」を「祓(はら)っ」て、村内を浄化することが目的であったと考えられるのです。そもそも犯罪の「処罰」ということが、中世までは、「穢れを祓う」ことに主眼があったと言ってもよい。現在の私たちが考える「処罰」とは、相当に異なったものだったと言わなければなりません。
「家」の「かまど」の火に宿る「かまど神」は、祖先の霊にほかならないと考えられていました。門・垣根・棟や庭の竹木にも「屋敷神」が宿っているとされ、これらの部分をふくんだ「家」全体が、「生命あるもの」だと考えられました。
かまど 岩手県立博物館
『極端に単純化すれば、建物としての家は、魂の宿る体に相当するものと考えられていた。〔…〕
自焼没落〔犯人が自分の家を焼いて退去する「自検断」――ギトン註〕の習俗は、自分の家を焼き煙をあげることにより、家(住宅)自体を他界の祖先神へ送り返すことを狙った行為で、〔…〕目的は、祖先神への供犠にあった〔…〕
検断役人が犯罪者の家を強制的に焼き払い、煙を上げる住宅検断は、家の霊を現世から他界へ永久に追放し、その現世での住み家である家を完全に消滅させることを目的としていた』
勝俣鎮夫『中世社会の基層をさぐる』,2011,山川出版社, pp.40,42-43.
このような呪術的色彩濃厚な「検断」は、何に由来するのか? ‥‥迷信深い王朝貴族の観念が影響を及ぼしているのか? それとも、民衆がもともと持っていた観念なのか? ‥‥あとのほうではないかと想像されるのは、次のような事件が記録されているからです。
1504年正月に、領主九条政基の居所(長福寺という入山田村内の寺)に招かれた隣村の者が、列席者の腰刀を盗む事件が起きた。
『政基は、犯人の源三郎宮内を処刑したが、その家が番頭〔領主が村民をグループに分けた「番」のカシラ。有力な農民を任命して、加地子(年貢)等を納める責任者とした――ギトン註〕をつとめる家で、公事(くじ)〔領主の公務――ギトン註〕を負担する公事屋であったため、住宅検断を行なわず家を残し、宮内の子につがせることにした。ところが、その後、村人たちは、この源三郎宮内の家に乱入し、残された妻子3人を殺し、〔…〕家を焼き払ってしまった。〔…〕
この領主の検断処分にそむいて行なった村人たちの自検断に対して、領主政基はこれを処罰することはできなかった。そして、このような地下人(じげにん)の自検断として行なわれた盗人の家の住宅放火は、決して例外的なことではなかった。〔…〕〔ギトン註――村内の〕制裁手段として慣習化していたのである。』
勝俣鎮夫『中世社会の基層をさぐる』,2011,山川出版社, p.35.
つまり、農民から見れば、領主が家の「検断」を行なうのは、いわば代行であって、領主が行わなければ、農民はみずから、「家を残す」という領主の決定に反してでも「検断」を実行したのです。そして、この「日根野荘」のケースで、村民が「家」を焼くだけでなく、犯人の家族をみな殺しにしていることは、私たちを戦慄させます。
ここから考えれば、犯人や縁者に対する村民の処刑も、「住宅検断」と同じく、「穢れを祓う」意識を伴なっていたと想像されます。そう考えて初めて、「クガタチ」のような神判が中世までつづけられた理由もわかります。“神の秩序” を回復する行為であれば、除くべき対象は、神に選んでもらわねばなりません。そして、領主の「検断」執行は、村人による「自検断」の行き過ぎを抑える意味もあったと考えられるのです。
以上、「住宅検断」について、やや詳しく述べてきましたが、読んで暗澹たる思いになったかもしれません。しかし、暗澹たる側面をあえて省略せずに、勝俣氏の著書にまで遡って引用してきたのは、それが、本日後半から次回にかけて述べる「一揆」や「無縁」と深くかかわるからです。安富さんは、暗い面をあまり書いていないのですが、そこをやり過ごしてしまっては、人びとの解放につながる「一揆」も、日本の古代・中世に存在した “自由” の現れというべき「無縁」も、一面的に理解することになってしまうと思います。歴史は、「良い」面も「悪い」面も見なければ、解明したことにならない。私はそう思うのです。
「一味神水」 惣鎮守の広場に集まって「一揆」をむすぶ村人たち。
全員が菅笠と覆面で変装している。うしろで、宣誓の鰐口を鳴らしている。
【40】「一揆」と「一味神水」「一味同心」
「一揆」と言うと、江戸時代の百姓一揆をイメージする人が多いと思います。これは、講談や時代劇の影響です。
秀吉の「刀狩り」以来、江戸時代には農民の「一揆」は禁止されていました。しかし、中世には、「一揆」は禁止されるどころか、農民も武士も、頻繁に「一揆」を行なっていました。武装を伴なう「一揆」も多かったですが、「一揆」すべてが争いや実力行動を目的としたわけではなかったのです。
農民が領主に要求やお願いをするための「一揆」もありましたが、地域の武士が連合体を組織するための「一揆」、守護大名が戦場で軍団を編成する「一揆」、武士たちが争いをやめて和解するための「一揆」、一山の寺僧が団結して強訴(ごうそ)を行なう「一揆」もありました。鎌倉幕府の「評定衆(ひょうじょうしゅう)」(裁判官)も、合議で公正な裁判を行なうために「一揆」を取り結んでいます。
中世の「一揆」とは、特定の目的のために人びとが結ぶ、一定の作法(さほう)にしたがった盟約であったのです。
『日本の中世、とくに 14世紀から 16世紀にかけての中世後期は、一般に一揆の時代といわれている。この時代あらゆる階層に、またあらゆる地域に、その集団の目的達成の手段として一揆が結ばれた。〔…〕私は、そのような〔目的達成のために結ばれた――ギトン註〕集団のうち、特定の手続きや作法にしたがって結成され、それに応じた特殊なメンバーのあり方を示す集団が本来的な一揆であったと考える。
現実には個々ばらばらの利害の対立をしめす社会的存在としての個人を、ある目的のために、その諸関係を止揚して一体化する手続きをとって結束した特殊な集団が一揆であった。すなわち、一揆とは、〔…〕「一味神水(じんずい)」という手続きをとり「一味同心」という連帯の心性を持つ人びとの集団であったといえる。』
勝俣鎮夫『一揆』,1982,岩波新書, pp.2-3.
「一味神水」とは、人びとが神社の境内や、大寺院ならば大講堂前のような広場に集まって、「衆議」を行ない、集団の達成すべき目的を決定すると、それを「起請文」に書いて全員が連署した紙を燃やし、その灰を「神水(じんずい)」〔神社に湧き出る聖なる水〕に溶かして、全員で回し飲みするのです。村人の「一揆」や「土一揆(つちいっき)」のように、文章を書ける人がいなくて、口頭のみで「一味神水」を行なう場合には、「衆議」の決定を宣(の)べ上げて梵鐘、鈴、鰐口〔神社の賽銭箱の上方に懸けてある丸い打楽器。がらんがらん〕などの金属具を打ち鳴らし、「神水」の回し飲みをします。(古墳時代の「銅鐸」祭祀に淵源するという説もあります)
こうして「一揆」を結成した人びとは、「一味神水」によって、「一味同心」という状態になったと、中世の人びとは考えました。この語の「同心」は、比喩ではありません。文字どおり、神の霊が人びとに乗り移り、人びとは完全に「一つの心」になってしまったと考えたのです。
こう言うと、「一揆」とは、参加者が個人としての自立も意識も喪失して神がかりになってしまう恐ろしい儀式だと思うかもしれません。たしかに、一面では、「神がかり」の一種にちがいありません。つまり、日常的な懸念やしがらみから解き放たれ、一時的に神に “変身” した心性です。しかし、人びとは、けっして迷信や、神仏に帰依するために「一揆」を結んだのではなく、通常の手段では達成しがたい社会生活上の目的を達成するために、意識して、やむにやまれず「一揆」という手段をとったのです。
『なぜこのような特異な集団をつくることが必要であったかというならば、当時の人びとにとって、その目的が、日常性をこえた問題、通常の手段では解決が不可能であると意識されたからである。〔…〕個人個人が、現実の社会的存在のままでは〔ギトン註――目的を〕達成することができないと意識されたため、〔…〕日常性や現実性をこえた特殊な集団を結成することが必要であったのであり、そのために、参加する個々の人びとが現実をこえた存在となることを目的とした作法や儀式が必要であったのである。
〔…〕メンバーが、〔…〕それぞれの社会的存在としての諸関係をたちきったところで、はじめて一揆という集団の結成が可能であったのであり、一揆はその目的達成のためにつくられ、その目的のためにのみ機能する非日常的な集団であったといえる。〔…〕一揆は、〔…〕目的達成、あるいは挫折によって解消されるのがその本質であっ〔…〕たといえる。』
勝俣鎮夫『一揆』,1982,岩波新書, pp.3-4.
つまり、「一揆」は、人びとが、個々それぞれの日常的な俗世の「縁」――しがらみを断ち切らないことには解決できないような問題に突き当たったときに、その「目的」限りで結成される、非日常的で一時的な集団だったのです。
たとえば現代でも、安倍政権が伝統的な専守防衛の枠を超える「安保関連法」を上程した時に、当該法案の阻止をめざして、法改正が不成立となった暁には、また成立してしまった場合にも、解散することを最初から決めて「フィールズ」という集団を結成した若者たちがいました。これなども、集団結成のやり方という面では、中世の「一揆」によく似たものだったと言ってよいでしょう。
目的不達成の場合には達成するまで頑強に闘いつづけるというのが、彼らの親の世代では一般的だったかもしれません。しかし、それでは就職にも経済生活の自立にも差し支えるので、そうしたことを気にしない、ごく少数の先鋭的な人しか集まることができません。目的に賛同する・より多くの参加者が集まるためには、特定の目的のために結ばれ、目的とともに解消する非日常的・一時的集団の結成という方法は、より賢く、また有効であったと言えます。
「一揆」の「衆議」は、まず全員が一切の利害を忘れ、他のメンバーとの間の関係やしがらみを顧慮することなく、自分の意見を述べます。ひとりひとり全員が、述べる義務を負っていました。その際しばしば行われたのは、覆面で顔を隠して集まり、声を変えて、能役者のような発声でしゃべることでした。これは全員がしなければ意味のないことなので、正体を明かして意見を述べたい人も、そうすることは許されず、かならず誰だか分からないようにして意見を述べました。またしばしば、正しいかどうかということは考慮せずに、意見を述べなければならないとされました。人びとの意識に即して言えば、「衆議」で表白されるのは個人の意見ではなく、「神の意志」だったからです。
そのあとで、全員の「一人一票」によって多数決が行われます。採決は “投票”〔紙を回して、各自賛成するほうに毛筆で1本の短線を引く、など〕 による場合もありましたが、賛成、反対それぞれについて喚声を上げて、声の数でどちらが多いかを見る場合もありました。しかし、注意すべきは、いくつかの条項がある「起請文」の場合、採決は項ごとに行われたのです。現代の議会や自治会、労働組合のように、一括採決とか、「議長団に一任」などということは、決して行われませんでした。あくまでも、全員が表明した意志によって多数決をすることが必要だと考えられたのです。
日本の社会では、古代でも中世でも、集団的な意思決定は「満場一致」がふつうでした。そうでなければ、天皇や将軍のような最上位者が決めます。「満場一致」というのは、意見の違う人が集まっている場合には、たがいに気兼ねして、勢力の強い者や、血縁、主従の縁のある者に附和・忖度して、けっきょく力の強い者の意見が通ってしまう。そうでもしなければ、全員の意見が一致することはありえないからです。また、反対する者がいるとまとまらない、と言って少数者を圧迫することにもなりがちです。ですから、「満場一致」は、決して民主的な方法ではないのです。
ところが、「一揆」においては、「一揆」においてだけは、多数決が行われたのです。上で述べてきた「神がかり」のような呪術的側面にもかかわらず、一面で、「一揆」は、現代にも通ずる・目的合理的で現実的なしくみを備えていたといえます。
『意志決定は、通常一揆成員が全員会合してなされるのであるが、〔…〕多数決制をとる例がみられるのを特徴とする。この多数決制という集団意志決定の手続きは、いうまでもなく、決定参加者の個々の主体的意志の表示、および参加者個々の意志表示の等価値性が前提とされねばならないのであって、この一揆の意志が多数決制にもとづいて決定されるということは、一揆の成員の一揆集団内部での主体的自立性および平等性を証するものであろう。』
勝俣鎮夫『戦国法成立史論』,1979,東京大学出版会, p.239.
比叡山・延暦寺 東塔・大講堂 延暦寺の僧は、ふだんは厳格な序列を
守っていたが、一朝ことあると、一山の門徒がこの大講堂前に集まり、
平等の資格で「衆議」を行ない、要求事項を決定して京都・御所へ
集団で押しかけて天皇に強訴(ごうそ)したという。
もちろん、現実の中世社会は、きわめて不平等で強固な身分制社会でした。農民や村人の一揆、「土一揆」の場合も、地域の領主層を集めた一揆の場合も、メンバーの間には貧富の差があるだけでなく、上下・主従の関係があり、上位の守護大名や、幕府、朝廷に対して服従する地位にあるメンバーも多かったのです。にもかかわらず、「一揆」という集団は、一時的にではあれ、それら主従・姻戚の「縁」を断ち切った個々のメンバーの自立、そしてメンバーのあいだの完全な平等を要求し、かつ保証したのです。厳しい身分序列が支配する社会のただなかで、このような特異な自立と平等の場を成立させえたものは、「一味神水」という・当時としては誰もが承認せざるをえなかった “聖なる” 作法、その結果としての「一揆」意志の成立に “神意の顕現” を見る、人びとの超越的観念にほかなりませんでした。
こうして、「一揆」は、主従・姻戚の「縁」を一時的に消し去った「無縁の場」として形成されたのです。
『彼らはこのもろもろの「縁」を止揚して全く新しい一揆という共同の場を形成した〔…〕「無縁」という状況の設定こそ、一揆形成・存立の基本的要件であったのである。
中世社会という強固な身分社会における「平等」、〔…〕個人の「自立性」という特異なあり方は、このような場においてはじめて可能になったのであり、同時に集団内部における「平等」・「自立」もまた、一揆形成の理念的必須条件であったのである。』
勝俣鎮夫『戦国法成立史論』,1979,東京大学出版会, p.240.
『親疎関係や好悪感情を一切たちきり、権力を恐れずといった主体性と自律性は、一揆を結んだ人びと特有のありかたなのであり、それは〔…〕「一味」〔共同の意志――ギトン註〕をつくりだすこと、一揆を結ぶことと不可分の関係にある〔…〕』
勝俣鎮夫『一揆』,1982,岩波新書, p.10.
『この一揆のメンバーの一揆集団内部における「平等」意識は、当然一揆の「衆議」とよばれる意志決定手続きと深くかかわっている。この意志決定は、通常、メンバーが全員会合しておこなわれ〔…〕「多分の儀」と称される多数決制によって決定されたのであり、多数決制による集団意志の決定もまた一揆の特性である』
勝俣鎮夫『一揆』,1982,岩波新書, pp.74-75.
本日は、まず、現在の大阪府泉佐野市にあった「日根野荘・入山田村」という戦国時代の村を取り上げ、そこでのできごとを題材に、中世の村における犯罪と、その処罰、ないし中世に特有な処理のしかたを見ました。そのうえで、「一揆」という・日本の中世に特徴的な集団結成の方法を通覧する諸章に移ったのですが、残念なことに、ここで字数の限界が来てしまったので、中途半端なところで切って次回に回さざるをえません。
次回は、「一揆」の諸相を引きつづいて見ていったうえで、「入山田村」で起きた農民の「一揆」にも触れることになります。そして、戦国時代には日本各地に現れた「自治都市(自由都市)」――堺のみならず、長崎、博多、堅田、伊勢大湊、桑名、‥‥――の成り立ちを見ることになります。こうして、中世の「無縁」をめぐる議論は、勝俣氏から網野善彦氏へとバトン・タッチされ、網野氏は、勝俣氏が暗示するように述べていたことをよりハッキリと、「無縁」とは、古代、中世の日本において「底知れない深さと生命力」を発揮していた・人間の本源的「自由」の原理にほかならない、と宣言するのです。
『彼ら〔一揆を結んだ地域領主層や、自治都市の豪商たち――ギトン註〕が強烈な平等原則によって貫かれた場を、ある場合、一時的であったにせよ、一揆・会合衆という形で創出したことに、われわれは注目する必要がある。〔…〕室町・戦国期、日本全国各地に、多様な形で姿を現わす一揆が、戦国大名から織豊政権、江戸幕府にいたる権力の専制的支配に抵抗しつづけ、自治都市とともに、そうした支配の完成に最大の障害となりつづけた理由は、まさしくそこにある。』
網野善彦『増補 無縁・公界・楽』,1996,平凡社ライブラリー, p.96.
よかったらギトンのブログへ⇒:
ギトンのあ~いえばこーゆー記
こちらは自撮り写真帖⇒:
ギトンの Galerie de Tableau
ジェイムズ・ティン 「アベルを死へみちびくカイン」