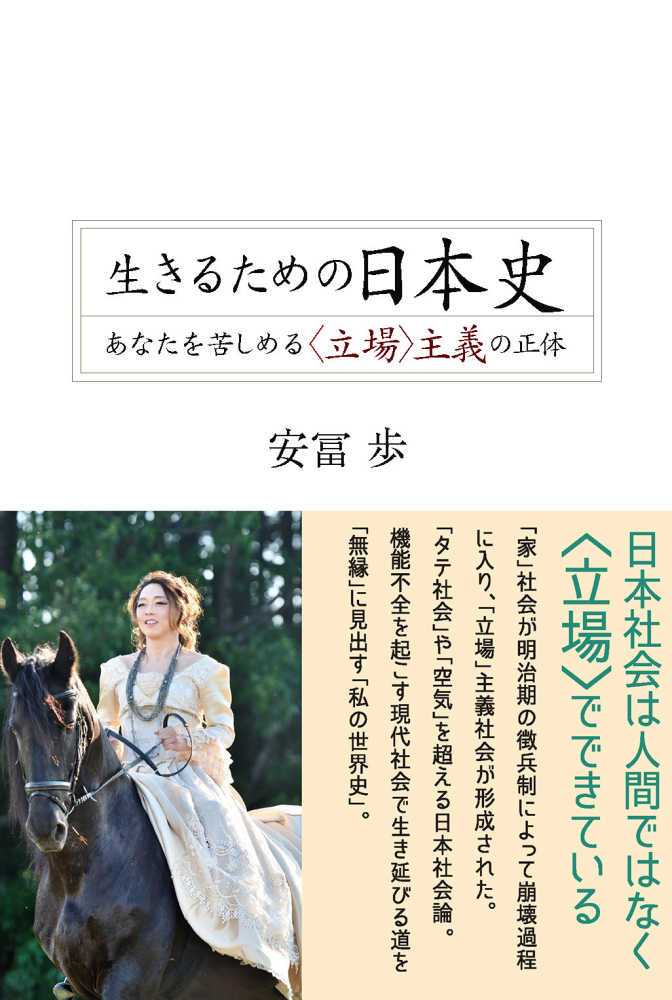「日朝共同平壌宣言」に署名後握手する金正日総書記と小泉純一郎首相 2002年9月17日
前回の「毛沢東、田中角栄」と比べ、どこかぎこちなく感じないだろうか?
【27】「体制派」vs「非体制派」――調停官田中角栄と、
小泉純一郎の逆襲
『体制派とは政策〔…〕の決定権を握っている人たちのことです。』
安冨歩『ジャパン・イズ・バック』,2014,明石書店, p.37.
戦後日本の「体制派」は、保守政治家、高級官僚、大企業経営者、‥‥こういった人々が、そのトップに立っています。しかし、社会全体を「体制派」と「非体制派」に分けて見る場合には、それだけでなく、野党政治家のかなりの部分、下級官僚・職員、大企業の労働者、自衛隊員や警察官、そしてそれらの配偶者も、「体制派」にふくめて見なければなりません。なぜなら、彼らはトップの人たちと “一蓮托生” だからです。したがって、投票行動も「体制派」です。それが日本社会の大きな特質であり、どうしてそうなるかと言えば、「立場主義」に理解のカギがあります。
『一般的に従業員は経営陣と対立する「反体制派」と思われています。しかし、大企業経営者と対立するのは〔…〕、〔非正規雇用、ブラック企業の従業員をはじめとする――ギトン註〕組織を持つことすら許されず生殺与奪の権を体制側に握られてしまっている人たちです。〔…〕大企業の従業員や公務員は明らかに体制派です。多くの大企業において、〔…〕労働組合担当になるのは出世コースであったり〔より正確には、企業内組合の幹部から、経営側の労務担当職に転身するのが出世コース――ギトン註〕、〔…〕という事実がそれを補強します。』
安冨歩『ジャパン・イズ・バック』,2014,明石書店, pp.37-38.
「非体制派」とは、国富の集中点である「体制」とは無関係な人たち、「体制」から距離の遠い人たちのことです。地方の農林漁業従事者、中小企業経営者とその従業員、零細自営業者、失業者、およびそれらの配偶者です。
日本が高度経済成長を遂げていた 1960-70年代に、「体制派」と「非体制派」の所得格差が開き、「体制派」は「非体制派」の利害に目が向かなくなりました。しかし、当時はまだ農業人口が多かったですから、「非体制派」は投票権を武器に反撃することができました。自民党の得票が減り、公明党のような小党ができたり、社会党が増えたりしました。
そこで、劣勢を挽回すべく、自民党の中から抬頭したのが、「田中派」です。田中角栄自身は新潟県の農家の息子から身を起こした土建業者で、農家や地方の中小企業をコアの支持基盤としていました。つまり「非体制派」です。
『「列島改造論」に代表されるように、彼は「地方と都会の格差の解消」をスローガンに掲げていました。つまり、〔…〕公共事業や補助金によって都会から地方に資金を還流させ、大都市・大企業〔が稼いだ――ギトン註〕経済発展の果実を〔…〕分かち合う。そういう政治手法です。〔…〕
ここで旧来の自民党=体制派との協調関係も成立します。田中派は票をかせぎ、体制派は公共事業・補助金を官僚を通じて出す。〔…〕官僚には、その公共事業周辺に発生する特殊法人その他に天下り〔…〕ポストを与える。』
安冨歩『ジャパン・イズ・バック』,2014,明石書店, pp.38-39.
そればかりでなく、田中内閣は 1973年には、年金受給額引き上げや老人医療費無料化などの福祉政策を打ち出して、社会党の支持基盤だった都市中小企業層を自民党に取り込みます。「田中システム」は、公共事業・補助金などの財政的バラマキがあくまでも中心ですが、老人福祉や社会保険の面では福祉にも傾斜をもったのです。そして、「田中派」亡き後の小泉~安倍の自民党政権は、福祉の面を大いに切り捨てて後退させることになります。
このように、「田中システム」は膨大な財政的浪費を基盤とするので、そのぶん票に結びつかない出費はできるだけ避けたいところです。「東西冷戦」がまだ続いていた当時、もっとも手ごわい懸念は防衛費の膨張でした。そこで、軍拡を避けるためには「アジアの安定」が不可欠ということで、まず、中東産油国との協調を図って、イスラエルのパレスチナ占領(じつは停戦協定違反)を非難し、アメリカに異論を浴びせます。そして、戦後 20年以上断絶していた共産主義中国との国交回復に取り組んだのです。
『つまり、田中角栄の政策をまとめると、
- 中国重視(対米一辺倒からの脱却)
- 地方への還流(公共事業)
- 都市非体制派の抱き込み(福祉重視)
の3点です。〔…〕
しかし、〔…〕巨大な公共事業や補助金をまかなうために、膨大な国債が発行されました。』
安冨歩『ジャパン・イズ・バック』,2014,明石書店, pp.39-40.
田中角栄が、アメリカのCIA?勢力が仕掛けたロッキード汚職に引っかかって失脚すると、「田中システム」そのものに対しても批判の声が高くなりました。膨大に膨らんだ国債を整理して、財政を健全化しなければならない。そのためには「非体制派」――田舎の保守層を、切れ!‥というわけです。
このころには、もう農業人口も減って、コメは「作りすぎ」と言われて栄誉を失い、地方の保守層は補助金漬けになって生きながらえている状態でした。そこへ、欧米でニューディール福祉国家へのアンチ・テーゼとして広がっていた「新自由主義」経済思潮を導入し、電信電話・郵政の民営化、食糧管理・流通規制の撤廃などが、国内の伝統保守の強い抵抗を排除して行われました。
『小泉政権が、大企業労使連合〔≒「立場主義者」「体制派」――ギトン註〕の〔新〕自由主義的利益を優先し、地方の保守主義勢力〔≒「家主義」の残党――ギトン註〕を切り捨てる、という方向性を持っていたことは明らかでしょう。小泉総理は、劇場型政治〔…〕でマスコミを統御し、田舎は切り捨てて、都市にいる立場主義者〔ここでは、「立場主義者」(体制派)のなかでも無党派化した人びと。大企業の中間管理職、国家公務員、それらの配偶者を指して述べている――ギトン註〕に「あなたの立場を守りますよ」と言って投票させるというメソッドを取りました。
小泉政権は、国債がどんどん膨らんでいって財政を何とかしないと仕方なかったので、田中派を切らないとどうしようもなかった。「自民党をぶっこわす」とはそういう意味です。〔…〕ぶっこわして、何とか財政の規律を回復しようとしたのです。〔…〕これが地方の造反を招き、民主党政権の成立という事態につながるわけです。』
安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, pp.189-190.
『「行財政改革」が叫ばれ、登場したのが小泉純一郎首相です。〔…〕
- 中国重視の否定(靖国神社参拝など)
- 地方の切り捨て(公共事業抑制)
- 都会の体制派の切り捨て(規制緩和・福祉抑制)
〔…〕つまり、田中主義の全否定です。これが、〔…〕
「自民党をぶっ壊す!」
の内容です。〔…〕〔ギトン註――田舎の保守層との〕妥協で成り立っていた自民党=田中主義を壊し、体制派〔なかんずく大企業――ギトン註〕に都合のいいように作り変えることを意味します。〔…〕
小泉首相は都会のおばさまたちに大変人気がありました。それは、〔…〕
「財政が破綻したら年金がもらえなくなる」
という都市の体制派、たとえば夫が大企業のそこそこの地位にある専業主婦、そんな人々の危機感によるものだったかもしれません。
このようにして都会人(いわゆる無党派層)の圧倒的〔…〕支持を取り付けた小泉政権でしたが、改めてその成果をふりかえると、イメージほどうまくいっていなかった〔…〕
歳出こそ〔…〕なんとか膨張を回避しましたが、税収が減り続けたのです。
なぜかというと、小泉政権は田中システムを壊しただけで、新しいシステムを構築できなかったので、経済が回らなくなったのです。〔…〕
その上、選挙対策として法人税と所得税の税率を引き下げ続けたことと、非正規雇用の拡大によって給与水準が落ち、実効税率が下がったために、税収がとんでもなく減ってしまいました。
また忠誠心の高い田中型選挙民を切り捨て、気まぐれな都市無党派層に依存するこのやり方のため、結局、〔ギトン註――小泉氏らが〕個人として耳目を集める「劇場型」の派手な立ち回りと、都会に出てきた田舎出身者に強固な地盤を持つ創価学会(公明党)とに依存しなければならなくなりました。〔…〕
〔ギトン註――小泉氏らの暴露型「劇場政治」の〕結果、「天下り」や「官僚支配」果ては「公共事業」までが必要以上に敵視されることになり、〔…〕体制派にとってもダメージになりました。
さらに頑固な靖国神社参拝は中国の態度を硬化させ反日感情を喚起し、経済的にも滞ります。これも大企業・財界つまり体制派にとっては実は大きな痛手です。〔…〕今や商売の相手としての中国のボリュームと将来性〔…〕は、アメリカを遥かに上回っています。
田中システムのあとに考えうるのは、東アジア全体を視野に入れた経済の循環の再編成しかありえなかったというのに、その可能性を自ら摘み取ってしまったのですから、経済が回るはずがなかったのです。』
安冨歩『ジャパン・イズ・バック』,2014,明石書店, pp.40-42.
【28】民主党政権・小沢一郎――「田中システム」の復活か?
あげくのはて、小泉純一郎が「劇場政治」を投げ出して引退した後、自民党は大混乱に陥り、2人の短命な首相が交代した後、民主党に政権を奪われました(2009年)。国民は、田中政治でも小泉劇場でもない「新しいやり方」を求めて政権交代に期待したのですが、期待は大きく外れました。その理由を端的に言えば、期待された民主党政権は、田中システムの焼き直し以外に新たなビジョンを持っていなかったからです。
民主党政権の前半期を仕切ったのは、小沢一郎と鳩山由紀夫。2人とも、もと田中派です。とくに小沢氏は、
『田中角栄の思想・政治手法の直接的継承者〔…〕です。〔…〕
- 09年12月、百数十人の国会議員を連れての中国訪問(対中国関係の重視)
- 農家直接所得補償の提案(地方への還流)
- 子ども手当(福祉重視)』
安冨歩『ジャパン・イズ・バック』,2014,明石書店, p.43.
これらは、民主党執権当初に小沢氏が提起した政策ですが、彼のホームページを見ると(2014年 本書執筆時)、「対等な日米関係」「中国、韓国、アジア諸国との信頼関係の構築」「中央集権制度を抜本的に改める」「天下りの全面禁止と政府関係法人の廃止で利権をなくす」など、「田中主義」以上であり、「体制派」への牽制を明確に打ち出しています。
『田中政権のように非体制派の政治家が体制派の官僚を使いこなして統治する、これが小沢一郎の描く「政治主導」の意味です。〔…〕
当然、財政はさらに膨らんでしまいますが、〔…〕日中関係は一気に改善、日中間の経済的連携は一挙に強化され、これが明るい兆しではありました。』
安冨歩『ジャパン・イズ・バック』,2014,明石書店, p.44.
ところが、 “幻の小沢政権” は、発芽直前に潰されてしまいます。「西松建設疑惑」で公設秘書が逮捕されて「小沢首相」は流産、さらに「陸山会事件」によって小沢氏自身が回復不能の打撃を受けて失脚します。しかし、「陸山会事件」は結局不起訴、検審決議で起訴されたものの無罪確定。「西松」で逮捕された公設秘書も、詐欺的な取り調べによって虚偽の自白調書を取られたと言われています。けっきょくこれらは、「小沢政権」の成立を妨害するために「体制派」が仕組んだ茶番劇だったと言わざるをえないのです。
そこで、かわりに首相になった鳩山氏は、沖縄「普天間基地問題」で、沖縄県外への移転を打ち出して官僚の妨害に遭い、日本の官僚からもアメリカからも袋叩きにされる状態で国民の信任を失って辞任。当時、外務省の幹部が、鳩山首相に賛成しないようにアメリカに要求していた文書が、のちにウィキリークスで暴露されています。
官僚、アメリカ、さらには日本の体制派マスコミが印象操作を行なって、「小沢は汚い」「鳩山は間抜けだ」というイメージを国民に植え付けました。小泉の「劇場政治」につづいて、民主党政権時に、国民が喜んでマスコミに踊らされる習俗ができあがったことが、そのあとの「安倍政治」を準備したと言えます。
【29】「立場」を奪われた人びと――
「プロレタリア」を操る安倍晋三
『有権者の質の変化という点も見逃せません。
具体的には「非体制派」の内容の変化〔保守的な「家主義」者から、「家」も「立場」も奪われた「プロレタリア」へ――ギトン註〕です。
田中主義が始まった頃には農村(田舎)にまだ人口がたくさんありました。これが票につながったわけですが、地方に鉄道と高速道路が伸びるにつれ、人は都会へと移動を始めます。〔…〕しかし長い経済成長のおかげで、〔…〕〔ギトン註――田舎から出て来て〕中小企業の従業員、自営業者など〔になった人びと――ギトン註〕もそこそこの蓄えやマイホームを持ち、中産階級化して〔…〕体制派にスライドしてしまっています。
〔…〕田舎の公立高校を卒業して志を抱き都会に出て就職、結婚、長いローンを組んだけれども無事マイホームを手に入れて子どもたちも大学へやる。これがあたりまえでした。
ところが今やこの「あたりまえ」こそが夢物語に近くなってしまっているのです。
そこそこの大学を出たり能力を持っていても、いったん正社員へのレールから外れると、安定した職はなくなり、不安を抱えながらその日暮らしに毛の生えたような派遣生活。
地方から出てきて就職したはいいものの、仕事に追われ歳を重ねて気がつけばひとりぼっち。田舎に帰ったって仕事はないので、ただただ黙々とひとりコンビニ弁当の夜を過ごす。
職がない、家族がない、あるいはその両方。
いわば、本物のプロレタリアート、〔…〕無産階級が誕生し、増加しているのです。』
安冨歩『ジャパン・イズ・バック』,2014,明石書店, pp.50-51.
「プロレタリア」というラテン語は、本来は、このような “寄るべなき人々” を指す言葉なのです。それを、工場労働者の意味に変えてしまったのは、マルクス主義者のトリックです。大企業が経営する大きな工場の労働者、あるいは大きな労働組合の組合員などは、「プロレタリア」の本来の意味からはもっとも遠い人たちです。
そして、本来の意味での「プロレタリア」の歓心を惹きつけ、彼らを組織することのできる運動は、共産主義でも社会主義でもありません。それは、ファシズムです。
ファシズムを加味して、増大する「プロレタリア」のオルグを始めたことが、いままでの自民党にはなかった「安倍政権(第2次以降)」の新しい特質なのです。
『この人たち〔「プロレタリア」――ギトン註〕には、〔…〕日本の社会で非常に重要な役割を果たしている「立場」がありません。家族の一員としての立場、会社の一員としての立場、地域社会の一員としての立場……以前ならばあたりまえのようにあったその「立場」を失った彼ら・彼女らが求めるもの、それは〔…〕「立場」です。
われらに「立場」を!
こうした人たちにとって響くのは、
「君たちに『立場』を取り戻してみせる」
という大見得なのです。
すべての立場を失った者にとって唯一残された「立場」、それは国籍です。〔…〕つまり、日本人であること。
ですから彼らはこの「日本人であること」に過大な評価を与え、価値観の軸に置きます。
そうすれば当然、〔…〕ベースにある「日本」が素晴らしいこと、を「事実がどうであるかにかかわらず」求めるようになります。
この結果、〔…〕右傾化が進み、排外主義が助長されます。〔…〕彼らにとっては自分たち唯一の「立場」、つまり「日本人であること」を補強してくれる(と約束している)安倍氏が魅力的なわけで、
「日本を取り戻す」
つまり、
「あなたの立場を取り戻す」
と絶叫してくれている限りは、別に何をやってくれてても構わないのです。』
安冨歩『ジャパン・イズ・バック』,2014,明石書店, pp.52-53.
『安倍政権の政治的体質をおさらいしてみましょう。
- 対米従属と反中国
- 体制派による、体制派のための、体制派の政治
- 立場なき人々の支持
問題はこの3点目です。〔…〕「立場のない」人々が支持しているからこそ、行きつく先は「戦争」になるのです。
なぜなら、〔…〕「立場のない人たち」の「立場」、拠って立つ根拠は、「日本人であること」「日本という国籍」しかありません。
となると、彼らの支持を取り付け続けるために必要なのはただ一つ〔…〕、「国威発揚」です。
この麻薬に手を出すと、戦争に向けて歯車が動き出してしまいます。具合の悪いことに、中国が 20数年前からこの麻薬に手を付けている、〔…〕
彼ら〔※〕が決まって採用する政策〔競争を激化させる自由化政策――ギトン註〕は、こういう人々の生活をより圧迫するものであり、そのために〔ギトン註――競争から〕こぼれ落ちた下層民の憤懣が溜まってきます。
これを発散させるのは、〔…〕外に目を向けさせる手法、すなわち戦争です。』
安冨歩『ジャパン・イズ・バック』,2014,明石書店, pp.82-84.
〔※〕原文では、「彼ら」は英米の政治家の名前を受けているのですが、引用ではあえて省略しました。かわりに、ここには「橋下徹」「竹中平蔵」などの「自己責任」論者を代入して読むと、安倍政権以降の日本の状況が、よりよくわかると思います。
【30】「家主義」vs「立場主義」――田中派 vs 小泉政権
安富さんによれば、1970年ころまでの自民党――「体制派」――「大企業労使連合」を支えていたのは「立場主義」でした。「立場主義」こそは、日本の企業による驚異的な高度経済成長をもたらした原動力であり、「日本型経営」の秘密として諸外国で持てはやされました。しかしそれは、かつて無謀な世界戦略に基づく日本の侵略戦争を、一糸乱れぬ統率のもとに遂行した「皇軍」兵士と銃後のエートスが、向きと形を変えたものでもありました。
これに対して、「田中システム」が依拠した「田舎の保守主義」――「非体制派」――農家や地方の土建業者は、当時はなお頑迷に「家主義」(の残滓)を守り続けていました。「田舎の保守主義」に依拠する田中派は「家主義」 ⇔ 「田中システム」をくつがえそうと大鉈(おおなた)を振るった小泉政権は「立場主義」――と、図式化して言ってもよいでしょう。
しかし、高度成長期が終り、「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と言われて幻想に酔っていたころ、すでに「立場主義」は没落の縁(ふち)に立っていました。「立場主義」を没落させたのは、「立場主義」の日本企業自身が、その優秀な頭脳と集約労働によって生み出した・コンピュータによる自動制御生産システムだったのです。
さて、今回は、政権の交代と政治過程の推移に目を奪われてしまったために、「立場」そのものについては十分に追究できなかったうらみがあります。「体制派」の官僚組織と大企業が、どうして「立場主義」だと言えるのか、いまいちイメージが湧かなかったかもしれません。
「黄金時代」から「没落」へ――「立場主義」の変遷を、次回は、もっと「立場」そのものに即して、見ていきたいと思います。
よかったらギトンのブログへ⇒:
ギトンのあ~いえばこーゆー記
こちらは自撮り写真帖⇒:
ギトンの Galerie de Tableau
Corrado Cagli ”Narciso”, 1976