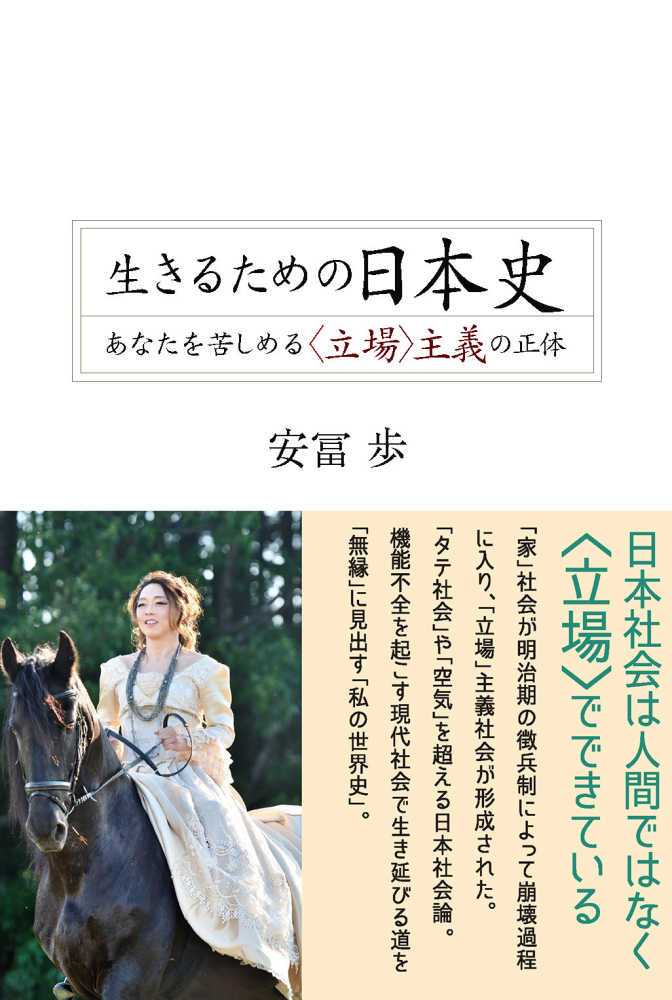安冨 歩
【1】真夏の憂鬱
このテーマ・シリーズ《新書日本史》は、岩波新書の「日本古代史」「日本中世史」「日本近世史」シリーズ・計15冊をレヴューしながら、雑然とした乱読でゴミ溜めのように積もっている私の日本史と考古学の知識を整理しておきたい、という欲求から始めたのでした。というのは、私が今こころざしている、もうすこし世界史的ないし「地域」史的な考察のためには、自分の足もとをよく見直しておくことが、不可欠の前提作業になる‥と思われたからでした。
ところが、いざ始めてみると、…上記の 15冊は――まだ最初の7冊を手がけた段階ですが――各著者それぞれに信念といってもよい歴史認識像を、大胆に描き上げるべく健筆を振るっているのですが、それにもかかわらず私には、事実羅列的で平板なものに見えてしまうのです。たしかに、いずれの著者も、学界の通説の範囲を大きく逸脱しない叙述を心がけているように思われ、その点では、汎用する基本的な筋で知識の整理をしたいと思っている私の要求にも合うのです。しかし、そうでありながら、私の中では、「こんな平板で表面的な、雑然と描かれた “絵” に、いったいどんな意味があるのだろう‥」という疑問が頭をもたげて来て、読み続けることが苦痛に思われてくることがしばしばです。
それでも、飛鳥時代に関しては、梅原猛氏の『聖徳太子』という好著を得て、梅原氏の描く歴史像との対決の中で私自身の歴史認識を鍛え上げ、【蘇我馬子と聖徳太子】全18回をアップすることができました。何よりも、自身の非専門家的な視点と現地踏査を重視する、梅原氏の歴史認識の姿勢が、私には、新鮮で快いものに思われました。
しかし、そのセクションが終ってみると、私は深い憂鬱に陥ってしまいました。新書のシリーズを、飛鳥~奈良から「中世社会のはじまり」へ向けて読み進めていくことはできるのですが、さまざまな知識が通過してゆくだけで、そこから「自分は何を得ることができるのだろう」という疑問に対する答えが、とんと浮かばない状態になってしまいました。著者たちは、それぞれに、「こういうことが、今の日本文化の起源になっているのだよ」「こういうことが起源にあることを知れば、自分たちの社会や文化に対する見方が変わるのではないかね?」といった問いかけを言外にしているのがわかるのですが、私のほうでは、それらの問いかけが、いまいち身に響いてこないのです。。。
おそらくその原因は、著者である歴史学者たちが言外に、生活感覚的に把えている「現在の社会」あるいは現在のこの国というものが、私の把えている、感じている日本‥この社会というものと、あまりにも懸けはなれているせいではなかったか、と思います。
たとえば、日本の歴史的社会の “深層”、ないし私たちの社会が不可避に抱える「神秘」の部分について、私なりの見通しがないわけではありません。それは、言うなれば「誰にも、特別な役割も地位も認めない平等性への固執」ということで、こちらの [サトレコ] の最後の部分で、縄文村落遺跡を見学した感想のなかで少し触れたことがあります。この「平等性への固執」は、日本の歴史的社会のさまざまな局面で、さまざまな形をとって現れてくるのではないか。その現れ方は、「平等社会」というようなユートピアの形をとるとは限らず、むしろ多くの場合には、差別、閉鎖的集団、格式と権威への固執、といった “ひっくりかえった形” ――「疎外態」と言ったらよいか――をとって現れるだろう‥
しかし、私のそうした観点に近いものは、どの時代を見ても歴史学者たちの叙述には見出されない‥、まぁこれは当然だとしても、そのヒントとなりうるものさえ、私は見出すことができないのです。
【2】この本を手に取るまで
安冨歩さんという人をはじめて知ったのは、「れいわ新選組」の最初の選挙運動で候補者演説を見た時で、正直言って私は、何を言っているのかよく解らない人だと思いました。そのあと、ふつうなら候補者が演説をするような場に白い馬を連れて来て、聴衆の子どもにニンジンを渡して餌やりさせているのも見ましたが、やはり何を言いたいのかわからない。選挙や国会政治とどういう関係があるのやら、首をかしげるほかありません。
今年の初め頃だったと思いますが、Youtube の『一月万冊』で、安冨さんが「れいわ新選組」を離党した理由を話しているのを見ました。その理由というのは、意見が違うとか対立するということではなくて、「今年の参院選で万が一当選してしまったら、自分は国会のような会議ができる性格ではないし、『れいわ』にも迷惑がかかるから、今のうちに、目立たないように辞めておく‥‥」。じゃあなんで、この前は立候補したんだ?‥ということになるわけですが、むしろ、「議員という仕事ができる性格ではない」という安冨さんの自己認識は、全くそのとおりだと、妙に納得してしまいました。
安富さんの話が理解できて納得したのは、これが初めてだったのですが、私だけでなく、多くの視聴者にとってもそうだったのではないかと思います←。
その後、『一月万冊』で安富さんの対談をよく見るようになって、とくに「安倍狙撃事件」の後は『一月万冊』をほとんど毎日視聴していますから、安富さんを見るのも毎日のことになりました。しかしそれでも、安富さんに抱いている “奇異の感” は、むしろ大きくなる一方です。対談を聞いていると、安富さんのほうの発言だけが、ときどき妙に浮いているのです。浮いた発言を、途中で相手にさえぎられて、それでようやく対談の話の筋が続いてゆくようにさえ見えます。主宰者の清水有高さんとの対談でも、他の人との対談でも、そういう場面をしょっちゅう見かけました。
そこで私が思ったのは、この安冨歩という人は、常人とは頭の回転のしかたが違うのだ、ということです。「違う」と言うのは、単に頭の回転が速いとか鋭いということではなくて(たしかに速いのですが)、回転の方向が違うのではないか、ということです。直前の話の文脈から、私の頭が右に回転しているときに、この人の頭は左巻きに回っている、そういうことではないかと思いました。
私は、安富さんと清水さんの話のなかで、安富さんが以前に岩波書店から出したけれども、読者にも出版元にも理解されずに絶版になっている『複雑さを生きる』という本を、清水さんが \34,000.-円という途方もない値段で‥‥しかし、それだけの価値のある内容だということで、‥‥『一月万冊』から再版した話を聞いて、これはぜひとも読んでみたいと思いました。3万4千円は、向こう1か月のエンゲル係数を下げる覚悟でなければ、とても買えないのですが、幸い《再販ルート》には乗っていませんから、今ならネット・オークションで1万円以下で買うことができます。(警告!『複雑さを生きる』復刊版の1万円以下の古書はボッタクリ詐欺です。被害情報が出ています。注文不可 !!)
しかし、安富さんとは「頭の回転」方向が違う、という問題があるので、きっとこの本は一筋縄ではいかない。いきなりアタックしたら敗退まちがえないと思われます。それで、事前に安富さんの、もっと通俗的な、いま書店の棚に出てるような本を何冊か読んで準備運動にしようと考えました。
そこで最初に選んだのが、この『生きるための日本史』というハードカバーの本です。
読んでみると、意外なことに、ユーチューブの対談のように奇異なことはありませんでした。おそらく、安富さんは、一般の読者に読みやすくするために、構成と内容を工夫している(しかし、レベルは落としていない)のだと思われました。ラッセル、ウィトゲンシュタイン、ハイデッガー、夏目漱石、網野善彦、‥‥といった、多読家なら一度は読んだことがある、読んだことはなくとも書評や孫引きは見たことがあるような、通りの良い著者名が並んでいます。「決定論的カオス」「ゲーデル」「フィードバック」など、読書人の眼を惹く話題にも事欠きません。そして、安富さん特有の考え方、見方については、本人の人生経験からそう考えるようになった経緯をふくめて、ていねいに説明しているのです。
そして何よりも、この本を読みはじめた数日前から、私は妙に元気が回復するのを感じました。憂鬱に覆われていた眼の前の風景が、もとの見慣れた視界に戻っていくように思われます。それは、「この国の歴史から何を得ようとするか」という、私の憂鬱のもとになっていた疑問に、この本が回答のヒントを与えてくれるように思われるからです。
【3】国民国家のための「国史」から、「私たちの世界」史へ
『歴史学がそもそも、ドイツとかフランスとか日本といった「国民国家」を形成するためのイデオロギー装置として「ドイツ史」「フランス史」「日本史」などを創り出すためにできた学問であり、いつまでもそんなものにかかずらっていては、真理の探究などできたものではありません。』
安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, pp.15-16.
これはまったく安富さんの言うとおりで、いまは「日本史」と言いますが、かつては「国史」と言いました。「国史」という言葉は明治時代に造られた言葉で、江戸時代までは、そういうものは無かった。それ以前でも、天皇の支配者としての正統性を明らかにするとか、日本が “神の国” であることを証明する、という意味での「歴史」は、何度も書かれましたが、「国家」としての国民のアイデンティティー、という意味での「国史」は、明治時代に、近代国家の規範の一つとして初めて提唱されたのだと思います。欧米列強に対抗しうるような「近代国家」を作り上げるためには、「国史」の教授によって国民に、自分はこの国家の臣民であるという “唯一・排他のアイデンティティー” を吹き込むことが、ぜひとも必要とされたのです。
同じことは、第二次大戦後に独立した新興国では、現在も続けられています。たとえば韓国では、学校で教えられているのは「韓国史」ではなく、いま現在でも「国史」です。「国史」の教科書を国定にするかどうかで、この 10年以上揉めています。韓国では、保守的な人びとにとっても、民主派の人びとのかなりの部分にとっても、「国民国家のアイデンティティー」は、異論を許さない国民精神の基礎なのです。
しかし、そういう意味でのイデオロギーとしての国家史、「国史」が、「真理の探究」を最上位に掲げなければならない「歴史学」とは懸け離れたものであり、しばしば背反さえする、ということは否定できません。
そこでいま、一般に「歴史学」の内部で起きているのは、「国家史」から「地域史」への移行です。一つの国家全体ではなく、「蝦夷・東北の歴史」とか「東国の歴史」というような「地域」の歴史、あるいは、「東アジア史」「地中海史」といった、いくつもの国家がその中で興亡するような大きな「地域」の歴史に、焦点は移って行こうとしています。
たしかに、「国民国家」というイデオロギー的枠組みを超えて「地域史」の観点に立つことによって、客観的な真理の探究は、より容易になるでしょう。しかし、それが私たちにとって何なのか? ‥‥私たちはそれによって、「国民国家」イデオロギーの呪縛から脱け出せるのかもしれない。しかし、脱け出せた先は、国家も民族もない大海原、ないし砂漠のような不毛の土地に、裸かで投げ出されるだけではないのか?
そこで、「歴史」というものに対する私たちの関心を、もっと個人的に、「自分」に即して考えてみると、どういうことになるか、……というのが、安富さんの問いかけなのです:
『たとえば、1973年に起きたオイルショックという歴史的現象が私という人格に与えた影響は、私自身はそれがどのようなものか認識していないとしても、きっと大きいはずです。私の人生は、私の両親の歴史と不可分であり、彼ら幼少期の恐ろしい戦争によって魂に刻まれた傷は、私の魂の傷と深く関連しています。私たちの人生は、私たちが生まれ育った社会の構造に埋め込まれた歴史的事件と不可分であって、それは世界の歴史と結びついています。
そういうわけで、「私」を出発点としても、必然的にひとつの「世界史」に結びつくはずなのです。その上で、私という「世界内存在」が、私自身のために書く「私の世界」の歴史たる「私の世界史」と、あなたがあなたのために書く「あなたの世界」の歴史たる「あなたの世界史」とを読みあえば、互いの世界史理解を深めることができ、そこから「私たちの世界史」をそれぞれの観点から考えることができます。これは、「間主観的世界史」と見ることができます。この「私たち」が国境を超え人種を超えてつながっていけば、その極限として、〔…〕真の意味での「グローバル・ヒストリー」が、「私の世界史」のネットワークとして析出されるはずだ、と考えたわけです。』
安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, pp.16-17.
この↑最後の段落、とくにその後半部分については、私は異論があります。『真の意味での「グローバル・ヒストリー」』『「私の世界史」のネットワーク』――いずれも耳には快く響きますが、見通しとして楽観的過ぎやしないだろうか?……しかし、そう言うだけでは、ただのヤジになってしまいますから、もうすこし分析的に私の疑問を記しましょう。
まず、「私の世界史」と「あなたの世界史」を並べれば、たし算のように、それぞれの観点からの「私たちの世界史」ができあがる、という見通しについてです。「私の世界史」と「あなたの世界史」は、多くの場面でダブっているはずです。同じ歴史的事件や、同種の事象を扱いながら、それぞれの「解釈」は真っ向から対立する場合が少なくないでしょう。それぞれの生い立ちの条件が異なる以上、これは避けられないことです。同じ事実に対する評価が異なるだけでなく、どういう事実があったか、ということについてさえ、しばしば見解は対立するでしょう。「私の世界史」と「あなたの世界史」とのあいだでは、互いの世界観を衝突させ、「論争と反省」のプロセスを通じてそれぞれの「歴史」を掘り下げてゆく作業が不可欠です。それによって、たがいにウィンウィンの形で解決する問題は少なくない。しかしそれでも、どうしても折り合えない問題は残るでしょう。
そこで、次に提起されるのは、「間主観的世界史」という見通し――ヴィジョンが孕む問題です。この「間主観性」というのは、安富さん自身が指摘しておられるようにエトムント・フッサールの提起した概念であり、したがってこの場合にも、フッサールの「間主観性」概念に対して一般に言われている批判を向けることができます。つまり、この構想の弱点は、指摘しておかざるをえない。
たしかに、「私」の主観的な世界史や、誰それ貴方の主観的な世界史をつなげていけば、たいへんに広々とした織物を織りあげることができるかもしれない。しかし、それは果たして「世界史」――この「世界」の歴史――だろうか? 「私」や「あなた」や誰それの認識が互いにどんなに異なっていようとも、私たちが生きているのは同じ一つの「世界」ではないのか? 「私」や「あなた」やその他誰それの生まれる前からこの「世界」が存在するのだとしたら、この「世界」には、私たちが認識する前から唯一の「歴史」があり、私たちがそれをさまざまに解釈するのとは無関係に、この「世界」の歴史は存在するのではないか?‥私たちがそれを完全に認識することはできないとしても。
もちろん、こう言ったからといって、安富さんの「間主観的世界史」の構想が否定されるわけではありません。それでも、疑問は疑問として記しておきたいのです。
【4】ハイデッガーの「三連発」を受けとめる
今回は、安冨さんのこの本の「序章」のレヴューを書いているのですが、さいごに、「序章」の最後にあるハイデッガーからの難解な引用にも、アタックしておきたいと思います。ハイデッガー/高田珠樹・訳『アリストテレスの現象学的解釈』,pp.45-46.からの引用だそうです:
『自らの歴史(ゲシヒテ)を解体しながらそれと対決するというのは、哲学的な探究にとって、かつて自分がどうであったかを説明するための単なる付録でもなければ、また他人がかつて何を「した」かを折にふれて回顧することでもなく、また世界史についてのさまざまの楽しい見取り図を描いてみる場でもない。解体とは、むしろ現在が自らのもろもろの根本動性において自分と出会わねばならない本来の道である。そこでは、おまえ(現在)自身がどれほどまでに徹底的な根本体験の可能性を体得し釈意するべく憂えているか、という絶えざる問いが、現在に対し歴史の中から発してくるというかたちで、現在は自らのもろもろの根本動性において自分と出会わざるを得ないのである。』
安冨歩『生きるための日本史』,2021,青灯社, pp.18-19.
↑文中でハイデッガーが「現在」と書いているのは、「自分」と読み替えてよいようです。
ハイデッガーにとって、歴史――ここでは直接には哲学史――を探究する、認識するというのは、「自らのゲシヒテ〔起きたこと、生じたこと〕を解体しながらそれと対決する」ことにほかならない。たしかに、歴史認識にとっては、対象である過去の事実関係を「解体」する、分析する、という操作が不可欠です。ひとつづきで折り目も境目もない「歴史」という総体に対して、私たちは、それをいったんバラバラの破片に「解体」し、分析して調べ上げ、ふたたび自分なりの歴史像に再構成する、という操作を行なおうとします。これは、「歴史」という巨大な「総体」との戦いであり、「対決」なのです。この戦いにおいて、私たちが拠って立つ根拠は、私たちの「現在」のほかにはありません。
この戦いにおいて、「現在」は、「自らのもろもろの根本動性において自分と出会わねばならない」。すなわち、私たちは私たち自身の「現在」を――その「根本動性」のすべてを賭けて、「歴史」と対決するのですが、そこで私たちが出会う “敵” ――総体としての「歴史」――とは、「自分」すなわち現在の自分そのものにほかならない、とハイデッガーは言うのです。
これを嚙み砕いて言えば、安富さんが前の段落に書いていたように、私たちは自分の育った時代や、両親の生きた時代から、直接・間接にさまざまな影響や「傷」を刻印されて生きている。歴史の探究によって私たちが出会うのは、私たち自身に刻印された、そうしたさまざまのものの “正体” にほかならない。――ということになるでしょう。
こうした「歴史という自分」との出会いにおいて、私たちに対して「歴史」の側から発して来るのは、現在という「おまえ自身が、どれほどまでに徹底的な根本体験の可能性を体得し釈意するべく憂えているか、という絶えざる問い」だと言うのです。さあ、ここまで来ると、私にはいったい何のことかわからなくなります。関心のある方は、ハイデッガーの本を直接読んでみてください。
ところで、以上の行論の中途で、ハイデッガーは、彼が排斥する歴史叙述の態度を3つ挙げて揶揄しています。一般的な歴史の書物はみな、この3つのどれかだ。どれもこれも、真摯な歴史探究などではない、と言うのでしょう。ハイデッガーの「三連発」です。順に挙げてみましょう:
①『かつて自分がどうであったかを説明するための単なる付録』
②『他人がかつて何を「した」かを折にふれて回顧すること』
③『世界史についてのさまざまの楽しい見取り図を描いてみる』こと。
①は、過去に起きたことがらを適当に「ご説明」したり正当化するための、いわば「ていのよい言い訳」です。「単なる付録」というのは、対象を「解体」も解析もしないで、ただ適当な説明書きを考えて添付しただけ、というわけです。
②は、まったくの「他人ごと」として、そらぞらしく叙述された「歴史物語」のことでしょう。外国史の叙述には、そういうものが多いかもしれません。これは、自分の「現在」から離れた「客観性」のみを追求しようとする空虚な歴史観への批判でしょう。
③は、マルクス主義の「唯物史観」の図式――奴隷制→封建制→資本主義→社会主義 というアレ――が典型ですが、他にもさまざまに「楽しい」図式があります。ロストウの「テイク・オフ近代化論」など、そうでしょうし、戦後の日本では、梅棹忠夫氏の「生態史観」から始まって、廣松渉氏によるその変形、山口昌男氏、柄谷行人氏、などなど、まさに諸子百家の賑わいです。たしかに、どれを読んでもそれなりに面白く、楽しいのですが、同時に、この種の図式がどんなにたくさん現れて争鳴しようとも、虚飾を見るように空しいことを知るべきです。
よかったらギトンのブログへ⇒:
ギトンのあ~いえばこーゆー記
こちらは自撮り写真帖⇒:
ギトンの Galerie de Tableau