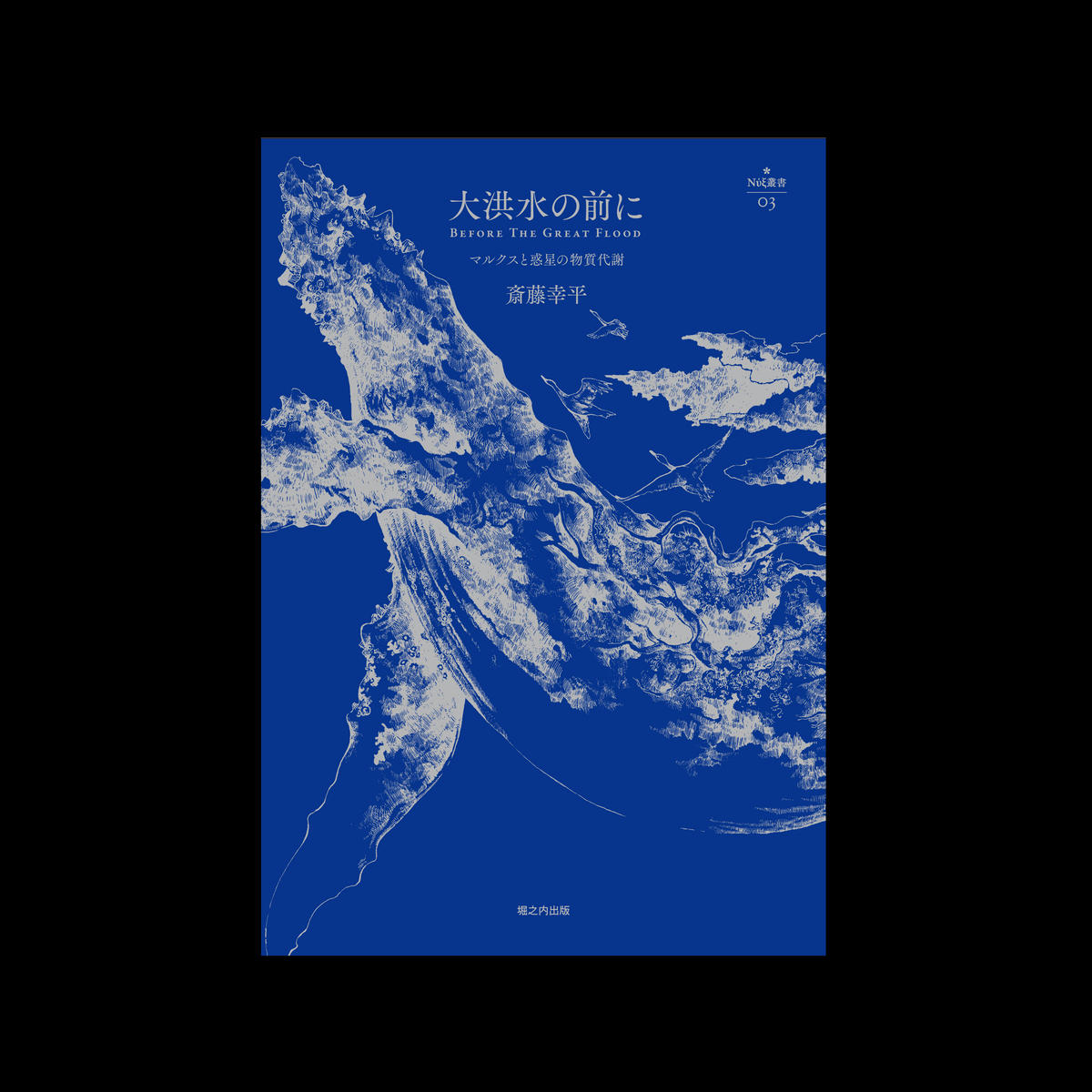〔8〕 「物質代謝」という概念
今回は、著者の博士論文の第2章「物質代謝論の系譜学」を
ダイジェストします。
著者によれば、『物質代謝』は、1866年の『資本論』第1巻以後の資本主義批判において、一方の柱をなす・マルクスのキー概念です。それは、『自然と人間の物質代謝過程』という言い方に示されるような、エコロジー的な意味合いをもっています。
いっさいの制約を突破して無限の『価値増殖』へと向かおうとする資本の運動は、『自然と人間のあいだの物質代謝』に亀裂を生じさせて、自然と人間を破壊し、労働の《疎外》をもたらします。
しかし、『物質代謝』という語は、マルクスの造語ではなく、当時(19世紀半ば)のヨーロッパで、さまざまな意味で使われていた、いわば流行語だったのです。もともとの意味は、生物が外界から取り入れた物質で体内の物質を更新する機能を意味する生理学用語でした。それが、一生物の機能を離れて広く、自然界での物質循環という意味で使われるようになり、さらにそのアナロジーで、おおざっぱに、社会の中でのさまざまな循環的な現象を指しても使われたのです。
『資本論』準備期の草稿類のなかでは、もっとも早い『物質代謝』の使用例は、1851年の『ロンドン・ノート』であり、そこでは、"社会の中での生産物の配分・取得・消費"という意味で、この語が使われています。近代社会では、『物質代謝』は貨幣との交換によって、広く行われうるけれども、古代社会では、特権層以外の者にとって交換は限られており、『物質代謝』は「彼を包摂している特定の分業に依存して」狭い範囲でのみ行われた、というのです(『大洪水の前に』,pp.80-82)。
1857-58年の草稿『経済学批判要綱』では、『物質代謝』は、3種類の意味で使われています。
① 『資本論』以降とほぼ同じ意味。人間と自然とのあいだの『物質代謝』は、歴史貫通的な『本源的』意味では、「生きて活動する人間たちと……自然的諸条件との統一」にほかならない。ところが、じっさいの(近代の)歴史社会では、『物質代謝』は、両者の「分離」を基礎としてしか生じない、と(『大洪水の前に』,pp.74-75)。
② 社会の中での商品交換――の意味で使われる場合。商品交換は、経済学的面では「形態転換」だが、使用価値の面から見ると、「素材転換(物質代謝 Stoffwechsel)」であると(『大洪水の前に』,p.87)。
③ 人間と関わりなく進行する、自然の『物質代謝』。自然の中での物質循環。たとえば、機械が錆びて崩れたり、食物が腐敗・分解する現象。この意味の用例は、『資本論』にも見られる(『大洪水の前に』,p.91)。
〔9〕 マルクスをリービッヒにつないだ男
ところで、初出例と思われる『ロンドン・ノート』の用例ですが、ここでの「物質代謝」の使用には、マルクス、エンゲルスの共通の友人であったケルンの医師ローラント・ダニエルスが関わっています。
ダニエルスは、1851年2月、自著『ミクロコスモス 生理学的人間学の構想』の刊行前原稿をマルクスに送り、批評を求めています。マルクスが、↑『ロンドン・ノート』で、彼としては初めて「物質代謝」という語を用いたのは、その翌月:3月なのです。ダニエルスの原稿が、マルクスにインスピレーションを与えたことはまちがえないでしょう。ただ、両者が用いているこの語の意味には、大きな違いがあります。
「『ミクロコスモス』は『行為の生理学的叙述』を通じて、『人間社会を唯物論的に把握する可能性』を示すことを目指した著作である。〔…〕生理学的知見を用いて、個人的ならびに社会的次元における人間の行為を唯物論的自然科学の対象にしようと試みている。そして、その中心概念が『物質代謝』であ」る。
「『ミクロコスモス』には、『物質代謝』という言葉が何度も登場する。ダニエルスは物質代謝を『同時的な破壊と創造であり、それによって身体がみずからの個体性を絶えず新たに作り出すことによって、維持する――非有機的物体の類のうちには類似物を見出すことができない特性――』過程として定義している。」
斎藤幸平『大洪水の前に』,2019,堀之内出版,pp.82-84.
つまり、ダニエルスは、本来の生理学的意味で「物質代謝」という語を
用いていました。そこには、生物の身体を構成している物質が、つねに
「破壊と創造」の過程にあって、物質的実体としては片時も同一に
とどまってはいないと同時に、そうやって転変しながら、しかも、常に
一定に「みずからの個体性を……維持」しているホメオスタシス
(恒常性)の側面が含意されています。
これは、リービッヒの『物質代謝』の定義に近いものです:
「リービッヒの『物質代謝』の定義によれば、それは有機体における物質の形成と排出からなる不断の化学的更新過程である。
『血の成分が脂肪、筋肉繊維、神経・脳物質、骨や毛髪などへ移行する〔…〕血に含まれる栄養物質の変態であるが、それは、新しい結合物が形成され、さらには排泄器官を通じて再び体から取り除かれる同時的過程なしには考えることができない。〔…〕』〔リービッヒ『農芸化学』1840年版〕
『大洪水の前に』,p.78.
しかし、ダニエルスの場合に特徴的なのは、そうした人間の『物質代謝』を、「動物的物質代謝と精神的物質代謝」に分けていることです。つまり、人間の精神活動も意識もすべて、『物質代謝』として説明しようとしたのです。その点、リービッヒはまだ"生気論"にとらわれていて、物質的な化学作用では説明できない「生命力」の存在を認めていました。ダニエルスは、リービッヒの不徹底さを批判して、「精神的物質代謝の唯物論的把握」によって、「心」と「身体」の哲学的二元論を否定し、心も精神も社会も、何もかも「物質の運動から万物を説明するラディカルな一元論を展開しようとして」いました。
「『人間有機体とその社会と自然への関係についての研究は共同的制度の改良、つまり社会改良のための唯一の確実な基礎をなす』〔ダニエルス『ミクロコスモス』〕」
『大洪水の前に』,p.85.
マルクスは、ダニエルスの『ミクロコスモス』に触発されて、『ロンドン・ノート』で「早速物質代謝の概念を自らの考察に取り入れ、生理学や化学にも興味をもつようになる。そして、リービッヒ『農芸化学』などの著作を同年〔1851年〕7月から研究し、『ロンドン・ノート』で抜粋したのだった。」こうして、「マルクスは物質代謝の概念を用いて、生産・交換・消費からなる社会的連関」の分析に向って行ったが、そこには、ダニエルスの↑上のような唯物論的構想「との共鳴を見出すこともできる」。
『大洪水の前に』,pp.84-85.
「不運にも、マルクスとダニエルスのさらなる知的交流はその後すぐに不可能となってしまう。1851年6月13日にケルンでの政治活動を理由にダニエルスが逮捕されてしまうのである。」『ケルン共産党事件』と称されるこのプロシャ政府による弾圧では、マルクスが議長を務めていた『共産主義者同盟』のメンバーが大量逮捕され、11人が裁判にかけられ 7人が有罪判決を受けた。ダニエルスは、その 11人の被告人のひとりとなった。彼は、『同盟』には所属していないとして冤罪を主張するが、彼の自宅から押収されたマルクスの手紙が、不利な証拠として法廷で読み上げられている。
1852年、ダニエルスは無罪判決を受けて釈放されたが、劣悪な拘留環境のために身体を壊しており、1855年に亡くなった(Wiki独語版「Roland Daniels」)。訃報に接したマルクスは、未亡人アマーリエ・ダニエルスに次のように書き送っている:
「『誠実で、忘れがたいローラント君が亡くなったという知らせに接した時の悲しみは、とうてい筆舌に尽くせません。〔…〕彼が若くして亡くなられたことは、ご家族や友人にとってばかりでなく、彼のこの上なくすばらしい業績を期待していた学界にとっても、また彼が忠実な先駆者の役割を果たしていた多くの苦しんでいる人々にとっても、何物にもかえ難い損失であります。〔…〕いつの日か故人の寿命を縮めた張本人どもに、追悼の辞などというよりももっと厳しい復讐を果たせるような世の中になればと思います。』」
『大洪水の前に』,p.86.
ケルン共産党事件。壇上左側に11名の被告人。
ダニエルスも、そのなかにいる。
〔10〕 《自然科学的唯物論》
じっさい、ダニエルスの無罪主張が認められたことから見ても、
彼は、マルクス、エンゲルスの敬愛する学問的友人ではあっても、
『共産主義者同盟』の同志ではなかったようです。『物質代謝』
をめぐる唯物論思想についても、ダニエルスは、マルクスや
ヘーゲル左派とは異なる《自然科学的唯物論》に属していたと
見ることができます。こんにちでは「機械的唯物論」と呼ばれる
思想的系譜です。両者の相違点は、たとえば、ダニエルスの
『ミクロコスモス』に関してマルクスがエンゲルスに書き送っている
批判的なコメントに表れています: マルクスによれば、
「ダニエルスの唯物論は、思惟、自由、人類史といったあらゆるものを『精神的刺激』に還元して、『刺激生理学的に』把握してしまうことで、素朴な物質主義に陥ってしまう危険性がある。〔…〕ダニエルスの唯物論にはあらゆる人間の活動を純生理学的で、社会的生産から独立した『反射運動』に還元してしまう傾向があるのである。それゆえ、『ミクロコスモス』は機械論的で、決定論的な見解との親和性が高いという欠陥を孕んでいた。」
『大洪水の前に』,pp.84.
《自然科学的唯物論》は、当時の産業革命期のヨーロッパでは、少なからぬ信奉者をもっていました。思想史的には、ビュヒナー、フォークトらがよく知られていますが、マルクス、ダニエルスとの関係で注目されているのは、オランダ人医師で生理学者でもあったモレスコット(Jacob Moleschott ドイツ語読みで、モレショットとも)です。フォークトは、‥‥
「精神の活動は『脳内物質の働きに過ぎず』、『思考の脳に対する関係は、胆汁の肝臓に対する関係や、尿の腎臓に対する関係と同じである』と主張した。モレショットも思想を脳内物質の運動に還元し、『思考とは物質の運動である』と述べている。肉体的・精神的活動や能力はどちらも根本的には、物質の摂取や排出によって規定されているとモレショットらは考えた。」
『大洪水の前に』,p.94.
しかし、たとえば、モレスコットは、生体の『物質代謝』の働きを重視するあまり、「人間とは、彼が摂取した食物のことだ」と言い切り、イギリスの労働者の勤勉さは、ローストビーフを食べているからであり、イタリアの乞食の怠惰は草食のせいだと述べています。ダニエルスも同様に、「肉食のインディアン」と「草食のインド人」の思考様式の違いを論じている。
たしかに、彼らの"自然科学的な人間観"の基本線は、今日でも通用するものですが、人間の精神活動のみならず、文化やさまざまな社会現象までも、人間の生理から短絡的に説明しようとする点に、大きな問題があることは否定できないでしょう。
リービッヒが土壌の無機成分(カリウム,リン,ケイ素,...)を重視し、それらは植物の生育に必須の養分であるとしたのに対し、モレスコットは、それを否定し、植物の栄養は、腐植(黒つち)に含まれる「腐植酸」〔当時存在すると信じられていた架空の物質〕であると主張しました。
「リービッヒは土壌の化学分析を通じて、それぞれの土壌にどういった養分が必要であるかを明らかにして効率の良い化学肥料を投入しようとしたのに対して、モレショットの物質代謝理解においては、自然の物質代謝は」、「腐植酸」を植物が吸収して、植物の枯死とともに再び土壌に還って「腐植酸」になるという永遠の循環過程――「輪廻」――がすべてだ、ということになってしまいます。肥料を作って投入するなどという人間の営為には、何の意味もないことになってしまう。人間も死ねば分解されて「腐植酸とアンモニア」になり、植物に吸収される。その限りで”自然の大循環”に参加しているにすぎない、ということになるのです。
『大洪水の前に』,pp.94-95,97.
〔11〕 『素材』的世界と、経済の『形態』メカニズム
しかし、これら《自然科学的唯物論》からマルクスが受けた影響は、
広くかつ深いものでした。「物質代謝」は、『人間と自然との物質代謝』
として、『資本論』以後のマルクスの基軸概念となりますが、
それにとどまらず、『物質代謝』のような「自然の『素材的側面』」が
経済のメカニズムという『形態的』世界に及ぼす影響を
しばしば取り上げ、注意深く考察しています。
たとえば、「固定資本」と「流動資本」の区別がそれです。イギリスの古典派経済学は、この区別に注意を払いませんでしたが、マルクスは、両者の回転期間が異なるために、そのズレが経済メカニズム――経済的『形態』規定――に対して及ぼす、制約的な影響について論じています。その発想のもとには、人体の生理における「物質代謝」――「絶えざる破壊と創造」――とのアナロジーが示唆されています:
「『人体の場合にも、資本の場合と同様に、再生産の際に様々な部分が同じ期間内に入れ替わるのではない。血液は筋肉よりも、筋肉は骨よりも急速に更新されるのであって、この面から見れば、骨は人体の固定資本と見なしうる。』〔『経済学批判要綱』〕」
『大洪水の前に』,p.105.
「流動資本」と「固定資本」の回転期間のズレが資本の運動に対して
及ぼす制約は、短期的には『価値増殖』の減速、長期的には
「利潤率の傾向的低下」です。機械化とイノベーションによって
「固定資本」比率が大きくなればなるほど、資本主義は『素材の
世界』に足を引っ張られることとなるのです。
「生産過程の素材的側面が、いまや『資本それ自体の質的な区別として、また資本の総運動(回転)を規定するものとして現れる』〔ebd.〕〔…〕この素材的制約は、資本の価値増殖過程にとっても重要な意義を持っている。例えば、固定資本の長期にわたる耐久性のために、資本の回転は遅くなり、価値増殖も減速する。さらに、この連関には、機械の導入と発展から生じる利潤率の傾向的低下を引き起こす資本主義の歴史的傾向性が含意されている。」
『大洪水の前に』,pp.106-107.
自然の『素材的側面』――つまり、物の『使用価値』の側面――が
経済の『形態的』メカニズムに及ぼす影響は、《自然》が資本の
『価値増殖』の運動を制約し、不安定化させるという形でも現れます:
「生産規模が拡大して、より多くの原料(綿花や鉄)や補助材料(石炭や石油)が必要となるにつれて、不安定な要因も増していく」。「『原料の再生産は、自然条件に結び付いたその生産性によっても左右される』」。凶作は、原料の生産量を減少させ、原料価格を沸騰させる。これは、原料の『価値』そのものが高騰するのだ。なぜなら、単位労働あたり産出する綿花の量は減少しているからだ。そこで、紡績工場の資本家は、資本を原料と労賃に配分する割合を変えなければならない。したがって、労働の投入を減らさなければならない。紡績機の一部は、動かす人がいなくなる。工場の生産量も売り上げも減少し、「『固定資本の一部分は遊休し、労働者の一部分は街頭に投げだされる。』
マルクスは恐慌が、生産過程の自然への依存性と無制約な資本蓄積への衝動のあいだの矛盾から生じる可能性を指摘している。〔…〕恐慌は、社会的物質代謝と自然的物質代謝のあいだの均衡における攪乱からも生じるということだ。
もちろん、〔…〕資本は自らが直面するあらゆる制約を乗り越えようとする。」「攪乱」を吸収して安定を維持しようとする「資本の弾力性」は、「素材的世界のもつ様々な弾力的な特性に基づいているのである。〔…〕
資本はこれまでよりも有用で、 廉価な原料や新しい市場を求めて全世界を探索し、自然科学やテクノロジーを発展させ、不作や資源枯渇が経済に致命的な攪乱を引き起こさないように防御策を張り巡らす。自然におけるあらゆる素材的制約を技術的・科学的支配を通じて乗り越えようとするのである。〔…〕とはいえ、その作用は〔…〕資本の価値増殖を最優先の課題として行われる限りで旧来の生活様式を破壊し、物質代謝の攪乱をより大規模でもたらすものである。
素材的弾力性は無限ではない以上、いくら市場を拡大し、技術を発展させたとしても、資本が乗り越えることのできない限界は常に存在し続ける。〔…〕資本主義は一方で自然の力――エネルギー、食料、原料――を徹底的に開拓していくことで、あらゆる制約を乗り越えようとするが、他方で、利潤獲得のための開発は世界規模で素材的世界に軋轢を生みだすことになる。つまり、資本は〔…〕自然と人間の物質代謝の亀裂を惑星規模でますます深刻化させ、人間的個性の自由で持続可能な発展を阻害する。ここに資本主義の生産力の発展が現実に克服することのできない限界があるのである。
〔…〕『ドイツ・イデオロギー』以降のマルクスは、〔…〕資本主義的形態規定との関連で物質代謝の包摂を分析しようとしていた。〔…〕つまり、資本の物象化のもとで被る労働過程の変容と、そこから生じる人間と自然の物質代謝の亀裂を分析するのが、『資本論』なのである。」
『大洪水の前に』,pp.107-110.
以上で、第2章のダイジェストを終えました。
第3章「物質代謝論としての『資本論』」は、ドイツの
ミヒャエル・ハインリヒらが進める「資本論の新しい読み方」と
著者ら日本の"マルクス研究最前線"とのあいだで資本論解釈が
食い違う部分。理論的にはたいへん興味深い争点なのですが、
ちょっと専門的すぎるので、飛ばします←
次回は、第4章「近代農業批判と抜粋ノート」。マルクスの
リービッヒ受容の経緯を丹念に追いかけた「抜粋ノート」研究
をダイジェストします。