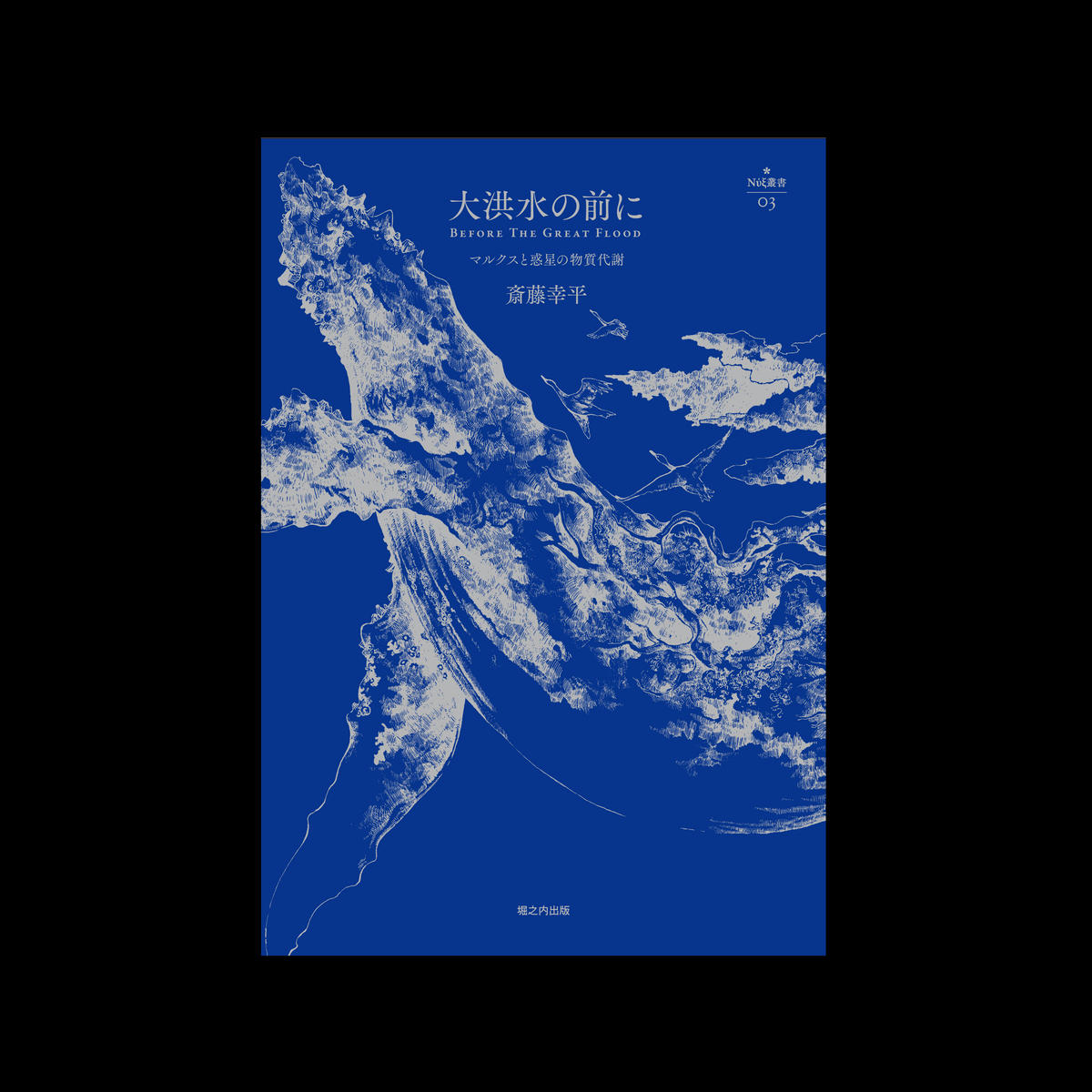〔4〕 『パリ・ノート』の《疎外》論
1843年秋、パリへ引っ越したマルクスは、エンゲルスの奨めもあって、スミス、リカードー、ベンサムなどイギリス古典派経済学を原著で読み、本格的に経済学の研究にとりかかった。映画『マルクス・エンゲルス』では、そのために英語を習い始めている。
「その過程で、翌年5~8月にかけて作成された抜粋ノート群は『パリ・ノート』という名称で知られている。このノートはあくまでも私的な勉強目的で作成されたものであり、」論文や著作の「草稿として執筆されたものではない。」抜粋のあいだに記されたマルクス自身の文章も、「抜粋を作成している流れのなかで思いついた発想が書き留められたもの」である。ところが、1931年にその一部が『経済学・哲学草稿』の名で『マルクス・エンゲルス全集』に収められて公表されると、その部分だけが、あたかも独立した著作のように扱われ、第2次大戦後に東西で大論争を引き起こした。「とはいえ、人間と自然の『統一』の意識的な再構築を将来社会の中心的課題として定式化したマルクスのノートには、注目すべき洞察が含まれている。」
斎藤幸平『大洪水の前に』,2019,堀之内出版,pp.29-32.
ただ、これをマルクスの経済学思想やエコロジーの典拠として読む場合には、①抜粋の部分も読む必要がある。マルクスの覚え書きは、読んだ本に対する・いわばコメントで、その前後に抜き書きされている抜粋とともに読んではじめて、真意を読みとることができる。ところが、『経済学・哲学草稿』版では、抜粋の大部分が省略されてしまっているので、『パリ・ノート』に戻って参照する必要がある。②マルクスの当時の理論的限界にも注意する必要がある。当時青年マルクスは、ルードヴィヒ・フォイエルバッハの『人間哲学』から大きな影響を受けていた。「そのため、『経哲草稿』にはあらゆる歴史的分析を抽象的で非歴史的な『本質』へ還元してしまう傾向があ」る。
『大洪水の前に』,pp.30,37.
フォイエルバッハの『人間哲学』は、社会の改革は、まず人間の「意識の
改革」からはじめなければならないと説きます。人びとは、宗教や
政治国家が与えるさまざまな“幻想”を、あたかもそれが現実であるか
のように信じて行動するので、迷妄から抜けきれない。哲学者は、
「神とは人間のことだ。」「神」とは、人間の自己意識を外部に投影
したものだ。あなた方は、自分の「似姿」を「神」と名づけて崇拝して
いるのだ。と、ことがらの『本質』を白日のもとに示して、人びとを
「夢から目覚めさせる」必要がある。そういう『啓蒙主義』でした。
人びとが“常識”だと思っている幻想に対して、それはほんとは、
こうなのだ。いっさいの偏見をとりはらって、人間としての感性に
したがって考えれば、わかるではないか!――と訴える。
《疎外》された現実に対して、“本来のもの”を持ち出して
対峙させる方法なのです。1944年の『パリ・ノート』の時点まで、
マルクスもまた、フォイエルバッハが言う「意識の改革」を
進めようとしていました。(⇒pp.60-61)
《疎外》という用語も、フォイエルバッハから受容したものです。
つまり、吉本隆明の「共同幻想」論みたいなもんですね。ただ、
フォイエルバッハとマルクスは、吉本とは違って、それを社会改革の
手段として意識していたのです。
そこでまず、『経哲草稿』(『パリ・ノート』)に関するこれまでの論争を整理すると、そこでは4種類の《疎外》が論じられている、とされてきました:
① 「労働生産物の疎外」: 「私的所有のシステム」の支配のもとでは、労働の成果であるはずの生産物は、労働者自身のものとして現れることがなく、「生産を通じた自分の能力の確証も与えられない。〔…〕『労働者が身をすりへらして働けば働くほど』」、彼をまわりからおびやかす「疎遠な、対象的世界」を強力にし、彼自身の内的世界を貧しくしてしまう。労働者は、労働を通じて外的世界を獲得するのではなく、逆に、彼の労働によって外的世界は「労働者を支配し、貧困化させる敵対的な力となる。」
② 「労働の疎外」: ①から導出される。「労働の結果が疎遠で、自立化した威力として現れるのは、労働者の活動そのものが、〔…〕他人に属するものとなっているからである。」本来、労働は、それ自体が目的であり、人間の自由な自己確証の活動であった。ところが、私的所有のもとでは、労働は、「生存のための単なる手段」、飲食、生殖のような「動物的機能のための手段」に貶められている。しかも、疎外された労働は、労働者の最低限の生存すら保証するものではない。
③ 「類的存在からの疎外」: ①,②から導出される。「本来、人間の本質的活動は自由で、意識的な生産によって特徴づけられており、そのうちに、人間の類的存在〔人類。ホモ・サピエンス〕としての普遍的性格が表れている。なぜなら〔…〕人間は自然に対して意識的に働きかけ、所与の労働対象や労働手段を能動的に大きく変えていくことができるからである。さらには芸術作品の制作」のように、目先の身体的欲求を抑えて生産活動に向かうこともできる点で、「労働は自由な活動だという。ところが、〔…〕類的本質の顕現としての自由で普遍的な創造性は疎外によって失われてしまう。」なぜなら、「『疎外された労働は〔…〕人間の類的生活を彼の肉体的生存の手段にしてしまう』」からだ。
④ 「他者からの疎外」: 「人間が必死になって自分自身の生存だけを追求するなら、他者との社会的協働は困難となっていくだろう。その結果、人間は類的存在としての生活を豊かにすることはできず、自由な他社との協働やコミュニケーションの代わりに、生き残りをかけての競争が支配的になっていくのである。」
斎藤幸平『大洪水の前に』,2019,堀之内出版,pp.32-35.
しかし、なぜ《疎外》が生じたのか? 人間の“本来”のあり方とは
異なる・労働者の悲惨な状態は、一体どういうことの結果として、
こうなってしまったのか? という質問への答えは、ここからは出て
来ません。実は、マルクスは、そちらのほうへ考察を進めているの
ですが、これまでのように、マルクスの抜き書きした抜粋を無視して、
コメントだけで意味を読みとろうとするやり方では、それは気づき
にくいのです。
つまり、マルクスは、現実に対して、“本来のもの”を対置するだけ
でなく、“本来”ではなくなってしまった理由、ないし過程を解明しようと
している。そのかぎりで、「意識の改革」というフォイエルバッハの
方法を乗り越えるほうへ、すでに一歩踏み出しているのです。
「『ロマン主義がこのこと〔土地の完全な商品化――ギトン註〕を嘆いてこぼす感傷的な涙は、われわれの知ったことではない。〔…〕第一に封建的土地所有はすでにその本質上、掛け売りされた土地であり、人間から疎外され、それゆえ、幾人かの数少ない大領主の形態をとって人間に相対している土地なのである。』〔『パリ・ノート』「第1草稿」〕
土地の商品化によって、土地所有者である貴族の気高い価値観や規範が失われ、ブルジョア的利己心が支配的になってしまったというロマン主義の嘆きに対して、〔…〕ロマン主義が拒絶する貨幣への際限なき欲求は、ブルジョア社会の合理性に照らし合わせれば、『必然的』で、『理性的』ですらある〔…〕近代的土地所有者の『浅ましい』振る舞いは道徳的欠陥ではなく、近代社会の合理性を端的に体現するものなの」だと、マルクスは言う。ロマン主義者は、それが理解できないために、過去を讃美して「近代市民社会の浅ましさをただ嘆くだけになってしまう。
ところが、実際には、封建的土地所有のもとでも支配・従属関係が存在しており、〔貴族(領主)以外の〕人間は土地から疎外されていたのであり、両者は〔土地は人間に対して――ギトン註〕対立していた」
『大洪水の前に』,pp.41-42.
〔5〕 大地と人間の『本源的一体性』の解体
「そのうえで、マルクスは封建的支配のもとで農奴が置かれていた状態について次のように述べる。
『すでに封建的土地所有のうちに、人間に対する疎遠な力としての土地支配が存在している。農奴は土地の付属物である。同様に、長男〔…〕は土地に付属している。土地が長男を相続する。そもそも土地占有とともに私的所有の支配が始まるのであり、土地占有はその土台である。しかし、封建的土地占有〔すなわち領主の占有(領有)〕においては少なくとも主人〔占有者=領主〕は占有地の王のように見える。〔…〕地所はその主〔領主〕とともに個人化し、その身分をもち、主とともに男爵領であったり、伯爵領であったりし、その特権、裁判権、政治的関係などを持つ。それはその主人〔領主〕の非有機的身体として現れる。』〔『パリ・ノート』「第1草稿」〕
封建的支配のもとで農奴は土地に対して自らの所有物として関わることができない限りで、自由な活動のための能力を奪われている。つまり、土地の独占のもとで、自然と労働からの疎外がすでにそこでも一定程度存在していたといえる。ここでは、自然は生産物を取得する土地所有者の『非有機的身体』として機能し、農奴は、〔…〕この非有機的身体の一契機(「付属物」)として作用している。〔…〕土地は領主の身体として『個人化』される〔…〕
封建的関係は『人格的』・『政治的』支配に依拠していたのであり、大地の生産物の取得は、領主が農奴に対して、直接的に生得的な特権をもった人格的権力として相対することで生じていた。〔…〕だからこそ、『一族の歴史、彼〔領主〕の家の歴史など』が支配の正当化のために不可欠の役割を果たしていたというのである。〔…〕こうして、土地と〔領主〕家族の歴史が土地の占有〔領有〕を『個人化』し、土地は領主の『非有機的身体』となるのである。」
このような「慣習と伝統に基づいた土地の個人化」に対応して、領主の農奴に対する「直接的な人格的支配」と生産物の収奪は、農奴に対して、独特の「生産者の土地への関係を生み出す。」
『同様に〔領主〕占有地の耕作者たち〔農奴と小作人★〕も日雇労働者のあり方をしているのではなくて、〔…〕主人〔領主〕の所有物であると同時に主人に対して敬意を払い、臣従し義務を負う立場にあるのである。それゆえに主人〔領主〕の彼ら〔農奴・農民〕に対する立場は直接的に政治的である〔家来として統率する――ギトン註〕とともに、また和気あいあいとした側面(eine gemütliche Seite)を持っている。〔領民の〕習俗、性格などは地所ごとに変わ」る。つまり、“何某伯爵領の領民に特有の風俗・性格”というものが形成される。「しかし後〔近代地主の場合――ギトン註〕にはただもう人間の財布だけ――彼の性格、彼の個性ではなく――が彼〔地主〕を地所へ関係させるようになる。』〔『パリ・ノート』「第1草稿」〕
註★「小作人」:中世末のイギリスでは、農民は、custom holder(農奴) と、定額の金納地代を支払う代わり身分的束縛からは解放されていた copy holder(小作人) からなっていた。
封建制のもとでは、土地の耕作者は人格的自律性を承認されず〔…〕土地の付属物として扱われる〔…〕この支配・従属関係は、近代市民社会における賃労働者の置かれている状況と決定的に異なっている〔…〕後者は直接的な政治的支配から解放され、自由で平等な法的主体である『人格』として承認されているからである。」しかし、だからといって賃労働者のほうが「自由で快適な生活を享受している」とは言えない。農奴は“土地緊縛”の裏面として「生産・再生産の客観的諸条件〔すなわち「大地」〕との統一を依然として維持していた」し、その限りで生存を保障されていたと言えるからだ。
「この点こそが疎外概念の理解にとって決定的である。封建制社会の人格的支配」のもとで、「耕作者は依然として『和気あいあいとした側面』を有していた」。農奴・小作人は、土地に対して無権利ではあったが、法的な人格否定・土地緊縛の半面で、「生産過程における自由と自律性」を維持していた。「ここでは資本の物象的支配の余地はない。〔…〕疎外も大きく抑制されていたのだ。〔…〕その根本的な一般的規定性は、土地と耕作者の統一性である。」
「土地の耕作者が人格の否定を通じて自然の一部となることで、自由や自律性を享受」できていた。"愉しき農夫"! その反面で、彼らの労働は牧歌的で生産性は低いので、「領主はわずかな収穫物しか手に入れることができない。」だからといって、資本家のように生産過程に介入して新しい農法を導入し生産力を上げて年貢を増やすことなど不可能だ。農奴も領主も慣習と宗教でがんじがらめで、生産過程は農奴の“昔ながらのやり方”にまかせておくほかないからだ。〔たとえば、各耕圃では各農民に1本の畝が割り当てられ、共同で同時に耕作された。耕圃に入る日もキリスト教の暦で決められていた。――ギトン註〕
「それに対して、近代社会においては、土地が完全に商品化され、〔…〕そこから〔…〕資本の非人格的で物象的な支配が生じ、疎外された労働が完全な形で成立する。
かつての人格的支配・従属関係が解体されることで、〔…〕形式的に自由で平等な『人格』という外見を生み出す。〔…〕だが、そのような外見の背後には、人格的な搾取関係の代わりに、非人格的な物象を媒介とした支配関係が入り込んでいる〔…〕かつての農奴が土地と強固に結びついていたのに対し、近代の労働者は〔…〕大地との結合を喪失し、本源的な生産手段から分離され」ている。「その結果、賃労働者は生存保証を失い、その活動は労働力の外化によって、他人に支配される。無所有、生活の不安定さ、疎外、搾取はすべて密接に連関しているのだ。〔…〕人間と大地の関係における歴史的転換が、資本主義的生産の特殊性を理解するために決定的なのである。
〔…〕近代の賃労働者はあらゆる直接的な大地とのつながりを喪失しており、自然から疎外されている。その結果が、自然、活動、類的存在、他者からの疎外、つまりは、生産における『和気あいあいとした側面』の完全なる喪失にほかならない。社会的生産は特定の具体的な欲求充足のために行われるのではなく、資本の価値増殖のために行われる。その際、個々の労働者は単なる価値増殖のための手段でしかない。〔…〕労働者の生活保障や生産過程における自律性はどんどん切り崩されていく。労働が疎外されていくのだ。」
『パリ・ノート』において、「マルクスは〔…〕資本主義的生産様式の特殊性と疎外の原因を封建社会との対比によってはっきりと把握していたのである。」マルクスのコメントを綿密に検討すれば、近代的「私的所有は、生産者とその客観的な生産条件〔大地〕の本源的統一の解体から生じるという論旨を」そこから読み取ることができる。
斎藤幸平『大洪水の前に』,2019,堀之内出版,pp.42-48.
〔6〕 解放への展望。「自由な個性の発展」
人間と”大地”の『本源的統一』が解体したために、
資本主義による『労働の《疎外》』が生じている――という
『パリ・ノート』の認識は、そのまま未来社会への展望につながる。
単純に考えれば、『本源的統一』を回復して《疎外》をなくせ!
ということになる。とは言っても、歴史をもとに戻すことはできない。
領主の支配のもとで農民の人格が否定されて宗教的慣習に
縛りつけられている状態は、『啓蒙主義』が批判してやまない
「意識の迷妄」だ。
そこで、資本家の代わりに、人格的に解放された生産者たちが、
平等な『アソシエーション』を結んで土地を共同で所有する
という構想が浮かび上がる。それが「共産主義」だと、
『パリ・ノート』のマルクスは言う。
(著者は否定するかもしれないが、)当時のマルクスは、プルードン
にも強い影響を受けていた。映画『マルクス・エンゲルス』を見ると、
それがよくわかる。プルードンの面前で彼を激しく批判するマルクスと
エンゲルス。それを、にこやかに迎えるプルードンの満足そうな微笑み。
『アソシエーション』は、もともとプルードンの用語だ。
「『アソシエーションは土地や地所に適用される場合には、〔…〕平等が実現される。アソシエーションはまたそれによって、理性的な仕方で――つまり、もはや農奴制や支配やばかげた所有神秘主義などによって媒介されていない仕方で――土地に対する人間の和気あいあいとした関係をつくりあげる。というのは、土地は〔商品市場での――ギトン註〕掛け売りの対象であることをやめ、そして自由な労働と自由な享受によって、再び人間の真なる、人格的な所有物になるからである。』〔『パリ・ノート』「第1草稿」〕
〔…〕つまり、ここでの人間と自然の統一は、〔…〕自由な社会的関係を、アソシエイトした諸個人による生産手段と生産物の社会的取得を通じて実現するものである。〔…〕『人間の真なる人格的所有物』としての大地との結合によって、万人による『自由な享受』が保証されるようになるのだ。マルクスの共産主義構想が疎外論の分析から一貫して導き出されていることがはっきりとわかるだろう。〔…〕
こうして打ち立てるべき共産主義『社会』は人間と自然の関係に対する意識的な組織と管理を現実化するものである。『こうして社会は人間と自然の本質的一体性の完成、自然の真の復活、貫徹した人間の自然主義と貫徹した自然の人間主義である』〔『パリ・ノート』「第3草稿」〕〔…〕これこそが、マルクスのエコロジカルな資本主義批判の始まり――もちろん始まりにすぎないとしても――なのである。」
『大洪水の前に』,pp.49-51.
以上のような歴史的展開に関するマルクスの着想は、
『パリ・ノート』から 1866年発刊の『資本論』第1巻まで一貫している。
封建社会における・生産者に対する人格的支配・の消滅、人間と
大地との『本源的一体性』の解体の結果、資本主義社会における
《大地》と人間の商品化、資本の支配と労働の《疎外》が成立した
過程は、『資本論』でも「本源的蓄積」として詳細に述べられる。
しかし、構想を発展させてゆく過程で、マルクスが、
封建社会と資本主義社会のあいだに挟まれた短い時期――
「イングリッシュ・ヨーマン」(独立自営農民)の時代、独立した商品生産者
の社会――に注目していることは、特筆に価するだろう。
1858年の『経済学批判・原初稿』で、マルクスは書いている:
「『農民はもはや、自分の土地生産物をもち、みずから農耕労働にたずさわる農民としてではなく、貨幣占有者として、地主に対峙している。〔…〕彼の生産物は自立した交換価値、一般的等価物、つまり貨幣であるから――〔…〕こうして〔地主と農民の関係の〕以前の形態〔=領主・農奴関係〕において〔両者の〕取引をすっぽりと包み込んでいた和気あいあいとした外見は消えてなくなる』
これに続く叙述でマルクスは、「『人格的な依存関係の棄却』の結果として支配関係が純粋に経済的な関係へ変容することを『市民社会の勝利』とみなしている。社会関係は商品と貨幣によって媒介され、商品所持者たちは形式的に自由で平等な人格として市場で相対するが、
現実にはこの関係は〔まもなく〕不自由と不平等の関係へ転化する。〔市場での競争の結果、貧富の差が拡大し、資本家と貧民、労働者に分かれてしまう――ギトン註〕その結果、資本主義社会においては『和気あいあいとした外見』さえも消失してしまうというのである。」
『経済学批判要綱』「第2部」(1857-58)では、次のように述べる: 資本主義社会では、労働者は、「みずからを実現するための物質的条件〔《大地》との結合〕を欠いているため、資本の支配に従属しなければならない。〔…〕
それに対して、『奴隷・農奴関係』においては、『こうした分離は生じない』〔…〕というのも『〔…〕労働そのものが生産の非有機的条件として、家畜と並んで、あるいは大地の付属物として、他の自然的存在と同列に置かれ』ているからである。それゆえ、この『前ブルジョア的な関係』においては、個人は『労働する主体』として振る舞うことができるというのだ。〔…〕この〔農奴が持つ〕労働者〔として〕の主体性のうちに、直接生産者として〔…〕農奴が有する個体性の自由な発展の潜在性★を見出すことができるだろう。〔…〕土地との統一性のために、彼らは生産過程における一定の自立性を有しており、小経営のもとで、みずからの生産手段と生産物を取得していた。この特殊な関係性が、封建制から資本主義への移行期において、『自由な個性の発展』のための物質的条件を提供したのである。
マルクスはこの移行期を『解放された労働にとっての黄金期』と呼んでいる〔…〕
『自由な個性の発展』は、マルクスがアソシエイトした生産者からなる将来社会〔すなわち共産主義社会〕を描く際に用いる表現であるが〔たとえば、『要綱』「第1部」〕、ここでマルクスは例外的に前資本主義社会〔というより、資本主義直前の社会――ギトン註〕における小経営に〔…〕その可能性を見出している。政治的・人格的従属関係の解体は、人間と自然の関係のうちに存在していた『和気あいあいとした側面』を支配関係なしに共同的に構築することを可能とし、人々はその自由を享受することができたからである。」
『大洪水の前に』,pp.51-57.
註★「農奴が有する…潜在性」: ここでは、農奴から独立自営農民(ヨーマン)への発展の連続性が強調されている。農奴は、生産過程において一定の自立性を持っていたので、身分的束縛が弛緩するにしたがって、その自立性が、自由な個人として「個性を発展」させてゆくための基盤になった、というのである。
〔7〕 『ドイツ・イデオロギー』――《物質代謝》の発見
「1845年以降、マルクスはそれまで絶賛していたフォイエルバッハ哲学を批判するようになっている〔…〕
それは『ドイツ・イデオロギー』におけるマルクスのヘーゲル左派批判のうちに見てとれる。つまり、彼らが疎外された現実に対して、ただその真なる『本質』を認識論的に対置しているだけであり、特定の社会的諸関係のもとで疎外が必然的に生まれる客体的条件を解明していないという点に批判が向けられるようになっているのである。〔…〕フォイエルバッハは『哲学者の「眼鏡」』を通じて現実を考察し、ただ認識的転換を社会変革の手段として要請しているにすぎないというのである。
〔…〕『ドイツ・イデオロギー』は哲学内部での真なる原理の『対置』というアプローチそのものを退ける。〔…〕フォイエルバッハが目指していたのは、神は幻想であり、」「神」とは、類的存在としての人間である「という真理を大衆に啓蒙することであった。ところが、フォイエルバッハは『人間がこれらの幻想を自分の「頭のなかへ入れた」ということはどうして起こったのか?』と問いはしない、とマルクスは批判する。『現実的、物質的な前提そのもの』を変革することがなければ、宗教的『幻想』は絶えず社会的実践によって客観的に再生産され続けてしまう。〔…〕
私たちは、現実の社会的諸関係から自由に、本質へのアクセスを保証するような純粋な感性を持つことはできない。〔…〕フォイエルバッハが追い求める『現実的』自然や『現実的』人間なる本質はそもそもどこにも存在しないのであり、自然や人間は特定の社会的諸関係のもとでつねに、すでに変容されている。〔…〕唯物論は諸個人が常に特定の社会的諸関係によって媒介されているという事実から出発しなくてはならない。
同じことは『自然』についても言える。〔…〕現実の自然は、常に一定の社会的関係のもとで、人間の生産活動を媒介として変容されているのである。そして、この歴史的環境が人間や動物の生活も規定しているのだ。だからこそ、人間と自然の関係性の変容を分析する必要がある。
〔…〕単に人間と自然の関係は本源的なもので、両者が相互規定のうちにあるという自明な事実を述べるだけでは不十分である。あるいは、人間と自然が本来統一的に存在しているべきなのに、資本主義のもとで両者の関係が疎遠になっていると非難するだけでは不適当なのである。〔…〕資本主義において、その人間と自然の歴史的に特殊な媒介過程がどのようにして構成されるようになるかを分析し、『なぜ』・『どのようにして』人間と自然の関係が疎遠で、敵対的なものとして現れざるをえないかを解明しなければならない。」
『ドイツ・イデオロギー』以後の「経済学研究と並行しての自然科学研究こそが、まさにこの」理論的「課題を遂行するものであり、人間と自然の関係の歴史的変容を明らかにしようとする試みだったのである。そして、その鍵となるのが『物質代謝』概念なのだ。」
斎藤幸平『大洪水の前に』,p.59-60,64-69.
エンゲルスとの共著草稿『ドイツ・イデオロギー』(1845年)は、
ドイツ観念論哲学との訣別点であり、
マルクスの経済学・エコロジー研究の出発点となりました。
それは、人間と《大地=自然》との『本源的統一』‥の解体、すなわち
人間と自然の関係‥の歴史的変容――を分析する出発点であり、
そこでのキー概念は、《人間と自然の物質代謝》‥の歴史的変容です。
それは、人間の側からいえば、商品、価値、資本の運動による
生産過程の変容と『本源的蓄積』、『外部化』、《労働の疎外》であり、
自然の側からいえば、《掠奪農業》による《大地》の消耗、
物質循環の阻害、労働者の生理的限界を超えた効率の追求、
資本の無限運動と《自然》の限界との衝突、といったことなのです。
すなわち、『ドイツ・イデオロギー』は、(狭義の)経済学批判と
経済学批判としてのマルクス・エコロジーの出発点となった。
その分析の中心概念が、『物質代謝』なのです。
以上で、第1章のダイジェストが終りました。
次回、第2章では、マルクスが『物質代謝』という
生理学概念を取り入れた経緯が語られます。
この用語を彼に教えたのは、親友の医師でした。
そこには、マルクスの"あまりに人間的な"姿が
浮かび上がるのです。