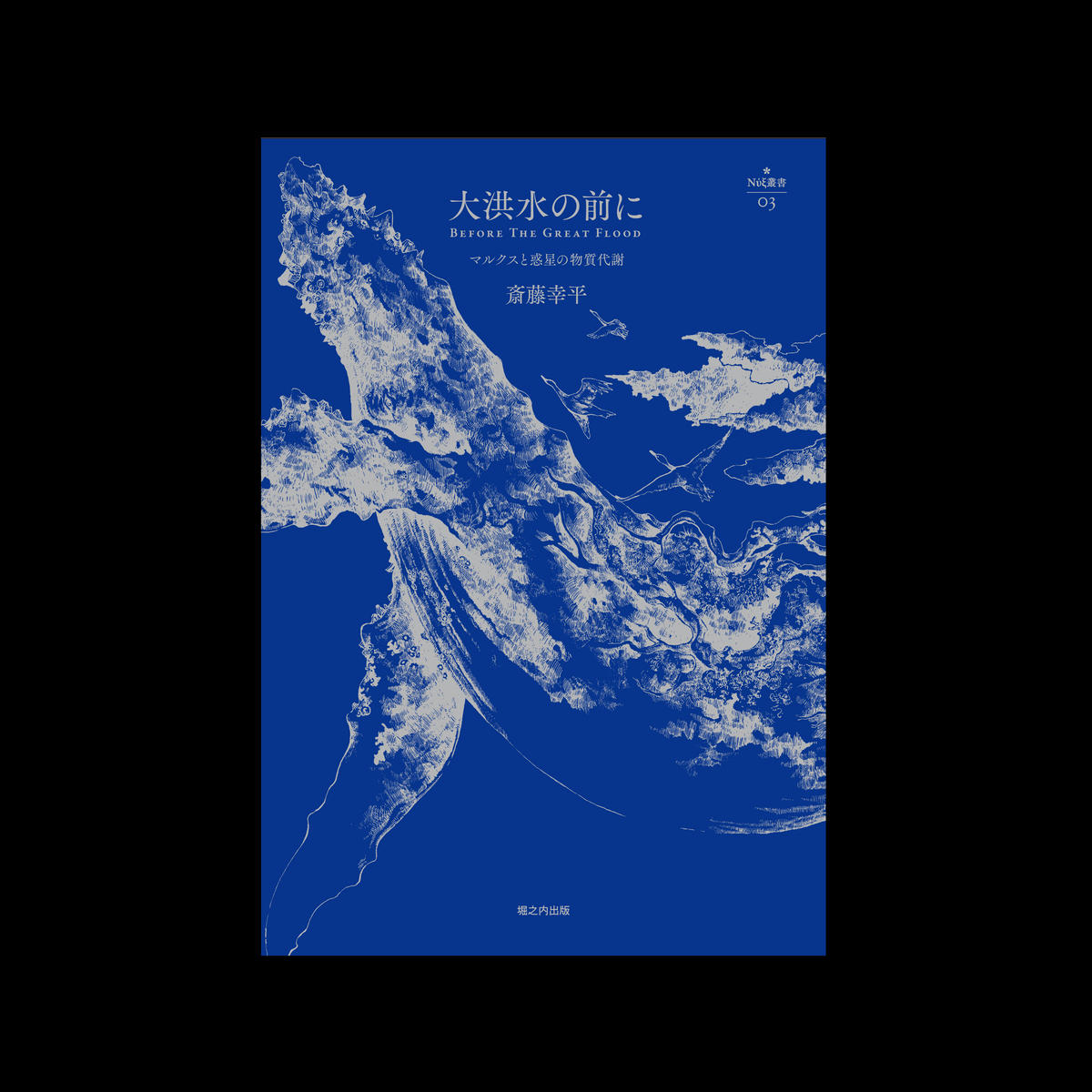「ひとつの幽霊がヨーロッパに出没する。あのマルクスの幽霊が。。。」
『人新世の「資本論」』で一世を風靡している著者が
2014年にドイツ・フンボルト大学に提出した博士論文。
すでに、4ヶ国語で出版されており、これは 2019年に
刊行された日本語版。博士論文に加えて、その後の
著者の論文を収録している(第4~7章)。各論文は
マルクスの諸著の解釈を論ずるもので、『人新世の
「資本論」』とはちがって、たいへん専門的な内容です。
しかし、著者の行論は論旨明快なので、私のような
専門知識のない者でも、どうにか付いてゆくことが
できる。その点が、ネグリ/ハートの『〈帝国〉』のような
一般向きに書かれているわりには難解きわまりない
問題作との違いでしょう。
今回は、著者の「はじめに」をダイジェストしたいと思います。
〔1〕 エコロジーなくして、マルクスは理解できない。
環境問題が世界的に提起された 1970年頃以後「数十年間にわたって、マルクスの思想は『プロメテウス主義』――極端な生産力至上主義であり、技術進歩によって、あらゆる自然的限界を突破して、世界全体を恣意的に操ることを目指す近代主義の思想――であると批判され続けてきた。」
もっとも、近年では、「日本語圏やドイツ語圏とは異なり、英語圏を中心に『マルクスとエコロジー』というテーマは大きな進展を遂げている〔…〕なかでも重要な著作が、ポール・バーケット『マルクスと自然』(1999),ジョン・ベラミー・フォスター『マルクスとエコロジー』(2000)だろう。〔…〕バーケットとフォスターは、マルクスとエンゲルスの著作や草稿などを丁寧に調べ上げることで、これまで見逃されてきたマルクスとエンゲルスの深いエコロジーへの関心を浮かび上がらせ、『プロメテウス主義』というレッテル貼りが誤っていることを説得力ある形で示したのである。〔…〕その鍵となる概念が、本書でも中心的な役割を果たす『物質代謝の亀裂(metabolic rift)』であり、マルクスの物質代謝論は資本主義的生産が人間と自然の関係性を惑星規模でどのように歪め、持続可能性の条件を破壊していくかを分析可能にしてくれるというのである。
その後 10年以上経って〔…〕プロメテウス主義〔生産力至上主義だ…〕という理由でマルクスを端から退けるような解釈は、〔…〕もはやほとんど採用されなくなりつつある。〔…〕
なるほど、バーケットやフォスターは様々なテクストを隈なく調べることで、マルクスの環境思想を浮かび上がらせることに成功している。ところが、その結果として、彼らがマルクスとエンゲルスも区別せずに、両者のテクストを恣意的に切り取って寄せ集めているにすぎないかのような印象を与えてしまっている。〔…〕
本書の目的は〔…〕、より体系的で、より包括的な形でマルクスのエコロジカルな資本主義批判を再構成していく。〔…〕まずマルクスのエコロジーを経済学批判との明確な連続性をもつものとしてより『体系的』に展開していく。さらに、〔…〕マルクスが〔…〕熱心に自然科学を研究するようになり、新たな知見を『資本論』に取り込んでいった過程が明らかとなる。その際の鍵となる概念が『物質代謝(Stoffwechsel)』〔…〕であり、この概念に着目することで、マルクスのエコロジーがもつ体系的性格を論証できるようになるのである。
〔…〕本書では、マルクスの環境思想を経済学批判にとって欠かすことのできない契機として体系的に展開する〔…〕本書が押し出すのは、〔…〕『マルクスの経済学批判の真の狙いは、エコロジーという視点を入れることなしには、正しく理解することができない』というテーゼだ。つまり、マルクスの経済学批判の体系的意義は、エコロジーという要素を十分に展開することによってはじめて明らかとなるのである。」
斎藤幸平『大洪水の前に』,2019,堀之内出版,pp.5,8-13.
『生産力至上主義』とは、やや乱暴に一言でいえば、“人間は自然を
どうにでも支配することができる。科学技術の可能性は∞であり、
自然のキャパシティ(容量)も∞である”という思いこみです。
これは、近代に特有の考え方です。資本主義の特有の運動――
無限の『価値増殖』をめざす運動――が、私たちに“無謀な夢”を
見させるのです。
著者の言う「マルクスのエコロジーのもつ体系的性格」とは、
これまた、著者の各章での議論を先取りして乱暴に言ってしまえば
マルクスの“経済学”体系は、いわば両面の盾であって、
経済学とエコロジーという両面が密接に結びついたものである――
ということです。
青年マルクスは、ヘーゲル左派の哲学者として出発しましたが(
学位論文は、デモクリトスとエピクロスの原子論の違いについて)
エンゲルスの影響を受けて、イギリスの古典派経済学を学び(
そのために初めて、英語を習ったらしい)、古典派経済学を批判して
独自の経済学体系を構築します。だから、彼の経済学は、
「経済学批判」なのです。著者によれば、マルクスの
「経済学批判」は、狭い意味での“経済学”,およびエコロジー
‥という両面から、なっています。つまり、エコロジーは、
マルクスの「経済学批判」体系の不可欠の構成部分なのです。
マルクスが、この“両面的批判”の着想をつかんだのは、1844/45年に
エンゲルスと共著『ドイツ・イデオロギー』のための草稿を練っていた
時でした(結局、この共著は完成に至らず、草稿はお蔵入りになって
しまいますが)。
〔2〕 『素材』と『形態』の弁証法
「マルクスの価値論と物象化論に着目し、マルクスの形態規定論にとって『素材』の次元が決定的であり、資本の論理による素材的世界の変容とその矛盾をめぐる分析が『資本論』の中心的テーマであるであることを示していく。〔…〕別の言い方をすれば、物象化の矛盾はエコロジーの領域において顕在化するのであり、マルクスはそこに資本の論理に対する抵抗の可能性を見出そうとしていた。」
斎藤幸平『大洪水の前に』,p.13.
↑この部分では、マルクスのエコロジーと(狭義の)経済学の
関係について、本篇を先取りしてかんたんにまとめています。
(ここは、「はじめに」の一部)
そこで、荒く説明すれば、『素材』の世界とは、エコロジー,《自然》
のことであり、それに対して、人間社会,経済活動の世界は
『形態』と呼ばれます。『形態』の世界では資本主義が支配します。
資本主義は、『素材』の世界を収奪して無限の『価値』増殖を進め
ようとし、また『物象化』によって、人間と自然の『物質代謝』(つまり
労働)を歪めてしまいます。資本主義の侵入によって、『素材』の
世界は変容させられていきますが、資本主義が望むように無限に
変容できるわけではない。《自然》には限界があるからです。
こうして、「資本の論理」は、『素材』世界の限界にぶつかって、
矛盾を露呈するようになります。それが、マルクスの時代から
警鐘を鳴らされていた・掠奪農業による「地力の消耗」であり、
工場の環境汚染であり、最終的には《気候危機》として顕在化
しているわけです。こうした矛盾の爆発が、資本主義に対する
「抵抗」のきっかけにもなりうることは、今更言うまでもないでしょう。
しかし、「物象化の矛盾」の顕在化とそれに対する「抵抗」は、狭義の
エコロジーの領域に限られません。マルクスは『資本論』第1巻第3篇
第8章「労働日」,第4篇第13章「機械と大工業」で、資本の「際限のない
増殖運動」が労働時間を極限まで延長して労働者の生存期間さえ縮め、
労働者の主体性を剥奪する状況を、イギリスの工場監督官報告書に
基いてレポートしています。そして、労働者の抵抗運動の結果、国家の
強制法による労働時間制限が実現し、職業教育が拡充されつつある
ことを高く評価しているのです。なぜなら、コミュニズムの目的は、資本
の支配からの労働者の解放であり、その核心は、生産過程における
主体性・自律性の回復にこそあるからです。
(『大洪水の前に』,pp.144-151)
「本書のアプローチは近年ドイツで流行しているミヒャエル・ハインリッヒに代表される『新しいマルクスの読み方(neue Marx-Lektüre)』とは大きく異なっている。というのは、マルクスの実践的・批判的な唯物論的方法で問題となるのは、経済的形態規定と具体的素材的世界の連関とその矛盾についての分析だからだ。〔…〕経済的形態規定がその担い手である自然の素材的次元との緊密な関係のもとで考察されなくてはならない。〔…〕『素材』の体系的役割が経済的『形態』との関係で正しく理解されるなら、環境破壊とは両者の亀裂から生じる矛盾にほかならないことが直ちに判明し、エコロジーを経済学体系のうちに容易に取り込めるようになる〔…〕エコロジーをもってして、経済学批判の体系性をはじめて十全に展開できるという命題の意味が理解可能になるのである。」
『大洪水の前に』,pp.15-16.
マルクスの体系的批判の中心は、
資本主義「経済」社会と、歴史貫通的な《自然》世界、すなわち
「経済的『形態』規定と、具体的『素材』的世界」のあいだの
密接な連関と矛盾の分析にあるのでした。
つまり、人間の生産活動も経済全体も、《自然》や生身の人間を
『素材』としてしか営めない(密接に連関する)ものであるのに、
資本主義の飽くなき『価値』増殖と“歪める力”が、《自然》と人間と
人間の活動を、むりに変容させようとして矛盾をきたし、
ついに資本主義を機能不全に至らせる。――――
マルクスの「経済学批判」の勘どころは、
(著者によれば)そこにあるのです。
ところが、ドイツのミヒャエル・ハインリヒを中心とする
『新しいマルクスの読み方』は、この点を把えそこなっています。
彼らは、『素材』的世界に関するマルクスの叙述(抽象的人間労働)を
軽視する結果、『素材』的世界(使用価値の世界)が、
「資本の論理」によっていかに歪められてしまうかを
分析してゆくマルクスの方法を、
十全に理解できないこととなります。
「抜粋ノートを考慮すれば、〔…〕『資本論』第3巻を完成させることがあったなら、――『物神崇拝』や『利潤率の傾向的低下法則』と並んで――『物質代謝の亀裂』を資本主義の中心的矛盾として扱うようになっていたのではないかという推測があながち的外れではないことがわかるはずである。」
『大洪水の前に』,p.17.
マルクスは『資本論』を完成させることなく、亡くなりました。
第1巻刊行後の 1868年に経験した大きな「理論的転換」が
構想の大幅な変更を不可避にし、マルクスは新たな構想をめざして
自然科学を中心とするエコロジーの研究に邁進するのですが、
原稿の完成には至らなかったのです。しかし、彼は、準備の記録を
遺しました。なかでも重要なのは、農学,化学,地質学などのさまざまな
文献からの抜粋を記したノートです。それらを精査した結論として、
“マルクスがもし『資本論』を仕上げていたとしたら、その最終章には、
『物質代謝の亀裂』が、「資本主義の中心的矛盾」のひとつとして
挙げられていただろう”―――と著者は言うのです。
〔3〕 「ノアの洪水」も恐くない。突き進む資本主義。
「なぜこれほど長いあいだマルクスのエコロジーは無視され続けてきたのだろうか? 〔…〕スターリン主義を批判した西欧マルクス主義もその隠蔽に加担してきたのである。実は、この問題には、エンゲルスの存在が関係している。第7章でみるように、マルクスの 1868年における理論的転換の結果、マルクスとエンゲルスの問題関心はずれをみせるようになっていく。エンゲルスは自然科学による宇宙の唯物論的説明を目指していたのであり、この違いがエコロジーという領域においても両者の見解に重大な相異を生み出すことになる。〔…〕まさにこの差異のために、マルクスのエコロジーはエンゲルスやその後のマルクス主義者たちによって軽視され、場合によっては抑圧されることとなったのである。
〔…〕21世紀に入ってからマルクスのエコロジーは深刻な環境危機を前にラディカルな左派環境運動によって再び注目されるようになっている。新自由主義的グローバル資本主義が〔…〕世界を包み込んだ結果、〔…〕惑星規模の環境危機をもたらしたことで、マルクスの有名な警告がいま再び現実味を帯びるようになっているのだ。
『〔…〕資本は、その実際の運動において、人類の将来の退廃や結局は食い止めることができない人口減少という予想によっては、少しも左右されないのであって、〔…〕誰もが〔愚かしくも〕望んでいるのは、自分が黄金の雨を受けとめて〔自分のものになった黄金を〕安全な場所に運んでから雷が隣人の頭に落ちるということである。大洪水よ、我が亡き後に来たれ! これが、すべての資本家、すべての資本家種族のスローガンである。』〔『資本論』第1巻, MEGA Ⅱ/6, S.273〕
〔…〕引用中に出てくる『人口減少』を『気温上昇』や『海面上昇』に置き換えたとしてもなんら違和感がないだろう。〔…〕
将来のことなど気にかけずに浪費を続ける資本主義社会に生きるわれわれは大洪水がやってくることを知りながらも、一向にみずからの態度を改める気配がない。とりわけ、1%の富裕層は自分たちだけは生き残るための対策に向けて資金を蓄えているし、技術開発にも余念がない。
だが、これは単なる個人のモラルに還元できる問題ではなく、むしろ、社会構造的問題である。それゆえ、世界規模の物質代謝の亀裂を修復しようとするなら、その試みは資本の価値増殖の論理と抵触せずにはいない。いまや、『大洪水』という破局がすべてを変えてしまうのを防ごうとするあらゆる取り組みが資本主義との対峙なしに実現されないことは明らかである。」
『大洪水の前に』,pp.21-23.
『資本論』第1巻刊行の段階で、マルクスとエンゲルスは、『エコ社会主義』
というべき共通のビジョンに達していました。資本主義の成果である
発展した『生産力』を継承し、さらに発展させてゆくとともに、資本主義の
『素材』的世界――《自然》と人間――に対する“歪める力”を除くために
国家社会の体制を社会主義に変更し、社会主義のもとで『生産力』を
高めてゆこう‥‥というビジョンでした。
マルクスのほうは、その後 1868年の「理論的転換」で、さらに
エコロジーへの傾斜を強めてゆくのですが、エンゲルスは『エコ社会主義』
にとどまり、1882年までに書かれた『自然の弁証法[遺稿]』では、
人間は「自然において作用する諸力の法則性を認識することによって、
自然を人間の意識的な制御のもとにおくこと」ができる。
人間は、「自然の意識的な、本当の主人」となるべきであって、
それこそが「自由の国」であり、理想的な社会主義なのだ、
と述べているのです。(『大洪水の前に』,p.203)
つまり、マルクスとエンゲルスは、ともに晩年は自然科学の研究に
向かったのですが、二人の進んだ方向は異なっていた。エンゲルスは
“人間が自然を支配する”、資本主義の影響も除去したうえで完全に
支配することを、めざしたのですが、マルクスは逆に、《自然》の限界を
わきまえ、人間と《自然》との関係を意識的にコントロール(自制)
しながら、《自然》との「持続可能な関係」を築いていこうとしたのです。
しかし、資本主義が環境との矛盾を、最期的な巨きさで顕在化している
この《気候危機》の時代に、二人が生き返ったとしたら、二人は一致して
「危機をもたらしているのは資本主義だ。破局を回避するには、
資本主義を廃棄する以外に道はない!」と叫んだことでしょう。
さて、以上で、著者の「はじめに」を、ひととおり読み終りました。
次回は、博士論文にあたる第1~3章へ読み進めることとします。