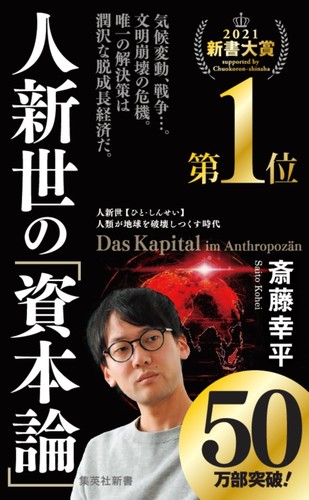著者は 1987年生れ、権威ある「ドイッチャー賞」を
2019年史上最年少で受賞した気鋭の経済学者。
受賞の前著『大洪水の前に』では、なお、ゆるやかな
成長経済を支持していたが、本書では
この経済界と全世界と左翼の“常識”に叛旗を翻し、
すべての「マルクス主義」者と大部分の経済学者を
敵に回して、《脱成長》をはっきりと打ち出すに至った。
というのは、この間の《気候危機》の進行はあまりにも
急速で、もはや経済成長を目標にしていたのでは
経済と社会の全面的な破局を防げないと
判断したからなのです。
「全面的な破局」とは、私たちのグローバルな経済を
支えている《資本主義》システムが機能しなくなり、
終りのない混乱に陥るということです。それに比べれば
「コロナ・パンデミック」などは、一過性の
危機にすぎなかったと振り返ることになるだろう、
破局は数十年のうちにやってくる、
と著者は警告するのです。
「大げさな‥」と言うかもしれない。
「陰謀論じゃないのか」と疑うかもしれません。
しかし、「危機」についての詳細は次回に
ご紹介するとして、今回は、著者が提唱している
《脱成長コミュニズム》という対案を、手はじめに
瞥見しておきたいと思います。
脱成長《コモン》のイメージとしては、
「生産協同組合」方式の農場や、労働者が共同管理する
工場などが例として挙げられますが、それにとどまらない。
重要な点は、専門家、政治家、政府を頂点とする
“トップダウン”方式ではなく、構成員や市民の協議・協力
による“自治”が基本になるということです。
たとえば、現在フランスでは、《気候危機》への対処として
なされるべき政策を、市民から寄せられた多数の案
のなかから、陪審制(くじ引き)で選ばれた市民が
決定する「気候市民議会」が行われている。これは
“過激”な非暴力「黄色いベスト」運動の成果として
マクロンの譲歩で実現したものです。
また、エコロジカルな(人と自然の代謝という)面
について言えば、日本の江戸時代の「里山」経済は
《コモン》にかなり近いところまで行っていたと
私は思います。(著者は言っていませんが)
植林された入会地から流れ出る肥沃な水は
海に流れこんでプランクトンを増やし、
海で漁れる「干鰯」と入会地で採取される「刈敷」
が肥料として施され、耕地の地力を回復したのです。
そこでは、定常的・持続的な《循環》(成長ではなく!)
が実現されていました。
このような《脱成長》の思想にマルクスが
たどりついたのは、最晩年のことでした。そのため
『資本論』には、まだそれははっきりと表れていない。
『資本論』は、むしろ《生産力至上主義》
として、これまで理解されてきたのです。
こうして 20世紀の「マルクス主義」、たとえばソ連は
急速な経済成長を(統計をごまかしてまで)誇って
いました。その結果は、自然と社会の
広汎な破壊・荒廃にほかなりませんでした。
「20世紀のマルクス主義は、社会主義になれば、労働者たちが技術や科学を自由に操るようになって、自然的制約も乗り越えられると楽観視していた。〔…〕
だが、そのような生産力至上主義は間違っている〔…〕
『資本論』を、『脱成長コミュニズム』という立場から読み直すことが必要なのである。〔…〕つまり、〔マルクス〕晩年のエコロジー・共同体研究の意義をしっかりと押さえることではじめて、浮かび上がってくる『資本論』に秘められた真の構想があるのだ。〔…〕
マルクスの脱成長の思想は 150年近く見逃されてきた。そのため、〔…〕経済成長をスローダウンさせるという文脈では、けっして定式化されてこなかったのである。〔…〕
減速は、加速しかできない資本主義にとっての天敵である。無限に利潤を追求し続ける資本主義では、自然の循環の速度に合わせた生産は不可能なのだ。だから、『加速主義』ではなく『減速主義』こそが革命的なのである。」
『人新世の「資本論」』,pp.298-300.
著者は、「ドイッチャー賞」受賞作『大洪水の前に』の「あとがき」
の最後に、なんと宮沢賢治の詩を引用しています。それをここに
再録しましょう。
賢治はこれを、ある年の盛岡中学校の卒業生に祝辞として
送るつもりで書いたのですが、当時は発表することができず、
遺族はその原稿を、終戦まで内密に保管していたものです。
「 生徒諸君に寄せる
〔…〕
(彼等はみんなわれらを去った。
〔…〕
彼等は百の速力をもち
われらは十の力を有〔も〕たぬ
何がわれらをこの暗みから救ふのか
あらゆる労〔つか〕れと悩みを燃やせ
すべてのねがひの形を変へよ)
〔…〕
潮汐や風、
あらゆる自然の力を用ひ尽すことから一足進んで
諸君は新たな自然を形成するのに努めねばならぬ
〔…〕
新たな詩人よ
嵐から雲から光から
新たな透明なエネルギーを得て
人と地球にとるべき形を暗示せよ
新たな時代のマルクスよ
これらの盲目な衝動から動く世界を
素晴らしく美しい構成に変へよ
諸君はこの颯爽〔さっさう〕たる
諸君の未来圏から吹いて来る
透明な清潔な風を感じないのか」
↑この宮沢賢治の詩からもわかるように、
著者の提示する《脱成長コミュニズム》は、
人間が自然のふところに抱かれ、
自然のままに、自然に左右されて生きる
原始共産主義社会のようなものとは
異なります。
自然からの一方的な資源の掠奪ではなく、
人と自然との関係を、人びとが共同で
コントロールし、自然の恒常性が損なわれない
ように編成しなおし管理してゆくイメージです。
それというのも、
“人間が手をふれなければ、
自然はおのずと自己回復する”
などと楽観的に言えた時代は、
《気候危機》の深化によって、
もはや永久に過ぎ去って
しまったからなのです。。。