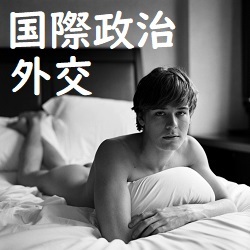↓こちらにレビューを書いてみました。
ドゥルーズ『スピノザ――実践の哲学』(1)―――
―――子ども、無意識、アモルフな身体
ドゥルーズのスピノザ論は、これが2冊目。
最初の『スピノザと表現の問題』は 1968年に出ている: この本は、折から《5月革命》に端を発する学生運動とカウンターカルチャーの熱気のなかで読まれ、従来のスピノザ解釈を一新する人びとの研究と議論のさきがけとなった。
こうして、1968年以降現在までつづく《スピノザ・ルネサンス》は、西洋近代哲学の「異物」(カール・レーヴィット)として書庫の奥にしまいこまれていたスピノザ哲学を巷間に引き出し、みちがえるような現代的姿で再登場させた。
『スピノザ――実践の哲学』は、そうした新研究のうねりと思想的熱気を受けて、81年に再び世に問うた著者のスピノザ論である。
ドゥルーズらのスピノザ解釈は、『60年代以降、ミシェル・フーコーらによって入念に築き上げられてきた、権力のミクロ・ポリティクスに関する分析と不即不難の関係を形づくっている。フーコーは、『知への意志』(1978)の中で、すでに現代の政治闘争における要求が、……〈生〉を目的とせざるを得なくなっていることを指摘している。「生命、身体、健康、幸福、欲求の満足の権利……」つまり、古典的な権力が、君主権の形をとるのをやめ、生命の養護・管理者としてテクノクラシーの支配権をはりめぐらすようになった時、権力の対象が生そのものになると同時に、生それ自体が権力に対する抵抗となったのである。』(浅野俊哉「現代のスピノザ・ルネッサンスが意味するもの : フランスにおけるスピノザ解釈を中心として」PDF)
そのような・われわれの時代の権力とは、スピノザの言葉で言い表すならば、“われわれの精神に対して、非十全(虚偽または不十分)な観念のみを与え、われわれの精神・身体の力能に基づかない衝動・観念・生理を、われわれの内部に植え付ける・外からの力のことである。”
『身体と同様、魂も病んだ者たちは、自分たちの神経症、不安、彼らの愛しい去勢、生に対する怨恨、汚らわしい伝染病をわれわれに感染させるまで、吸血鬼のようにわれわれから離れようとはしないだろう。すべては血なまぐさい。自由な人間になるのは容易ではない。……
人々だけでなく、既成権力がわれわれに悲しみの情念を伝播させることで利益を得ている。既成権力は、われわれを従属させておくために、われわれの悲哀を必要としているのだ。悲哀、悲しみの情念とは、われわれの行動する力を落とすすべてのものだ。圧制者や、聖職者、魂のブローカーたちは、われわれに、人生が辛く、重荷であることを説かなければならない。権カは、われわれを抑圧するのではなく、むしろ不安に陥れ、あるいはヴィリリオがいうように、われわれのささいな内心の恐怖心を、管理し、組織化する必要があるのだ。』(ドゥルーズ,クレール・パルネ『対話』)
このような権力には、どうしたら対抗できるのか? 本書『スピノザ 実践の哲学』でドゥルーズが注目するのは、スピノザが『エチカ』で提示する・《共通概念》の形成という方法である。〔《共通概念》とは、人が自分の身体と、日常接触する物や人とのあいだに見いだす‘ローカルな普遍性’のこと――Giton〕
『神=自然=実体という等式を立てることで、結果的にあらゆる超越〔神、仏、また道徳規範のように、《世界》の外部から超越的な力ないし権威をふるう絶対的存在――Giton〕を認めないスピノザの立場によれぱ、われわれは、一つの空聞内において互いに触発L、触発される関係の束としてとらえられる。』(浅野俊哉、前掲PDF)
そこでは、個体どうしの「出会い」は、ある場合にはたがいの協働をうながしておのおのの力能を高めさせ、合一によってより大きなまとまりを構成させるが、ある場合には、互いに排斥しあって弱体化するよう導き、あげくは分解消滅に至らせてしまう。前者の場合には、《よろこび》の感情がわき、われわれは《共通概念》、すなわち《理性》的思惟・活動能力を得る。しかし、後者の場合、われわれは《かなしみ》や《恐れ》の感情にとらえられ、外部への依存を高めてしまう。したがって、われわれが努めるべきは、われわれの活動力を高め、より広範な結合をもたらす前者の「出会い」を選択し、組織すること、逆に、争いを惹き起こしてわれわれの力を弱め、「権力」への隷従をまねくような「出会い」を避けることだと言える。
しかし、どのような「出会い」が「合一」をもたらし、どのような「出会い」が「解体」をもたらすかは、実験的・経験的にしか知ることができない。十分に経験を蓄積したのちでも、つねに各「出会い」が“試練”である。つまり、“スピノザ主義”には、できあがったイデオロギーも法則も運動方針もプログラム綱領も、あるわけではない。
『われわれは、一つの「実験」を促されているのかもしれない。私たちは、一つの身体、一つの心が、ある出会いにおいて、ある組込みにおいて、ある結びつき合いにおいて、何をなしうるかあらかじめ知らない。したがって我々は、「意識に還元されない思考の力」を通して、どのような関係のもとで、自分たちの情動が最大限の肯定を表出しうるかを、そのつど確かめていかねぱならないのである。』(浅野俊哉、前掲PDF)
『そうしたコンテクストの中でのスピノザには、当然のことながら、もはや単なる神に酔える観念論哲学者ではなく、近代的な思考様式に対して異義申し立てをする、一種の認識論革命を行なった思想家としての位置づけがなされてくる。
こうした事態は、むしろ歓迎すべきことであろう。隠れてしまったか、見過ごされてきた思考の営みに照明を当てていく作業こそ哲学史なのだとしたら、今われわれは、ようやくスピノザをリアリティーを持って読むことのできる時代、すなわち近代の思考が拠って立つエピステーメーの限界をいやがおうにも検討せざるをえない時代に到達したといっても過言ではないのである。』(同)
【追記・私見】 『実践の哲学』でのドゥルーズのスピノザ解釈の戦略は、“出会い→構成→《共通概念》の形成→力能(理性)の向上→より有益かつ広範な出会いの組織化” というものだろう。ネグリの「マルチチュード」はその延長上にある。しかしそこに、“病んだ者に対する忌避” “少数者の視点の欠落”に陥る契機がふくまれてしまうことは否定できない。スピノザは多面的で多義的だ。『エチカ』には、“欠陥とは比較によって生ずる不十全な(誤った)表象であって、すべてのもののすべての状態は、それ自体として完全である” という発想もある。こちらに定位して読み直すことはできないだろうか。スピノザの生きた黄金時代の“自由なオランダ”は、“海上帝国”の覇権に支えられていた。現在のネオ・リベラリズムが、“地球帝国”アメリカの覇権に支えられているように。スピノザもまた、時代の思想――“強者の自由”の論理――に浸透されながら、時代の思想と格闘していたのではないだろうか。