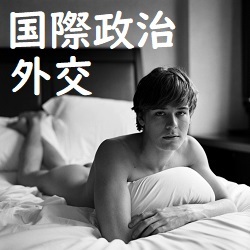大塚久雄『共同体の基礎理論』
岩波現代文庫,2000年.
山本太郎さんの提言をリブログしながら この本を思い出した。
戦後マルクス=ウェーバー学の大御所であった著者が
大学での講義の手引きとして書いたこの本は、
マルクス=ウェーバー学がとっくに凋落してしまった現在でも
一読の価値を失わない。
いまあらためて注目されるのは、“形式的平等”の原理だと思う。
全員(全国民+外国人)への「一律給付」という“形式的平等”は
ヨーロッパでは当たり前の常識に基づいている。
大塚氏によればそれは西欧中世以来の“常識”なのだ。
残念ながら日本では、批判が多くて実現しない;
“形式的平等”の合理性が理解されないからだ。
「金持ちにも一律に 20万円(30万円,10万円)配るのか?」
という“批判”が多い。‥そうではない、
金持ちが何億円損しようと 20万円しか補償しないのだ。
柄谷行人氏の流儀で言えば、“形式的平等”は
「友愛」の基礎であり、ネーションを形成し
第4の交換形態「χ」につながるものだ。
ネーションの一体性、連帯の意識は、
誰もが同じ権利を保持し同じ恩恵を受ける
ことによってはじめて醸成される。
『共同体の基礎理論』は、資本主義以前の「共同体」から
①「アジア的共同体」
②「古典古代的共同体」
③「ゲルマン的共同体」
という3類型(理念型)を抽出する。
「アジア的共同体」では“実質的平等”の原理が、
「古典古代的共同体」と「ゲルマン的共同体」では
“形式的平等”の原理が支配する。
「ゲルマン」の“形式的平等”の原理は、
各個人(農民)の能力の違いを度外視して
一律に同じ広さの土地(地條耕作権)を給付する。
たしかにそれは、不平等と資本主義が発展する出発点となる。
しかし、“権利の平等”という価値理念をも与える。
大塚氏の“ウェーバー学”とは異なって、
“形式的平等”が西欧の専売特許でないことは
多くの実証研究によって証されてきた。
たとえば、熊本県五家荘の耕地割り替えは
“形式的平等”に従っていた。
だから私たちがいまこの本から受け取るべきは、
私たちの“アジア性”を嘆くことではないし
“アジアの良さ”を称揚することでもない。
アジアのなかでは日本は西欧的だ――それは今日実証的に疑問――
と言って誇ることでもない。
“形式的平等”“権利の平等”という価値―――
それもまた人類の獲得した重要な遺産であることを
理解することだと思う。