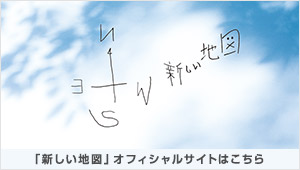引き続き、ドラッグラグ、ドラッグロスについて、あくまで一個人の意見として書いていきます。
前回の最後に、世界の創薬は創薬ベンチャー企業が担うようになってきたと書きましたが、ドラッグラグやドラッグロスの原因を考える前に、もう少し創薬ベンチャー企業が台頭してきた経緯を確認したいと思います。
そこには製薬産業界で起こっているパラダイムシフトが大きく関係しているようです。
これまでは薬のターゲットとなる分子の探索から始まり、非臨床試験、治験、製造、マーケティング、MR活動に至るまでを、製薬企業が一手に担い、創薬の上流から下流までを一貫して手がける「垂直統合型」のビジネスモデルでした。2000年代前半頃までは、このビジネスモデルを維持するために、大手製薬企業は経営統合や買収を繰り返しており、GIST治療薬で知られるスニチニブも、元はSugenという創薬ベンチャー企業から生まれ、ファルマシアという企業が開発していましたが、2003年にファイザー社に買収され、最終的にファイザーから発売されています。
当時はまさに規模を求めるM&Aが活発な時期でした。
ところが、時はゲノム医療、バイオ医薬品の時代に突入し、国としてもライフ・イノベーションを押し進める中で、革新的な薬剤の創出をおこなっていくためには、その過程のすべてを1企業で賄うのは必ずしも得策ではなくなり、逆に非常に難しくもなってきました。
数々の革新的、先進的技術を取り入れた創薬のためには、大手製薬企業もベンチャー企業やアカデミア(大学の研究機関)との連携、すなわちオープンイノベーションが必要となり、現在は「水平分業型」のビジネスモデルが製薬産業の主流となっています。
そうなってくると、創薬のシーズを保有している創薬ベンチャー(上図赤枠)が臨床開発や製造に特化したCROやCDMO、あるいはデジタルに強いIT企業を利用して、上市まで行うことが可能になってきました。なぜそうなったのかまでは分かりませんが、最近は創薬ベンチャーが2種類、3種類の新薬を上市(発売)まで行うケースが増えています。
そのこと自体は特段悪い事ではないと思うのですが、問題はその新興創薬ベンチャー企業さんのお財布事情です。
医薬産業政策研究所の調査では、新興企業は設立から上市までに平均で15年かかっており、上場からも7年近く収益の無い期間があります。その間の研究開発費の一部は当然借金でしょうから、一日も早く借金を返し利益を上げるためには、どの国でまず開発を進め、上市(発売)すればよいか慎重に選ばなければならず、その選択は非常にシビアなものであると想像できます。
前回紹介したGIST治療薬の「AYVAKIT」と「QINLOCK」も、こういった事情で、日本がピボタル試験(初回の国際共同治験)から外されたため、日本へ入ってくる予定の無い薬:ドラッグロスとなってしまいました。
でも実際にアメリカなどに拠点を置く新興創薬ベンチャーから日本はどう映っているのでしょうか?
上記政策研がアメリカと日本の相対的な市場規模を比べてみると、アメリカを100とした時に、日本は2010年には30でしたが、2015年には18、2020年には16と、10年前には1/3程度だったのが1/7にまでその類推規模が縮小しています。 以下引用文です。
新興企業にとって足場である米国の市場規模と成長性を基準とすると、日本の市場は規模も小さく、マイナス成長に映ることが示された。この10年の推移をみると、日本の医薬品市場は魅力的なマーケットとは捉えがたく、新興企業にとって投資優先度は低い可能性が推察された。
PhRMAの調べでも日本におけるバイオ医薬品の投資優先順位が徐々に下がってきており、承認される薬剤数も年々低下していることが分かります。
では日本から引き上げられた投資がどこに向かったかというと、多くは中国であると言われています。上記政策研のアメリカを100とした時の市場規模では、2010年の17から2020年には27と大きく伸びてきており、PhRMAの治験数の調査でも、中国で治験段階にある新薬の数は、2016年の881件から2020年には3003件と急拡大しています。ちなみに日本は1127件から1319件と横ばいにとどまっていました。次世代技術を使った新薬開発のシェアでは、2010年代後半に日本は中国に逆転されており、世界の医薬品開発の中で後回しにされ始めている日本では「ドラッグラグ」が再燃しているという状況です。
次回はその原因に迫ってみたいと思います。