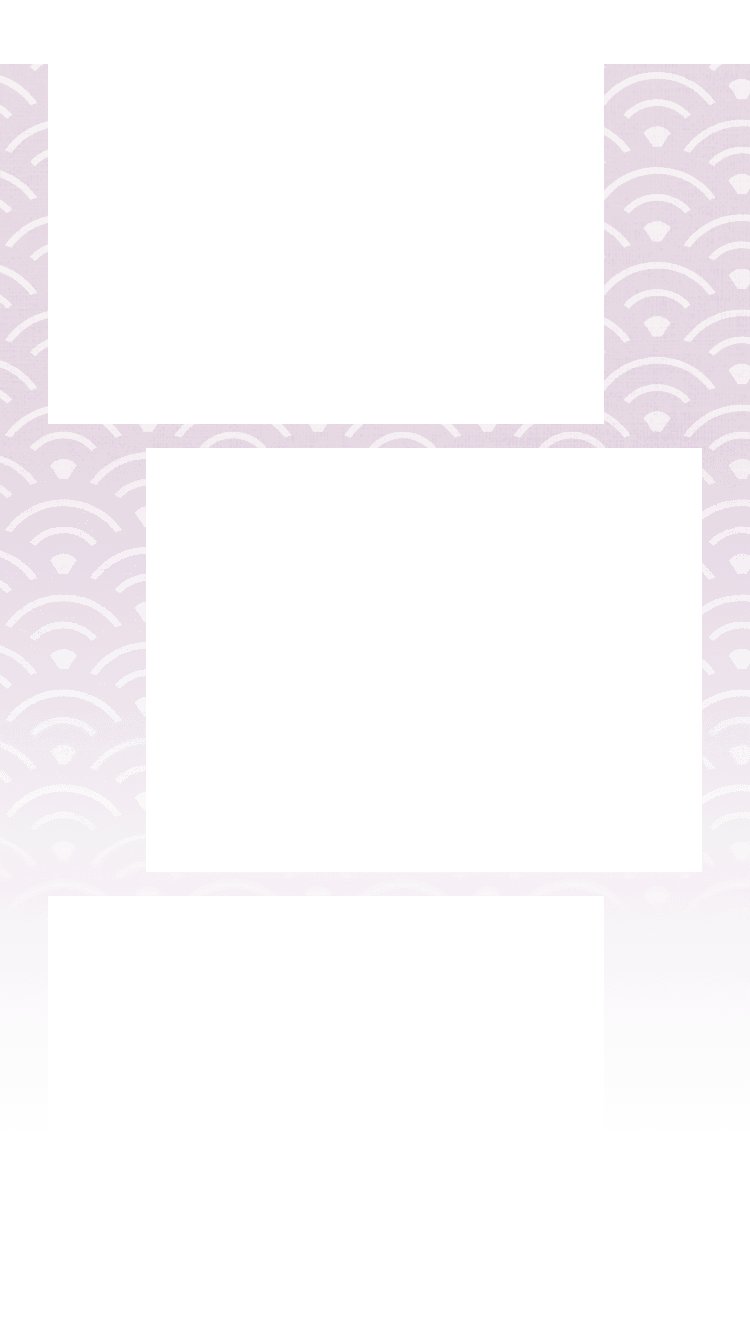Aemilia Arsの仲間でもある沖縄の友人が集中レッスンも終え帰宅の途についた翌日、掛け合い漫才の相方のような彼女の不在に台風による気圧の急変が絡み、どうにも心身の居心地がよくなく、定期的に通うからだのメンテナンスに、予定を早め飛び込んだ。気血水を整えればそれで充分、その夜からフツフツと寝入った。目覚めれば来廊してくれた知人たちに礼を伝え、そしてふたたび針を持つ。居場所から熱狂の思いがしだいに薄れていく。
まずひと針。着地など見定める必要もない。図案が示す道筋を素直に辿れば、自ずから納まりどころに至る。刺し始めもその終わりにも結び目はない。糸が足りなくなれば、わずかな目数糸を重ね、また辿り出す。正しい道を選ぶ余地はない。道を読み解き紛えれば先に行かない。そこを無理に押し通すと満足な形を手にできない。継承する者が少ないわけだ。でもこの困難さが、Aemilia Arsの魅力なのだ。
展示会終了の翌朝にパオラ一行と京都に向かった。会期中も糸や布を商う都内あちこちの店を訪れその合間に、寸暇なく観光し歩いた84歳が、京都まで足をのばせるのだろうか。半信半疑の面持ちで新幹線ホームに向かった。
落ち合うのは乗車する車両前よと、前日に何度も確認したそこに約束の10分前に着くが、彼らはまだいない。
「ホテルがタクシーを予約してくれていなかった。どうしよう。あっ、いまタクシーがつかまった」
慌ただしいメールが東京駅に向かう私の携帯に着信してから逆算しても、すでに東京駅に彼らは到着しているはずだ。
そこに「Ciao,Arrivate carrozza 4」フランチェスカからメッセージがくる。いやいや4はシートナンバーで、乗車車両は14だ。14と4を混乱されてもと、シートナンバーは書かず乗車ホームと車両番号だけを伝えた私のメールをきちんと確認せずに、ただ手にあるチケットの番号をしかも後ろから読んだに違いない。
いやいや車両は14。慌てて返事をしながら、私も彼らのいる方向に歩き出すと稍して、大きく手を振るパオラが目に入った。
「他のふたりはどうしたの?」「あそこでコーヒーを飲んでいる」
確実に私と落ち合えると分ったら、すぐにコーヒーだ。すでに乗るべき新幹線はホームに着いている。パオラの済まなそうな顔つきにそれ以上何かにを言っても仕方がない。
飲みきれなかったコーヒを抱えたふたりと合流したのは、発車時刻の3分前だ。
日本に着いての翌日、押すスケジュールで頭がいっぱいだった私は、イタリア組に予定を説明しながら何度も腕時計の文字盤を叩いたらしい。
「日本人ってなんでそんなに時計を叩くの?」と訊くクラウディアの悠長さに、思わず吹き出した。そもそも彼らが日本到着の日程を1日間違えたのが、この慌しさを生んでいる。暢気な彼らはそれをすっかり意識から外している。
来廊くださったDMC日本社長の自社インスタグラムへの掲載
持参したレースを展示し終えたパオラが、私たちの展示の前につかつか近寄った。レースを見る彼女の眼光の厳しさは見知っているとはいえ、私の技術伝授が問われるこの瞬間、頭から鉄棒が突き抜けるように緊張した。
この展示の仕方はいいね。私の作業したレースの1枚を指さし、うん、これはいい。
ただそれだけ。もう他に言葉を求められない気配がパオラから漂っている。
パオラの師アントニッラ・カンテッリは、仕上げたレースを差し出すと、無言のままそれを受け取りしばらく眺めるとほどなく、大きなため息とともに一切言葉を添えず、手にしたものを返してきたという。パオラにアントニッラが重なった。
私たちの展示仕様はほぼ手作りで賄った。極力自然の様子でレースを見てもらいたいと検討するうちに、そうした展開に落ち着いた。幸運にも額装について職人技を持つひとりが仲間にいたお陰で、私たちの展示への思いは可能になった。
色糸さんもクロスステッチ作品からアクリル板を外し展示をされたので、会場は暖かで柔らかな風景に包まれた。
手作り感満載の会場でパオラたちに、日本文化の片鱗を紹介できたことは大きな喜びだった。尺八奏者小濱明人さん来廊の際は、祝いのひと節を披露してくれた。旧知の茶人が申し出てくれた伊太利亜茶会、最終日の深草アキさんと甲斐いつろうさんのライヴ。心尽くしの交流が幾重にも叶った。
会期を終え確かに私たちは疲れた。疲れたはずだ。しかしそうした状況に漂いながらも、満ちてくる充足の思いを味わったのではないだろうか。
暢気な私たちはお名前をいただくカードは300枚で充分と考えた。ところが展示会初日から来廊くださる方が切れずに続き、結局私たちの予想の倍を遙かに超す方々に展示を見ていただいた。
初日にパオラに来廊者数を報告したところ、翌日から「今日は何人の人が見えた?」と毎日チェックが入るようになり、それがまたすぐにボローニャに報告され、あちらの教室の仲間たちとも喜びを共有した。
1年半かけての企画が終わり、時間の経過とともにあの熱狂の風景に私たちがいたのかどうかも薄れていく。「あったこと」は、方々の寄せてくれた言葉に拠るしかない。
魂のこもったというか、そんなものを感じました。気迫というのでは無いのですが、無心に今ここにある、
というその空のエネルギーから生まれたもの、というのでしょうか、、、
これがこうなってこうなるのよ、というのがわかるような細やかな演出も、見る者には、
理解と興味を深めることが出来、展示会の味わいをふかめていたと感じました。
彼女との長い付き合いはまた、私の生きた軌跡と重なる。彼女の言葉から透いてくる私の過ごした時間をあらためて感じ入った。
京都での最期の食事のテーブルで、来廊くださった方にこうした人がいてね、とフランチェスカに話すと、「この人?」
彼女は携帯にある1枚の写真を私に見せた。
「そう、この人。どうして彼の写真を撮ったの?」「何だか問答するようにレースを見ていたから」
そんなことがあるのですね。
フランチェスカさんという方のその会話に驚いています。
まだまだ私にはレースの世界の足下にもたどりつけませんが、そこになにか大きなものがある、
ということだけは感覚的に分かったような気がしました。
おそらくそこにはキリスト教的な世界が深くあるのでしょうね。白は神の色と思います。
初めて宇宙飛行をしたガガーリンの言葉として、日本では「地球は青かった」という発言がよく知られていますが、
欧米では、そこは気に止めることもなく、彼の言葉として「天に神は居なかった」が衝撃を与えた、ということを、
なぜか思い出していました。
人は出会った新たな世界と、身体にあるそれまでの文言との問答で向き合う。ドイツ哲学の見地から宮沢賢治やシューベルトについて多くの著書を持つこの筆者から投げかけられた言葉を、反芻していきたい。
京都から帰った翌朝、私たちはパオラ一行を空港で見送った。幾度も繰り返される抱擁と歓声のあと、セキュリティの列に並ぶパオラが、私たちに背を向けた瞬間、眼鏡を外しさっと涙を拭った。
熱狂の日々もいつかひとつの記憶となる。パオラが丹精込め作ってくれたこのビオラのブローチを、孫のひとりが胸に飾るとき、すでに不在となった私とAemilia Arsの思い出をこの小さな花びらが語ってくれるかもしれない。
una mia micro storia。