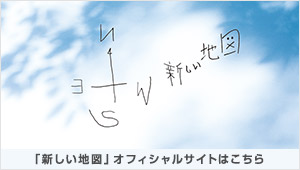●香高堂メディア文化考=東京2020記録映画はいつ?
<時代の変わり目と世代交代>
昨年、政府や都知事の自粛要請に素直に従って、大きな感動をもらい、感涙に咽びたくて、東京五輪を自宅観戦した。政治もスポーツ界も「世代交代忘れて、老害のみが残る」と言うのが半年経っての感慨だ。
スポーツは身体性の能力を競う手段である故か、古いものは廃れ、時代の変わり目が見られる。新しい世代が生み出す競技が増えて、若さとベテランの世代交代、新旧競技の栄枯盛衰、女子力の高さ、二十歳世代の活躍を見ることが出来た。世代交代する過程でメジャースポーツの驕りが出て、マイナースポーツの躍進が見られる。BMXにサーフィン、スケートボードなど若者カルチャーから生まれてきた新競技が出てきた。
例えばスポーツクライミングは、12mの壁を登る速さを競う「スピード」と4mの壁を制限時間内にいくつ登れるか競う「ボルダリング」、12m以上の壁を制限時間内にどこまで登れるか競う「リード」の3種目の合計点で順位が決まる。バランスの取れた筋力が必要とされるようで、思わず見入ってしまった。マイナースポーツに参加する少数競技者は独自の文化を持ち、窮屈さから解き放たれているのかもしれない。マイナーだった時代の媚びない爽やかな姿をぜひ維持して欲しい。
女性をテーマにしたドキュメント番組もあった。昨年8月9日、17日間の舞台裏を記録したNHKスペシャル「私たちの闘い」が放送された。密着取材の中からアスリートの真摯なコメントを抜き出していた。▽伊藤美誠・葛藤と覚悟 ▽大橋悠依・地道な努力 ▽ソフトボール・日米の友情と被災地への思い ▽池江璃花子・この先へ ▽バドミントン・フクヒロペアの闘い。
メディア、特にテレビはコロナ関連のニュースが一気に減り、競技の中継と選手のメダル獲得の笑顔だけを伝え続けた。一方、競技中継の途中で<ニュース速報音>がビンビンとなっていた。件の禍や台風接近の中でも「日本が銅メダル獲得」と字幕が出る。何故これが速報なのか、メディアは盛り上げの指示が出ているのであろうか、傲慢なメディアの悪行は続いている。さらに増田明美の僥舌だが中味の無いマラソン解説、つまらない内容に辟易していた。「アスリートファーストとレガシー」は今や<腐臭の漂う言葉>になっている。ところで、五輪記録映画はどうなっているのであろうか。
<河瀬直美監督の東京2020記録映画は>
2020東京五輪の記録映画はいつ公開されるのだろうか。昨年の五輪玉終了後、ずっとずっと気になっていたのが五輪記録映画の製作と公開だ。NHKが年末に「河瀬直美が見つめた東京五輪」と言う番組を放送、公式記録映画監督の河瀬直美の発言内容が問題になっている。大手SNSでは「#五輪を招致したのは私達ではありません」というハッシュタグが飛び交っているようだ。
河瀬直美は番組で、「オリンピックを招致したのは私たち」「みんなは喜んだはずだ」「だからあなたも私も問われる」と述べ、「私はそういうふうに描く」「招致したのは私達だけど、国民全員が喜んで共有したから、皆も一緒に問われることになる」とコメントした。<私・あなた・私たち・皆>とは誰の事だろうか、その上から目線があまりに気になる。実は昨年五輪終了後から、この河瀬作品の方向性が気になり、懸念していた。
河瀬直美の創作姿勢はこれまでの映画から「個を見つけて、丁寧に追いかける眼差し」と言われてきた。肥大化した商業イベントに順応せざるを得なくなってしまうのではないかとの疑念を持つ人々もいた。ニューズウィーク日本版は昨年、河瀬氏は「つながり」をテーマに設定する構想を明らかにしたと伝えた。「見えないところで頑張っている人」「母親である自らの視点」「難民選手団紹介」「パンデミックを深く意識」と発言していた。
さらに「五輪の反対意見にも耳を傾ける」「次の時代の人たちはどう考えるのか。」とも言っているが、利権につながる政治家たちが嘘と賄賂で招致したのは明らかである。一部の人々が儲けるだけ儲けて、責任は全く問われずにいるのも明らかだ。それを糊塗するために「東京五輪・成功賛歌」になることは想像されるが、国民は「私たち」とか言い出され、みんな連帯責任とか一億総懺悔するんだろうか。
五輪記録映画で強烈な印象を残したのは1968年の冬季五輪グルノーブル大会の「白い恋人たち」だ。映画「男と女」のクロード・ルルーシュ監督がメガホン、フランシス・レイが作曲したテーマ曲、「これは公式映画ではなく、たまたまグルノーブルにいた映画人が、13日間の感動的な日々を、見たままに描いた作品である」とのコメントが流れる。聖火リレーの映像で始まり、競技や選手の日常のさまざまな断片が何の説明もなくちりばめられ、大会後の静けさで終了する構成、ルルーシュ監督がエスプリを利かせた。
市川崑が総監督を務めた1964年の東京五輪の記録映画の記憶は薄れ、篠田正浩が総監督の1972年の札幌大会はトワエモアの歌だけ、1998年の長野五輪は全く覚えていない。
<五輪秘密結社の奇祭とパリ五輪の行方>
「スポーツによる平和の祭典」と言われるものは五輪秘密結社の奇祭だった。東京2020が終わって半年が経つ今、日本の人々の心に五輪は残っているのだろうか。1964年の東京オリンピックは、同時代を生きた人々の心にポジティブな記憶を残している。東京2020は「ひと夏の夢」のように泡と消えている気がする。
緊急事態宣言を発令せざるを得ない感染状況となった中で、五輪開催への日本国内の反発は強かった。実際に開幕すると開会式の視聴率は1964年の東京五輪の61.2%に迫るものとなった。日本選手が活躍し、世界のアスリートの躍動が伝わると、五輪に対する空気は変わった。テレビのワイドショーや新聞の論調も五輪を盛り上げた。
だが、菅前首相も「安心安全な大会」を謳うだけで、この五輪の意義を訴えるべきリーダーが黙していた。日本オリンピック委員会こそが、理念上のリーダーシップを取るべきであっただろう。競技団体が準備した感染対策とそのデータの有効性も、団体維持に拘る幹部の盲従に繋がった。日大事件を見れば、いかにお金が絡むのか分かるであろう。
中でも小池都知事の自己保身と自己顕示がより目立ち、政治利用の欺瞞性だけが残った。もはや「スポーツによる平和」は幻想で、「北京五輪の外交ボイコット」なる言葉に現れている。メモを取りながら呆れたが、開会式演出の酷さに始まったテレビ中継は醜く、メディアの劣化が増々目立った。
昨年12月にパリ五輪組織委が発表した開会式の構想は、パリ中心部を流れるセーヌ川が会場となり、選手たちは160隻の船に乗って入場行進するという。少なくとも60万人が開会式を直接見ることができるという。東京2020の閉会式でのパリからの生中継は圧巻で期待させるものがあったが、マクロン政権は生き延びているか。