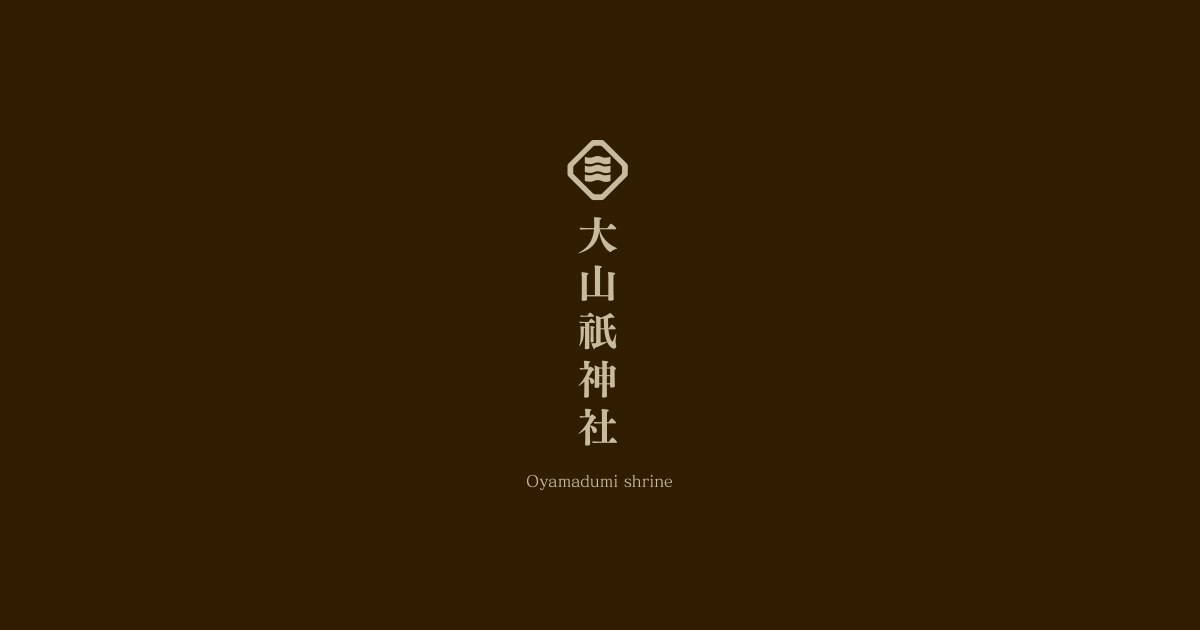こんにちは、元気ですか(・・?
日本の政治も今年に入っていろいろ動いているね。表面に現れているのは、表象。このブログでは、いろんな記事もアップしていますが、一つの流れがあると自分自身考え、そのきっかけとなる記事をアップしています。ただね、日本は動きが鈍い。あえてこうしているのかもしれませんが、鈍い。
信長の考察は、この日本の鈍さが、なぜ起きているのかという原因も考察してます。通常一つの国家ならば、国家の方針を持ってそれに沿うにはどうすればいいか、或いは国民の間で、考えや政策などの違いが表になるのですが、どうもそれすらない。一般の庶民にとってみれば、今の食事と待遇を維持してくれればいいというのが大多数かもしれませんね。長い間、海、強い海流で守られていた日本列島にいたから、今でもその効果があると思っているのか、それとも地球儀を見ながら日本を考えていない人が多いのかどうかわかりませんが、世界の知識層は、地球儀を見て考え、今では、宇宙をみて考えているように見えます。
一般には、世間の人のためになることをしたいというのが、通常のまともな人間の考え方。そして、役人(ここでは政治家も入りますが)だけが、人の幸せを守るのではない。人の幸せをまもるために、各々がどうすればいいか考えるのが、人間社会。
前回の信長ブログの動画、「世界の王が日本列島に来る前の話」は、日本列島は、西からの渡来人が中心として成した列島という前提。果たしてそうなんでしょうか。
もう一つの動画、hirosi hayasi さんのエンリル、エンキと、数々の日本の古代建造物の証から、果たしてこのような歴史を日本列島はたどってきたんでしょうか。そのような動画に疑問を持ち、この信長のブログを考察していきます。疑念を持って考察する。この姿勢でいきます。
人間の歴史(世の中)は、「嫉妬とソロバンだ」と発言した田中角栄翁の名言があります。
田中角栄の名言50選【偉人の名言 名言集】
岸田総理にしても地球儀で日本をみれなく、永田町世界でしかモノを見る手段しかない。総理の一言で何もかも決まるということもできないのが現実。官僚にしても同じ。日本政府の中の世界でしか物事がみれない。他をみると、嫉妬とソロバンという敵が介在しだす。では庶民はどうすればいいのか。それは、狭い世界でしかみることができない現代の日本でいう上流社会の人たちの目を、庶民に向かせるという運動しかないような気がするね。そのために、江戸時代は、一揆などがあった。
信長の行動もその流れの一巻でもあった。桓武天皇の時代をもう少し考察しましょうか。
我々日本列島に住む人間社会の中で、嫉妬や争いよりも怖いものは、なんでしょうか。能登地震に現れているように、突然襲ってくる大地震。地震によって火災がおきたり、津波にさらわれたり、さらには、その後に来るかもしれない、飢饉と疫病。
こういった経験を我々日本列島に住んでいる日本人は、たえず向き合っていた。突然大地を揺るがし、火山は大噴火、数十メートルもの高さの津波も経験してきた先祖たち。
米国や中国大陸などにも地震などの災害がありますが、国土の面積が違う。それなのに国土が大きい大陸国家の大災害に匹敵する位の大災害が、この日本列島におきてきた。
過去の日本の歴史は、大地震などの自然災害による影響で、日本の政治は、支配層、庶民を中心に大きく変わっていくのは当然のこと。
天武天皇からというよりもそれ以前から、天皇家というのは、地震などの災害、飢饉、そして争いがもたらす怨霊に悩まされていた。天武天皇の時代は、雨が全く降らないという気象にあい、天皇が祈祷をしてもその現象はおさまらず、そこで役行者の祈祷によって豪雨がもたらされたという、天皇の地位そのものが危険になるような事件もおきたしね。
桓武天皇の時代は、平城京から長岡京へと遷都した後、九州の霧島大噴火がおこり、その6年後に長岡京自体が大地震に合う。遷都したばかりの大地震は、不吉であると当時の住民がささやくような事態。そして平安京への遷都へと向かう。
長屋王の祟り、他戸親王による天武系の断絶、早良親王(祟道天皇)の祟りというように、さらには、藤原四兄弟が疫病により相次ぎ亡くなるなど、おどおどした状況だった。平安朝になったとしても、天皇家にとっては、地震などの自然災害が怨霊と結びつきを意識せざる負えない事態だった。
政争=怨霊
系図上では、桓武天皇は、自分の三人の息子を異母姉妹と結婚させて純潔を保とうしているようですが、どうでしょうか。
系図上、桓武天皇は、天武天皇の「武」という文字の言霊を含むことで継続を表し、母親和新笠の名を高野新笠として称徳・孝謙天皇の諱である高野を言霊として受け継ぎました。
桓武天皇の同父同母といわれる早良親王は、餓死されましたが、桓武天皇は、早良親王の御霊の祟りであるとして上御霊神社に祀った。
上御霊神社
この地は、平安遷都以前から出雲市の氏寺・上出雲寺があり、当社の元は、鎮守社であったとされている。桓武天皇と早良親王は、本当に兄弟でしたんでしょうかね。早良親王は、出雲系の王族かもしれませんね。早良親王の他に、伊予親王・藤原吉子・観察使藤原仲成・橘逸勢(はやなり)・文屋宮田麿等が祀られている。伊予親王は、桓武天皇の皇子であるとされているが、異説もあり、母は、藤原吉子。平城天皇に対する謀叛の罪により母とともに幽閉され、自殺した。藤原吉子の母親は、不明とされているが、橘真都我ともいわれており、もとは犬養氏。京の陽明門の警固を従来は県犬養門といったが、のち山門というようになる。犬族の本貫は、秩父としたら、桓武天皇の父、光仁天皇から蝦夷討伐が始まったようですから、この時代に天皇家による大きな変が始まったということだと感じるね。単なる天武系から天智系の変化ではないような気がします。
伊予親王の変
大山祇神社
大三島大社ともいい、以前色についての考察によって、三島=青を表す。この時代は、藤原家と非藤原家の争いも天皇家の争いとともに生じていた。
秦氏が開拓した長岡京という地域は、淀川(桂川)支流となる小畑川を使って長岡京の近くまで船で物資を運べる便利な土地であったが、たびたび洪水に見舞われ、小畑川の氾濫が長岡京を短命にさせた原因でしょうね。大地震の頃は、数十回という小地震がおきたはずですからね。当然、長岡京の場所は、高台にあり淀川の氾濫がおきても影響を受けないような場所に建てられていたはずであり、淀川の影響よりも小畑川の氾濫の影響の方が大。
健児の制 ~百人の弱兵よりも一人の強兵~ 歴史ドラマ 百花繚乱歴史伝
792年、健児の制。
律令制度の中に徴兵制、成人男性の三分の一が、軍隊所属であり、軍団ともいいましたが、この軍団を廃止し、代わりに郡司とよばれる役人の子息の中から武芸集団を結成した。それまでは、多くのものが百姓。よって、百姓から兵役を解放した。しかし、全国的に解放されたのではなく、蝦夷対策のために必要な土地には、解放されていません。日本海陸軍が、自衛隊になったようなものか、それとも警察署のようなものになったものかというくらい縮小したということでしょうね。
桓武天皇がこのような動きをしたということよりも、徐々に、犬(徳)族が、政変をおこしながら桓武天皇の政治体制を修正していったように思える。まっとうな体制へと修正していく。
長岡京は、小畑川の度重なる氾濫と、怨霊、さらには開発した秦氏などの反対運動もありなかなか造営も難しくなり、桓武天皇は遷都を決意する。
日本列島というのは、河川が多い。よって川の氾濫も多い。遷都をしても結局は、川の氾濫などによって都もその影響を受けやすかったのが、当時の日本。川の氾濫によっておこされる洪水の不安を解消させたのが、秦氏。そして考案されたのが、堰。堰をおくことによって、川の流れがせき止められる。
秦氏というのは、カメレオンのような技能集団だったかもしれませんね。絹織物で、時の支配者に取り入れられ、桓武天皇の時代は、川の流れをせき止める堰をつくることによって桓武天皇以後の天皇に受け入れられ、かつ政商ともいえる権力の中枢に政治から受け入れる富とともに、時の支配者のスポンサーとなる財力を手に入れる集団。聖徳太子の時代から支配者側のブレーンといいながら、いつの間にか消え伏せ、突然現れ、また消え伏せというように、謎の集団ですね。このブログでは、秦氏というのは、中国大陸長安を都とした部族としました。
織田信長が支配した濃尾平野。ここも利根川、揖斐川、長良川、木曽川という大河川があり、川の氾濫で悩まされていたでしょうね。しかし、この堰を設けることによって力強い国土が形成される。川の氾濫や洪水の不安さえなくせば、川の流域は、立派な田畑となります。当然、信長は、そこに目を付けるはずです。信長は、秦氏を味方につけていたことはわかりますね。秦氏を表す言霊の文字は、桂。秦氏の一部のグループは、信長と行動を共にしていた。有力な犬(徳)族と秦氏が、信長を支えていた。
天武天皇から内乱もあったかもしれないが、近畿圏内の人口も増加していった。近畿に都ができたことにより、日本列島での最大消費地となった。中国大陸唐の内政が安定しだし、いわゆる外敵に対して恐怖が薄くなり、その影響が、内政、内需へと向かう。現代のエネルギーの原料は、石油。当時は、木材。木材は、エネルギー材料だけでなく、家屋(寺)、船、工具などに使用される。つまり、木材は、人間の生活にとって一番重要な消費財となる。
この時代から、日本列島禿山の時代へと進む。刀などの鉄器具にしても膨大な木材が必要。近畿周辺から森林地帯がなくなりはじめる。この影響により、各地で川の氾濫がおこりだす。
以前三囲神社の話をしましたね。三方の山で囲まれた土地には、きれいな水が流れ、田畑にそのきれいな水が流れおいしくて甘い米がとれる。しかし、森林の伐採がおこり、そのような恵まれた土地も、洪水がおこり、その洪水によって汚物などが盆地に溜まり、その影響で奈良は、悲惨な土地へと変わった。人間の行為によって起こされた悲劇。それまでにいた多くの優秀な人材は、政変などもあり、その土地をはなれ、新たなる新地へとむかったのが、たぶん東海、関東だったような気がするね。
その点、京都は、上流部には琵琶湖という大きな湖があり、水はそこからながれてくるので奈良盆地のように水が枯れることはなかった。信長が、秦氏とともに管理した濃尾平野も同様、豊富な水と海という利便性を持っていた。
桓武天皇も秦氏を無視することはできなかったでしょうね。信長も同様。
桓武天皇の別称を柏原帝という。落葉樹に分類される柏の木。紅葉ののちに葉枯れを起こし、冬の間に落葉に至るのが、通常の落葉樹ですが、柏の場合、翌春の新芽の芽吹きまで枯れ葉のままで枝にとどまり続けるという珍しい特徴を持つ。柏の意味には、間を置かずに新旧の葉が入れ替わるという意味があり、つまり、代が途切れない、世代交代が切れ目なく続いていくという縁起の良い植物として捉えられていた。
柏の葉は、古代から調理器具、食器などを加熱調理の際に土器の内底に敷くという利用がなされていたようです。炊く葉(かしくは)とよばれ、これが柏の由来となったとされる。また、隋書・東夷伝には、当時の日本人(倭人)は、皿やまな板を使う習慣がなく、柏の葉に食物を盛って・・・といった記述があったことから、更の代わりに柏の葉を利用していたようです。そのような習慣が信仰の場にも反映され、崇拝の対象に捧げる供え物の器のかわりに植物の葉を用いられていたようです。その影響が宮中祭祀へと引き継がれたようです。
これは推測にすぎないんですが、このころから天皇家、王家の神道形式もかわり、扶余・百済方式宮中祭祀になったような気がしますね。さらには、先に述べたように、柏の葉は、枯れ葉となっても落葉せずにそのまま越冬し、翌春に新芽と入れ替わるまで枝木にとどまるため、葉がおちないように守る神が宿っていると考え、「葉守りの神」と呼ばれていたそうです。たぶんここで王家が変わったことを意味するのかもしれません。
桓武天皇の別称は、柏原帝の他に、日本根子皇統弥照尊ともいう。前回のブログの「世界の王が日本列島に来る前の話」動画では、扶余国は、モーゼの国。となると、大和王朝は、モーゼの王国となった。この時期ではね。
日本では、こういう記号で浮かぶのが家紋。
公家では、中御門家とその庶流。そして神道関係者。
代表的なものが、
伊勢神宮 久志本氏
熱田神宮 千秋氏
吉田神社 吉田氏
武家では、
葛西氏(桓武平氏)、平将門、平清盛、執権北条家など(坂東平氏)
葛西氏
土佐山内氏
土佐山内氏
信長以降の武将の家紋は、系図とはあまり関係ないかもしれませんがね。
人間世界の時間、10年という間は、自然社会では短期間な世界であり、この日本で数年ごとに各地で大きな地震がおこるというのもなんらかの政変のサインかもしれませんね。
前回のブログの終わりに紹介した徳政相論。これは桓武天皇崩御の三ヶ月前に討議されたのでありますが、すでに桓武天皇はこの時期、生きていたのか、ほとんど病に伏していたのかどうかわかりませんが、この時期に朝廷内で政道について討議するほど政情不安が問題になっていたんでしょうね。
wikiによると、藤原緒嗣(おつぐ)と菅野真道との政策論争とされている。
菅野真道は、前回のブログで説明したように百済からの渡来人王辰爾の後胤。もともとは楽浪郡の有力豪族。たぶん半島系華僑でしょうね。日本海貿易圏をきずいてきた生活圏が、気象の変化によりいきづまり、北九州を中心とし、韓半島の南部、慶州、全羅道付近と楽浪郡の商人(華僑)に属した末裔。王辰爾は、高句麗からの国書を読み解き、その上交渉を失敗させ、倭国における高句麗の不信感を高めさせ、高句麗使との関係も邪魔し、倭国と高句麗を分断させ、百済有利な外交を進めた百済派官僚の一族。
藤原緒嗣は、藤原式家であり、藤原四兄弟の三男宇合の系統。母は、伊勢大津の娘となっている。藤原百川の正妻は、久米若女ですが、久米氏は、百済亡命時の渡来貴族で連姓を持ち、高位貴族出身。しかし藤原緒嗣の母は、無名。
伊勢大津の娘とはだれでしょうかね。これも推測ですが、天武天皇の時代、壬申の乱で、天武天皇は、伊勢の方を向いて天照大神を拝み、戦を制した。それ以来、国をあげて伊勢神宮をお祭りしたという。伊勢神宮の斎王となったのが、大来皇女。天武天皇の娘で、大津皇子の姉。大津皇子崩御後、斎宮の任を解かれ京に戻る。その後は不明。
たぶんその系統の姫を母に迎えたように思えるね。当時は、男親の元で育てずに母親の一族の元で育てられる。
徳政相論では、32歳の青年参議であった藤原緒嗣は、
「方今天下の苦しむ所は、軍事と造作となり。此の両事を停むれば百姓安むぜむ」
とし、軍事(蝦夷討伐)と造作(平安造都)こそが天下の民を疲弊させている原因として強く停止を主張。
これに対して65歳の菅野真道は、
「真道意義を確執し、聴くことを肯むぜず」
菅野真道は、桓武天皇の信任が厚い渡来系氏族出身の腹心。桓武天皇の生母と同じ百済渡来系族。この決着を桓武天皇の判断で藤原緒嗣の意見を採用したことになっているが、どうでしょうかね。ここでは、信長の考察とあまり関係がないので桓武天皇は、緒嗣の意見を採用したということにしておきます。歴史もそう記してあるからね。
菅野真道は、続日本書記の編者の一人として、藤原緒嗣は、日本後紀の中心的編者。
そしてもう一人の参加者、坂上田村麻呂。神号は、田村大神。
舒明天皇は、田村皇子と称していたね。
坂上田村麻呂が生まれた坂上忌寸は、後漢霊帝の曽孫阿智王を祖とする漢系渡来系氏族の東漢氏。明確に言えば韓半島の華僑。母親は不明。祖父は、坂上犬養。犬(徳)系のような気がするね。坂上田村麻呂は、嵯峨天皇と平城天皇との争いで嵯峨天皇側についている。
桓武天皇が崩御し、平城天皇が即位する。和風諡号は、日本根子天推国高彦天皇。母は、藤原宇合の次男藤原良継の娘、藤原乙牟漏。系図上では、嵯峨・平城天皇どちらも同母である。ただ、785年に平城天皇が生まれ、786年に嵯峨天皇が生まれと続けている。ここらも不思議。
平城天皇
早良親王に変わって皇太子となり。806年即位。wikiでは、病弱だったために三年後の809年嵯峨天皇に譲位するとある。
次回は、平城天皇と嵯峨天皇の時代の考察へと進みます。光仁天皇、桓武天皇と続いた内乱、自然災害、それと造都と征夷で国家財政逼迫し、さらに徳政論議までしなければならない状況。たぶん内乱などが頻発し、観察使などを各地に創設しなければならなかった。この時期から弘法大使が、活躍しはじめる。少しづつ、少しづつかもしれないが、政治を安定へと向かわせようとしているグループが、朝廷内にはいたということがわかりますね。
ここまでで。
【源頼朝じゃなかった!?】教科書でみたこの肖像画の正体は…
【バベルの塔とは?】本当にあったの?神様が怒って壊した?なぜ?高くしすぎたから?ノアの方舟とも関係?そもそもどこに建っていた塔なの?【ブリューゲル1世】
バベルの塔が崩壊したのは、都市化が原因だった。アラブ諸国中東にしても現代が、この時代に近い。都市化が進み過ぎると砂漠化がすすむ。といって、アラブの王族は、そのことを知っている。つまり次の世界を目指すためにバベルの塔をわざと現代つくっているようにみえるね。
源頼朝の絵も、足利直義だった。徐々に歴史がはがれてきているね。
藤原道長の父 兼家の野心と紫式部の父 為時の極貧生活の理由 平安貴族はなぜ貧乏だったのか「大河ドラマ 光る君へ」歴史解説03
平安貴族の暮らしがどうだったか、上の動画を紹介。
自民党 悪夢の30年に終止符を(古賀茂明)【山田厚史のここが聞きたい】
ハンガーストライキを実行する猫
ネコでもストライキする。庶民の手段は、ストライキしかないのが現実。
女王の教室「特権階級と凡人の関係」お前らは家畜だ
ではごきげんさんで。