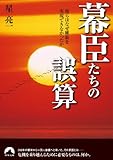読んだ本紹介。
星亮一・著
著者は会津を中心とした奥羽越列藩同盟に大変思い入れのある方なので、会津を窮地に追い込んだ人物は官軍、幕府軍に関わらず、あまりよく書かれない傾向にあります。
本作においても薩長系の人物はもちろん、幕府側でも徳川慶喜や勝海舟を評価せず、小栗忠順や土方歳三、榎本武揚のような最後まで会津と共に抵抗した人物を評価しています。
それは正しい面はありますが、一面的であるようにも感じます。
立場が違えば評価が分かれるのは世の常ですが、こと日本史上の人物については、大局的に考えるべきではないかと個人的には思います。
さて、内容については、ライトユーザー向けというか、最近は研究書ばかり読んでいる身としては物足りなさを感じてしまいました。
幕臣たちの誤算は何だったのか、深く掘り下げてはいなく、ちょっと残念でした。
以前読んだ同じ著者の本(敗者の維新史)は、大変面白かったのですが・・・。
ただ、大局的な視野の喪失、硬直化した組織の機能不全、経済的視点の欠如、トップの優柔不断さなど、幕府を崩壊させた原因は、現代の日本でも当てはまるものだと思います。
あとがきに大変いいことが書いてありましたので引用させて頂きます。
「翻って、今日の日本の状況を見ると、幕末の日本に、あまりにも似ているのに驚く。抵抗派は尊王攘夷の浪士のようでもあるし、人を作り出す教育は、あらゆるところで疲弊し(中略)閉鎖的である」
「その結果、何年習っても外国語は喋れず、テストばかりで独創性も失われた。悪平等が蔓延し、いい意味での競争がない」
「一国平和主義も、考えてみれば、鎖国政策そのものではないか。日本さえ平和であれば、それでよい。イラクの復興も我れ関せず。軍備も何もいらないという人さえいるのだから、世紀末というしかない」
「前世紀の遺物のような固定観念に、しがみ付く日本は危うい」
歴史を学ぶというのは、過去にもあった同じような状況が招いた結果を学び、活かすことです。
歴史は繰り返すのです。
歴史学というは本当に大切な学問なんですよ。