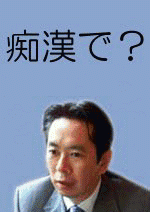昨日は久しぶりに友人と「超」がつくような長話をしました。
その友人はリアル世界で、学校現場での繊細な親子や弱い立場にある方々をなんとかしたいと尽力していて(事件は現場で起こっている)、いっぽうわたしは1月のエントリー
で紹介した、教育基本法改正情報センターの集会資料
などをもとに「上のほう」で何が行われようとしているかなど、お互いの情報を補い合いつつ交換するので、どうしても長くなります。
互いに、「誰もが、1円の得にもならないのに、って言うんだけどね」と笑いあいましたが…
友人が関わっている公立校では、(おそらくは)無理のある数値的目標や、ある程度モノを言いやすい環境になったため、かえってこれまで封殺されていたことが目に見える形の問題となって噴出し、良心的な先生はこの数ヶ月、すっかり疲れきっているそうです。
また、保護者の側にも様々な家庭事情や雇用事情で子どもに深く関わることが難しくなっている人が増えていて、でも(何もかも学校に頼るわけではないにせよ)、疲れきった現場では不安定な状況にある生徒たちを少しだけでもサポートしたくても、それもできなくなっているようだ、とのことです。
~~~
そのとき、二人で再度読み直した集会の資料の中でも、御手洗ビジョンや、学校評価(目標管理表)の問題など実例には、しばり暗澹とします。
後者(学校評価の関連資料)について、少し引用しておきます。
具体的な「学校評価結果」が学校ごとのサイトに、詳細に公開されている事例が数多くあります。
検索エンジンで、「学校評価自己評価表」「外部評価に関する協議会 小中学校用」などで探してみていただきたいと思います(ここで、特定の学校のデータにリンクを張るのはさすがにためらわれるため)。
もちろん、前向きな改善項目もありますが、目を覆いたくなるような長期的展望の片鱗もない短期目標も無数に設定されており、たとえば、ドリル学習を実施する回数目標値とその達成度や、挨拶の頻度の達成度が数値で記載され、それらに対して4段階評価が行われていることがわかります。
これは産業界ですらさすがに否定されつつある、旧弊な成果主義の運用手順そのものです(ということは1月にも書いたけれど)。
ややダブルスタンダード的発言ですが、このような目先の達成が学校間の比較に使われるとするなら、もうトップが結果をごまかすような意図でも持たない限り(偽装を推奨するわけではないけれど)児童生徒にかかわりを持つ、ほんのわずかの余裕を持ちきれないかもしれません。
【学校評価における数値目標例】
◆目標管理と内面への干渉-広島県「学校評価」の「豊かな心」関連の項目から:
・黙って最後まで掃除する子が80%を上回る。
・集会の目的を理解し、場に応じた態度が取れる子が80%を上回る。
・[道徳の時間の]価値項目を自己の生き方に結び付けて考える児童を80%にする。
・自分と向き合う黙思黙想を週1回以上実施し児童のYes回答を95%にする。
・校門での礼やあいさつができる児童を100%にする。
・夢や希望を持っている児童を90%以上にする。
・「外遊びが好きだ」という児童を80%以上にする。
・校内外でボランティア活動を企画し、それに全生徒年間2回は参加し、大変活動の充実を図る。
◆これらに対しての評価基準
A 80%以上の達成 目標を達成できた
B 60%以上80%未満の達成 概ね目標を達成できた
C 40%以上60%未満の達成 あまり目標を達成できた
D 40%未満の達成 目標を達成できなかった
ふだん批判的精神を持たない(生真面目で従順な)人には決して悪いことには見えない項目が連ねてある点、タチが悪いですね。
これらの管理が恒常化しているもとでは、子どもの権利条約 も批准できないことも明白です。
特に、第12条の「自由に自己の意見を表明する権利を確保」、第14条の「思想、良心及び宗教の自由についての児童の権利を尊重」を侵害しています。
それと、精神的に児童生徒を追い詰める教職員が指導力不足の1つの類型としてあったとして(というか率は低くとも現実に存在するわけなのですが)、彼ら彼女らの問題行動はこうした評価表では検出できないし(それよりは、場に応じた態度を生徒たちに取らせないことがかえって悪とされる)、だからむしろこの数値データを守らせるためには子どもに強制をしなくてはならないと考える向きが現れ、弊害をもたらすことは、「あって当然」だと思う。
そんな拘束を乗り越えようとする熱心な先生は、数値目標では文句を言わせず、加えて自主性のある教育を実現しようとして、結局は働きすぎになってしまいます(というか現実に知りうる範囲で存在しています)。
続けて引用します:
◆外部評価に関する協議会の報告より抜粋(東京都某区の例)
[教職員と児童の関係]
・教職員は一人一人の児童への声かけを大切にしており、児童も指導を受け入れている。
(外部評価者からの説明)
ほとんどの教職員はおおむね問題ない。ただし、2年生、5年生のクラスで問題が発生した事実からは十分でない教職員がいると判断される。
(今後に向けての考え:学校の受け止め方を明確にして)
・児童の多くは品位ある態度で教師とかかわり、教師も児童の実態に合わせて丁寧な指導をしてきており、児童は楽しい学校生活を送ってきた。ご指導の学年は、担任教師の指導観に問題があったことを認め、改善策をもって学校体制で臨み所定の成果があった。今後は防止策を徹底させる。
こんなあいまいな目標に対して、達成度をどう数値化するのだろう?
結局は「児童が指導を受け入れている」クラスの比率なのでしょうか?
またそこで、2年、5年のクラスの問題が願人教師の「指導観に問題がある」と特定するのは誰でしょうか?
表面上客観的な評価の後の分析と検証は内部に一任されているのだとすると、最悪の場合、いかようにでもこの結果をもとに好き嫌い人事の駒を進めることが可能ではないでしょうか?
~~~
そして、昨年9月の時点で、基本法改悪から今年7月の教育振興基本計画施行(参院選絡み?)のロードマップがあったのだそうです(先月入手したものなので、もっと早くアップしておくべきでした)。
この日程に沿って、事態は強行に進められ、また再生会議のアウトプットが貧相であったから・期日が記載されていなかったから、さっさと「平成19年度通常国会で」という文言に改竄する、そんなことは朝飯前だったわけですね。
【クリックで拡大します】
~~~
「ともかく安倍政権が本格的に稼動するのは参院選後だ。私は安倍氏に『やりたいことは半分にしとけ、まずは参院選に勝つこと』と言っているし、安倍氏も分かっている」と、森喜朗氏は語ったそうです(産経2006/10/31記事を『世界』07年3月号より孫引き)。
たしかに、随所に7月までの「仕込み」が目立ちますね。事実をもとにした問題提起の重要性を感じます。
せめてこちらができることとして、出すべき情報はじゃんじゃん出しておかなくちゃ、と思います。
【追記】
教育基本法については2/9に民主党案が再提出
されて、第165国会の参院案と同じ内容とのことですが、この再提出の意図はさらに知りたいところです。このことが、結局与党も野党も同じ・・・という小ぢんまりした見解に修練していかないためにも。
~~~
植草事件に関する書籍出版バナーを、雑談日記のSOBAさん のところからお借りしています。
未読書も大いにスタックしてしまっていますが、こちらは購入して読みたいと思います。
---
トラックバックピープル「安倍晋三」 に参加しています。
トラックバックピープル「教育基本法」 に参加しています。
トラックバックピープル「2007年参議院選挙 野党共闘 」 に参加しています。
News for the People in Japan のリンク集 に登録していただいています。