★ 輪島塗って? 1 ★
Bonjour

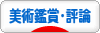 にほんブログ村今何位でしょう?
にほんブログ村今何位でしょう?

人気ブログランキング参加中 1日一回の
素敵なクリック♪
1日一回の
素敵なクリック♪
 ありがとうございます
ありがとうございます
前回の一時帰国で、パリから向かったのは、 羽田乗換え能登
羽田乗換え能登
能登半島といえば、先日「世界農業遺産」に登録された能登半島のシンボル的存在、美しい棚田の「白米千枚田」(しろよねせんまいだ)があるところです。 世界農業遺産は、環境保全に目配りした特色ある農業が実践されている地域に対して認定されます。日本から登録されているのは、この石川県能登半島と新潟県佐渡市。(国の特別天然記念物トキとの共生を目指す減農薬農業)。


訪れたときは、まだ認定されていませんでしたが、そのすぐ直後に日本から初めて登録されました。
というわけで、もちろん目的は別。それは、「輪島塗」です。「輪島塗」は、日本全国にある漆器の産地の中で、唯一重要無形文化財に認定されています。
ところで、「輪島塗」って何でしょう 何が、他の漆器と違うのでしょう
何が、他の漆器と違うのでしょう
輪島塗の特徴は、厚手の木地に生漆と米糊を混ぜたもので布を貼って補強し、生漆と米糊、そして焼成珪藻土を混ぜた下地を何層にも厚く施した「丈夫さ」 に重きをおいて作られている漆器である、ということです。
に重きをおいて作られている漆器である、ということです。
漆は天然漆を用い、加飾は沈金・蒔絵によります。木地は、ヒバ ケヤキ カツラ もしくはホオノキ、またはこれらと同等の材質。
「布着せ」は、木地に布を貼ることで、椀の縁や高台、箱ものの角など傷つきやすい所を補強するために施すものです。漆工芸における基本的な工程ですが、現在広く流通している漆器では省略されることが多く、輪島塗や越前塗、京漆器等の一部の漆器産地でつくられるものにしか見受けられなくなっています。でも、逆にいえば、これだけでは、「輪島塗」とはいえません。

輪島塗では、漆を木地に吸着させ丈夫にするために地元で生産する珪藻土(けいそうど。藻類の一種である珪藻の殻の化石よりなる堆積岩)を使います。漆にフィラーを配合して作ったペースト状の下地材を何層にもわたってヘラ木で塗装していく工程を「本堅地(ほんかたじ)」といい、これも漆工芸における基本的な工程です。輪島塗ではこのフィラーに「輪島地の粉」と呼ばれる焼成珪藻土を用いるのが特徴なのです
正確にいえば、なんと124工程もあり、その一つ一つがそれぞれの職人の手によります
最終的に価格が高くなってしまうのも、ナットク、ですよね

まずは、木地やさんから見ていきましょう
 人気ブログランキング。
人気ブログランキング。 クリックご協力くださいませね
クリックご協力くださいませね



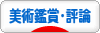

にほんブログ村美術部門 にほんブログ村女性社長部門
にほんブログ村女性社長部門
こちらからは、アート・デザイン系のランキング~



人気ブログランキング参加中
 1日一回の
素敵なクリック♪
1日一回の
素敵なクリック♪

前回の一時帰国で、パリから向かったのは、
 羽田乗換え能登
羽田乗換え能登
能登半島といえば、先日「世界農業遺産」に登録された能登半島のシンボル的存在、美しい棚田の「白米千枚田」(しろよねせんまいだ)があるところです。 世界農業遺産は、環境保全に目配りした特色ある農業が実践されている地域に対して認定されます。日本から登録されているのは、この石川県能登半島と新潟県佐渡市。(国の特別天然記念物トキとの共生を目指す減農薬農業)。


訪れたときは、まだ認定されていませんでしたが、そのすぐ直後に日本から初めて登録されました。
というわけで、もちろん目的は別。それは、「輪島塗」です。「輪島塗」は、日本全国にある漆器の産地の中で、唯一重要無形文化財に認定されています。
ところで、「輪島塗」って何でしょう
 何が、他の漆器と違うのでしょう
何が、他の漆器と違うのでしょう
輪島塗の特徴は、厚手の木地に生漆と米糊を混ぜたもので布を貼って補強し、生漆と米糊、そして焼成珪藻土を混ぜた下地を何層にも厚く施した「丈夫さ」
 に重きをおいて作られている漆器である、ということです。
に重きをおいて作られている漆器である、ということです。漆は天然漆を用い、加飾は沈金・蒔絵によります。木地は、ヒバ ケヤキ カツラ もしくはホオノキ、またはこれらと同等の材質。
「布着せ」は、木地に布を貼ることで、椀の縁や高台、箱ものの角など傷つきやすい所を補強するために施すものです。漆工芸における基本的な工程ですが、現在広く流通している漆器では省略されることが多く、輪島塗や越前塗、京漆器等の一部の漆器産地でつくられるものにしか見受けられなくなっています。でも、逆にいえば、これだけでは、「輪島塗」とはいえません。

輪島塗では、漆を木地に吸着させ丈夫にするために地元で生産する珪藻土(けいそうど。藻類の一種である珪藻の殻の化石よりなる堆積岩)を使います。漆にフィラーを配合して作ったペースト状の下地材を何層にもわたってヘラ木で塗装していく工程を「本堅地(ほんかたじ)」といい、これも漆工芸における基本的な工程です。輪島塗ではこのフィラーに「輪島地の粉」と呼ばれる焼成珪藻土を用いるのが特徴なのです

正確にいえば、なんと124工程もあり、その一つ一つがそれぞれの職人の手によります

最終的に価格が高くなってしまうのも、ナットク、ですよね


まずは、木地やさんから見ていきましょう

 人気ブログランキング。
人気ブログランキング。 クリックご協力くださいませね
クリックご協力くださいませね



にほんブログ村美術部門
 にほんブログ村女性社長部門
にほんブログ村女性社長部門
こちらからは、アート・デザイン系のランキング~



