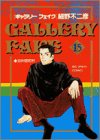★ 金唐革と金唐革紙2 ★
Bonjour!

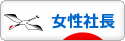
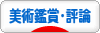

人気ブログランキング参加中 ココをクリック♪
ココをクリック♪
1日1回素敵なクリック お願いします♪
お願いします♪

金唐革(きんからかわ)と金唐革紙(きんからかわし)の違い
マンガでお読みになりたい方は、こちらで
名前の通り、「革」と「紙」です。
左が金唐革、右が金唐革紙
ヨーロッパで金唐革が次第に下火になっていく少し前、江戸時代前期の17世紀半ばに、オランダ経由でスペイン製の「金唐革」が輸入されて人気を博しました。が、鎖国を行っていた日本にとって、これは極めて貴重かつ入手困難な品物。そこで、いつの時代も賢い日本人、和紙を素材とした代用品の製作を試み、1684年に伊勢で完成した製品が「金唐革紙」 (「擬革紙(ぎかくし)」ともいう。) の始まり
(「擬革紙(ぎかくし)」ともいう。) の始まり

こちらは、金唐革のタバコ入れ。
金唐革紙(きんからかわし、Japanese leather paper)もしくは金唐紙(きんからかみ)は日本の伝統工芸品 です。和紙に金属箔(金箔、銀箔、錫箔等)を押し、版木に当てて凹凸文様を打ち出し、彩色をほどこし、全て手作りで製作する高級壁紙。金唐革とほとんど特徴が同じですね
です。和紙に金属箔(金箔、銀箔、錫箔等)を押し、版木に当てて凹凸文様を打ち出し、彩色をほどこし、全て手作りで製作する高級壁紙。金唐革とほとんど特徴が同じですね 金属箔の光沢
金属箔の光沢 と、華麗な色彩
と、華麗な色彩

 が建物の室内を豪華絢爛に彩ります。
が建物の室内を豪華絢爛に彩ります。

旧岩崎邸内部。金唐革紙の壁紙。
さて、これに目をつけたのが、18世紀中頃に生きた異能の人、平賀源内です。日本の工芸技法を駆使して、大量に作ろうとしたのですが、 どうやら彼の目論見は成功しなかったようです。その後の明治10年(1877年)、第一回内国勧業博覧会には、九つのメーカーが擬革紙を出展し、これをきっかけに、本来の用途である壁紙が本格的に和紙で作られるようになりました。 叩いても破れない丈夫な紙を漉く技、
叩いても破れない丈夫な紙を漉く技、 浮世絵のための版木彫りと刷りの技、
浮世絵のための版木彫りと刷りの技、 薄い箔作りの技、
薄い箔作りの技、 漆の技と、日本の得意とするさまざまな工芸の技があってこその金唐革紙の誕生だったといえます。(参照 handmade japan
)
漆の技と、日本の得意とするさまざまな工芸の技があってこその金唐革紙の誕生だったといえます。(参照 handmade japan
)
そして、明治時代には、大蔵省印刷局が中心となって製造・輸出され、ウィーン万国博覧会・パリ万国博覧会など各国の博覧会で好評となり、欧米の建築物(バッキンガム宮殿等)に使用されました。この頃が金唐革紙の黄金期

国内では、鹿鳴館等の明治の洋風建築に用いられましたが、その多くは現在消滅し、現存するのは数ヶ所だけという貴重な文化財です。その後、質の低下もあり、昭和初期には徐々に衰退し、その製作技術は完全に途絶えていました。
1985年、上田尚氏が、50歳で金唐紙研究所を設立し、試行錯誤を経て復興。現代版「金唐革紙」を復活させました。「金唐紙(きんからかみ)」とは金唐紙研究所製品にのみ用いる、研究所によって新しく考えられた造語です。
2005年、研究所を代表して上田尚氏が、 選定保存技術(文化財の修理復元等のために必要な伝統的技術として文部科学大臣が選定するもの。)の保持者に認定されました。2010年現在、研究所は本格的な製作体制は終了し、現在、金唐革紙製作全般にわたる本格的な製作技術を有しており、現役で製作可能なのは、2名だけです。
選定保存技術(文化財の修理復元等のために必要な伝統的技術として文部科学大臣が選定するもの。)の保持者に認定されました。2010年現在、研究所は本格的な製作体制は終了し、現在、金唐革紙製作全般にわたる本格的な製作技術を有しており、現役で製作可能なのは、2名だけです。
金唐紙研究所 →
金唐紙研究所は、さまざまな重要文化財の修復をてがけ、2002年には、旧岩崎家住宅(重要文化財、台東区)の復元を行いました。

この岩崎家住宅の洋館を設計したのは、ジョサイア・コンドルというイギリスのロンドン出身の建築家。お雇い外国人として来日し、政府関連の建物の設計を手がけました。鹿鳴館、旧宮内省本館も彼の作品。東大法文科教室も。そのほとんどが、取り壊しや焼失してしまっているのが残念です。 また工部大学校(現・東京大学工学部建築学科)の教授として辰野金吾ら、創生期の日本人建築家を育成し、明治以後の日本建築界の基礎を築きました。東大構内にも、こんな像があるそうです。。存じませんでした。きっと工学部の方にあって、普段足を踏み入れないところにあったのでしょう。
また工部大学校(現・東京大学工学部建築学科)の教授として辰野金吾ら、創生期の日本人建築家を育成し、明治以後の日本建築界の基礎を築きました。東大構内にも、こんな像があるそうです。。存じませんでした。きっと工学部の方にあって、普段足を踏み入れないところにあったのでしょう。

旧岩崎邸は、内外装とも全体のスタイルや装飾は英国17世紀のジャコビアン様式を基調としつつ、南面のベランダにはコンドルが得意としたコロニアル様式がよく表れています。一方、客室の天井装飾、床のタイル、暖炉などの細部にはイスラム風のデザインを施すなど様々な様式を織り交ぜています。客室や集会室などがあります。2階の2部屋に2種類の金唐革紙(手製の高級壁紙)が使用されており、現在は復元品がはられています。




祖父母の家にこんな壁紙があったような。。。
それにしても、こんな素晴らしい技術がなくなってしまうのは、惜しいですよね
なんとかならないのかしら
 人気ブログランキング。
人気ブログランキング。
 どうぞクリックご協力くださいませね
どうぞクリックご協力くださいませね





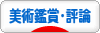
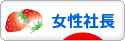 ベスト10復活?
ベスト10復活?
 にほんブログ村美術鑑賞・評論部門
にほんブログ村美術鑑賞・評論部門
こちらからは、アート・デザイン系のランキング~




人気ブログランキング参加中
 ココをクリック♪
ココをクリック♪
1日1回素敵なクリック

金唐革(きんからかわ)と金唐革紙(きんからかわし)の違い

マンガでお読みになりたい方は、こちらで

名前の通り、「革」と「紙」です。
左が金唐革、右が金唐革紙
ヨーロッパで金唐革が次第に下火になっていく少し前、江戸時代前期の17世紀半ばに、オランダ経由でスペイン製の「金唐革」が輸入されて人気を博しました。が、鎖国を行っていた日本にとって、これは極めて貴重かつ入手困難な品物。そこで、いつの時代も賢い日本人、和紙を素材とした代用品の製作を試み、1684年に伊勢で完成した製品が「金唐革紙」
 (「擬革紙(ぎかくし)」ともいう。) の始まり
(「擬革紙(ぎかくし)」ともいう。) の始まり

こちらは、金唐革のタバコ入れ。
金唐革紙(きんからかわし、Japanese leather paper)もしくは金唐紙(きんからかみ)は日本の伝統工芸品
 です。和紙に金属箔(金箔、銀箔、錫箔等)を押し、版木に当てて凹凸文様を打ち出し、彩色をほどこし、全て手作りで製作する高級壁紙。金唐革とほとんど特徴が同じですね
です。和紙に金属箔(金箔、銀箔、錫箔等)を押し、版木に当てて凹凸文様を打ち出し、彩色をほどこし、全て手作りで製作する高級壁紙。金唐革とほとんど特徴が同じですね 金属箔の光沢
金属箔の光沢 と、華麗な色彩
と、華麗な色彩

 が建物の室内を豪華絢爛に彩ります。
が建物の室内を豪華絢爛に彩ります。
旧岩崎邸内部。金唐革紙の壁紙。
さて、これに目をつけたのが、18世紀中頃に生きた異能の人、平賀源内です。日本の工芸技法を駆使して、大量に作ろうとしたのですが、 どうやら彼の目論見は成功しなかったようです。その後の明治10年(1877年)、第一回内国勧業博覧会には、九つのメーカーが擬革紙を出展し、これをきっかけに、本来の用途である壁紙が本格的に和紙で作られるようになりました。
 叩いても破れない丈夫な紙を漉く技、
叩いても破れない丈夫な紙を漉く技、 浮世絵のための版木彫りと刷りの技、
浮世絵のための版木彫りと刷りの技、 薄い箔作りの技、
薄い箔作りの技、 漆の技と、日本の得意とするさまざまな工芸の技があってこその金唐革紙の誕生だったといえます。(参照 handmade japan
)
漆の技と、日本の得意とするさまざまな工芸の技があってこその金唐革紙の誕生だったといえます。(参照 handmade japan
)そして、明治時代には、大蔵省印刷局が中心となって製造・輸出され、ウィーン万国博覧会・パリ万国博覧会など各国の博覧会で好評となり、欧米の建築物(バッキンガム宮殿等)に使用されました。この頃が金唐革紙の黄金期


国内では、鹿鳴館等の明治の洋風建築に用いられましたが、その多くは現在消滅し、現存するのは数ヶ所だけという貴重な文化財です。その後、質の低下もあり、昭和初期には徐々に衰退し、その製作技術は完全に途絶えていました。
1985年、上田尚氏が、50歳で金唐紙研究所を設立し、試行錯誤を経て復興。現代版「金唐革紙」を復活させました。「金唐紙(きんからかみ)」とは金唐紙研究所製品にのみ用いる、研究所によって新しく考えられた造語です。
2005年、研究所を代表して上田尚氏が、
 選定保存技術(文化財の修理復元等のために必要な伝統的技術として文部科学大臣が選定するもの。)の保持者に認定されました。2010年現在、研究所は本格的な製作体制は終了し、現在、金唐革紙製作全般にわたる本格的な製作技術を有しており、現役で製作可能なのは、2名だけです。
選定保存技術(文化財の修理復元等のために必要な伝統的技術として文部科学大臣が選定するもの。)の保持者に認定されました。2010年現在、研究所は本格的な製作体制は終了し、現在、金唐革紙製作全般にわたる本格的な製作技術を有しており、現役で製作可能なのは、2名だけです。
金唐紙研究所 →

金唐紙研究所は、さまざまな重要文化財の修復をてがけ、2002年には、旧岩崎家住宅(重要文化財、台東区)の復元を行いました。

この岩崎家住宅の洋館を設計したのは、ジョサイア・コンドルというイギリスのロンドン出身の建築家。お雇い外国人として来日し、政府関連の建物の設計を手がけました。鹿鳴館、旧宮内省本館も彼の作品。東大法文科教室も。そのほとんどが、取り壊しや焼失してしまっているのが残念です。
 また工部大学校(現・東京大学工学部建築学科)の教授として辰野金吾ら、創生期の日本人建築家を育成し、明治以後の日本建築界の基礎を築きました。東大構内にも、こんな像があるそうです。。存じませんでした。きっと工学部の方にあって、普段足を踏み入れないところにあったのでしょう。
また工部大学校(現・東京大学工学部建築学科)の教授として辰野金吾ら、創生期の日本人建築家を育成し、明治以後の日本建築界の基礎を築きました。東大構内にも、こんな像があるそうです。。存じませんでした。きっと工学部の方にあって、普段足を踏み入れないところにあったのでしょう。

旧岩崎邸は、内外装とも全体のスタイルや装飾は英国17世紀のジャコビアン様式を基調としつつ、南面のベランダにはコンドルが得意としたコロニアル様式がよく表れています。一方、客室の天井装飾、床のタイル、暖炉などの細部にはイスラム風のデザインを施すなど様々な様式を織り交ぜています。客室や集会室などがあります。2階の2部屋に2種類の金唐革紙(手製の高級壁紙)が使用されており、現在は復元品がはられています。




祖父母の家にこんな壁紙があったような。。。
それにしても、こんな素晴らしい技術がなくなってしまうのは、惜しいですよね

なんとかならないのかしら

 人気ブログランキング。
人気ブログランキング。
 どうぞクリックご協力くださいませね
どうぞクリックご協力くださいませね





 にほんブログ村美術鑑賞・評論部門
にほんブログ村美術鑑賞・評論部門
こちらからは、アート・デザイン系のランキング~