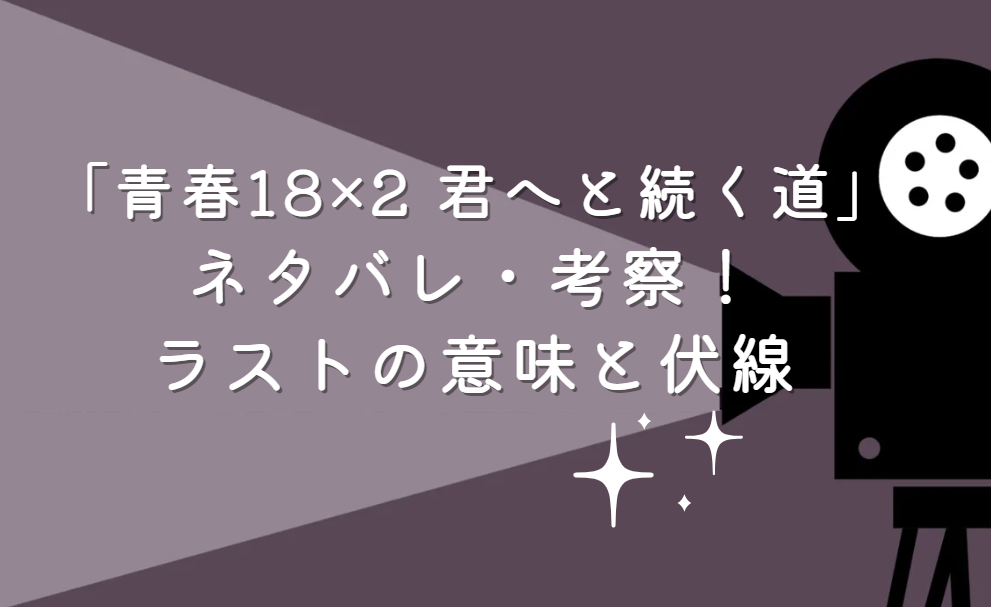2006年の台湾、2024年の日本
物語は2024年の台湾から始まります。
36歳のジミー(グレッグ・ハン)は大学の同窓生とゲーム会社を共同経営していますが、周囲の決定により取締役職を解任され、故郷の台南に戻ります。
実家で18歳の時に受け取ったハガキを見つけ、それは彼がKTVで働いていた時に出会った日本人バックパッカーのアミ(清原果耶)からのものでした。
アミはお金がなくて店で働いて宿泊を交換しており、若いジミーは彼女にすぐに魅了されます。
会社の取締役としてのジミーは最後の仕事のために東京へ行き、任務を完了するとゆっくりとした列車で旅に出ます。
東京を出発し、鎌倉、長野、新潟を経て、福島へ向かう途中、ジミーはさまざまな人々に出会い、初恋の相手であるアミとの思い出を振り返ります。
「日本映画」と「台湾映画」の間
「日本映画」と「台湾映画」の間で、この作品の日本部分はロードムービーのようであり、台湾部分は旅行映画のようなスタイルです。
スクリーンに現れる台湾の文化は、二人乗りのバイク、夜のライトアップされた賑やかなナイトマーケット、ジミーとアミが一緒に寺院を訪れるシーン、ジミーの父親が手で淹れた台湾茶、そして空に昇る天燈など、すべてが「まさに本物の台湾文化だ」と叫びたくなるようなものです。
本来、これらのシーンの多くは「アミが見る台湾」であり、したがって日本の視点で台湾を描写することにはその必然性があります。
初恋の懐かしい物語を回想する中で、台湾の街並みはしばしば「レトロなノスタルジア」と形容されますが、写真家の今村圭佑のカメラワークによって、現地の風景が緊張感に満ちた独特の方法で時折描かれ、絶妙なバランスが保たれています。
一方で、日本の部分は完全に「ジミーが見る日本」とは言えません。
列車の外の雪景色は見事であるものの、風景よりも、日本の部分は人物に重点が置かれており、台湾でも人気のある日本文化が多く登場します。
例えば、漫画『SLAM DUNK』やゲーム『桃太郎電鐵』、監督岩井俊二の映画『Love Letter』(95年)、日本の国民バンドMr. Childrenが主題歌を歌うなど、これらの文化表現がスクリーンに登場する日本よりも、その存在がより強く、Jimmyの物語を支えています。
この映画では、日本と台湾それぞれの俳優だけでなく、両国の土地と文化が交錯しています。
結果的に、制作側がこれらの要素を解釈する立場も曖昧になります。
――このため、この作品が「日本映画」と「台湾映画」の間で揺れ動く印象を与えるのは、間違いなくこのような「揺れ動き」から来ているのでしょう。
青春18きっぷ
原作は作者のライフー(賴吉米)が2014年にウェブサイトに投稿した旅行記で、JRの「青春18きっぷ」を持って日本各地を旅する体験を描きながら、初恋の相手であるアミとの思い出を回想しています。
プロデューサーの黄江豊(ロジャー)がこの旅行記を見て、4年かけて映画の脚本を執筆し、その後、監督の藤井道人が映画の脚本を完成させました。
映画の撮影計画が進行する中で、原作の著者は自ら小説化し、2024年2月に台湾で出版されました。
映画は原作のウェブサイト旅行記を基にしており、2024年にジミーが一人で日本を旅する様子と、2006年にジミーとアミが台南で過ごした時間を行き来しながら物語が展開します。
日本の部分では、人生の岐路に立つジミーが旅行中に青春時代の初恋を回想し、冷色系の画面が彼の内なる孤独感を表現します。
一方、台湾の部分では、過去の感動的で忘れられない初恋を称え、鮮やかな暖色系の画面が暑い台南を思わせます。
女性主人公のアミのキャラクターは、日本の少年漫画で描かれる「憧れの姉」を思わせる雰囲気があります。
彼女は捉えどころのない要素を持っており、先ほど言及した『消失のバレンタイン』といった、台湾の恋愛映画の女性主人公とも共通点があります。
さらに、男性が成長して初恋の物語を思い出し、日本文化への憧れを抱く様子は、台湾のヒット映画『あの頃、君を追いかけた』(2011)を思い起こさせます。
しかしながら、これらの多層性があっても、時間や国境を軽々と越えることができる脚本自体は決して複雑ではありません。
むしろ、この作品全体の基盤はシンプルで繊細です。
映画の核心に触れるため、細部にこだわりすぎることを避けるよう努めていますが、物語の後半では劇的な展開が見られ、これは監督の藤井が過去に取り上げたテーマとも共通しています。
実際、このような展開はウェブのオリジナル散文と酷似しており、藤井監督がこの作品を撮影するのに最適だと感じさせます。
続きは>>