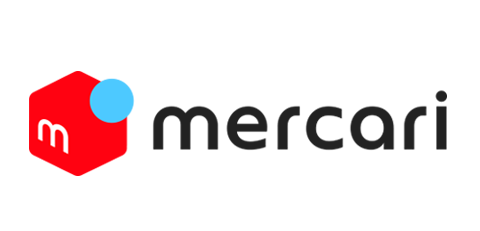死についてのさまざまな事象は変化しますが、死という現実は普遍的なものです。ベタニアで行われたラザロの葬儀のような場面は、世界中で何度も日々繰り返されています。嘆き悲しむ家族は墓の周りに集まり、友人たちは何を言おうかと頭を悩ませます。どうすることもできない沈黙、うつむいた目、ひきずる足は、慰めというより気を紛らわせるものです。予期していなかった死である場合、なぜ死んでしまったのかという思いは、息を詰まらせる煙霧のように空気中に漂います。
人々はエルサレムやその周辺から、悲しみと義理に引かれて、ベタニアに住む人の葬儀に参列するために来ていました。イエスの友人であるラザロが亡くなったのです。闘病期間は短く、ラザロの病気に効く薬は一つもありませんでした。イエスはラザロのところに向かっていましたが、間に合いませんでした。暑い国の知恵に従い、遺体はすぐに包まれて埋葬されました。4日後にイエスは到着しました。
ヨハネ福音書の11章には、イエスとマルタ、マリアの姉妹、そして彼らの兄弟ラザロとの関係が描かれています。新約聖書に登場するベタニアのマリアは、エルサレムの近くにあるベタニアで、弟のラザロと姉のマルタとともに生活していました。
章の冒頭では、ラザロが「イエスに愛された者」として記されています。この表現は、イエスと最も親密な弟子との関係を示すのに用いられたものと同じです。イエス、ラザロ、マリア、そしてマルタは、まるで実際の家族のようにお互いを考えていたとされています。
歴史上よく知られているのが、そのときイエスがしたことです。それはまたイエスの人となりだけでなく、彼が何のためにこの世界に来たのかを最も鮮明に示す事件でした。
**ラザロの死:ヨハネ福音書 11章の物語**ある日、イエスは墓地を訪れました。そこには、四日前に亡くなったラザロが眠っていました。その墓地は、エルサレムから十五スタディオンほどの距離にあるベタニアという町にありました。
ラザロの姉妹であるマルタとマリアの家には、ラザロを悼むために多くのユダヤ人が集まっていました。イエスが来たと聞いたマルタは、すぐにイエスを迎えに行きました。一方、マリアは家の中で座っていました。
マルタはイエスに言いました。「主よ、もしあなたがここにいらっしゃったら、私の兄弟は死ななかったでしょう。でも、あなたが神にお願いすれば、何でもかなえてくださると私は信じています。」
イエスは「あなたの兄弟は復活する」と答えました。マルタは、「終わりの日の復活の時には、彼は復活することを私は知っています」と答えました。
イエスは、「私は復活であり、命である。私を信じる者は、死んでも生きる。生きていて私を信じる者は、決して死ぬことはない。これを信じますか?」と尋ねました。
マルタは、「はい、主よ。あなたが世に来る神の子、メシアであると私は信じています」と答えました。
その後、マルタは家に戻りマリアに耳打ちしました。「先生が来て、あなたを呼んでいます」と。マリアはこれを聞くとすぐに立ち上がり、イエスのもとへ行きました。
イエスはまだ村に入っておらず、マルタが出迎えた場所にいました。家の中でマリアと一緒にいて、慰めていたユダヤ人たちは、マリアが急に立ち上がって出て行くのを見て、彼女が墓に泣きに行くのだろうと思い、後を追いました。
マリアはイエスのところに来て、イエスを見るとすぐに足元にひれ伏しました。「主よ、もしあなたがここにいらっしゃったら、私の兄弟は死ななかったでしょう」と言いました。
イエスは、マリアが泣いているのを見て、心に憤りを覚え、興奮しました。「ラザロをどこに葬ったのか教えてくれ」とイエスは尋ねました。彼らは、「主よ、来て、ご覧ください」と答えました。
そして、イエスは涙を流しました。ユダヤ人たちは「見てください、イエスがどれほどラザロを愛していたか」と言いました。
↑↑↑ ラザロの死 ↑↑↑
マルタは、イエスのところに来てこう言います。「主よ、ここにいらっしゃったら、弟は死ななくてすんだでしょう」。ここでのマルタの信仰告白は模範的で美しいものです。まずマルタは、イエスは奇跡を行うことができる、という信仰を告白します。イエスは病気のラザロを癒すこともできるし、さらには死んだラザロを今でもよみがえらせることができる、と彼女は信じています。
このすぐ後に、今度はマリヤが来て一字一句同じことを言います。 二人の姉妹、同じ状況、全く同じ言葉です。しかし驚くべきことにイエスの二人への反応は 全く違います。
イエスは、マルタに対してほとんど議論する勢いで応じます。「来るのが遅すぎた」という彼女の言葉のニュアンスに、イエスは「私は復活であり、命そのものです。私にとって遅すぎるということはありません」と答えます。彼は彼女の心に満ちる絶望を抑え、疑いを叱りつつも希望を与えるのです。
一方で、マルタと同じ言葉を言ったマリヤに向かい、イエスは真逆の反応 を示します。議論をするどころか、実際のところ言葉を失っているかのようでもあります。彼女の心から悲しみがあふれるのを押しとどめるどころか、自分もその悲しみに入っていきます。嘆く彼女のそばに共に立ちます。涙を流し「彼をどこに置きましたか」と聞くのがやっとなほどに。
例えば、人間の姿になりすましてこの世に来た神についての物語を創作するとしましょう。その物語でこの神は死んだ友人を蘇らせる力を持っており、友人の葬儀に姿を現したとします。その時、この神の内面の感情をどのように表現するでしょうか。微笑みをたたえ、喜びを抑えられない様子を描写しないでしょうか。
そのような存在が、マリヤの苦悶に吸い込まれ、ただ泣きながらその場に立っているなどとは私たちは全く想像もしません。さっきまで雄々しかった彼が、なぜ次の瞬間には、かくも人間的になれるのでしょうか。
しかし、これは創作ではありません。そしてこの記事は、新約聖書が別の箇所で前提としていることを、劇的に示しています。つまりイエスが本当に神であり、そして完全に人間でもあるという前提です。人間に変装した神でもなく、神の雰囲気をもつ単なる人間でもな く、神でありそして人なのです。最初にマルタ、次にマリヤとの彼の出会いは、イエスが神でもあ人間でもあることを表しています。
マルタとのやり取りの中で彼はこう言います。「私はよみがえりであり、いのちです」。神性の主張です。神だけがいのちを与え、取り去ることができます。単に「私には超自然的な神としての力があるから、ラザロをよみがえらせることができる」と言っているわけではないことに注目してください。むしろ「私はよみがえりであり、いのちです。わたしが、すべてにいのちを与え、生かすことができる力だ」と言うのです。
神性についてのイエスの間接的な主張はどの箇所にも表れています。例えばイエスが罪の赦しを宣言したことです。誰にとっても明らかなのは、赦すことができる相手は、直接自分に罪を犯した人だけだということです。
例えばA氏に嘘をついたB氏を、あなたが赦すことはできません。A氏だけが、彼に嘘をついたB氏を赦すことができます。だからイエスが中風の人に「子よ。あなたの罪は赦されました」と言ったとき見物人たちは、イエスがすべての罪は自分に対して犯されているとほのめかすことによって、自分が神であると主張していると適切に結論づけたのです(マルコ2:5)。
イエスの明確な神性の主張は他にもまだまだあります。ヨハネ5章でイエスが自身を神と等しくしているのを聞いた群衆は、彼を石打ちにして殺そうとします。8章ではアブラハムが生まれる前から自分がいると言うだけでなく、自分を神の名で呼び永遠の存在だと主張するイエスを彼らは同じ石打ちで殺そうとします。
一世紀のユダヤ人たちは神が偉大な存在であると考え、神の名を書くとか、発音することさえ拒絶していたという点です。神が血肉を伴った弱い人間としてこの世界に来るといった考えは、どんなものでも激しく非難されました。つまり第一に、神であり人間であるという考えは、どれほど宗教的指導者に対する尊敬が高くても、ユダヤ人にとっては男女問わず全く考えられないことでし た。第二に、どんなペテン師であっても、ユダヤ人の弟子たちに、自分が神だと言って説得する試みさえしなかったということです。そんなことをしても成功する確率は皆無だと誰もが思っていました。
歴史的研究からはキリストの死後、ユダヤ的一神教に誠実であることを標榜しながらも、イエスをただひとりの本当の神として礼拝し始める人たちが飛躍的に増加したことがわかります。 偏った小規模の集団以上の人たちに、自分がこの世界の創造主であり裁き主であると説得すると いう歴史上他の誰もなしえなかったことをするために、イエスは一体どんな生涯を送ったのでしょうか。そのような馬鹿げた主張に強硬に反対するユダヤ人たちを納得させた彼は、一体どんな人物だったのでしょうか。
**イエスの怒りと憤り:死と裁きへの直面**
イエスの涙を、死と暗闇が人間の心を支配していることと、周囲にいた人々の「不信仰」について泣いておられたとの見方もあります。38節の訳「心に憤りを覚えて」(新共同訳)は「怒りに唸る」という意味のギリシ ア語が用いられていてどういうわけか、どの翻訳者もギリシア語の専門家や注解者によるこ の箇所に共通する理解に躊躇を感じたようです。イエスは無条件に怒り狂っていました。怒りに打ち震え、唸るほどだったのです。彼は何に、あるいは誰に対して、怒っていたのでしょう。
イエスは、死に対して憤っていました。「さあ、現実を見つめなさい。誰だって死ぬのだから。それがこの世の習いだ。運命に身をゆだねなさい」などとは言いませんでした。 彼はそう言いません。イエスは私たちの最大の悪夢に正面から立ち向かいます。
それがイエスの流儀です。
しかしながらイエスは剣を手にやっては来ませんでした。むしろ釘を携えてきたのです。裁きをもたらしにではなく自ら裁きに耐えるために来ました。そして、この箇所はイエスのジレンマを明らかにし始め、さらにそれを示していきます。この章の後半でイエスのその権威の示し方を見た宗教指導者たちはこの奇跡によって、思っていたよりも彼がさらに危険な存在になると認識しました。
イエスはもちろん、これらすべてを知っていました。彼は死んだラザロを生き返らせたら、宗教的グループが彼を殺そうとすることも知っていました。ラザロを墓から生き返らせるためには、唯一彼自身が墓に入らなければならなかったことを。私たちを死から救うなら自ら十字架に向かい、私たちが受けるべき裁きを耐えなければならないということを。だからこそイエスは墓に向かうとき、怒りに打ち震え涙を流したのです。私たちを死から救うのにどれだけの犠牲が必要なのか、彼は知っていました。おそらく死という脅威が今まさに彼をのみ込もうとしているのをひしひしと感じていたのでしょう。そういうすべてを知り経験しながらも、彼は叫んだのです。
「ラザロよ。出てきなさい」と。
そばにいた人たちはイエスについてこう言いました。「主はどんなにラザロを愛しておられたことか」。しかし本当はイエスが私たちをどれほどに愛してくれているかに驚きを覚えるべきでしょう。彼は私たちのために、いのちに限りがある、「か弱い」殺したら死んでしまう人間になられたのです。