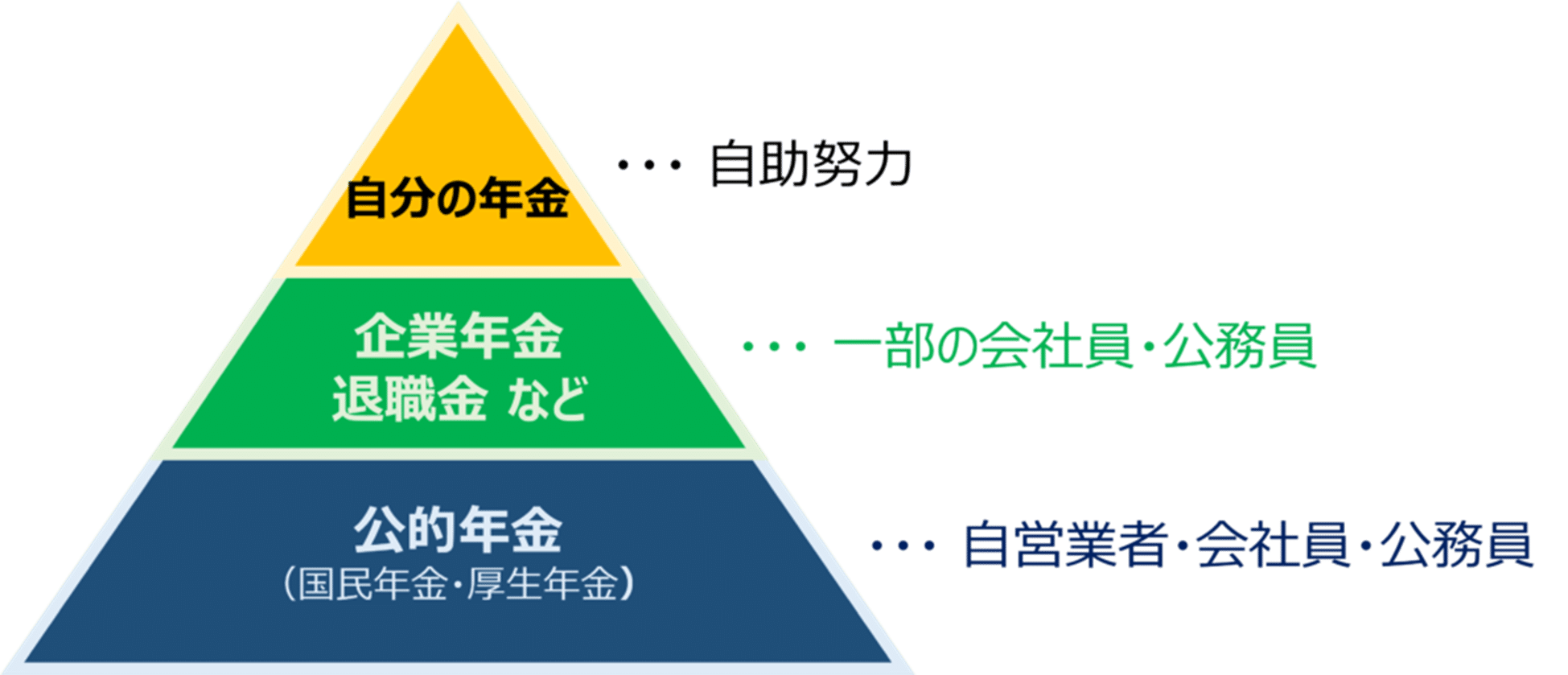団体信用生命保険は、略して「団信」(だんしん)と呼ばれることが多く、住宅ローン専門の生命保険のことです。
住宅購入資金を借りた人に万が一のことがあった場合や、高度障害の状態になった場合に、生命保険会社が借入残高分の保険金を保険金の受取人になる銀行等の金融機関に支払ってくれます。
金融機関はその保険金を借入残高の返済に充てるという仕組みになっています。
今回は団信の加入の際に検討すべき項目をいくつかピックアップして簡単に説明していますので、下記リンクよりご覧ください。
主な内容は以下の通りです。
・団信に加入するにあたって、別にお金が必要か?
・団信には絶対に加入しないといけないのか?
・団信にはどんな種類があるのか?
・団信の引受保険会社は自分で選べるのか?
・住宅ローンの借り換えをしたら団信はどうなるのか?
・団信の保険料は年齢によって変わるのか?