江原啓之と靖国(3)
というわけで、やっと靖国の話が絡んできます。
さて、「死んだら靖国で会おう」ということで亡くなっていった人たちが、「靖国神社に祀られることをスピリチュアル的な意味で捉えていて、神様の元に行くような想いでいたとしたら、やはり靖国神社に祀ってあげなければ、かわいそう」なので、そういう人たちは靖国に「祀られていていいと思います」と述べる。ここには靖国神社の戦争推進「装置」としての役割についてはなんら批判的な文言はないが、そこはおいておく(『靖国問題』高橋哲哉がわかりやすい)。
ところが、同じ祀られるにしても、スピリチュアルの観点からは、その「動機」によって意味が変わるのだそうだ。つまり、「霊的」に靖国が捉えられていればいいのだが、靖国に祀られることが、まるで勲章をもらうかのように捉えられていたら、それは「物質主義的価値観」であり、祀られる意味は減じられると説く(いや、まさにそれも戦争推進「装置」としての重要な役割の一つであると思うのだが)。
で、この話はここで唐突に終わる。「動機」によって祀られる意味の大小が変わるということの意味は語られない。
かわって、A級戦犯の問題が出てくる。
まず、靖国の見解、つまり、分祀しても、もとの霊は靖国にも残り、いなくなるわけではない、というのが紹介される。
それに対し、江原はこう述べる。
ここから話は国際政治になる。おそらく、分祀に反対している人々を説得しようというつもりなのだと推測されるが、その意図はいいとして、ロジックが幼稚すぎる。
もしこうした分祀を実行したら、あるいは首相が靖国参拝を中止したら、中国の「内政干渉」に屈するのではないか、という意見があるが、そうではない、と。中国にも問題がないわけではないが、
江原は、現代中国の言い分は、しかし物質主義的な政治カードと化してきているとした上で、それでも、首相が靖国に行かずに済むならば行かなくてもいいのではないか、と言う。
しかし、どうしても「英霊」に感謝を表す「形式」にこだわりたければどうするか。
「首相公邸に遥拝所を作って、祈りを捧げるというのもひとつの方法だと思います」いやいやいや、明後日の方向というのか想像のナナメ上というのか、とんでもない提案をしてくれるものだ。もちろん、政教分離の問題は江原も指摘しているが、首相公邸は首相の家でもあるのだから、信仰の自由から言っても「我が家」に遥拝所を置くのは問題ないのではないか、と言うのだ。
最後のまとめがまたすごい。
というわけで3回にわたって「靖国」について江原が書いたことを見てきた。
一見してわかるように、その結論は、「分祀すべき」「首相は参拝すべきでない」という穏当なものだ。
しかし、それを導くロジックは無茶苦茶であり、その端々から漏れる江原の理解は実に浅薄なものだ。
これが、江原が心底そう思って、たんに本人が無茶苦茶だから無茶苦茶なロジックを展開してしまったのか、そういう結論にしておけば、「ロハスな人々(笑)」に市場を拡げられるかも、というマーケティング戦略なのかはわからない。しかしいずれにしても、この人は戦争についてもっと勉強したほうがいい。
連休中に押入れ整理していて出てきたので、その意味も込めて、水木しげるの「総員玉砕せよ!」を挙げておく。あのような形(すいません読んでください)で「自決」に追い込まれた兵士たちも大勢いたのである。そのような人々についてまで、オーラだの「たましい」だの軽々しく語るのは、私は許せない。
さて、「死んだら靖国で会おう」ということで亡くなっていった人たちが、「靖国神社に祀られることをスピリチュアル的な意味で捉えていて、神様の元に行くような想いでいたとしたら、やはり靖国神社に祀ってあげなければ、かわいそう」なので、そういう人たちは靖国に「祀られていていいと思います」と述べる。ここには靖国神社の戦争推進「装置」としての役割についてはなんら批判的な文言はないが、そこはおいておく(『靖国問題』高橋哲哉がわかりやすい)。
ところが、同じ祀られるにしても、スピリチュアルの観点からは、その「動機」によって意味が変わるのだそうだ。つまり、「霊的」に靖国が捉えられていればいいのだが、靖国に祀られることが、まるで勲章をもらうかのように捉えられていたら、それは「物質主義的価値観」であり、祀られる意味は減じられると説く(いや、まさにそれも戦争推進「装置」としての重要な役割の一つであると思うのだが)。
で、この話はここで唐突に終わる。「動機」によって祀られる意味の大小が変わるということの意味は語られない。
かわって、A級戦犯の問題が出てくる。
まず、靖国の見解、つまり、分祀しても、もとの霊は靖国にも残り、いなくなるわけではない、というのが紹介される。
それに対し、江原はこう述べる。
しかし、スピリチュアル的な考えに立てば、分祀は可能です。というのは、靖国神社は、戦争で亡くなった方のたましいと交流、面会する場所です。その観点に立てば、実はお墓と一緒だとも言えるわけです。お墓には遺骨が入っているわけですが、そこにたましいは存在していません。たましいがいるとしたら、生前から「死んだから、たましいは墓にいるのだ」という考え方に執着を持っていた人のたましいぐらいです。ということで、「分祀は可能」だそうである(実際に可能かどうかについては、靖国の教義なりなんなりの問題があるのでおいておくが、祀るということが遺族をはじめとする生き残った人々のためにあるのだとすれば、その人たちの意思を優先してやれよ、とは思う。結局は人間が作ったルールなのだから[靖国の人々はそう思わないんだろうけどね])。
では、お墓とは何かといえば、それはたましいと交信するためのアンテナの役割を果たすものです。(中略)神道の教義や思想がいかなるものであれ、たましいと交信するのであれば、「あなた方のアンテナはこちらですよ」と新しいアンテナに移せばいいだけです。霊的な世界観で言えば、分祀ができないということはありえません。
ここから話は国際政治になる。おそらく、分祀に反対している人々を説得しようというつもりなのだと推測されるが、その意図はいいとして、ロジックが幼稚すぎる。
もしこうした分祀を実行したら、あるいは首相が靖国参拝を中止したら、中国の「内政干渉」に屈するのではないか、という意見があるが、そうではない、と。中国にも問題がないわけではないが、
ただ一つ言えるのは、中国の取る態度は虐待を受けて育った子どものトラウマに似ていると思うのです。だと。無論日本は「虐待」どころではない無茶苦茶を長年東アジアの国々に対し行ってきたのだが、それをマトモに反省しようとせず、隙あらば戦前を賛美し、教育勅語などの戦前体制の象徴のようなものを復活させようとする日本政府に対し、その行動を「トラウマ」とはあまりにもひどくないか。
江原は、現代中国の言い分は、しかし物質主義的な政治カードと化してきているとした上で、それでも、首相が靖国に行かずに済むならば行かなくてもいいのではないか、と言う。
しかし、どうしても「英霊」に感謝を表す「形式」にこだわりたければどうするか。
「首相公邸に遥拝所を作って、祈りを捧げるというのもひとつの方法だと思います」いやいやいや、明後日の方向というのか想像のナナメ上というのか、とんでもない提案をしてくれるものだ。もちろん、政教分離の問題は江原も指摘しているが、首相公邸は首相の家でもあるのだから、信仰の自由から言っても「我が家」に遥拝所を置くのは問題ないのではないか、と言うのだ。
最後のまとめがまたすごい。
このような論議をしている中、はたして英霊たちは今の日本の様子をどう思っているのでしょうか。もし政治家が「英霊たちに感謝を捧げたい」と思うのであれば、日本をよくしていくことが彼らの死に応える行為のはず。親が子を殺し、子が親を殺す。若者が働かずニートになる……そんな国を作るために彼らは命をかけたわけではないからです。いやいやいや、誰がニートにさせてんねん!
というわけで3回にわたって「靖国」について江原が書いたことを見てきた。
一見してわかるように、その結論は、「分祀すべき」「首相は参拝すべきでない」という穏当なものだ。
しかし、それを導くロジックは無茶苦茶であり、その端々から漏れる江原の理解は実に浅薄なものだ。
これが、江原が心底そう思って、たんに本人が無茶苦茶だから無茶苦茶なロジックを展開してしまったのか、そういう結論にしておけば、「ロハスな人々(笑)」に市場を拡げられるかも、というマーケティング戦略なのかはわからない。しかしいずれにしても、この人は戦争についてもっと勉強したほうがいい。
連休中に押入れ整理していて出てきたので、その意味も込めて、水木しげるの「総員玉砕せよ!」を挙げておく。あのような形(すいません読んでください)で「自決」に追い込まれた兵士たちも大勢いたのである。そのような人々についてまで、オーラだの「たましい」だの軽々しく語るのは、私は許せない。
- 靖国問題 (ちくま新書)/高橋 哲哉

- ¥756
- Amazon.co.jp
- 総員玉砕せよ! (講談社文庫)/水木 しげる
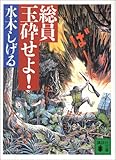
- ¥700
- Amazon.co.jp