二酸化炭素は普通気体だが冷やせば液体になる。逆に高温になれば分解されて炭素と酸素になるだろう。その挙動を考えるにあたって化学の状態図というものがある。
次のようなものだ:
相転移
相には気体、液体、固体があり、それぞれ気相、液相、固相という。物質がある相から他の相に変わることを相転移という。
固体が液体に変わる現象を融解といい、このときの温度が融点である。液体が気体に変わる現象が沸騰であり、この温度が沸点である。固体が液体にならずにそのまま気体になる現象が昇華であり、このときの温度が昇華点である。
下に水と二酸化炭素の圧力と温度によるおおまかな状態を示す。
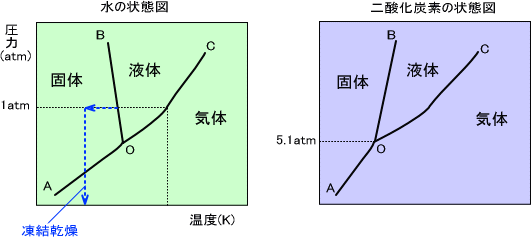
このような図を状態図という。曲線OCは蒸気圧曲線、曲線OBは融解曲線、曲線OAは昇華曲線を示している。固相、液相、気相の三相が互いに平衡となっているO点を三重点という。
図の右側が二酸化炭素で参考のために水の場合も図がある。
改めてみるとこの図は興味不快。
高校生の時はなあんにも考えずにただありのままに知識として
詰め込まされたのだが、
なぜ相変化があるのか、どのようにして起きるのかを考えて
そのアナロジーで物理の理論が触発されている。
例えば宇宙の相転移とビッグバンの推移など、
人間は元になる現象があって始めて宇宙の相転移のようなアイデアに行き着く。
だからみじかな水や二酸化炭素の相転移を考え直すことは意味あることだ。
そんな高尚なことでなくても
二酸化炭素を分解できるかということは気候変動にとっても
重要なことに違いない。
基本に戻って考える。
この場合、二酸化炭素を分解すると
固体(炭素)と酸素(気体)に分離され右図のような図は適用されないだろう。
右図は二酸化炭素としての化合物の状態図だからだ。
とするとそれぞれの状態図が突然出現することになる。
もはや高校化学の知識を超えることになるのか。
だから科学は面白い。