2012年末に原書を読んで、最近、日本語訳本を読んだ、ビル・エモット著"GOOD ITALY, BAD ITALY"。
改めて読み直してみると、表からは見えないイタリアの社会・経済の「深い闇」が見えてきます。
イタリアを停滞させた要因は外部環境にあるのではなく、ダイナミックで進歩的な力である"Good Italy"と、利己的かつ閉鎖的で保守的な力である"Bad Italy"のバランスが崩れ、後者が前者を凌駕しつつあるから、というイタリア人気質に問題の焦点の当てています。
この分析視角(アプローチ)は非常に興味深く、約300ページの本を読みながら、メモを取り、そして「鹿児島の場合はどうだろう」と反芻してみると、鹿児島の社会・経済が抱える多くの課題が思い浮かびます。
ほぼ日手帳を10ページ(=10日間)使用する勢いで、イタリアの社会・経済で起こったことが、鹿児島で起こっている、あるいは、起こりうるのかということを、考え、書き連ねていったら、手帳がびっしりと埋まってしまいました。
ただ、ここでふと思ったことは、「現在の鹿児島は多くの人々にとってGOODなのであろうか、それとも、BADなのであろうか」ということ。
手帳10ページが埋まるくらいなので、私の中では、やや(というよりも相当)悲観的な部分も多いのですが、そうではない視点や視野を持っている人も多いのだろうなと。
私は鹿児島という地域を愛する「愛国者」なのですが、人生の大部分を鹿児島で過ごし、そして、鹿児島で小役人という仕事に就いている立場なので、内部がよく見えているつもりになっていても、実は、それは虫の目で粗探しをしているに過ぎず、鳥の目で見れば大きな(しかも前向きな)変化が起きているかもしれません。
それを知るためには、やっぱり多くの人、特に、鹿児島に移住してきた人から見たGOOD KAGOSHIMAとBAD KAGOSHIMAを知る必要があり、そこに可能性と課題があるような気がします。
本研究会も開設して、間もなく3年を迎えようとしており、地域課題との向き合い方を変えようとも思っています。
その方向性を確認する意味でも、GOOD KAGOSHIMAとBAD KAGOSHIMAに関する調査を進めてみたいと思います。
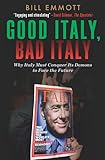 | Good Italy, Bad Italy Amazon |
 | なぜ国家は壊れるのか Amazon |
