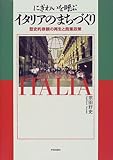大河ドラマの誘致に当たり、多くの関係者が要望活動やマーケティングに尽力さていることは重々承知ですが、あえて問題提起として、今回の投稿をさせていただきます。
大河ドラマ『西郷どん』の放映が決定されて以後、観光業界だけでなく、鹿児島県の経済界全体として、大河ブームに乗った活動が展開されつつあります。
過去の大河ドラマの経済効果を勘案すれば、ここは大きなビジネスチャンスということで、集中的なマーケティングを展開することは、経済合理性の観点からは理解できます。
しかし、その活動は蓋を開けてみれば、皮相的な経済活動に過ぎず、大河ドラマ終了後の持続的効果につながるかといえば、誰も自信をもって明確に答えることができません。
なぜなら、過去2回の大河ドラマ放映の経験によれば、いずれも「ブーム」ということで一時的な絶頂期を味わい、後は後退局面につながるという傾向にあったからです。
個人的には、大河ドラマ誘致は「麻薬」のようなものだと感じています。
一度ブームによる特需を経験すると、それが通常の需要だと勘違いし、落ち込みが目立つようになると、またもやブームによる特需を仕掛けようとする。
問題なのは、特需は所詮特需であって、永続するものではないにもかかわらず、一攫千金の特需のために無駄な資源を投入してしまうことです。
ここらへんは感覚的に感じていた部分なのですが、それが確信に変わったのは、こちらのを本を読んでから。
歴史的景観を整備し、観光客誘致により観光を産業化することに成功したイタリアのまちづくりの経緯や展開について詳述した書籍ですが、その30年間にわたる都市計画が紹介してあります。
30年と言えば、大河ドラマ『翔ぶが如く』から『西郷どん』までの期間が約30年です。
地道に法制度を整え、都市景観と都市コミュニティを保護する政策を推進したイタリアには、現在、津々浦々まで観光客が訪れています。
そこには一時的な経済活動としてではなく、美しく住みやすい文化・社会活動を選択した地域の姿があります。
単なる観光キャンペーンではない、歴史・文化の香り漂う鹿児島とするための、大きな転換点として、今回の『西郷どん』ひいては明治維新を位置づけることはできないのでしょうか。