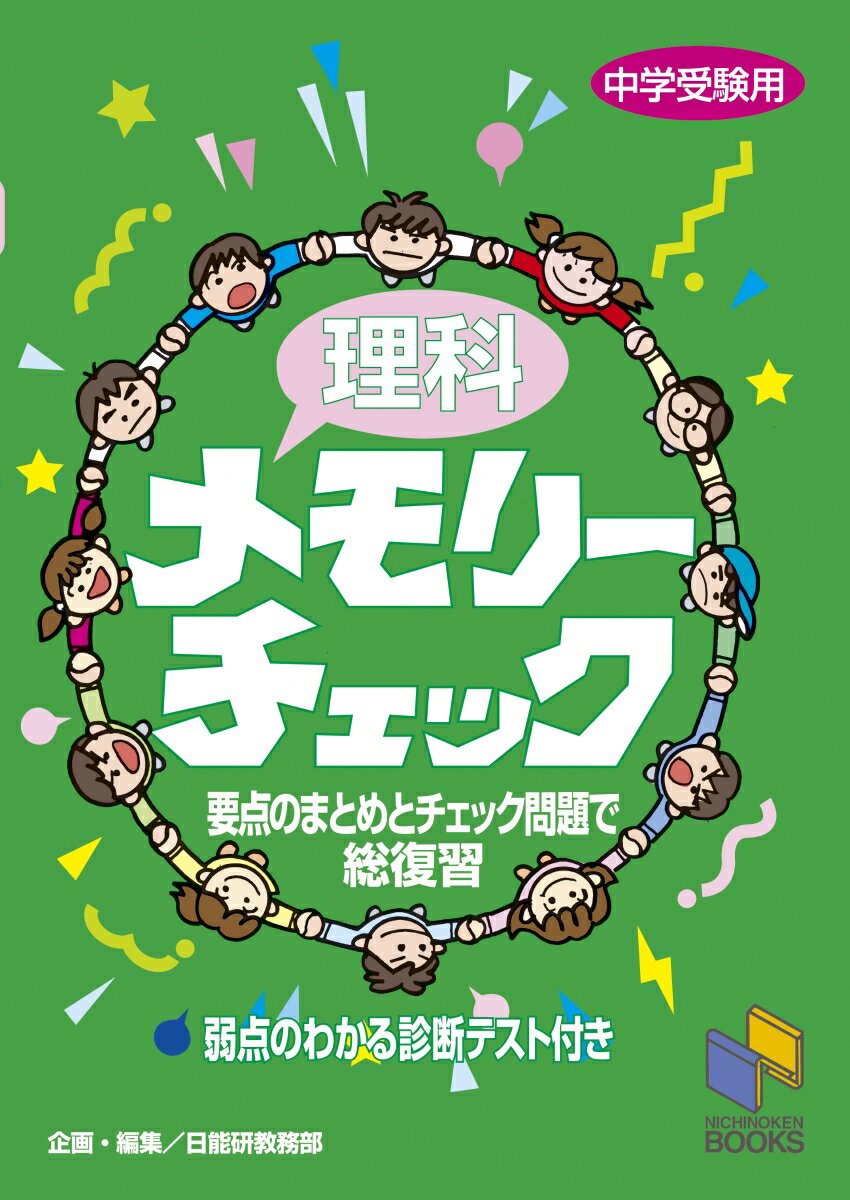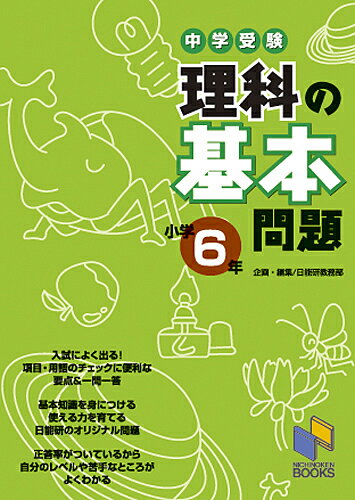先生自身も苦手分野がある?
理科は得意不得意が大きく分かれる科目です。また、物化生地の4分野を学ぶため、得意な単元とそうでない単元の差激しい科目でもあります。
さらにいうと理系講師は大学受験で生物や地学を使わないケースも多いので、若い講師だと忘れてしまっていて効果的な授業ができない可能性があります。
塾業界というのは教務的な研修は基本的に行われません。割と研修が丁寧なところでも授業の進め方、演出、板書の書き方などがメインで、科目の知識については自分で勉強しろというスタンスです。したがって勉強しない人、塾講師になるまでに得た知識でなんとかしようという先生だと先生自身が苦手分野を抱えたままで生徒を指導することになるということですね。
ただ先生を批判しても問題は解決に至らない事の方が多いです。勤勉でない大人を変えることは無理でしょう。
子供の苦手分野克服のためには
なぜ苦手が生まれるのかという原理原則に立ち還れば答えは自ずと見えてきます。
苦手は「基礎の未定着、理解不足」で発生します。ならば基礎の再定着、再理解を行えば苦手が得意にはならないまでも一旦、苦手でなくなるということになりますよね。
苦手分野の発見と克服の手法
基礎問題を全単元振り返り正答数が少ないところを探します。結局これですね。但し、過去の塾のテキストを引っ張り出してきても駄目です。何故か。
昨今の塾のテキストはクレーム防止のためであったり「テキストの問題が出題されました」と的中アピールをするためか、情報量が多すぎます。本来は情報も初学、定着、応用、発展と段階に分けて徐々に情報を与えるべきなのですが、応用ぐらいまでの情報を一気に与えるような構成のものが増えました。これでは効率よく苦手分野の発見ができません。
診断テストついていますのでそれを使って苦手分野を把握するのがオススメです。次に苦手分野がわかったらメモリーチェックのその単元をやる前に別の問題集をやります。メモリーチェックも割と基本寄りの本ですが、苦手な子には難しく感じる問題も入っています。先にやるのはこっち↓です。
日能研生の50%以上が正解している問題ばかりを集めたという問題集です。ABに二段階構成になっていますから先に苦手分野のA問題だけをやり、その後にB問題に着手。その後メモリーチェックに戻り同一単元を演習という流れがいいと思います。
とりあえず他の科目の足を引っ張らないように基本を徹底するならこの2冊をやり込んでみてください。
理科の克服は意外と時間がかかるもの。理科に苦手意識があるなら今から着手してください。今からならまだ間に合いますよ。