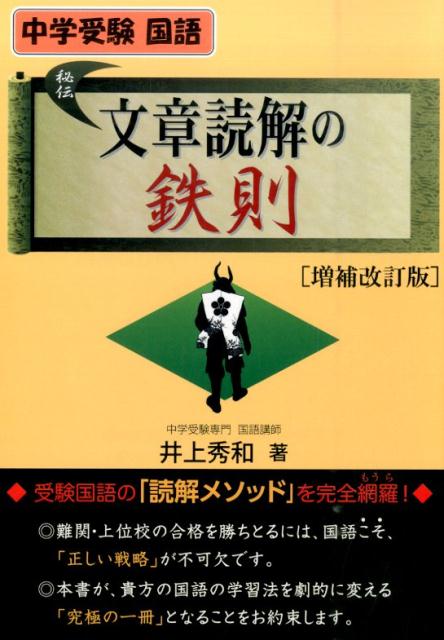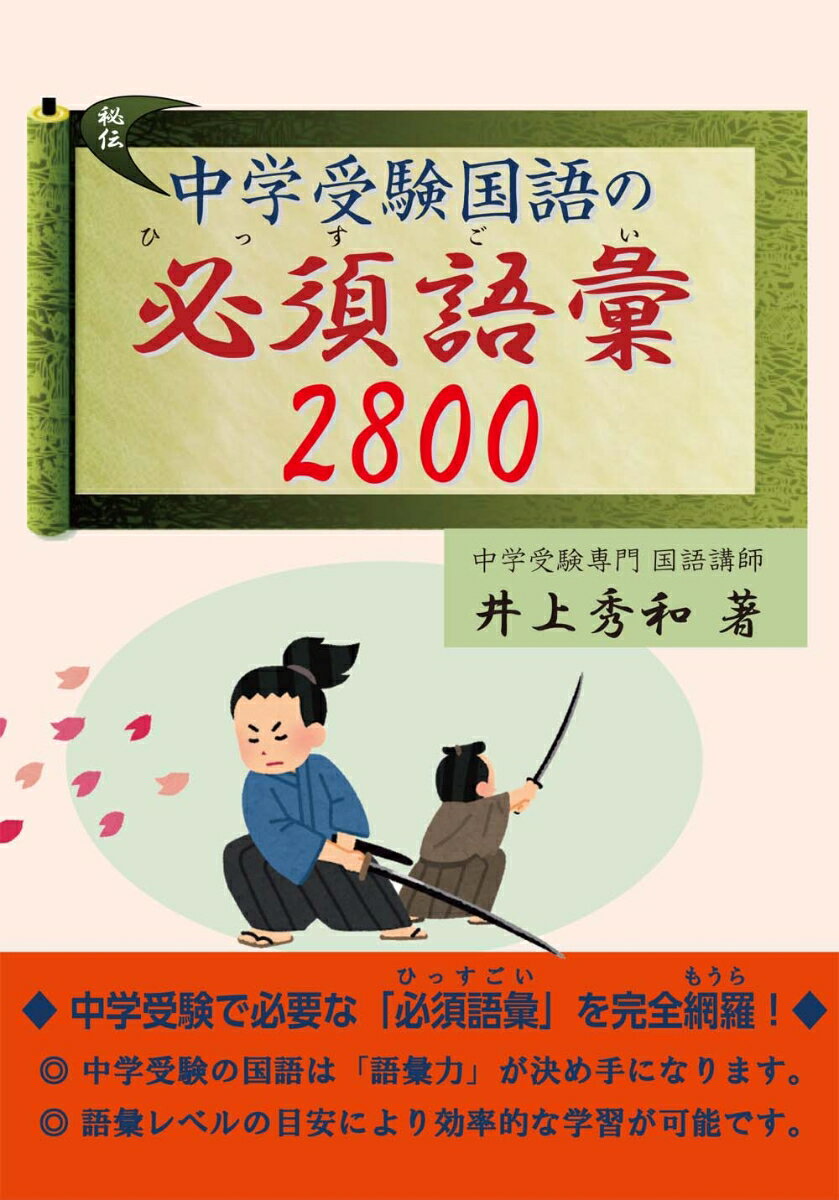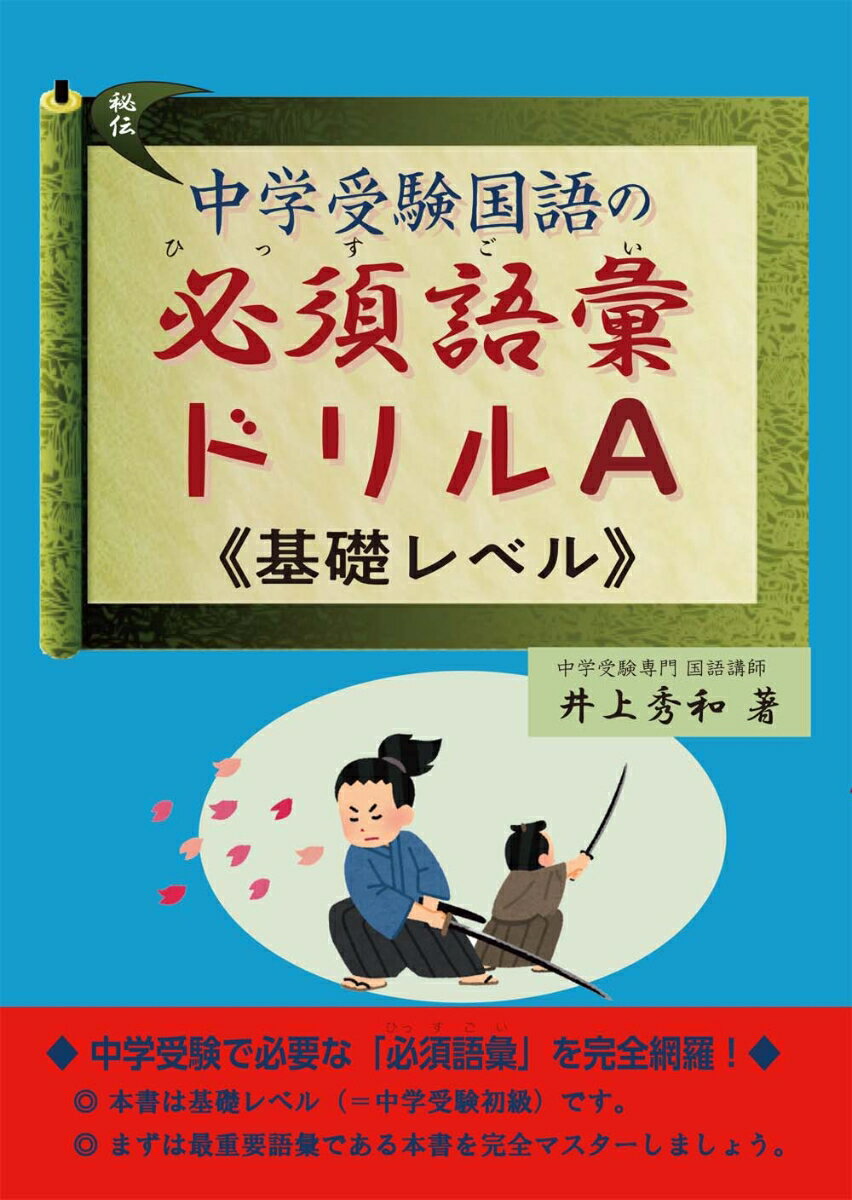読解の家庭学習は…
国語の読解は4科目の中で最も自学自習に向かない科目です。そもそも読解とは勉強ですらないんです。言葉、特に文字を使った出題者とのコミュニケーションです。ですから出題者の質問に正確に解答できている間は自学自習でも問題ないのですが、不正解だったときに第三者の介入と解説が必要になります。これを「自分一人でできる子」はそもそも読解がある程度できる子です。
Pick Item
国語の読解は基本的に学年は関係ないです。特に小5と小6の違いはほとんどありません。だんだん読む文章が難しくなる傾向にありますが小5で扱う読解問題も入試問題からの抜粋、一部改変のようなものがほとんどですから、読解が苦手な小6が小5の読解問題で練習をすることは全く問題がありません。それどころか非常に効果的なトレーニングだと私は思います。
どんな教材を使ってトレーニングをすればいいのかというとら何度か当ブログでも述べていますが四谷大塚の「予習シリーズ」が最も良い教材だと思います。何が良いのかというと「解説が充実している」という点と「問題集に徹している」という二点がポイントです。変なテクニック論が始まったり、合格体験記のような話が書かれていたりということがなく、解別冊の説は解説に徹しています。
四谷大塚のホームページから購入ができますので小5の上巻からやりはじめてはどうでしょうか。
どうして解説が充実していることを理由にあげるのかというと「親が読んで我が子のできないところを解説してあげられるからです。」
そうです。読解の自学自習ができない以上、お子さんの読解練習は保護者の方が見てあげる他にありません。塾では「多くの生徒が間違える問題」についての解法やよく使うテクニックなどを授業で教えますが、極端に読解ができない子の成績を上げる術はありません。それをやるとクラス全体のバランスを崩すので、やりたくてもできないといった方がいいかもしれません。
具体的には親子とも同じ読解問題に取り組む。
先に親が先行して読解問題をやる。我が子が引っ掛かりそうな部分を想定しておくとスムーズです。その後、解説を読んでおく。
準備が整ったら、子供に自分が予習しておいた読解問題をやらせる。子供の解答を○つけする。間違えたところの考えたをヒアリングする。で、なぜ間違えたのかを把握して、正しい考え方に導く。
これが基本的な家庭学習になります。読解が苦手なお子さんのテコ入れこそ保護者の方だけができるのです。
こちらも↓お読みください