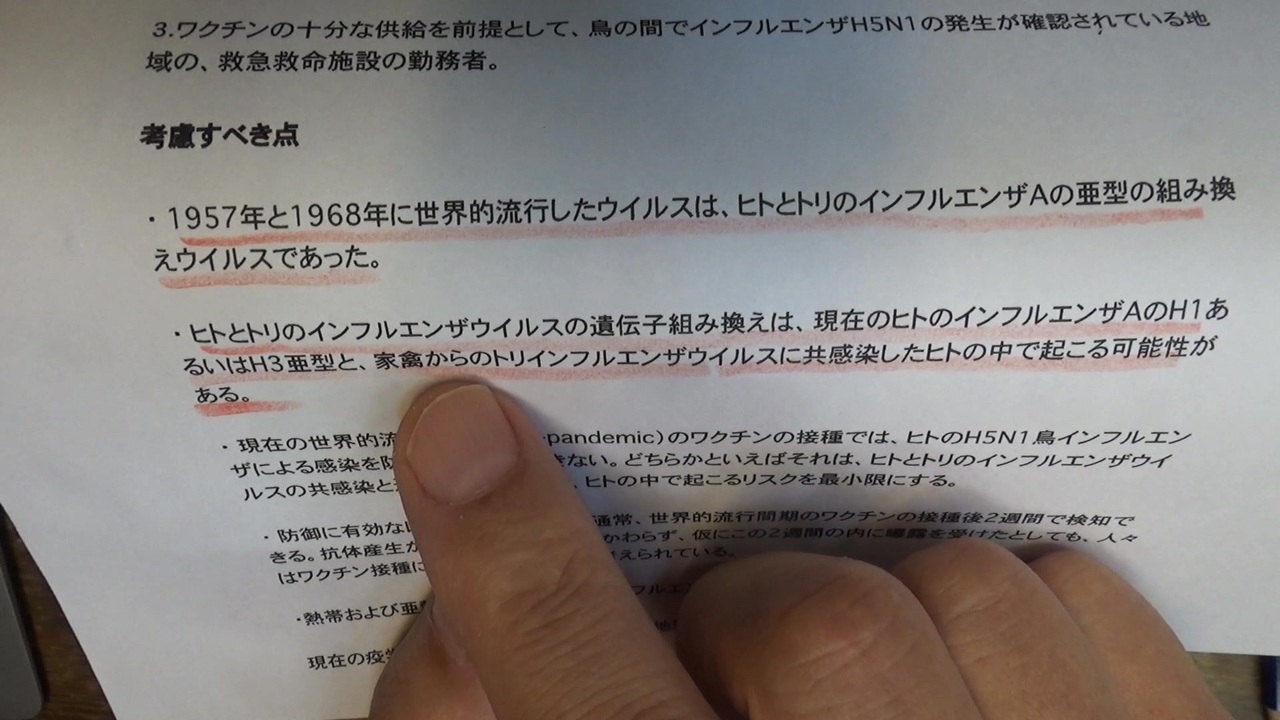https://twitter.com/Alzhacker/status/1789848865245626614
https://t.co/j70EQc90aZ
— Alzhacker (@Alzhacker) May 13, 2024
レプリコンは細胞外小胞を介して細胞間感染し、増殖できる: virusesに掲載された論文から 荒川央博士
記述の妥当性について質問:
Claude 3…
この記述は、最近発表された研究論文に基づいており、レプリコンワクチンの安全性に関する重要な懸念を提起しています。以下、記述の妥当性について詳細に検討します。
1. 研究内容の要約:この記述は、増田道明教授らのグループによるviruses誌に掲載された論文「Dissemination of the Flavivirus Subgenomic Replicon Genome and Viral Proteins by Extracellular Vesicles」の内容を正確に要約しています。論文では、日本脳炎ウイルスとデングウイルス由来のレプリコンが、細胞外小胞を介して細胞間を伝播し、感染細胞内で増殖できることが示されています。
2. レプリコンワクチンとの関連性:記述にあるように、この研究で使用されたレプリコンRNAは、抗原タンパクの代わりにルシフェラーゼ遺伝子を持っていますが、その他の点ではレプリコンワクチンと同様の構造を持っています。したがって、この研究結果は、レプリコンワクチンにも同様の作用機序が働く可能性を示唆しています。
3. 細胞外小胞を介した感染の意義:従来、ウイルスは特異的な細胞受容体に結合することで感染すると考えられてきましたが、この研究は、細胞外小胞を介した感染経路の存在を明確に示しています。この知見は、ウイルス学の観点から重要であるだけでなく、レプリコンワクチンの安全性評価においても考慮すべき点です。
4. レプリコンの増殖能:この研究では、レプリコンRNAが感染細胞内で増殖できることが示されています。この結果は、レプリコンワクチンによって導入されたRNAが、長期間にわたって体内で増殖し、抗原を産生し続ける可能性を示唆しています。
5. 安全性への懸念:記述にあるように、この研究結果はレプリコンワクチンの安全性に関する懸念を提起しています。レプリコンワクチンが細胞外小胞を介して個体内で広範に伝播し、長期間にわたって抗原を産生し続ける可能性があるとすれば、予期せぬ副作用やリスクが生じる可能性があります。
以上の点から、この記述は妥当であり、レプリコンワクチンの安全性評価において重要な論点を提示していると考えられます。ただし、この研究はin vitroの実験系で行われたものであり、生体内でも同様の現象が起こるかどうかは、さらなる研究が必要です。また、レプリコンワクチンの安全性を総合的に評価するためには、この研究結果だけでなく、他の知見も考慮に入れる必要があります。
いずれにせよ、この研究は、レプリコンワクチンの安全性に関する新たな視点を提供するものであり、今後のワクチン開発と評価において重要な意味を持つと考えられます。慎重な検討と追加研究を通じて、レプリコンワクチンの安全性と有効性を確保することが求められます。
___
https://twitter.com/molbio08/status/1677799620251099137
今回はエクソームが呼気に含まれているとことを査読済み論文ベースで紹介します。加えてレプリコンワクチンのリスクについても議論したいと思います。…
— molbio08 (@molbio08) July 8, 2023
https://twitter.com/5rHxIhQGQnnRSOe/status/1677900243428605954
人工ウイルス、自己拡散型ワクチン、自己増殖型mRNAワクチン: Scienceに掲載された記事からー荒川博士https://t.co/3yYbhi60iU
— 苦労人の改 (@5rHxIhQGQnnRSOe) July 9, 2023
両氏による、レプリコンの危険性、エクソソームを介した薬剤からの感染とも呼べる伝播の可能性の解説。十分考えられる事です。 https://t.co/cYwRDjT6ai
https://twitter.com/keisuke4713/status/1789825495539871942
自己増幅RNAが感染性粒子を作る
— tune (@keisuke4713) May 13, 2024
30年前雑誌Cell論文https://t.co/4dAFpDuubM
自己複製RNAから水疱性口内炎🦠蛋白発現で新規感染性粒子が生成https://t.co/XDZOGqh4f6
自己増殖型mRNA💉→感染性粒子の放出risk
replicon導入細胞が光る:24h後
時間経過と共に細胞全体に拡大
まるで🦠感染と同様の現象 https://t.co/283rWItZXl pic.twitter.com/RNO7bRLwL0
https://twitter.com/TM7157/status/1789784816776290353
【獨協医科大学・増田教授のグループによる】
— T M (@TM7157) May 12, 2024
2024年3月
レプリコンRNAが細胞に感染し得る事を培養細胞の実験系で証明しました。
感染はエクソソーム等の細胞外小胞(EV)を介して起こり、しかもレプリコンRNAは感染細胞内で増殖できたのです。
※つまり他人への伝播のリスクの慎重な検証が必要です。 https://t.co/rpu1WE9KHR
https://twitter.com/5rHxIhQGQnnRSOe/status/1789095833570603050
過去のレプリコン関連投稿掘り起こし。
— 苦労人の改 (@5rHxIhQGQnnRSOe) May 11, 2024
①接種後6カ月たっても高レベルの抗体生産 https://t.co/AelGIAgXIB pic.twitter.com/XOjDaqMbIp
https://twitter.com/5rHxIhQGQnnRSOe/status/1730454148649529804
3μg接種で0週目からIgG4。
— 苦労人の改 (@5rHxIhQGQnnRSOe) December 1, 2023
因みに現在のファイザー用量の10分の1。
打ってすぐIgG4作りっぱなし。
レプリコンで貴方の体はmRNA生産マシーンとなります。 https://t.co/upO6Y4mFBd
https://twitter.com/5rHxIhQGQnnRSOe/status/1733727540827861374
コスタイベ筋注用(レプリコン)ー審議結果報告書https://t.co/mbrkh4szDm
— 苦労人の改 (@5rHxIhQGQnnRSOe) December 10, 2023
何が変わったのか分からないが、製法変わってますね。
LNP使ってるので当たり前っちゃ当たり前ですけど、全身に回ります。卵巣もね。 pic.twitter.com/OXJaShYFPl
https://twitter.com/fseiichizb4/status/1789887225179570616
2024.5.13鹿先生
— 福田 世一@小倉台福田医院 (@fseiichizb4) May 13, 2024
2023年11月医学雑誌Cellに掲載された論文によれば、レプリコンワクチンの安全上の懸念は流行中のウイルスとの遺伝子組み換えの可能性がある
レプリコンワクチンのRNA複製酵素レプリカーゼとコロナウイルスの病原性が合体した新しいウイルスを作ってしまう可能性があるんじゃないか pic.twitter.com/Sy3plYzVYP
JPSikaDoctor
https://www.nicovideo.jp/watch/sm43783738
https://twitter.com/fseiichizb4/status/1788950697746276485
2024.1.7鹿先生
— 福田 世一@小倉台福田医院 (@fseiichizb4) May 10, 2024
自己増幅型のレプリコンワクチンは未知の増幅能力の可能性がある。
試験管内で感染性粒子を形成して、ウイルスと同じような感染性を確認したという論文がある。… https://t.co/RdTApkM2do pic.twitter.com/1RJ5n4NGiw
https://twitter.com/GVdFrnRWbN18944/status/1789608997483651153
明治製菓ファルマのレプリコン「コスタイベ筋注用」の審議結果報告書によると、スパイクタンパク遺伝子全長を使ってるみたいですね。
— ヒト (@GVdFrnRWbN18944) May 12, 2024
なお、RBDに限定してるのは、第一三共のmRNAワクチン「ダイナロチ筋注」です。
どちらも毒であることに変わりはありませんが、ご参考までに。 pic.twitter.com/bsW5wsoQYN
https://twitter.com/7xCzVz2knym9PSL/status/1787332388877648023
専門家の誤情報・偽情報を見破るには「何を言及していないか」に焦点を絞るとよい😀
— 毒母乳 (@7xCzVz2knym9PSL) May 6, 2024
ちゃんと説明すんのかな?😅
--
①今回はACE2受容体に結合できるスパイクもセット
②レプリコンの場合は兆単位のmRNAを体に直接注入してから増殖
③蚊が媒介する可能性
④近隣ウイルスとの遺伝子組替えによる殻の獲得 https://t.co/VHL1zPMQLz
https://twitter.com/7xCzVz2knym9PSL/status/1789486670842364354
◆レプリコンRNAは、In vitroでは細胞間で伝播する(査読済み)
— 毒母乳 (@7xCzVz2knym9PSL) May 12, 2024
◆Novel infectious particles generated by expression of the vesicular stomatitis virus glycoprotein from a self-replicating RNAhttps://t.co/vyYLsteg20
https://twitter.com/corowaku_memo/status/1789607855588536683
レプリコンワクチン治験についての資料
— ふう子 (@corowaku_memo) May 12, 2024
●1枚め pic.twitter.com/zeLSHgebQp
https://twitter.com/AaronOtsuka/status/1789865005409825034
レプリコンはどのように設計されているか?
— アーロン大塚 (@AaronOtsuka) May 13, 2024
レプリコンの場合は環状のDNAを感染させる。(A… pic.twitter.com/INlhgbUcPi
https://twitter.com/AaronOtsuka/status/1789829624345862546
台本によると
— アーロン大塚 (@AaronOtsuka) May 13, 2024
政府「H5N1 鳥インフルエンザのパンデミックが来ました。」
マスコミ「こら大変だ。」結膜炎のクライセス・アッター募集。様々病気に繋がると恐怖のマーケティング。
政府「これを避けるにはレプリコンが必要である。100日にエピデミックを止められる。」… https://t.co/qWxDvZq7Fm
https://twitter.com/AaronOtsuka/status/1789882476770562527
元CDCロバート・レッドフィールド博士
— アーロン大塚 (@AaronOtsuka) May 13, 2024
「鳥インフルエンザが一番心配なのは明らかだ」
「今のところ、ヒトに効果的に感染させるには、5アミノ酸の変化が必要です。」
「それはかなり重い種族の障壁ですね...」
「しかし、実験室では、数ヶ月でヒトに感染力を高くすることができます。」… https://t.co/UV3Zg1HSKD
https://twitter.com/AaronOtsuka/status/1789914482682351856
東京大学でのH5N1 の機能増幅実験
— アーロン大塚 (@AaronOtsuka) May 13, 2024
新型コロナ作成に当たり武漢研究所とノースカロライナ大学は悪名高い。次は東大なのかな?
鳥インフルエンザ を人間に感染される研究は東京大学で行われていたかな?… pic.twitter.com/ioMEEh6JaB
https://twitter.com/7xCzVz2knym9PSL/status/1778401950771614091
___
コメント:逃げよう