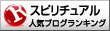内宮に引き続き、外宮にも早朝参拝。当然ながら、同じ日に両方の早朝参拝はできないから、外宮は旅行最終日である3日目の早朝という日程にした。
よく順番として外宮が先だとかいうことに異常にこだわる人がいるのだが、そうしたければそうしてもいいけど、別にそこまで厳密に守るべきルールでもない。神社の世界、宗教の世界には人間の神に対する恐れが生み出したルールがよくある。おおよそ、空気を読んでルールを守ったりもするが、本当は人間が勝手につくっただけのルールも多い。神とは人間の延長線上の小さき存在ではないのである。人間の恐れが生み出したルールなど要求はしない。もちろん、敬意は払うべきである。そうでなければ、参拝する意味はないのだから。
さて、外宮の早朝参拝であるが、内宮ほど早く行く必要はないだろう。2日連続の一番電車はきついし。人が少ないという意味では、前回は夕方にも外宮に行って、写真を撮るという観点ではそれで充分かなとも思った。そんなわけで、前日よりは遅く、外宮到着は朝6時50分頃だった。
当然かもしれないが、やはり人はいる。しかし、内宮ほどではない。朝6時50分の外宮の状況について、内宮と同じような書き方をすれば、以下のようになる。
1)境内社はもちろん、正宮前でも「タイミングを待てば、人が写らない写真が撮れる可能性は高い」
2)境内社はもちろん、正宮でも列に並ばずに参拝が可能。もちろん、横に広がっての参拝が前提。
3)拝殿前の参拝(祈念)時に、中央を避けて端の方に寄って立てば、長めの祈念をしても大丈夫。
内宮では宇治橋や正宮前石段下で人が映らない写真を撮ることは至難の業だが、外宮ではタイミングを待てばほぼ全ての場所で人が映らない写真を撮ることができるのではないだろうか。
外宮についても内宮と同様に境内の神宮125社の再確認と参拝を行う。「外宮の境内」の正式な定義があるのか、また、その範囲が私にはよくわからないのだが、ここでは表参道鳥居と北参道鳥居の内部ということにする。公式サイトの外宮の域内マップでもその範囲しか書かれていないので、これでよいかとは思う。
そのほかに、外宮と一続きの社叢の中に、度会大国玉比売神社、伊我理神社・井中神社、山末神社があるのだが、いったん表参道鳥居または北参道鳥居を出ないと行けないようになっているので、ここでは除外する。
内宮と同様にまずは正宮へ向かう。
正宮の手前に式年遷宮用の土地。次の遷宮ではここに正宮が移るのだろう。2倍の土地が必要なのだから、凄いものである。これだけの広い土地を式年遷宮のためだけに確保するとは。
ご覧の通り、正宮の写真もタイミングを待てば人が入らない写真が撮れた。もちろん、この先は撮影禁止。この状況であるから、少し長めの祈念をしても問題はない。
内宮であれ外宮であれ、せっかく来たのだから通常通りの時間をかけて参拝(祈念)をしたいものである。しかし、これまではそれが叶わなかった。人が多すぎて、長時間の祈念は迷惑であるから。そんな人は早朝参拝がやはりいい。外宮の場合は夕方も狙い目ではあるが。
正宮の参拝が終わったら、残りの9社の参拝をしていこう。
外宮境内には3つの別宮があるので、そちらに向かうのだが、途中に画像のようなところがある。内宮の四至神(みやのめぐりのかみ)に似ており、外宮にも四至神はあるのだが、ここは違うので注意。この画像は 「三つ石」 と呼ばれる石だそうである。参拝時には私も知らなかった。外宮の四至神は後で紹介する。
別宮方面の道。この小さな橋の上にあるの石は亀石と呼ばれる。
別宮の3社はすいていそうなところから参拝すればよいだろう。私は土宮(つちのみや)から参拝。御祭神は大土御祖神(おおつちみおやのかみ)。
続いて風宮(かぜのみや)。御祭神は級長津彦命(しなつひこのみこと) 、級長戸辺命(しなとべのみこと)。どちらも風の神で一般に同一視される(別名の扱い)ようだが、神宮では二柱の神様を祀っているということのようである。内宮の風日祈宮と御祭神が同じである。
大祓詞(おおはらえのことば)にこういう一節がある。この「しなと」である。
「科戸(しなと)の風の天(あめ)の八重雲(やえぐも)を吹き放つ事の如く」
風が八重雲を吹き払うかの如く(罪・穢れが消え去る)
最後の別宮、多賀宮(たかのみや)は石段を上った先にある。
御祭神は豊受大御神荒御魂(とようけのおおみかみのあらみたま)。
荒御魂(あらみたま)の説明は神宮公式サイトより引用。
<神様の御魂のおだやかな働きを、「和御魂」と申し上げるのに対して、荒々しく格別に顕著なご神威をあらわされる御魂の働きを、「荒御魂」とたたえます。>
なお、和御魂は「にぎみたま」と読む。
正宮の御祭神の荒御魂を祀るので外宮の第1位の別宮である。内宮の第1位の別宮が荒祭宮(あらまつりのみや)だったのを覚えているだろうか。あちらも御祭神は天照大御神荒御魂(あまてらすおおみかみのあらみたま)だったので第1位の別宮ということだろう。
順序にこだわる人は序列1位の別宮である多賀宮から参拝するのがよいのかもしれない。
以上、外宮の3つの別宮はほとんどの参拝者が訪れる神社ということになろう。ただし、内宮同様にここからの神宮125社巡りが難しい。
3つの別宮が集まる場所から奥(正宮と反対側)に向かって小径が伸びている。この先にほとんどの参拝者が訪れることのない神宮125社がある。
下御井神社(しものみいのじんじゃ)。外宮所管社。内部に井戸があるそうである。
公式サイトの引用。
<日別朝夕大御饌祭を始め、お祭りにお供えする御水をいただく上御井神社で不都合があった場合は、下御井神社でいただいた御水をお供えします。>
通常は上御井神社(かみのみいのじんじゃ=後述)の水を使用するが、下御井神社の水が備えとしてあるということらしい。
参拝が終わったらメインの参道、授与所のあたりに戻る。
下御井神社はまだ稀に参拝者が来るのであるが、ここはメインの参道に面しているにもかかわらず、本当に誰も参拝しない。いつものセリフだが、私以外に参拝している人を見たことがない。
ここが外宮の四至神(みやのめぐりのかみ)である。「ここが」のここってどこを指すのかということになるが、公式サイトに「社殿や御垣はなく、榊が立つ石畳の上に祀られます」とあるので、その辺りに向かって参拝すればよいだろう。
この四至神は外宮の中で参拝難易度第3位(Fさん調べ)である。これより難しいのがあと2社ある。
この四至神と授与所の間の北参道を歩くと、難易度第2位の神社があるのだが、綿密に調べておかないと、まず間違いなく通り過ぎてしまうだろう。
見落とさないように左側を見ながら歩こう。
左側に一般立ち入り禁止の道がある場所を探す。この正面の建物がそうらしい。
御酒殿(みさかどの) 。外宮所管社である。一般立ち入り禁止であるから、この位置から遥拝になる。
残り3社。あとの3社はひとまとまりである。北参道をさらに北に向かって歩き、左手方向への小径を見つける。ここもめったに人が来ない場所。
これは神馬が休むための御厩(みうまや)という建物で、この先を左折。
少し長い小径。しばらく歩くと向かって右手に神社を発見する。
度会国御神社(わたらいくにみじんじゃ)。外宮の摂社である。
さらにこの小径のすぐ先、行き止まりの右手にもう1社。
大津神社(おおつじんじゃ) 。外宮の末社である。
さきほど残り3社と言ったが、行き止まりまで来たのに2社しか見つかっていない。あとの1社はどこにあるのか。
実は残りの1社はこの辺りにあるわけではない。またしても立ち入り禁止区域にあるのだ。それが上御井神社(かみのみいのじんじゃ)。下御井神社の項で既に説明した。
上御井神社はどの辺にあるのかということになるが、実は大津神社と反対方向を向けばよい。
反対側は立ち入り禁止の立て札があるが、よく見ると小径が続いている。
これがおおよそ上御井神社の方向なので、この位置からそちらに向かって遥拝する。ここが外宮の中の参拝難易度第1位(Fさん調べ)である。
外宮の参拝の所要時間は1時間10分ほどだった。
前回の参拝時にも神宮125社はテーマだったのであるが、綿密に調べていなかったので、やはり確信が持てなかったり、実際に見逃した神社もあったのであるが、今回これで内宮・外宮の境内に関しては全て巡拝したことになる。
ブログランキングに参加しています。是非2ヶ所の応援クリックをお願いします。いつもクリックしていただいている方、ありがとうございます。愛と光のエネルギーを送ります。
メンタルブロックを消すためのワークとしても使えます。 自分の内面を直視して、クリックした時の気持ちがどう変化するのかを見ていきます。損した気分にならずに、躊躇せずにクリックできるようになり、さらに喜んで応援クリックができるようになった時、なんらかの良い変化が起きたということは言うまでもありません。