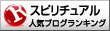ゴールデンウィークに奈良を中心とした神社巡り旅行に行ってきた。これまで奈良県では、大神神社、石上神宮、春日大社、橿原神宮などに参拝したことがあり、今回は今までなかなか行けなかった吉野などの山の方を中心に巡ってきた。
とても全てを紹介できないので、適当に省略しながら神社を紹介していきたい。
旅行1日目は移動日で、二十二社(平安時代に確立した神社の格式の一種であり、当時の畿内の神社のトップ22のようなもの)のうち未参拝だった廣瀬大社、龍田大社などに参拝(省略)。
2日目は葛城エリア。以前に年末年始旅行に当地に来て、降雪のため途中で神社巡りを断念という経緯がある。この時、雪の降る中、高鴨神社に参拝をし、次の高天彦神社に向かう途中で「勇気ある撤退」をするのだが、今回、高天彦神社神社に行ってみてこれが大正解であることを知った。山の中だったのだ。ともかく、私は地図を平面的に見る(標高を考えない)という悪い癖があり、これで何度も痛い目に会っている。今回はその時のリベンジというか、再チャレンジである。
葛城エリアの神社を巡る起点は近鉄御所駅となる。しかし、公共の交通が大変不便であり、近鉄御所駅から南北に延びる国道24号沿いに奈良交通バスが走っているほかは、1日3本程度の御所市コミュニティバスに頼るほかない。あとは全て徒歩である。しかも、かなり広いエリアであるので、それなりに疲れることは間違いない。
まずは、唯一駅から徒歩圏内と言える鴨都波神社(かもつばじんじゃ)。 近鉄御所駅より徒歩6分ほどのところにある。一般の方は画像を見て、なんだか地味な神社と思うかもしれない。しかし、平安時代の公式の神社リストである「延喜式神名帳(えんぎしきじんみょうちょう)」に記載の名神大社(みょうじんたいしゃ)である。近代社格は県社。延喜式神名帳には2861社が掲載されており、そのうち名神大社は226社とのことである。単純化すると、当時の全国神社リスト上位226社に入っていたと思ってもらいたい。そして、この葛城エリアには地味な(超有名ではない)名神大社がいくつもあるのである。
画像を見ての通り、緑豊かで社叢に恵まれており、なかなかの気を放っている。超絶すごい神社というわけではないが、なかなかの好印象。評価は4.0-(5点満点)。
次に、ここから徒歩40分をかけて葛木坐火雷神社(かつらきにいますほのいかづちじんじゃ)へ。普通の人は近鉄御所駅に戻ってタクシーにでも乗ってもらいたい(この先たくさん歩くので)。「(地名)に(い)ます〇〇神社」というのは関西にのみ残る由緒正しい神社名称だと思うが、難しいのでやめてもらいたいというか、たぶんタクシーで行き先を言う際に正式名称で言っても通じないと思う(予想)ので、この場合は通称である笛吹神社(ふえふきじんじゃ)と伝えるのが良いだろう。
この神社も名神大社であり、近代社格は郷社(県社の1つ下)。こちらも緑豊かなのだが、先ほどよりも若干だけ明るく爽やか目の公園的な神社である(さきほどのような「深い」」感じの気の方がパターンとしては多い)。こちらも評価4.0-。
次は鴨山口神社(かもやまぐちじんじゃ)。
葛木坐火雷神社と比べて見た目に緑が濃い。これが場の気の印象と直結するのかと言うと、直結する。色彩は印象を決める要因となる。この画像は比較的「気」というものが伝わる画像であり、視覚的に神社らしい場であることが見て取れると思う。だから、さきほどの公園的な雰囲気よりも、通常はこちらを私は好むのである。ただ、好みと評価はまた別ものであり、画像では理由が伝わらないと思うが、評価は3.5+。当社が低評価なのではなく、葛木坐火雷神社が高評価なのである。
次はいよいよ当エリアで最も知名度が高いと思われる葛城一言主神社(かつらぎひとことぬしじんじゃ)。関東でも茨城県常総市に一言主神社がある。
ここまで、自分以外の参拝者は、鴨都波神社0人、葛木坐火雷神社0人、鴨山口神社1人。ところが、ここには人がたくさんいて驚いた。
文字通り、一言の願いならどんな願いでも叶えてくれるという神様。古事記に出てくる話は私も記憶にあり、印象深い。
雄略天皇一行が葛城山に登った際、向かいの山に同じように登山する一行を見る。それが天皇一行とそっくりな姿だった。「大和の国の王は私のほかにいないのだが、おまえは何者だ」と問うと、同じ言葉が返ってくる。天皇一行が弓を相手に向けると、相手も天皇一行に弓を向ける。天皇が「名を名乗れ」と言うと、「私は、凶事も一言、吉事も一言で解決する神、葛城の一言主の大神である」と返事が来て、天皇が敬意を示して謝罪するという話である。
神社そのものの場の気としては一宮クラスには及ばないかもしれないが、参道がとても素敵で、当社後方の葛城山と相まって素晴らしい景色と雰囲気である。 評価4.0。
この後、式内社(延喜式神名帳の掲載社)の長柄神社(ながらじんじゃ)に参拝し、付近で昼食をとろうとする。しかし、あてにしていた蕎麦屋が休業。そして、もう1つしかない飲食店がほぼ満席。神社巡りでよくある展開で、まさに過去記事「覚醒に向けた意識レベルの向上のために(7)」の「ラメッシの唯一のサーダナ(ページ一番下)」に書いた通りのことが起こる。仕方なく、コンビニでおにぎりを購入するのだが、座って食べられる場所が見つけられずに、そのまま次の高天彦神社(たかまひこじんじゃ)へ。しかも、飲み物を買い忘れたのが痛かった。
この日初めてバスで移動。地名の高天は古事記等に出てくる「高天原(たかまがはら)」の高天であり、神話の里ということである。
ここはまだ一の鳥居的な場所で、バス停から5分ほどのところ。ただ、相当に雰囲気は出ており、「神はいる」と思わせる場所だった。しかし、地図を平面的にしか見ていないことで、またしても痛い目に会う。
15分ほどとはいえ、完全に登山である。しかも、飲み物を切らしてしまった。一滴の水も飲めない登山(泣)。高天彦神社では水が飲めるだろうか。
目の前が開けた時は本当に嬉しかった。この後、高天彦神社の駐車場付近でまさかの自販機発見!神はいた。普通は参拝してから食事なのだが、この時は限界だったので、先にベンチでおにぎりを食べる。正直、いままで食べたコンビニおにぎりで一番おいしかった。というか、この生涯一番のおにぎり。感激。この経験のために蕎麦屋が休業で、もう1つの飲食店が満席(に近い混雑)だったか。
当社も名神大社だが、近代社格は村社(郷社のさらに1つ下)。しかし、社殿を取り巻く社叢から放たれる気、威厳はすごい。間違いなく神はいると思わせる場所。評価4.0。
知名度はあるらしく、一言主神社の次に参拝者がいる神社だった。というよりも、その2社以外はほぼ参拝者がいなかった。
参拝して写真を撮って、ベンチに座って休憩していた。最後に私と年配の方とだけになり、私もそろそろ行こうかとしたところ、その方に話しかけられた。目の前の道が葛城古道であること、このような昔ながらの風景はもうあんまり残っていないけど、ほかには天理方面に山の辺の道(万葉集に出てくる日本で一番古い道)があることなど話をされた。私も「ああ、わかります。そっちの方(山の辺の道)も行ったことあります」などと話をしてから、別れた。
ここで再びバスで移動。次はこのエリア最後の神社、葛木御歳神社(かつらぎみとしじんじゃ)へ。本当は比較的近くに高鴨神社というこれまた名神大社があるのだが、以前に参拝しているし、移動手段と時間の都合で今回は見送った。
女性宮司の「みとしの森」というイタリアン・カフェがあるのだが、休業日が多く、当日もやっていなかった(事前調査済み)。「みとしの森」というくらいだから、当社も社叢には恵まれた環境なのだが、この日参拝した神社の中では、あまり感銘を受けなかった。評価3.5。当社も名神大社であり、近代社格は郷社。
参拝していたら、高天彦神社で会った方が後からやってきて、とても驚いた。高天彦神社から見て当社は距離が離れているし、次に参拝するコースの神社でも何でもない。神社巡りにおいて、「あの人さっきの神社でも見た」というシチュエーションはそれほどはなく、徒歩数分程度の距離にある神社間でたまにある程度である。
高天彦神社には参拝者が結構いたのだが、当社では私たちだけだった。「人が来る神社と来ない神社と結構差がありますね」などと話して別れた。寺社と自然をこよなく愛する方だった。
この日訪れた葛城エリアの神社。
当ブログを応援してくださる方はクリックをお願いします。