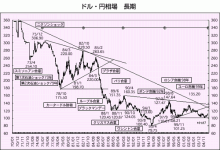一昨年来の金融危機で、ドル円通貨ペアは、07年6月の124円台前半から、今年1月の87円台前半へ、30%もの円高に変動しました。
あれよあれよと暴落してゆく相場に追従する勇気が湧かず、ただ呆然とチャートを眺めていたことが多かったのは、まだまだ記憶に新しいところです。
この状態を、「100年に1度の・・・」と形容するのを、しばしば目にします。 「これって、どういうことなの![]() 」と疑問を抱き、ちょっと調べてみますと、さまざまなドル円の歴史を知ることになりました。
」と疑問を抱き、ちょっと調べてみますと、さまざまなドル円の歴史を知ることになりました。
まず、
ドル円が相場にデビューしたのは、1871年、明治維新後のことだそうです。 そのときの換算率は、なんとドル円が1円だったとか。
その後、日清戦争に勝利した日本は、清国から賠償金を英ポンドで受け取り、1897年、それをイギリスで金に変え、ドル円=2円時代のスタート。
次の転換期は、第一次世界大戦、それに続く不況の後、1923年、ダメ押しのように襲った関東大震災。 1年間で29%近くの円安となり、ドル円は2円4銭から2円63銭へ。
さらに、1931年、イギリスにならって日本も金本位制から離脱。 ドル円は一気に200%近く、5円へ円安。
大混乱の時代の始まりは、1945年、第二次世界大戦後。 ドル円は15円から50円(1947年)、270円(1948年)、360円(1949年)へ。 な、なんと、2400%の円安。
次の転換期は、1971年、ベトナム戦争後のニクソン・ショック(米国、金本位制の停止)によるドル安・円高、ドル円は360円から180円を割り込み175円ミドルへ。
その後、1978年、カーターショック(ドル防衛策)によるドル高・円安、ドル円は278円へ上昇。
次は、1985年、ドル高是正のためのプラザ合意(各国による協調介入)。 ドル円は、週明けの市場は12円以上の窓を空ける暴落で始まり、2週間で31円もの急激なドル安、240円付近から1年で153円台、1年4ヶ月で150円切れへ。 小康状態が続くが、さらに1年半後には121円切れ。 約50%の下落、わずか2年半の出来事。
1990年、160円越えの円安を抑制しようとドル安誘導政策開始。
1993年、100円台前半、戦後最安値を更新。 さらに1年後、1994年、100円台を割り込み、戦後最安値を更新。 そして、ついに、1995年、80円を割り込む史上最安値。
ドルを大量に保有する中東諸国・アジア中銀から『ドル離れ』の警告を受け、ドル高政策に転換。
その3年後、1998年、148円付近まで急進するが、米ヘッジファンドの破綻をきっかけに、ドル円は10月の1週間で136円付近から111円半ばまで急落。 介入の繰り返しにもかかわらず、翌年、1999年には102円へ。
2001年、ドル円は135円台に回復するが、同時多発テロをきっかけに反転、2003年、米軍のイラク侵攻も加勢し、2005年、再度、101円半ばへ。
その後、回復しつつ、2007年のサブプライム問題勃発前夜へと向かう。
ざっと140年、ドル円は、このような歴史を歩んできたようです。
ここ40年余のドル円変動とその事由を、わかりやすくまとめたチャートがありましたので、ここに引用しますね。
長年の歴史を経て、人類は多くのことを学び、急激な変動を回避するためのさまざまな抑制策や緩和策を生み出し、プラザ合意以降、「為替の変動は小さくなった」と言われていますが、どうなんでしょうか?
50%程度の変動はざらに起きているし、その時その場の人々は人智を傾け策を講じてきたはず。
「歴史は繰り返す」とも言われているし…。
今回の金融危機による、ここまでのドル円の変動は30%。
先の予想はできないけど、しっかり損切りだけは儲けておこうっと![]()