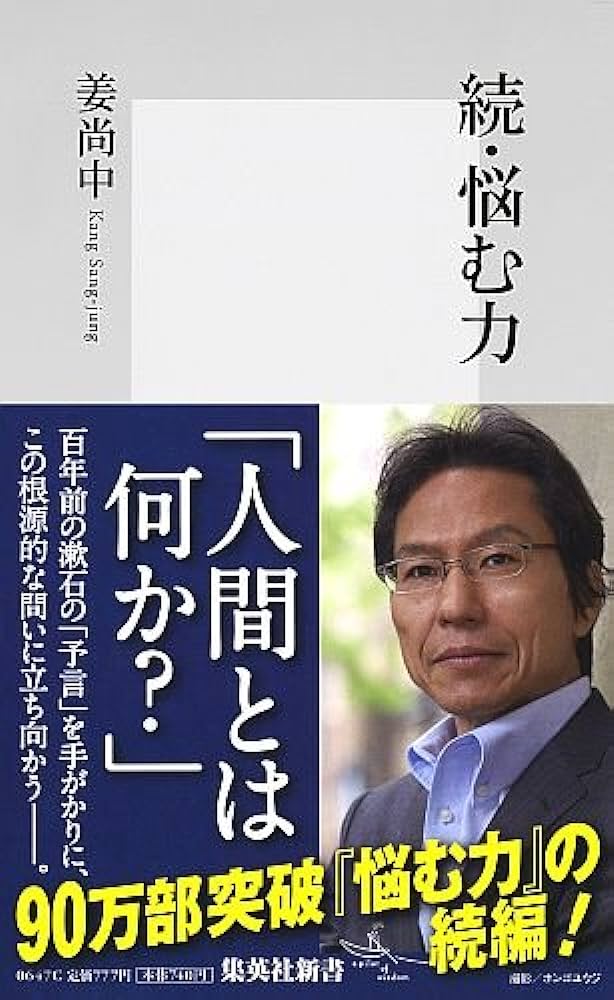【書名】続・悩む力
【著者】姜尚中
【発行日】2012年6月20日
【出版社等】発行:集英社
【学んだ所】
・かつてであれば、悩みのタネを解消するのは呪術や宗教の役割だった。⇒哲学にもそれが期待されていた。⇒しかし、現代でそれらに匹敵する役割を期待されているのは、科学。⇒少なくとも、科学によって幸福の障害になるものが確実に少しずつ取り除かれていくに違いないと期待していた。
・東日本大震災と福島の原発事故は、科学への信頼が大きく揺らいだ出来事だった。⇒もっといえば、その信頼の喪失。
・科学との隔絶感が、われわれをかくも絶望させる。=科学と呼ばれるものが、いつの間にか、疑似宗教的なものになっていた。⇒といっても、仏教やキリスト教のような具体的な信仰のことではない。⇒よりどころとか、心のよすがとかいったもの。そのような位置に、いつのころからか科学が大きく陣取っていた。⇒それへの信頼が失われたため、我々は足もとの床が抜けたような不安に駆られるようになった。
・すでにウィリアム・ジェイムズは、19世紀末、「多くの人々にあっては、科学はまぎれもなく宗教の位置にある」と指摘し、そのような場においては、「自然の法則が崇拝されるべきものとなっている」と述べている。=科学が神のような存在になっているということ。⇒先見の明のある謂だったこの言葉は、その数十年後には当たり前のこととなり、100年後のわれわれには、もはや意識せざる日常の前提となっていた。⇒しかし、原発の事故によって、それが一気に覆されてしまった。⇒信頼というものは、いったん崩れてしまったら、よほどのことがない限り、取りもどせない。
・「吾輩は猫である」より苦沙弥先生の仲間である迷亭君の、「江戸時代の遺物」のような頑固者の伯父が時代のなかに寄せてきた新しい学問の波(=科学)を評してこう言う。⇒「凡て今の世の学問は皆形而下の学で一寸結構な様だが、いざとなるとすこしも役には立ちませんてな。」
・漱石が生きた時代は、科学がそれまでにない勢いで世界を覆いはじめた時期。⇒大方の人は驚き、喜び、魅了され、その利便性を盲目的に享受することになる。⇒識見ある人びとは、それは明るい未来を作るものではなく、人類を不幸の方に引っ張っていくのではないかと疑っていた。⇒ヨーロッパでは、第一次世界大戦ののちに、そのような言説が目立つようになる。⇒なぜかというと、その大戦が科学と先端技術を駆使して行われた情け容赦のない大殺戮戦だったから。
・ポール・ヴァレリーも、われわれにとっては食べれない黒パンのような科学と技術が未曽有の殺戮をもたらしたと、「精神の危機」のなかに書き記した。⇒ウェーバーやジェイムズも、科学はダメかもしれないと懐疑の目を向けた。
・ウェーバーは、大戦ののちに出版した「職業としての学問」のなかで、次のように述べている。⇒「天文学なり、生物学なり、物理学なり、化学なりの認識によって、世界の意味といったものが教えられるなどと信じているものが、今日でもまだいるだろうか。もし科学の認識に何かふさわしいことがあるとすれば、それは、世界の意味といったものが存在するという信仰を根だやすということである! いわんや、学問が神への道だなどという考えのごときはもってのほかのことである。科学は万能ではなく、世界の意味を解き明かすものではない。」
・漱石とウェーバーはほぼ同じ時期に、科学というものの役割を認めながらも、それによって地球上の人類が非常に深刻な事態に巻き込まれはじめたと危惧した。
・ジェイムズも「宗教的経験の諸相」のなかで鋭いことを述べている。⇒「もし諸君の沈黙の直観が合理主義の結論に反対するならば、合理主義は諸君を信服させることも、回心させることもできないであろう。諸君がいやしくも直観をもたれるならば、その直観は、合理主義の住み家である多弁な段階よりもいっそう深い段階である諸君の本性からくるのである。そして、理屈をこねる合理主義がいかに巧妙に語って反対しようとも、その合理主義の言葉よりも、そういう結果のほうがいっそう真実でなければならないことを、諸君のうちにある何かが、絶対的に知っているのである。」
・科学のご宣託というものがこの世界における絶対的な真理であり、それに反する行動をとることはまったく非合理的だと考えがちだけれども、時によっては科学の法則よりも、自分が心のなかにもっている直観のほうが真理であることもあると、ジェイムズは言っている。⇒これは科学万能主義への明らかな懐疑。⇒だからといって、ジェイムズは非科学を奨励しているわけではない。生きものである人間として、自分の生命や安全にかかわるような一大事が起こっているときは、科学による合理性や理知による言語よりも、自分自身の感情や本能といった内なる声に耳を傾けてみよと言っている。
・日本の場合は、西洋をまるごと模倣した「追いつき追い越せ」の文明開化と帝国主義路線を突っ走り、その結果、手痛い敗戦を喫した。⇒そこで、戦後は思想性と宗教性をすべてキレイに洗い落とし、代わりに無色透明の科学と技術を胸いっぱいに抱いて、かつてにも増した情熱をもって、未来に向けて走りはじめた。
・科学と技術は確かに驚異的な復興と経済成長を実現させ、世界中が驚愕するような豊かさをもたらした。⇒しかし、このことによって日本は科学信仰の国になってしまったともいえる。
・当時は科学というものに対するイメージは圧倒的に明るく、鉄腕アトムの主題歌にあるように、まさに「心やさしい科学の子」が、十万馬力のパワーをもって、我々の人生を後押してくれるものだと思っていた。=科学への信頼は、大人も子供も含めて、とてもあつかった。⇒だが、その信頼は揺らぎ、大きなしっぺ返しを受けている。
・科学は決して本来的に善なのではなく、そのなかから、たとえば、原子力の研究を通じて原爆が作られたり、遺伝子の研究を通じてクローンが作られたりする。⇒それらが我々の生命や倫理、信仰や死生観にまで影響を与える以上、科学やその用い方を生活世界や社会のなかにしっかりと着床させ、専門分野を越えて集まった人びとの検討を経て、反省的な考察の仕組みを作っておく必要がある。=いまこそ、何が人間にとって「心やさしい」のか、何が十万馬力なのか、よく考えてみなければならない。⇒そのためには、これまで惰性的に抱きつづけてきた、より速く、より強く、より大きく、より高くといった、いわば資本主義の弁神論が讃えるような力への信仰をもう一度見直してみるべき。
・二度生まれ:人は生死の境をさまようほど心を病み抜いたときに、はじめてそれを突き抜けた境涯に達し、世界の新しい価値とか、それまでとは異なる人生の意味といったものをつかむことができる。⇒健全な心で普通に一生を終える「一度生まれ」よりも、病める魂で二度目の生を生き直す「二度生まれ」の人生のほうが尊い。
・漱石とウェーバーもまた、まさに二度生まれの人びと。
- 漱石の場合は、自分には手本にすべきモデルはない、自分は前人未到の地平を切り開いてやるという意気込みで文学の道を突き進んだ。⇒その結果、神経衰弱になり、胃潰瘍にもなる。⇒明治43年(1910年)、「門」の連載終了後に胃潰瘍が悪化し、ついには血を吐いて生死の境をさまようことになった。⇒「修繕時の大患」と呼ばれる、人生最大の危機だった。
- ウェーバーも、過敏な神経とありあまる知性と家庭的な確執が原因となって、心を病み、一時精神病院に入った。⇒彼の場合は、ブルジョア的な俗物である父親と敬虔なクリスチャンである母親の間にはさまれて、精神的に引き裂かれるところがあった。⇒冷たい手で心臓をつかまれて、底なしの沼に引きずり込まれるような日々だった。
・そのような死地から彼らが生還してこられたのは、もともと彼らが並々ならぬ精神力の持ち主だったから。⇒一度は精神や命の危機に瀕しながら、奇跡的に復活できたという経験が、彼らは常人とは異なる世界を見せ、非凡な文明批判を可能にした。
- 漱石の小説は修繕時の大患ののち、以前にも増して深刻さを増した。⇒「行人」では、自我の地獄のなかで七転八倒する漱石の分身ともいえる一郎を描き、「心」では近代的知性の象徴のような先生を書き、そして、人間心理の極限ともいえる「明暗」へと進んだ。
- ウェーバーも精神病から立ち直ったときに、「プロテスタンティズムと倫理と資本主義の精神」を書いた。⇒資本主義と信仰心の逆説的な関係を解き明かしたこの研究は、父母と自分のアイデンティティを徹底的に探究する意図から出発したものだったかもしれない。⇒彼の場合はとくに、精神を病んだままであったら、まったくの無名で終わった可能性があるが、見事にカムバックして社会学者として成功し、ドイツのアカデミズムの世界で押しも押されもせぬ存在として活躍することになる。