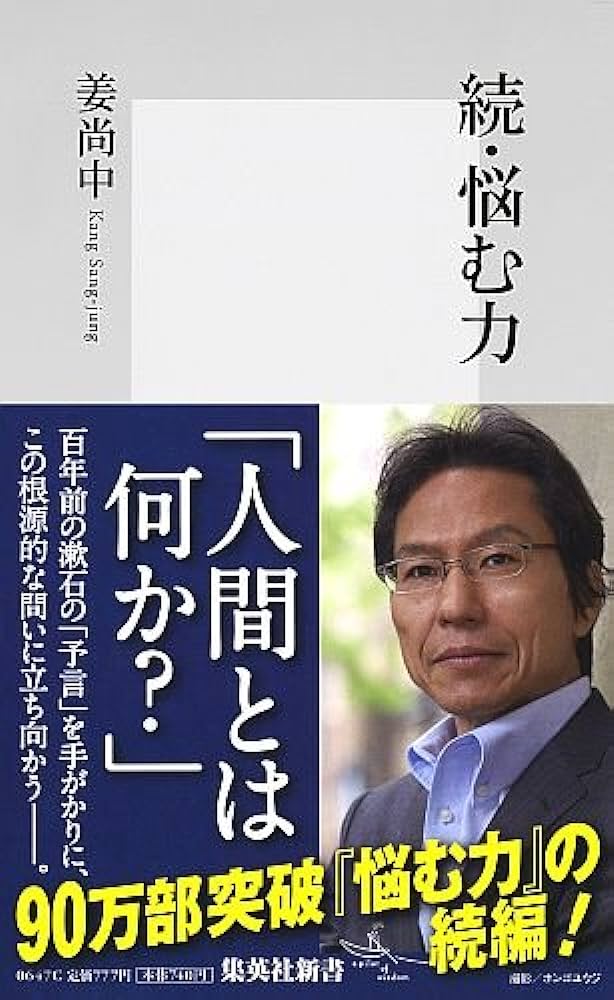【書名】続・悩む力
【著者】姜尚中
【発行日】2012年6月20日
【出版社等】発行:集英社
【学んだ所】
・東日本大震災以後、日常のありふれたしっかりとした光景が何やら液状化し、溶け出していくような感覚に襲われる。⇒液状化する近代を生きているといえる。⇒そうした近代の液状化は、震災以前から、グローバリゼーションによって、急激に、しかもそれこそ地球上の至るところで、不均等な展開を遂げながら拡大した。
・ITや情報化を通じて人間の活動する空間が飛躍的に拡大し、地球的規模の市場経済のシステムができあがるとともに、それらは身近な共同体や国家から解き放たれ、人間の生活実感からますますかけ離れるようになった。⇒その結果、人間は、まるで巻き添え被害に遭うように、思ってもみない非常事態に晒されることになった。⇒東日本大震災と放射能被害は、そのような巻き添え被害を実に物理的に目に見える形で見せつけることになった。⇒こう見ると、今は、日常化した非常事態を生きていることになる。
・もし生きる意味が、幸福感にあるとすれば、それは、幸福と感じる心のもちようを指している。
・人の数だけ幸福の感じ方があってよいのに、それがなくなってしまったところに、いまの世の中の不幸がある。⇒何を幸福と感じるのか、人生にどんな意味があるのか、それが変われば、これまでとは違ったものに価値を見いだし、これまでとは違った幸福感を味わうことができるはず。
・これまでとは違う幸福感を手に入れるためには、まるでこれまでの時代と社会のDNAであるかのように受け入れられてきた幸福の方程式を根底から疑ってみる必要がある。⇒少なくともそれを篩にかけてみる必要がある。⇒この問いをギリギリまで問いつづけ、答えを見いだそうとした先駆的な巨人が、夏目漱石とマックス・ウェーバー。
・漱石やウェーバーが重要なのは、東と西でほぼ同時代を生きた二人の巨人が、すでに100年以上も前に、慧眼にも幸福の方程式の限界についてほかの誰よりも鋭く見抜いていたから。⇒いま、幸福の方程式の終わりの終わりを経験しつつあるとすれば、漱石とウェーバーはその終わりのはじまりを見抜き、そのことを文学や社会学という表現方法を通じて教えてくれている。=それらの一言一句が、彼らの全実存を賭けた近代という時代との格闘劇を物語っている。
・漱石の作品のなかには、資本主義とからんだねじれた幸福論にとらわれた人たちが、たくさん登場する。⇒彼らはいずれもいまの人たちとたいへんよく似ていて、それだけに、終わりの時代がすでにはじまっていたことをありありと感じさせてくれる。
・「それから」の代助は、親のすねかじりの高等遊民で、いまふうにいえばニート。⇒しかし、一軒家に住み、書生を置き、舶来品の買い物などして、現代のセレブとまではいかないまでも、かなり優雅に暮らしている。⇒そんな日々が送れるのは、彼の父親が明治維新以降、この国を覆った資本主義の潮流にいち早く乗って成功したから。⇒代助は親の俗っぽさを軽蔑しながらも、富の分け前にあずかることには疑問をもっていない。⇒それゆえに、友人の妻である三千代との恋愛関係が親に知れて見放されたときに、はじめて、口に糊することのきびしさを思ってパニックに陥る。
・もう一人、そこそこいい生活をすることが当たり前になっている人物に、「明暗」のお延がいる。⇒彼女も、彼女の夫である津田も中流以上の家庭に生まれ育ったため、揃ってぜいたく病なのだが、津田の給料があまり高くないため、生活費が足りない。⇒しかし、彼らには生活を切りつめようといった発想はなく、代助と同じく不足のぶんは親に出してもらえばいいと思っている。⇒働かないお延の指には立派な宝石の指輪が光っている。⇒彼女の頭のなかには親の迷惑といった感覚はほとんどなく、考えているのは自分たち夫婦の世間体と快適さだけ。⇒そして、彼女はやたらに愛、幸福という言葉を連発する。⇒代助やお延の考え方や経済感覚は、不思議なくらい、いまの人たちとよく似ている。
・漱石の作品の大きな特徴は、主な登場人物が中流以上ばかりだということ。⇒そういう人たちが、豊かさゆえに、あるいは教育の高さゆえにどつぼにはまる姿、ほとんどそればかり書いたといってもいいくらい。⇒底辺に生きる人間のたくましさだとか、プロレタリアートのがんばりだとかいったことには、漱石は少なくとも作品中ではほとんど関心を示していない。
・ウェーバーは代助のドイツ版のようなところがある。⇒彼の父親はいわゆる新興ブルジョワジーの政治家で、ある意味では市民主義的なヒーローの仮面をかぶっている人だった。⇒ウェーバーにとっては、自分の父親のような成り上がりの人びとこそが、資本主義に末期的なものをもたらした人たちであり、彼らのありようのなかに、時代の終わりがはじまったことを鋭く感じとっていた。
・漱石が進学先の一等国イギリスに日本の末路を垣間見たように、ウェーバーも新大陸アメリカに近代の資本主義の行く末、その終わりを見いだしていた。
・ウェーバーは、「プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神」で、「精神のない専門人、心情のない享楽人。この無のものは、人間性のかつて達したことのない段階にまですでに登りつめた、と自惚れるだろう。」と言っている。
・神を信じる信じないに対して、どちらが価値的に優れているかというような客観的な判断などなくなってしまい、私念である限り、何を信じても、信じなくてもいい自由が与えられることになった。
・いま一度、幸福と苦難あるいは不幸について根本的に考え直してみる必要に迫られている。⇒「幸福論」のなかでカール・ヒルティが語っているように、人が、「意識に目ざめた最初の時から意識が消えるまで、最も熱心に求めてやまないものは、何といってもやはり幸福の感情」⇒逆にいえば、ヒルティは「幸福論」のなかで指摘していることが「この地上では現実に幸福は見つからないものだと完全に確信」した場合、これほど「痛ましい瞬間」はない。=人が経験することのなかで最も「痛ましい瞬間」をくぐり抜けることで、この地上ではない世界に救いや解法、安心立命の場所を求めようとしている。⇒漱石やウェーバーは、この地上では、とくに近代という時代の洗礼を受けて以降、もはや幸福は見いだせないのだと確信していた。=その意味では、彼らの人生そのものが、「痛ましい瞬間」の連続だった。
・同時に彼らは二人とも、宗教の門をくぐることも、かといってそこから遠く離れ、すべてを達観した古代の賢人のように振る舞うこともできなかった。⇒小説「門」の主人公、宗助が禅寺で味わう苦悩は、漱石のそれとダブり、自らを宗教的音痴と呼んだウェーバーの皮肉っぽい言い方には、信仰を求めながら、協会の門の前で立ちつくしている姿を思い浮かべたくなる。⇒彼らにもっと別の楽しいことを想像するようにすればよいとアドバイスしても、それは何の慰めにもならない。⇒漱石とウェーバーには、人間の不幸をあれこれ数え上げる愚かさからまぬがれることができるなどとは考えられなかった。⇒ある意味で、漱石やウェーバーたちが100年以上も前に悩み、苦しんだ問題が、液状化する近代のなかでより大衆化され、日常化され、ハッキリと現在目の前に立ち現れている。=これまでの幸福論でやり過ごすことはもはやできなくなっている。⇒むしろ苦悩や受苦に目を向け、その意味についてより深く掘り下げていくことで、はじめて新たな幸福の形が見えてくる。