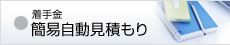来年1月から家事事件手続法が施行され,いくつか新しい規定が設けられていますが,その中で高裁で家事調停が可能になったというものがあります(家事事件手続法274条)。先日のブログでコメントを頂いたこともあり少し調べてみました。
これまで,高裁で家事調停を行うことができなかったのを,家事事件という性格にかんがみて,高裁でも家事調停を行えるように改正したということです。
高裁に係属する家事事件としては,①家裁が判決を出した離婚事件などの人事訴訟事件の控訴事件と②家裁が審判を出した遺産分割事件や養育費請求事件などの家事審判事件の不服申立である抗告事件とがあります。
高裁が家事調停をすることができるのは,家事調停を行えるとされている事件に限られますので,家事審判事件であっても,後見開始審判に対する不服申立の抗告事件などは,そもそも家事調停をできないので,高裁も調停することはできません(そもそも調停で解決することが予定されていないので)。
もっとも,従来から①の人事訴訟事件の控訴事件については,和解という形で,実質的に話し合いである調停のような形で手続が進められていたこともあったので,あまり変化はないように思います。
変化があるとすると,上記②の抗告事件ではないかと思います。
従来,家裁で遺産分割の審判や婚姻費用・養育費の審判がなされて抗告がされても,当事者に対して呼出しがあるわけでもなく,裁判所に行くこともなく,いつ決定が出されるのか知らされるわけでもなく,そのまま据え置かれて,突然決定が送付されてくるということが多くありました(なお,家事事件手続法ではこのあたりについても改正がなされています)。
抗告事件で高裁が家事調停でもう一度解決しなおしたいと考えた場合には,高裁での家事調停という制度が活用されるのではないかなと思います。
高裁での家事調停については,高裁の裁判官1名と家事調停委員2名以上で調停委員会を構成するパターンと高裁の合議体がそのまま調停委員会を組織するパターンの2つが規定されています。家事調停委員については,家裁の名簿を活用するのではないかと思いますが,わざわざ調停委員を選任して家事調停を進めるのも少し手続として重いように思いますので,基本的には,高裁裁判官の合議体が調停委員会を組織するパターンになるのではないかと思います。ただ,当事者の申立がある場合には高裁合議体での調停委員会の組織はできないこととなっています。
仮に,高裁合議体が調停委員会を組織した場合には,裁判官が加わって家事調停が進められることになりますが,この場合には,家裁での家事調停と異なり,最終的な判断をする裁判官が手続の最初から主体的に関与することになりますので,最終的な判断をバックにして当事者に対して互譲を迫るということも考えられるように思います。この点を懸念して,家事調停の組織に関して当事者の申立権を認めているわけです。
そもそも,家事事件に限らず,高裁に事件が上がると,「強制和解プレイ」のような状態になることは弁護士の間ではよく知られています。
勿論,結論が明白であったり,当事者の対立が激しすぎて和解しようもないような事件はこの限りではありませんが,下級審段階の事実認定の差で危うく勝ちを拾ったような微妙な事件などでは,高裁でひっくり返されるかもしれない可能性も残りますので,高裁裁判官はその辺りを指摘して和解を強烈に進めてくることも多いのです。
家事事件の場合,事実の評価次第で結論が異なることは多くありますし,相続の分野では法的に明確になっていないところなども多いので,上記のような家事調停の進め方になってくることも考えられるかなあと思っているところです。
もっとも,以上は私のまったくの私見ですので,実際にどのように運用されるのかについても未確認ですのであしからず。
■ランキングに参加中です。
■着手金の簡易見積フォーム
(弁護士江木大輔の法務ページに移動します。)