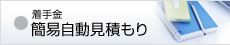民事訴訟手続では,立証責任という原則もあります。
これは主張責任に基づいて主張した事実を立証しないと勝てませんよという当たり前のことです。
なお,民事訴訟では,主張した事実について相手方が認めたり,争わない場合にはその事実は立証しないで事実として認めるというルールがあります(民事訴訟法179条 民事上の自白といいます)。
ですので,当事者が事実を立証しなければならないのは,主張した事実に対して相手方が争ってきた場合ということになります。
立証責任というと「証拠を挙げる責任」という語句のイメージですが,民事訴訟の勉強では,立証責任は「裁判官が心証を取れなかった場合に敗訴する責任」などと定義付けられています。この「裁判官が心証を取れなかった場合」というのがポイントです。
貸金請求事件で,「お金を貸したこと」は貸金の返還を求める原告が主張し,被告が争ってきた場合は,原告が契約書などを提出して立証しなければなりません。
原告が立証に失敗して,裁判官が「原告がお金を貸したかどうかよく分からない」と思えば,原告の敗訴になります。当然ですよね。
この際,問題となるのが被告の立場です。「立証責任は原告にあるのだから何もしなくて良いのだ」と考える人がいるのですが,それは立証責任を誤解しています。
さきほども述べたとおり,立証責任は「裁判官が心証を取れなかった場合」に問題となるものですので,裁判官の心の中は誰も分かりません。裁判官がどういう心証をもつのかは最後の最後に分かることです。
「立証責任は相手にある」と考えて何も反論せずにいて,相手の立証が成功していたとしたら自分が敗訴することになります。また,結審間際になって,敗訴しそうだということに気づいてあわてて反論しようとしても,時機に遅れた攻撃防御方法として排斥される場合もあります(民事訴訟法157条)。
また,立証責任は,「裁判官が心証を取れなかった場合」に使う裁判官のための道具なので,当事者には関係ないとも言えると思います。
実際にも,相手方に立証責任がある事実について反論を求められた場合に,「それは相手に立証責任があるので反論の必要はありません」という切り返し方はしません。「相手の主張や立証をもう少し整理してもらってから反論します」ということはあります。
なお,日本の伝統的な裁判官の考え方は立証責任を使っての判決というのは好まないとされています。つまり,事実をきちんと認定して判決を行なうのであって,「事実は不明なので立証責任を使って判決する」ということはあまりしないとされています。事実を認定できないというのは職業裁判官の沽券に関わるというところでしょうか。
ですので,裁判官が心証を取ろうとしている審理の途中で「立証責任」を持ち出すのは,裁判官に対して「あなたは最後まで心証を取れないでしょう(何が事実なのか分からないでしょう)」といっているのと同じことで失礼なのです(と,私なりに考えています)。
■ランキングに参加中です。
■着手金の簡易見積フォーム
(弁護士江木大輔の法務ページに移動します。)