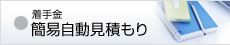民事訴訟法で主張責任という原則があります。
当然のことといえば当然ですが,訴訟で勝ちたいと主張する側は,勝訴を基礎付ける事実を主張しなさいという原則です。裏返して言うと,勝訴するために必要な事実を主張しないと敗訴になるということです。
難しい言葉で「弁論主義の顕れ」などと言ったりもします。司法試験の民事訴訟法では必ず学ぶ原理原則です。
例えば,お金を貸したが返してもらえないという貸金返還請求を起こそうという原告は,①お金を貸したこと②返済期限が来たことを主張しなければなりません。
ちなみに「既に弁済したこと」は被告が主張すべき事実ですので,原告は「弁済を受けていないこと」を主張する必要はありません。
普通,主張責任ということを神経質に意識することはあまりありません。普通にやっていれば,主張すべきことは自然と主張されているからです。
ただ,原告として訴状を書くときは主張責任というものを意識します。
私たちが弁護士になる前の修習生の段階では,訴状を書くときに,「被告が欠席したとしても勝訴できるだけの事実を主張すること」というのを教え込まれます。
先ほどの例で言えばお金を貸したこと、返済期限がきたことの事実を主張していないと,主張責任によって裁判所は原告を勝たせてくれません。被告が欠席したからといって,すべて原告の勝ちとなるわけではなく,必要最低限の主張責任を尽くしていないといけないのです。
ちなみに,必要最低限の主張のどれかを落として訴状を出してしまい,被告にも送達され,第一回口頭弁論期日に被告が欠席した場合に,その段階で必要な主張が足りていないということになると,原告は準備書面で主張を補充しなければならず,もう一回被告を呼び出して期日を開かなければなりません。
・・・・と偉そうなことを書きましたが,私も必要最低限の主張を漏らしてしまい,裁判所から指摘を受けて訴状を補正したことがあります。幸い,第一回期日前に裁判所から指摘して頂きましたので助かりましたが(@Д@;
従来,保証契約は口頭のみの合意で足りる諾成契約と呼ばれるものでしたが,平成16年の民法改正で,書面で契約することが保証契約の有効要件となりました(民法446条2項)。
さきほどの主張責任で言えば,「書面で契約した」ことを原告として主張しなければ,有効な保証契約の成立を主張したことにならないことになります。
ついうっかり,証拠書類を引用しつつも「保証契約に合意した」という書き方をしてしまったのですが,裁判所から「書面で合意した」と訂正するよう指摘され,そのように訂正しました。
■ランキングに参加中です。
■着手金の簡易見積フォーム
(弁護士江木大輔の法務ページに移動します。)