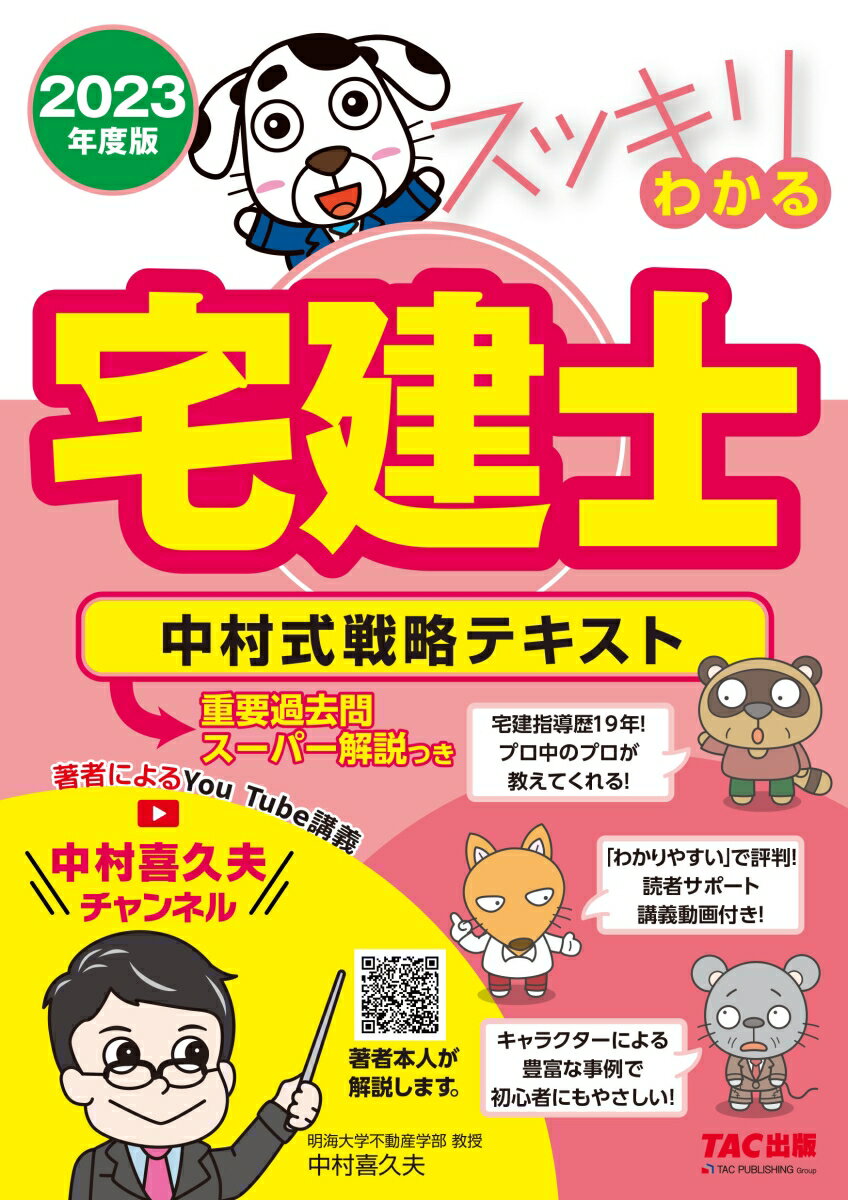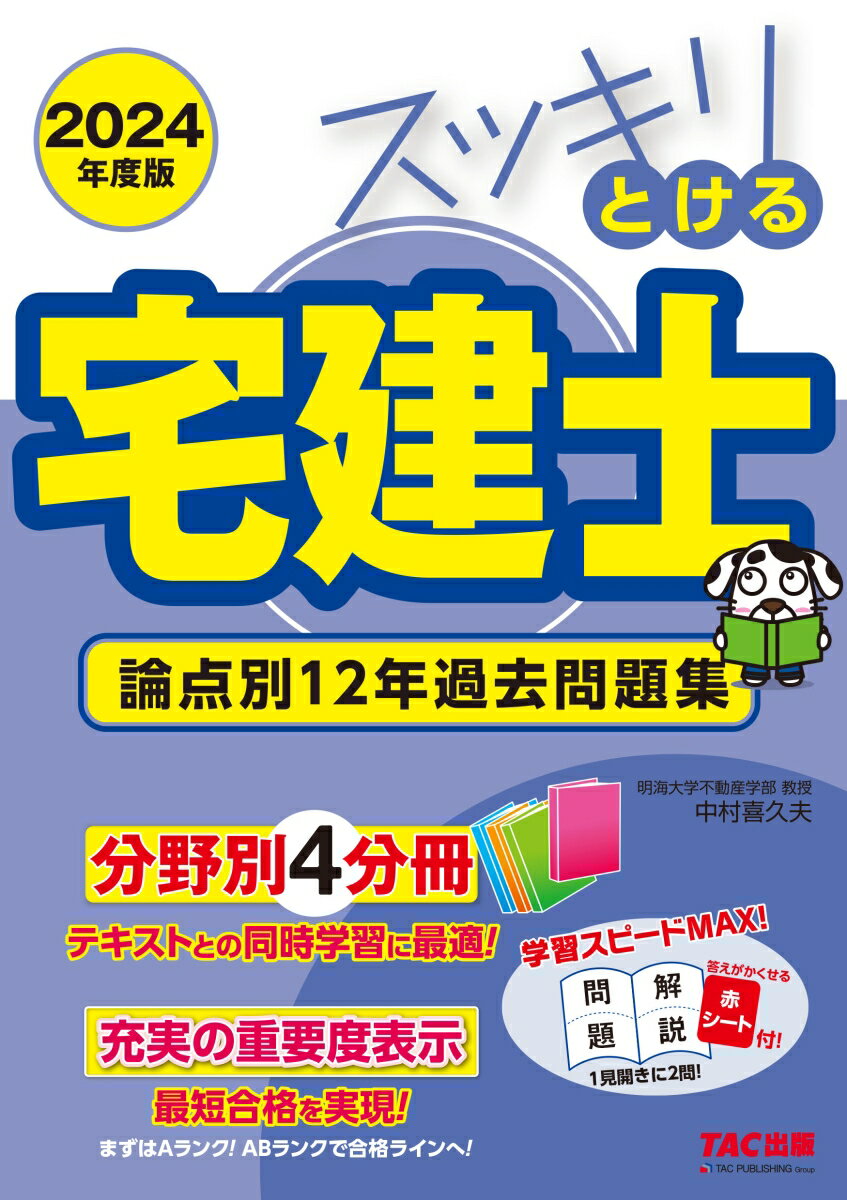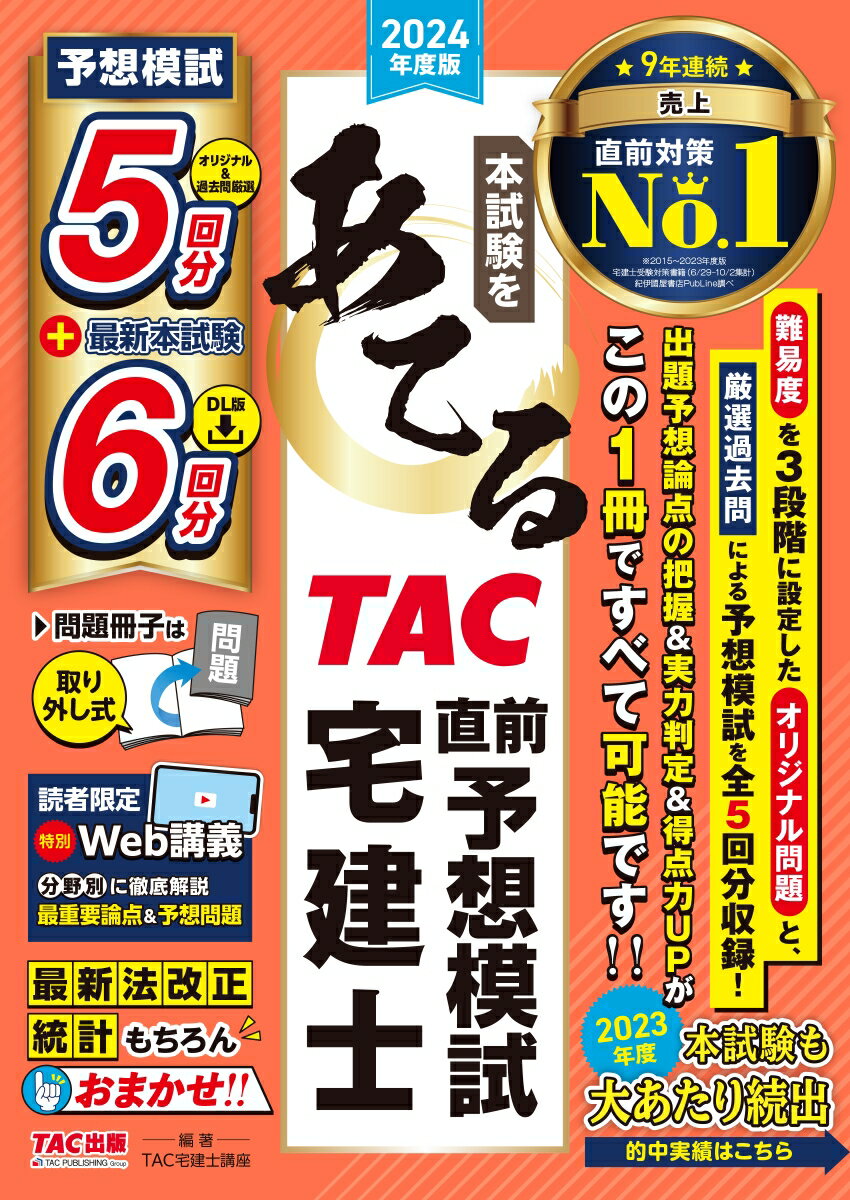こんにちは。
昨日に引き続き、試験対策についてまとめてみようと思います。
私は去年、
育休中、独学で宅建に合格
しました。
試験対策時間は大体2ヶ月半、
勉強のタイミングは双子の昼寝時間、
1日の勉強時間は大体40分〜1時間
トータルの勉強時間は200時間も取れなかったと思います。
育児で忙しい方でも、
隙間時間の勉強で合格できる!
そんなポイントをまとめてみました。
受験を考えている方の参考になると嬉しいです。
まず、今回お世話になったテキストはこちら↓
表紙にいますね、可愛い動物たちが。
スッキリ資格取得シリーズのこのゆるい守護獣たちがお気に入り。
また、著者の中村先生がYouTubeで講義動画を出されています。
都市計画法とか、とっつきにくい分野は動画を見てからテキストを読みました。
先生の落ち着いたら語り口もおすすめポイント![]()
テキスト、過去問はどちらもに分野ごとに分冊できるので、持ち歩きに便利です。
この予想模試は問題文のクセ?がすごくて
1周目は全く歯が立たず…![]()
10月から取り組んだので、とても焦りました![]()
変化球の問題が多いので、どんな問題が来ても
動揺しない心を持てるようになります。
余裕のある方にはおすすめです。
私の宅建の試験対策は、FPの試験対策と同じく、
過去問を4周する
でした。
ただ、宅建試験の厄介なところが一つ…
7割得点しても、受かるとは限らないんです![]()
受験者の上位17%の人が合格するというのが恒例のようで、受験者のレベルが上がると、その分合格ラインも上がってしまうのです。
実際に令和元年から令和5年までの合格ラインの点数は34点〜38点と、だいぶ幅があります。
7割取れても合格できない年もあるんですね…![]()
なので、私は8割越えを目指して試験対策を行うことにしました![]()
宅建は4択問題から一つ答えを選ぶ方式の試験。
4択の一問一問、全て答えられるようにしました。
例えば、「正しいものはどれか」という問題なら、
正しい選択肢を選ぶだけで無く、
間違っている選択肢の文章を読んで、どこが間違っているかが分かる段階まで持っていく。
そうすると一問とくときに4つの論点を確認することができて、知識の精度をあげることができます。
あとは、試験本番まではひたすら過去問を解き、テキストを逆引きして知識を固めていく。
以下は過去問を4周した時の大体の流れです。
・過去問1周目は、宅建の世界観に慣れる段階
初めての分野のことなんてわかるわけないので、
「へー、こんな言葉があるんだー」
「何言ってるのか全然わからん」
という状態。
用途とか権利とか何も知らない状態からスタートです。とにかく気にせず読み進めて、目と頭を慣らします。
・2週目はテキストを辞書にして逆引きする段階
過去問の問題を解く時に、テキストを辞書代わりにして解く。よくわからない単語はネットで調べてました。
・3週目は2週目と同じ作業、脳に刷り込む段階
テキストを索引しなくても解ける問題がほんのちょっと増えます。自力で解けた問題には丸をつける。
わからない問題は迷わずテキストを索引します。
・4週目からは本格的に過去問を解く段階
ここまできたらテキストを見ずに解いてみます。
◯のついてない問題をとく。
全部に◯がついたら、もう一度解き直し。
2回解けたら◎
3回解けたら花丸
試験本番までに全部の問題に花丸が
ついていれば、一安心です![]()
大体1週間で一つの分野を一周を目安にすると良いと思います。
私は、初めのうちは1週間で宅建業法、1週間で権利、1週間で法令上の制限というふうに進めていました。(その他税法は10月に詰め込みました)
最初こそ時間はかかるけど、4週目に入る頃にはできない問題を覚えるだけなので、一周がかなり早くなり、1週間で全ての分野を周回できるようになります。
そして、試験当日は
1問目から淡々と解き、見たことない問題は適当にマークを埋め、過去問で解いたことのある論点だけは確実に解くことを意識![]()
結果、43点で合格することができました![]()
私の受験番号は1414-0027…
あった!!
自分の番号があると嬉しいよね〜![]()
宅建を勉強するきっかけは数年前に家を購入したからなのですが、試験対策をするなかで登記とか、
重要事項説明など身に覚えのある項目が出てくると、契約時のアレやコレはこういう事だったのか〜!と分かって楽しかったです![]()
今回は宅建試験対策について振り返ってみました。
これから試験対策を練る方の参考になれば嬉しいです![]()
それではまた次回!