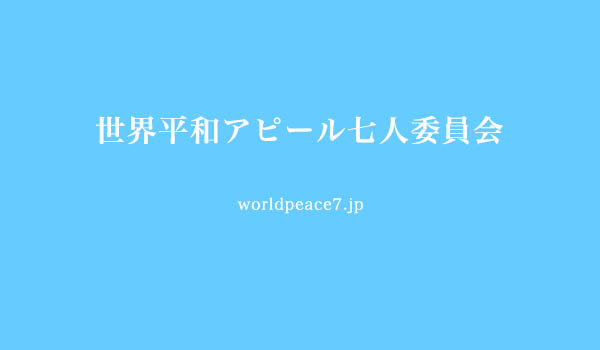前回もちらっと書いたけど,《新書で世界と時代を読む》みたいなタイトルで今年中に新書100冊のガイドブックを書こうと思っていて,今その準備をしているのだが,やはり時代やテーマを絞らないと収拾がつかなくなりそうなことに気づいた。そこで2015年以降に出た新書に限定して100冊を選び,それぞれの紹介文・書評を書きながら,この10年がどういう時代だったかを検証するものにしたいと,今のところは考えている。
今から10年前の2015年,すなわち戦後70年の年に『岩波新書で「戦後」をよむ』という新書が,もちろん岩波新書で出て,大変面白い企画と内容だった。1945年から2015年までの70年間を10年ごとに7つの時期に区分し,それぞれの時期の代表的な岩波新書を3冊選んで,3名の学者さん(文学者・歴史学者・社会学者)が討議するという企画モノであった。取り上げられた計21冊のうち,私が読んでいたのは半分より少なかったが,こうやって改めて岩波新書を吟味してみると,各時代の特徴というか,その時代の「空気」や「課題」が見えてくる。と同時に,戦後の知的な営みを辿ることもできる。そうした意味で岩波新書は,「戦後」を検証するのに必須のアイテムだなと思った。岩波新書に限らず,新書は決して侮れない存在だなと思い直したわけである。
戦後80年の今年,岩波新書からは同様の企画本は出そうにない。政治に目を転じても,石破首相は「戦後80年談話」を出さない方針だという。安倍のトンデモナイ「70年談話」で終わりにしようとしているのだ。それは,もう日本国は過去の侵略戦争や植民地支配に対して謝罪も補償もしませんよという意思表示でもある。そういう歴史に背を向けた後ろ向きで歴史修正主義的な政府の態度に対して,批判の声はあまり上がってこないし,言論の世界でも戦後80年という問題意識は希薄なようだ。
そんなことを考えていたら,一昨日「世界平和アピール七人委員会」が「新たな日本外交の礎に戦後80年談話を」と題するアピールを発表した。時宜を得た発表であり,現状の国際情勢を踏まえた的確なアピール文だ。下にリンクを貼っておきます。短い文章なので,是非読んでいただきたい。
加害者であった日本が、もはや謝罪をしないといえばいうほど、反省が足りないと被害国側がいい続けることになっている。戦後が終わるのは、被害国側が、日本は加害の歴史を直視していると判断するときである。
…いまなおアジア各国に残る戦前の日本の残像を何度でも注意深く取り除く努力をすべきであり、それなくして真の友好も協調もない…。
今や「戦後」の内実が無視され,無化されようとしているなかで,このアピール文には「戦後」を問い続ける真摯な姿勢がある。だから私は共感する。「戦後」が問われなくなれば,「戦前」も捨象される。つまり,もはやあの戦争はなかったことにされる。歴史修正主義が人々のスタンダードな歴史観になり,戦前回帰には何の障害もなくなる。そのように「戦後」が失われることへの危機感がこのアピールの根底にはある。
今年,戦後80年は戦後社会の決定的な分岐点となり得るという緊張感が私にはある。すなわち,この戦後80年という機会をスルーしてしまえば,このまま日本は軍拡と戦前回帰への道に突き進んでいくのではないか,という確信的な危機意識が私をとらえている。だからこそ,現首相には安倍元首相の欺瞞的な「戦後70年談話」を乗り越えて,加害の歴史を直視した真摯な「戦後80年談話」を出してほしいと思うわけである。そして言論でも積極的に「戦後」を問い続けることが必要であろう。私が新書100冊を使ってこの10年を検証しようと思ったのも,そういう問題意識からである。この10年で戦後の知的な営みがどう受け継がれ,あるいは受け継がれなかったのか――。
私には戦前回帰や歴史修正主義への危機感が強い一方で,戦後の「知」が危機打開への糸口になるのではないか,との微かな期待も併せ持っている。「戦後」の本当の闘いはこれから始まる…
⚠気づいたときには手遅れ
— わと🐧5/1(木)改憲発議阻止デモ🚩 (@wato_mac_bisco) April 25, 2025
5月3日は #憲法記念日
憲法は国民の命と自由を守るため、権力にブレーキをかけるルール。世界では非常事態を口実に憲法がゆがめられ、今、日本でも災害や安全保障などを理由に変えようとする動きが…。
憲法を知ること 生かすこと
あなたのその一歩が
平和をつなぐ力になる pic.twitter.com/XSB3WAdQrI