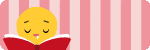アメブロ読者には不向きの長文だが,環境問題の「ポポフ」を見つけ出そうとして書いた力作で,本人お気に入りなので再掲することにした。関心のない方はスルーしてほしい。翌日書いた「補遺」からも関連部分を抜粋で載せておいた。
なお余談だが,いま世間を騒がせている尖閣ビデオ流出事件は,最後のジョークにあるのと同じくらい馬鹿げた「国家機密漏洩」である。
「環境問題の陥穽(かんせい)」(2010年1月31日付)
今日は,昨日書く予定だった環境問題について。
少々ややこしく,はっきりした結論の出ない,まとまりのない話になると思うが,その点はあらかじめ了承いただきたい。現在,日本で喧しい環境問題の議論が見落としている点を指摘できれば,と考えている。
いろいろと面倒な話の前に,今日はまずジョークから始めたい。まだソ連が存在していた頃のロシアン・ジョークである。
多数の政治犯が収容されているシベリア強制収容所にて―――
ある牢屋の囚人の一人が長い沈黙を破って,呟くように言う。
「どうしてお前はここにいるんだ?」
ゆっくり振り向いた,もう一人が
「俺はポポフに反対してここに放り込まれた。で、お前は?」
「俺はポポフを支持したから,放り込まれた。」
「なるほど,そうか。」
二人の話を聞いていた,もう一人の別の囚人は黙りこくったままだった。そこで二人が彼に聞く。
「お前はどうなんだ?」
すると,彼は重い口を開いて答えた。
「俺はポポフだ」
これは古典的名作で,ご存知の方も多いかもしれない。なかなか味のあるジョークである。ポポフに反対しても賛成しても政治犯として捕まえられるという,メチャクチャな政治状況。しかも,ポポフ自身まで捕まえられているとは,と不意を突かれる。このようなロシアン・ジョークは,当時の社会主義的政治体制を反映していて毒があり,自虐的で,命と引き換えに語られた。身の危険を感じながら語られたがゆえに,味わい深く面白い。
今日はソ連の政治の話をしようというわけではない。環境問題の話である。このジョークについてはまた後で取り上げることにしよう。
近年,地球環境への関心が高まり,温暖化による危機が声高に叫ばれるようになった。そこで,先進国各国がCO2をはじめとする温暖化ガスの削減に取り組むようになった。日本でも鳩山首相が2020年までにCO2の25%削減という目標を掲げた。先進国がこのように温暖化ガスの削減に取り組むこと自体,地球環境の視点からは特に異論はない。
だが,先進国がこれまで文明を発展させてきた歴史を振り返ってほしい。石炭,石油などの化石燃料を大量に使うことで,工業をはじめとする産業を成長させ,高度な文明社会を築いてきた。日本では今でも石油による火力発電は,発電量全体の65%を占めている。今の物質的に豊かで便利な生活スタイルを変えて,今より物質的に乏しく不便な生活を送る覚悟があるのかどうか。また,そうした生活をしていく上での「生活の知恵」といったものが,現代人に身に付いているかどうか。
地球環境や資源・エネルギーの観点から,エコやリサイクルを訴えるのは間違っていないが,自分自身の生活のこととなると話が違ってくるのではなかろうか。総論賛成・各論反対という論理だ。
日本でも半世紀前は,反対に,自然や資源などのことよりも,生活を豊かにし経済を成長させることだけに奔走してきた。もし,当時エコとか環境とか言っても,誰も相手にしてくれなかっただろう。高度成長の終わる1970年代頃から,公害問題が表面化し,また石油ショックなどがあって,自然保護や資源の問題がクローズアップされ,その大切さが認知され始めた。とはいえ,ここ最近までは,日本では経済や産業の発展が至上価値で,自然環境の保全は周辺的な価値として顧みられるにすぎなかった。
それがここ数年で,経済(文明)から環境(自然)へと,社会全体の振り子が大きく振れた。経済的な豊かさを追求し続けた結果,自然環境を破壊し,資源を浪費したことに気づき,やっと今,「これではいけない」と自然の見方を変え,自然環境を保護しようという流れになった。成長の限界点ギリギリのところで,本当の意味で自然の大切さに気づいた。そこで,社会全体の価値観が,経済(文明)から環境(自然)へと転換したのだ。すでに70年代に,ローマ・クラブが「成長の限界」というレポートの中で,経済的成長の限界が目前に迫っていることを警告し,これからは自然環境の保護や人間的な成長の時代であることを指摘していたはずである。あまりに遅すぎた転換と言ってよい。
さて,日本人のこのような変わり身は,他の国にはどう映っているだろうか。先ほど述べた温暖化ガスの削減については,すべての国が賛成しているわけではない。実は,環境保護とかエコとかという考え方は,すべて先進国の論理なのだ。日本をはじめ先進国は,これまで化石燃料などの資源を使いたいだけ使って,文明・文化を発展させてきた。それがここ最近になって,やれ地球環境だ,やれCO2の削減だ,ということになった。今,急成長している中国やインド,さらには,これから成長していかなければならない発展途上国にとっては,はなはだ迷惑な話である。「お前たちはもう発展しているからいいが,俺たちはこれからなんだ。みんなが生きていくためには,豊かにならなければならない。自然資源を使わずに,文明や産業を発展させる方法があるなら教えてくれ!」という途上国の言い分が聞こえてきそうである。
先進国の立場からすると,経済成長とか豊かさといったもの(文明)はもはや古い価値観になったが,まだ文明の低い段階にある途上国にとっては,キラキラに輝く新しい価値なのである。では,われわれはどうしたらよいのか。自然環境と文明とのどちらを優先していけばよいのか。簡単に結論の出る問題ではない。ただ,今関心が集まっているエコとか環境保全という流れは,人類の長い歴史の中で言うとごく最近のものであり,また,あくまで先進国側の主張であって,必ずしも人類すべてに通用する正義ではないということは言っておこう。
話が大きな問題に入り込みすぎた感があるので,ここでストップしよう。だが,環境問題について何か大切なことを見落としているような気がする。そうだ,「ポポフ」だ!
冒頭で紹介したジョークを思い出していただきたい。ポポフに反対したりポポフを支持したりすることに気を取られて,ポポフ自身のことを忘れていた。すなわち,自然を保護するか,自然に手を加えて文明を発展させるか,ということだけに気を取られて,それを行う人間自身のことを忘れていた。人間とは一体どういう存在なのか。―――もしかすると,この問いが解決されない限り,自然か文明か,という問題も解決できないのではないか。逆に言えば,この問いが環境問題解決の鍵を握っているとも言えるだろう。
当然,これも簡単に結論の出るような問題ではない。が,少し取っ掛かりだけ作って,今日の話を終えたい。
英語の辞書で「ネイチャー(nature)」を調べると,もちろん「自然」という意味が出ている。が,それ以外に,必ず「本性,天性,人間性」あるいは「性質,気質」といった訳語が掲げられている。これらの訳語は,すべて人間に関わる言葉である。というのも,「人間の中の自然」という考え方が,これらの訳語のもととなっているからである。つまり,人間にはもともと持って生まれたもの(自然)があるという考えである。
こうして人間の中に自然があるとするなら,それに手を加えること,すなわち教育・啓蒙を施し,洗練・修練を加え,経験を蓄積することによって,より優れた状態が作り出されるに違いない。つまり,「教養」や「知識」が身に付くだろう。
もし人間の中の自然が,「自然」の中の一部だとしたら,どうなるだろうか。
この人間の中の自然を損なわず,それに沿った形で磨きをかけることにより,「自然」の大きな営みの中で文明を享受する知恵,つまり自然と文明とのバランスをとる知恵が生まれてくるのではなかろうか。
さて,地球の表面に与えられた「自然」の中で,人間(人類)はどのようにして生き延びていくことができるのか。人間らしい生き延び方で・・・
Michael Jackson "Earth Song"
NERDHEAD "BRAVE HEART" feat.西野カナ
「補遺」(2010年2月1日付)
( 略 )
昨日のブログについては,本論よりも,導入で紹介したジョークが好評であった。そこでの「ポポフ」は時と場所によって,ゴムルカだったりフルシチョフだったりしたらしい。とにかく,東西冷戦時代における,ソ連を中心にした共産圏の政治状況(一党独裁というか個人崇拝)を風刺していて,大変面白くトゲのあるジョークだった。言論が弾圧されている国で―――ひっそりと―――語られるジョークだから面白いという側面がある。「ポポフ」の部分を鳩山に変えても,ちっとも面白くない。何か規制があったり束縛されたりしているから,そこから逃れようとか自由になろうとしてギャグやジョークが生まれる。そういう意味で,日本のように言論の自由が一応保障されているような国では,歴史に残る面白いギャグやジョークは生まれにくいのかもしれない。20年以上前だったと思うが,漫才師のビートたけしが「赤信号,みんなで渡れば怖くない!」というギャグを放って,ヒットした。命と引き換えに語られるほどのギャグではなかったが,信号無視なんぞは交通事故の原因でもあるし,そんなルール違反を肯定するとはけしからん,と物議を醸した。たけしに対する世間の批判は大きかった。しかし,ルール違反もみんなでやればそれがルールになるという,日本人の集団指向的な特質(言い換えれば,個人より集団を優先するお人好しな国民性)も見事に突いていて,それを皆も陰では気づいていたから流行した。なお,余談の余談だが,ギャグ(gag)という言葉には,もともと猿ぐつわとか言論弾圧という意味があった。
好評に付き,今日は同じくソ連時代のロシアン・ジョークをもう一つだけ紹介しておこう。
モスクワの「赤の広場」にて――――
ある男が,スターリンの独裁に対する不満を爆発させて,何度も繰り返し叫んだ。
「スターリンの大馬鹿野郎!」
そこで早速,その男は秘密警察に逮捕され、強制収容所送りになった。
刑期は25年。
男は,何でそんなに長いのかと尋ねた。
すると,その内訳は……
「国家元首侮辱罪」で5年。「国家機密漏洩罪」で20年。
やはり侮辱罪よりも,国家機密!?を漏らした方が罪は重い。
( 略 )