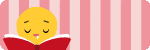一昨日のブログで紹介した荷風が言っていたように,日本人は欠点をあげつらい弊害を論じるのが好きで,それは日本人の特徴とも言える。荷風は「猥褻(わいせつ)」を例に挙げて述べていたのだが,煙草もその良い例である。誰か敢えてその利益を論じてみる愚をなせという荷風のリクエストに応えて,煙草のメリットについてひと言だけ言わせてもらいたい。もしかすると,「災い転じて福となす」,害あるもの転じて利となることも無きにしもあらずなので。因みに,私はかつてはヘビースモーカーであったが,今は喫煙者ではない。
煙草は,天正年間(1573~1592年)にポルトガルから伝えられたと言われている。やがて江戸時代にはたびたび喫煙禁止令が出されたが,喫煙の習慣が広がり,禁令は有名無実となったらしい。このことは,日本人がどれだけ煙草好きだったかを示している。当時,禁止令が出されたのは,おそらく健康上の,医学的な見地からではなく,モラル・風紀上,社会生活上の観点からであろう。煙草はモラルを低下させ,風紀を乱すと考えられた。だが実際は,煙草は人々の「連帯」「団結」,と言うと大げさだが,人と人との「つながり」と言うか「和」「一体感」を強めた。それは煙草ののみ方に現れている。すなわち,当時人々は煙草を何人かでまわしのみする習慣があった。まわしのみをして,それに参加する人たちの気持ちを一つにした。このまわしのみがもともと煙草ののみ方であったらしく,煙草発祥の地アメリカの先住民の間では,それが和解の儀式だったらしい。ちょっと前までは日本でも煙草を吸うとき,相手にも煙草を勧めるのがマナーであったし,また今でも,キャバクラなどに行って,煙草を吸おうとしたときにはホステスが火を差し出してくれるのが,これまたマナーである。
言われてみれば,煙草にはそういう人間関係を良好にする面は確かにあるだろう。まわしのみまではしなくても,一緒に煙草を吸っていることで仲良くなる人間関係は確かにある。私も20年近く前,入院していたとき,病院に喫煙スペースがあって,そこでたむろして一緒に喫煙していた連中と仲良くなり,退院後もずっと付き合った友人が何人かいる。
煙草は人の体の内部では悪さをするが,人と人の間では「接着剤」あるいは「仲人」のような良い役割もする。言い換えると,煙草は自然科学的には悪者だが,社会的・文化的には善人である。一概に禁止令を出したり,大幅に値上げしたりして禁止することにより,自然科学的・医学的な問題は解決するにしても,逆に社会的・文化的に良好な役割がデリートされてしまう。煙草の害悪ばかりが一方的に吹聴されて,煙草が世の中から追い出されることによって,人間関係がますます希薄になることを危惧する。
これで荷風のリクエストに応えたことになるだろうか。煙草も用い方次第で罪が転じて徳になることあらんや。
注)煙草の伝来については2010年10月5日付中日新聞・夕刊を参照