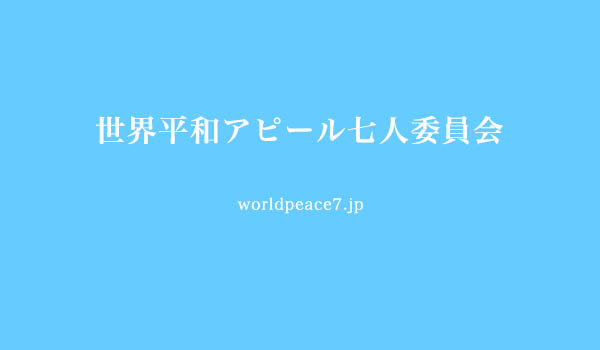話は10年以上前に遡るが、アメブロから始まり、旧TwitterやらGmailやらのSNS上で私にしつこく付きまとっていた「○んじゅ」というネットストーカーがいて、ずいぶん迷惑や精神的苦痛を被った。ブログの記事の内容を書き直せとか、ねちねちと毎日のように長文のメールやメッセージを送り付けてきたりするので、アメブロのコメント欄やメッセージは閉鎖し、TwitterもGmailもすべてのSNSのアカウントを停止した。唯一続けているのがこのアメーバブログである。このアメブロにリブログ機能が追加されると、私の記事を勝手にリブログして意見するようになったのでリブログも停止した。最近はアメブロにブロック機能ができて、当然ブロックしているから、相手もブロックされているのを分かっているはずで、もうストーカー行為はあきらめただろうと思っていたのだが、つい最近、別のSNS上で前回の私のアメブロ記事を勝手にシェアしているのを見かけたのだった。こういうストーカーというのは一生あきらめることなく付きまとうのだなと、吐き気を抑えながら理解した。以前アメブロで付き合いのあったリ●さんという人は、アメブロで知り合った人から実生活でストーカー被害を受けたと話してくれたが、確かにそういう実害もありそうだなと思い恐ろしくなった。
このアカウントでアメブロを続けている限り、○んじゅというストーカーはたぶん永久に付きまとってくるだろう。そう思うと、本当に頭がくらくらする。いろいろと考えたが、今後、一切ここで記事を書くことはやめることにしました。 このアカウントを削除してしまうか、それともこのまま放置しておくかは、まだ決めていませんが、とにかくここでブログ記事を書くことは今日で終わりにします。もし他の場所で書くことがあれば、個別に連絡いたします。長い間、お世話になりました。
ところで、20年以上前から、たまに物凄いめまいと吐き気に襲われることがあって、大学病院で脳や耳などの検査をしたけれども原因が分からず、良性発作性頭位めまい症かメニエール病かと思っていたのだが、しばらくめまいの発作もなかったので治ったと思っていた。それが最近また、たまに起こるようになり、ネット上でいろいろと調べていたところ、仙台の耳鼻科の先生から、
前庭神経炎
の可能性が高いとコメントをもらった。それで前庭神経炎について調べてみたら、私の症状や経過にほとんどあてはまっていて、間違いないと確信した。その先生が言うには、私のように何度も繰り返すのはウイルス性の前庭神経炎だという。子供の頃に罹った水疱瘡のウイルス(水痘・帯状疱疹ウイルス)が、耳と脳をつなぐ前庭神経の節に潜伏していて、ストレスや過労などで免疫力が下がると、そのウイルスが「再活性化」して激しいめまいと吐き気、嘔吐を引き起こすのだという。そういえば私の場合、20代になってから水疱瘡に罹っていた。前庭神経炎は難聴とか耳鳴りとか耳の症状は生じないから、聴覚検査をしても異常は出ない。
10年以上前、そのネットストーカーに付きまとわれていた頃、激しいめまいがよく起こった。ストーカーが原因でまた恐ろしいめまいを起こしたくないというのも、ここで記事を書くのはやめようと決断した理由の一つである。この前庭神経炎になった人にしかわからないと思うが、ある日突然、強烈な回転性のめまいと吐き気が起こり、それが数時間~1日,時には3日くらい続くこともある。少しでも頭を動かせば嘔吐してしまうから、ずっと横になったままでいるしかない。実際に嘔吐してしまうこともあった。頭はぐらぐら、全身汗びっしょり。救急車で運ばれたこともあった。命に別状はないらしいが、もう二度と発症したくない。帯状疱疹を経験している人は多いかもしれないが、それと同じで、ストレスや過労、睡眠不足などで免疫力が落ちると起こりやすい。一番効果的な治療というか予防は、抗ウイルス薬(バルトレックスなど)を早めに飲むことらしい。でも、発作が起こった後では、あまり効果がないという。だから、先ほどの先生からは、抗ウイルス薬を常にお守りのように持っておいて、めまいの前兆のようなものを感じたら、すぐに飲みなさいと指示された。
ネットでは、このようにとても得難い出会いもあるが、しつこいストーカーや誹謗・中傷に悩まされることもあり、両刃の剣と言えるが、あまりSNS上でのコミュニケーションやコミュニティには深入りせず、適度な距離感であくまで便利な情報交換の場として利用していくのが賢明な使い方であろう。
それから、以前にもちょっと書いたように、今年は戦後80年ということで、本を出したいと思っているのだが(ちょっと間に合いそうにないが)、別に売れる本ではないので、出版社を通した自費出版ではなく、自分で印刷や製本を手配する完全な自己出版で100~200部くらいを出す予定。もし出版社を通すとしても、半分くらいは自分で買い取って、知り合いや関係者に配るつもりである。電子書籍ならオンデマンドですぐに出せるが、やっぱり紙の本が良い。いわゆる情報収集はデジタルで構わないと思うが、私たちの認識や思考の基礎をなす知性や教養といったものはデジタルではなかなか身につかないと思う。知というものはやはりじっくりと本を読んで、時間をかけて身につけていくものだろう。だから、
「デジタルを捨てて本に還ろう!」