山本おさむ「どんぐりの家」
ヤマト運輸・小倉昌男
氏が、
最も感動したマンガとして、
上げている障害者の物語。
著者は、「遙かなる甲子園」にても、
障害者を描いています。
「どんぐりの家」は、埼玉県に実在する、
ろう重複障害者が通う作業所がモデル。
若干、古い本であるためか、
ツタヤやマンガ喫茶にもなかったため、
漫画全巻.com
にて、購入しました。
特に印象的だったのが、著者あとがきで、
ろう学校を見学した際の感想。
「手記に書かれた感動的なエピソード、
それが起こるためには家庭や学校や地域で
このような何も起こらない時間、毎日毎日の
積み重ねが必要だったのであり、
私はこの「何も起こらない時間」にも感動した。
そこには、ゆっくりとした、しかし確実な成長を
見ることができ、その成長をかけがえのないものと
捉えるとき、その延長線上に共同作業所の必要性も、
いわゆる障害者問題も見えてくると思う。
まず障害者問題ありきではなく、まず人間ありき
家族ありきでありたいと思う。」
このマンガを読むと、いろいろ考えさせられますが、
整理すると次のような流れになります。
身体的・精神的障害-->コミュニケーション不足-->自閉-->自傷
子供というのは、もともと気分が変わりやすく、
精神的に安定しないため、指導者は、
かなりの根気、忍耐が要求されます。
人は、言葉によるコミュニケーションを
中心としますが、自分としては、
障害者自身のためにも、犬をはじめとする
動物と積極的に、関わるようにしたら、
いいのではないかと思うのです。
別の機会に紹介しますが、毎年、保健所では、
数十万匹の犬、猫が処分されています。
動物と接することにより、言葉が上達するわけでは、
ありませんが、動物との非言語でのコミュニケーションで、
また、動物は人間と違い、見返りを求めませんし、
感情が衝突することもありません。
保護者からすれば、こども一人でも大変なのにと
思うかもしれませんが、動物を飼うことにより、
子供が笑顔になり、精神的に安定し、成長すれば、
飼う価値は、十分あるのではないでしょうか。
もし、自分が時間的にも、金銭的にも自由であれば、
実験的に、障害者を対象にしたアニマルセラピー、
施設等を設けられればと思います。
障害者を育てるということは、植物の世話をするのと同じで、
生長も少しずつであり、こっちの意志で、
急に花を咲かせようとしても、やっぱりダメなのです。
また、障害者同士のつながりもそうですが、
それ以上に、障害者の親同士のつながりは、
もっと重要であると感じました。
それは、世間から冷遇されたり、
健常者とは、全く異なる苦労をしているわけで、
それを共有し、励ましあっていくこと。
普段は、数字ばかりに追われ、
障害者と縁する機会が少ない自分ですが、
このマンガを通じ、改めて考えさせられました。
山本おさむ「どんぐりの家」
おすすめです。
- どんぐりの家 第一巻 Big comics special/山本 おさむ
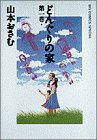
- ¥866
- Amazon.co.jp