
皆様、新年明けましておめでとうございます㊗️ 本年令和6年もどうぞ宜しくお願い致します🙇
40代となり仕事の責任が大きくなるにつれ筆はどうしても遅くなってしまいますが、その辺りの事情を何卒ご理解頂ければ幸いです🙏
前回のエントリーに引き続き、2020年の停戦合意が破られる形でアゼルバイジャン🇦🇿(以下アゼリーで統一)が強制平定に乗り出したナゴルノ=カラバフ共和国(正式名称はアルツァフ共和国。副称がナゴルノ=カラバフ共和国。以下ナゴルノで統一。ナゴルノは山岳の、ないしは高地を意味する)について取り上げて参ります。前回のエントリーから3ヶ月ほど間隔が開いてしまいましたが、時間が許す限り筆を取って参りたいと思います。ナゴルノを巡るエントリーは今回で2回目となります。
既に過ぎ去った出来事として認識されているナゴルノ紛争を再度取り上げる理由は、本日1月1日只今を以てナゴルノ共和国は一切の行政機能を停止することになるからです。ナゴルノはこの間国際社会からは承認されておらず、アルメニア🇦🇲本国さえ建前上は承認をしていない。言わば“禁断の花園で咲いてしまった国家に準ずる勢力”。アゼリーによる強制平定を咎める声など立ち所にかき消されてしまうだろう… そうであっても、2度の戦火の末に引き揚げを余儀なくされた20万余の人々(2020年の2度目の紛争後は9万〜10万、強制平定の後は12万〜15万人が引き揚げを余儀なくされたと見られる)にはそれぞれの人生、それぞれに守るべき家族があった筈だ。それをバカなやつだとせせら笑うような考えは私の主義には合わない👊

【座視できない停戦合意破棄-可能性を排除できない本国強襲】

30年余の歴史に幕を閉じることになったナゴルノ共和国。 強制平定を後押しした主因は、1にも2にも国際社会の「無関心」であろう。打ち続く露によるウクライナ侵略戦争、10月7日のイスラーム原理主義組織ハマースによるイスラエル🇮🇱越境攻撃に世界の関心が注がれる中、ナゴルノへの関心は相対的に弱まる。加えて、ナゴルノは国際的にアゼリー領だと認識されていること、そして全域がアゼリーによって平定をされている為、国際社会の大勢は終わった出来事として事態が進んでいる。それを象徴するのが10月15日のアリエフ大統領のステパナケルト訪問劇であろう。御大自らの来訪は現状変更が行われた現実をまざまざと突きつけるものである。
冒頭でも申し上げたが、強制平定後も形式上存在しているナゴルノ共和国は、翌2024年の1月1日を以って一才の行政機能を停止することが既に表明されている為、ナゴルノ側も現実を受け入れている。その為アルメニア本国🇦🇲が再反撃をする可能性は考えられない。そうではなく、私が何故アゼリー側に注視をしているかと言うと、本国への強襲というシナリオがありえない話ではないからである。
ここでいう>「あり得ない話ではない」というのは、10月に入り米国が本土強襲への懸念を明言していることなのである。9月の平定劇を重大に受け止める必要があるのは。これが他国間による停戦合意を破る形で行われていること。これがまず1つ。件の停戦合意には無論、仲介役として城塞会が加わっており、城塞会は停戦合意を背景にラチン回廊に7000人規模の平和維持部隊を派遣していた。城塞会にはしかもCSTO(集団安全保障)の枠組みからアルメニアを防衛する義務が生じるわけだが、この義務をあっさり放棄した。これが2つ目。
AA両国との間にはナゴルノが平定されても火種がまだ残っている。それはアゼリー本国と飛び地のナヒチェヴァンが陸上で切り離されており、アゼリーは長年この間を結ぶ「安全回廊」(ザンゲズール回廊)の構築を渇望していること。既に死文化をしているとはいえ、2020年の停戦合意には件の安全回廊構築にアルメニアが責任を持つ旨の一文がある。アゼリーが先に停戦合意を破った為、遵守の義務があるかは疑問だが、勢いに乗るアゼリーが順守を要求すれば拒否はできまい…。

恐ろしいのは、この安全回廊の要求は全面戦争の前段になりうることなのである。これが安全回廊の構築だけでは飽き足らず本国への侵攻に繋がった例では、立派な前例がある。これについては後述します。アゼリーが渇望する本国と、本国とは切り離されたナビチェヴァンとの接続。その背景として無視できないのはアゼリーを事実上同族支配で固めたアリエフ一族にとってどのような意味を持つかということ。同地はアゼリーのアリエフ大統領の実父で先代大統領・ヘイダル氏の郷里。先代は冷戦構造が下火になった1990年に郷里・ナビチェヴァンの最高会議議長に収まり、それを足がかりに中央政界に打って出た経緯がある。ナビチェヴァンはその意味でアリエフ一族にとって「本貫」とも言うべき特別な地であることなのである。


これに類する例が、やはり20世紀初頭のドイツ🇩🇪であろう
。同国が第一次大戦敗北に伴い、本国と東プロイセン(第二次対戦後は、城塞会のカリーニングラードとポーランドのマズールィ州に分割編入)が切り離されたことが新たな大戦の発火点となったことは今更いうまでもない。第一次大戦の結果、その代償として旧第2帝国は崩壊。多額の賠償金を要求されただけでなく、東方においてはポーランドが独立。これによりドイツ本国と東プロイセンは飛び地として切り離される屈辱に苛まれる。このことに対する独国民の喪失感は計り知れず、この喪失感を吸収する形で声望を集めたのがあのナチスだったことは歴史が証明するところである。
その一例が1930年の総選挙であろう。同年の総選挙でナチ党(国家社会主義ドイツ労働者党)が第2党に躍進するわけだが、その際には全国規模での得票はそれ程ではない。象徴的だったのはその中でも得票数が一位だった地域がただ一つあること、それが東プロイセンである。日本とは異なりドイツが歴史的に統一国家だった時代は短い。その中でも東プロイセンが異彩を放ち、特別な意味を持つのは歴史的な経緯である。古くは旧ドイツ騎士団の根拠地であり、第一次大戦で瓦解した第2帝国に繋がる旧プロイセン王国が勃興した地も、やはり東プロイセンであること。となれば不満を持つ国民が「第3帝国」の勃興を期待する地もやはり…
東プロイセンを巡ってですが、この例えが正確かどうかは分かりませんが、あの明智光秀で言うとドイツ本国が丹波一国だとすれば、東プロイセンは坂本城のようなものである。あの本能寺の挙兵を巡っては、諸説あり未だに決定打とされるものはないが、動機の一つとされるのが主君信長から恒常的に受けていた、
「はぁー、契約取れませんでしたやと説」
ですね。平たく言えば、光秀が仮に山陰攻略に成功しても失敗しても丹波一国と坂本城は🏯召し上げると言うものである。
前年1938年のズデーテン併合、翌39年のメーメル併合に“味をしめた”ナチスが旧ポーランド🇵🇱に対して建前上要求していたのは、一見穏当に見える安全回廊の構築(ポーランド)です。だが、気がつけば全土の併合に及んだことは歴史の教訓の最たるものだ。しかもナチスは全土侵攻1週間前には、「これから強盗に押し入りますよ」旨の密約をソ連邦と交わしているのだ。大事なことですのでもう一度繰り返しますが、ナチスは前年にはズデーテン併合を、そして同年にはメーメル併合に及んでいる。領土的野心と危険性は誰の目にも明らかである。既にこの段階でポーランド🇵🇱本国には匕首が突きつけられた状況である。既に十分に膨れ上がった占領地に加え、それに味を占めた国軍、暴走しないわけはないのですよ😩
しかもポーランド侵攻に関して、責任が大きかったのは英仏だと言わざるを得ない。ポーランド本土侵攻というあってはならない事態に発展するまで、この両国は日和見に徹していた。俗っぽく言えば、これが当時の英仏の本音だったと言えよう。
「メーメルなんかあげたらええやん。まさかポーランド本国まではやらへんやろ?!」
無論それは全くの無根拠の期待に過ぎないのだが、恐ろしいと思うのはナゴルノ平定を成し遂げたアゼリーもこれと全く同じ状況にあると言うこと。2020年の2度目のナゴルノ紛争、そして9月の「1日戦争」に勝利をした背景がある。当然、ナチス同様軍や治安機関が味を占めないわけがない。しかも、ナチスがソ連邦と共同正犯だったことと同様に、アゼリーには盃を交わした“三日月の代紋”🇹🇷が背後に控えているのだ。本土強襲があり得ない話ではないのは、その際には挟撃というシナリオが現実味を帯びる。事実、“三日月の代紋”は2度目のナゴルノ紛争の際、軍事顧問団を派遣している。
軍事顧問団の派遣は援軍の派遣と実質同義語。わかりやすい例を選挙で言えばそうですね、例えば自民党と連立を構成する公明・学会は国政選挙の際、必ず方面長会議を開催するのですが、これと似たようなもの。戦争において一蓮托生となるということ。従って事実上の選対本部の立ち上げを意味する。選挙を学会本体が取り仕切るのだから、学会が公明より上に立つ構図がここにある。前川の逆恨みの際の解散で新聞各紙が解散を確信したのも、方面長会議の開催がその前段となる為。ちなみに、今年の通常国会の会期末に「解散風」が一時吹き荒れたが、これ政治をわかっていない話です。その際には、方面長会議は全く開かれていない。実際、岸田総理というのは歴代の総理大臣の中で最も公明・学会とパイプが弱い。例えば安倍元総理は太田元公明代表と、菅前総理は学会で文字通り選挙を取り仕切る谷川佳樹・筆頭副会長、佐藤浩副会長と、亡くなった小渕元総理は学会の秋谷栄之助元会長をそれぞれカウンター・パートナーとしていたが、岸田総理にはそうしたパイプがない。
話が学会に少し脱線しました。申し訳ない🙏
一方、10月の15日ごろになり、アゼリーの外交当局者は一転して侵攻を打ち消す発言を繰り返している。このタイミングでの軌道修正は米国が本国強襲への可能性を察知した為で、強襲のシナリオをあえて打ち消すことで、事態が米国との対立に直結することをアゼリー側が回避していることがわかる。この点は紛争再燃後のアルメニア側の立ち回りが上手かったことがわかる。というのは、9月に3度目のナゴルノ紛争が再燃した際、アルメニアのパシニャン首相が真っ先に連絡した国はどこかと言うこと?! 当然、「子分を助ける優しい親分など存在しない」のあの国ではなく、それ以前から「接近を隠さない」米国🇺🇸と仏🇫🇷両国の首脳だった。

アルメニアは既に露とは決別、3度目のナゴルノ紛争を前に西側への接近を鮮明にしているが、意外に思われるのは、米国に加えフランス🇫🇷を頼みにする理由である?! まず、仏におけるアルメニア・ロビーの強さである。仏国内には50万〜60万人ものアルメニア系住民を抱え、数の上でも存在を無視できない。アルメニア系仏人ではF1🏁のLegend-アラン・プロスト氏や、サッカーのアラン・ボゴシアン氏などが挙げられる。ボゴシアン氏などは実際にアルメニアとの二重国籍を有する。そうした経緯から、仏は2度目のナゴルノ紛争以前にナゴルノを国家承認する構えを見せており、ウクライナ問題とは対を成すかのようにアルメニアに対する肩入れは際だっている😲
まず、ナゴルノ陥落後10万人を超える引き揚げ者が生まれた際には、700万ユーロの支援金を赤十字を通じ拠出した他、10月にはコロンナ外務大臣自らが防衛装備品の供与で合意している。防衛装備品を露製から仏製に移行することは露からの離反が決定的になることを意味する。
より深化が見られるのか米国との関係で、米国🇺🇸とは9月の初頭にアルメニア国内で合同軍事演習「Eagle Partner」が敢行された他、ナゴルノ陥落後の9月後半には米国の当局者がアルメニア入りをしている。ナゴルノの失陥は無論、パシニャン氏自身も望んだものではないが、失陥は結果として「肉を切らせて骨を断つ」に変化している。ナゴルノは国際的には勿論、アルメニア本国でさえ建前上は承認していない。だが、それが失われた事実は、呪縛として横たわっていた露との関係を断ち、西側への接近を図る上で障害が亡くなったことを意味する。パシニャン氏が結果として2度の敗北を強いられながら、国民の支持が落ちない背景も底流にある西側志向と無縁ではないだろう。何よりアルメニア国民の西側志向は、冷戦構造が下火になった時から、鮮明にあるのですよ。これについてはchapter3で詳しく説明致します。

【アルメニア🇦🇲 古代と現代が交錯する国】

ナゴルノ紛争終結後の課題について触れる前に、アルメニア🇦🇲本国ついて説明をしておきたいと思います。アルメニアはカフカース、アジアとヨーロッパの狭間に位置する完全内陸国であり、文字通りアジアとヨーロッパが交錯する国。同国は長らく旧ソ連邦の構成国であることを強いられていた為、意外に思われるかもしれませんが4世紀初頭にキリスト教を国教とした世界最古のキリスト教国。そうした歴史的な経緯を反映してか、同国が登録されている世界遺産3箇所は何れもアルメニア正教の神殿になります。地政学的に洋の東西を分かつ位置に属することは、言い方を変えれば古代と現代が交錯する国でもあると言うことです。

アルメニアという名称は国際名称であり、正式名称は「ハヤスタン」になる。現地の言葉でハイは自称になる。首都はイェレヴァン、総面積は29800㎢ほど、これは九州よりも小さい規模になります。総人口は280万人ほど。総人口のほぼ全体98%程がアルメニア人、公用語はアルメニア語、アルメニア語は周辺のどの言語にも見られないアルメニア文字が使用されている。アルメニア本国を語る上で切り離せないのは、何より地形です。同国は大変な山岳国であり1000m〜3000級の高地が国土のおよそ8割を占める。首都イェレヴァンは、平均より少し低いものの、標高990程の高地に位置します。同国の最高峰はアラガット山と言う火山になりますが、同山岳の標高は4090m,これは無論富士山よりも標高が高い。冒頭の部分でナゴルノは「山岳の」という意味を持つと申し上げましたが、こうした山岳地帯はアルメニアからナゴルノに横たわるというのが正確です。
ちなみにナゴルノ側の最高峰は、ムラヴ山というカルバジャールに属する巨峰で標高は3724m,富士山🗻より50m程低い。次に標高が高いのがキルス山⛰になります。キルス山は2725m。


話は少し脱線するかもしれませんが、FF3の主人公の故郷はウルという街になりますが、その一帯はパルメニア山脈という山岳地帯に位置します。このパルメニアと言う山岳名はアルメニアから拝借をしたものと思われるのと、同作はヨーロッパの世界観を反映していると言うよりもカフカースから中東にかけての世界観をモチーフにしている。ウルは古代のイラク、パルメニアを超えた先のカナーンという街はやはり古代のイスラエル🇮🇱。序盤にはジンと言う難敵が中ボスとして登場しますが、ジンとはイスラームにおける悪魔の一つ。歴史や地理に対する理解が深まればこうした娯楽作品もより味わい深く見ることができる(^^)

また、アルメニア人の家名としては「〜ヤン」、「〜ニャン」と言った特徴が見られます。例えば現在の首相はニコル・パシニャン氏、2018年まで同国を牛耳っていたのは前大統領のサルキシャン氏。これは「○○さんの子孫」を意味するとのことです。↓〜ニャンってこの人のことじゃないですよ😅

アルメニアを説明するにあたり、動画をご紹介させていただきます。アルメニアにお住まいのヒロキさんと言う方がおられます。アルメニアで事業をされる傍ら、現地の魅力を発信する為、幾つか動画をupされています。アルメニア🇦🇲に馴染みのない方でも入って行きやすいと思います。
【アルメニア🇦🇲の民主主義の下地は、8月クーデターにおける立ち位置にある】
同国を巡る状況はここ30年余りは激動の時代だ。東西冷戦下においてはソ連邦構成12ヵ国の一角だったが、ソ連邦が崩壊過程に入るや、止まっていた時計の針を進めるかのように1991年の9月には独立宣言を敢行。プーチン政権がその政権を認めず、不当な侵略戦争に及んだウクライナの独立宣言が同年8月だったことを考えればアルメニアの独立意識も相当なものだったことが窺える。これも意外に思われるかもしれませんが、アルメニアには民主主義の下地が立派にある。
ここで言う>「民主主義の下地」とは、同年8月の抵抗勢力のクーデター世に言う「8月クーデター」において、どのような立場を取ったか、だ?! アルメニアはナゴルノ紛争(これは後述します)において露を長らく頼みにしていた為、意外に思われるかもしれませんが、抵抗勢力(主導はKGB長官のクリュチコフ。リーダー格であるヤナーエフは多分に神輿である)ではなく幽閉されていたゴルバチョフ側に与した。無論この判断は大正解です。
同年のクーデターを巡ってはソ連邦の上部権力だけではなく、構成12ヵ国も同様に対応を迫られることになった。同クーデターにおいては、同様にゴルバチョフ側に与した国がありますね。それはお察しの通り今なお大義も正義もない侵略戦争の渦中にあるウクライナ🇺🇦になります。事実は興味深く、今にして思えばこの8月クーデターにおける立ち位置こそが、両国が露から決定的に離反する伏線にもなっている😲 反対に、構成国の中で抵抗勢力に与したのがベラルーシ🇧🇾とアゼリー、トルクメン🇹🇲、ウズベク🇺🇿。とりわけトルクメンなどはベルディームハメドフ父子が何事もなく2代世襲を実現させたことからもわかるように、強権志向の勢力ほど抵抗勢力を支持し、方や民主主義の下地がある勢力ほどゴルバチョフ側に与し、西側志向の根強さがこの時の立ち位置を見ればよくわかるのである。
一方、8月クーデターにおいては抵抗勢力にくみしたベラルーシは、クーデター後、開明派であるシュシケヴィッチ氏が主導権を握り西側への接近が鮮明となり、そしてこの年の暮れにはベラルーシとウクライナがソ連邦に引導を渡すことになる。世に言う「」ベロヴェーシ合意である。
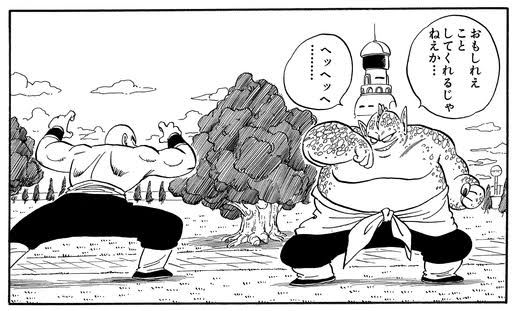
では何故、アルメニアが抵抗勢力に与せず、同時期にウクライナと同じように独自の道を道を歩み出していたかというと、それは1にも2にも開明的なリーダーの存在です。ここでいう開明的指導者とは、90年の旧最高議会選で勝利したレヴォン・テル=ペトロシャンという人物で、同氏は共産党を破る形で政権の座についている。このペトロシャン氏は維新の頃で言う板垣退助のような人物で、ソ連邦解体については確信犯と言って良い。
その一例が、まず前述の8月クーデターに与しなかったこと。それだけではない、件のクーデターには前段があり、それに先立つ91年3月には従来のソ連邦とは異なる各共和国の独立性強化を盛り込んだ「新たな連邦条約」を巡る国民投票にアルメニアが加わっていない事実である。同国民投票には元々旧ソ連構成国ではないバルト3国、グルジア🇬🇪、モルドヴァ🇲🇩は加わっていない一方、留意をすべきなのはウクライナ🇺🇦はこれに参加をしていることなのだ。あの維新の頃でも、2度目の長州征伐が失敗に終わった段階では雄藩は討幕で一致をしていたわけではなく、むしろ「公武合体論」が主流だった。新たな連邦条約はこれに近いと理解を頂ければ良い。そして旧ソ連の抵抗勢力が件の8月クーデターに及んだ動機は、ゴルバチョフ氏の失脚を企図したものというより新たな連邦条約の阻止にある。抵抗勢力が挙に及んだ8月19日というのは、件の新たな連邦条約の調印を控えたその矢先の出来事だった…
件のクーデターはご存知のように抵抗勢力側の前面敗北に終わる。これにより鮮明になったのがクーデター阻止を主導した露のエリツィン氏が求心力を高めたこと、もう一つが「どっちつかず」だったウクライナの国論がソ連邦離脱で固まったことである。件のクーデターでゴルバチョフ側に与した露、宇、カザフ、キルギスは一方で新たな連邦条約には参加をしている。それまではソ連邦離脱で国論が固まっていない。要は態度を決めかねていた中間派に「アイソを尽かされた」、その結果なのですよ😩
そう考えた際、ソ連邦崩壊は抵抗勢力のいわば自爆、自業自得でしかない。そして僅か3日で軟禁が解かれたとはいえ、主導権を発揮できない中急速に求心力を失ったゴルバチョフ氏。同氏の失墜の遠因は、氏は依然共産主義に未練を残しておりこうした考えと決別できなかったことの弱さでもある。
傍目には、坂を転がり落ちるように真っ逆さまに崩壊へと突き進んで言ったかのように見えるソ連邦の終幕…。こうした推移を見るにつけ、この間終始軸がブレなかったのがペトロシャン氏である。無論、アルメニア🇦🇲に根底にある西側志向もこの頃から。政治が継続性を伴うものである以上現首相のパシニャン氏がペトロシャン氏の系譜を受け継いでいることがお分かりいただけると思う。
ペトロシャン氏は91年に「実権大統領制」を導入、自らその地位についた。この間の業績も成る程国父に相応しいもので、1993年の独自追加「ドラム」の導入と95年の自主憲法制定により名実共に独立国に至る。94年に終結した最初のナゴルノ紛争の功績もペトロシャン氏にある。だが、完全独立の過程で断ち切れなかった「呪縛」がある。それは言うまでもなく安全保障上の依存を強いられることになった指定暴力団・城塞会🇷🇺(当時の組長はボリス・エリツィン)との関係である。その過程でアルメニアはCSTO(集団安全保障条約)の構成国となる。

【知らぬ仏より知っとる鬼の方がマシじゃけぇのぉ】
ではソ連邦崩壊前から意外に開明的だったアルメニアが、何故一変して対露依存に傾斜して行ったかと言えば、その理由は一にも二にも、ソ連邦解体に伴う地政学の激変になる。平たく言えばアゼリー🇦🇿の脅威である。
ソ連邦の解体は昨日までの「危険な隣人」を「隣国の脅威」へと変質させる。ここで言うアゼリーとの安全保障上の懸念とは、言うまでもなくナゴルノを巡る争いである。ソ連邦の存在は悪い言い方をすれば「巨悪が矛盾を封じ込める」と言うこと。その“巨悪”の制御が及ばなくなった過程で表面化したのが最初のナゴルノ紛争になる。最初のナゴルノ紛争とは、1988年のスムガイトにおける衝突になる。スムガイトはアゼリーの主要都市の一つだが、当時のアゼリーはアゼリー人とアルメニア人が混在しており、不幸なことに同市においてアゼリー人によるアルメニア人惨殺事件が勃発する。これをアゼリーの警察当局が黙殺したことで対立が激化。住民同士の諍いは治外法権状態にあった旧ナゴルノ・カラバフ自治州に拡大。90年代には両国間が実質的な戦争に突入する。最初のナゴルノ紛争である。
第一次ナゴルノ紛争は94年に終結。同紛争はアルメニア🇦🇲本国・ナゴルノ両勢力が要衝のシュシャ(アルメニア名称はシューシ)を陥落させたことでアルメニアの圧勝に終わる。国土面積がアゼリーの半分以下でしかないアルメニア側が圧勝できた背景は、1にも2にも「城塞会との兄弟盃」である。これは従来西側志向を旨とするペトロシャン氏にとっては意図せざる連携だったが、安全保障上の脅威を前にしては背に腹はかえられず、血の連帯はそれを凌駕する。俗っぽく言えばこういうことです。
「知らぬ仏より、知っとる鬼の方がマシじゃけのぉ」

一方、ソ連邦の崩壊に伴い勢力圏の後退を迫られていた露にとっても、アルメニアへの肩入れは勢力圏の後退を水際で押し留める効果があった。この点は、やはり「禁断の花園で咲いてしまった」沿ドニエストルに肩入れする形でモルドヴァ🇲🇩の西側接近を阻止した構図と全く同じ。自らの勢力圏を手段を選ばす阻止する思考は、西側志向が強かったエリツィン政権と言えども例外ではなかったことがここからもおわかりいただけよう。
何よりナゴルノ紛争を巡り、「知っとる鬼」を頼みにしたことは代償を伴った…。最初のナゴルノ紛争が期待を超える圧勝を伴う側、それに比例するかのように台頭した勢力がある。それはナゴルノ紛争に勝利に導いた軍部や治安機関、ナゴルノ共和国において中枢を担った勢力からなる複合体、いわゆる「ナゴルノ閥」の存在です。この手の勢力は皆露と密接に結びついており、腐敗の温床となる。城塞会もまた、ナゴルノ罰に肩入れする形でペトロシャン氏の影響力排除に勤しんできた。最もソ連邦崩壊過程で改革の旗手的存在だったペトロシャン氏自身、最初のナゴルノ紛争終結後の96年ごろには強権性を強め。同年実施の大統領選においては勝利はしたものの、不正疑惑に晒されることになった。98年には求心力を失い失意のうちに大統領職を退くことになる。

件のナゴルノ閥の代表格が、アルメニア独立の際首相職を務めたマヌキャン氏であろう。同氏の2020年の2度目のナゴルノ紛争で敗北した際の言動は、同勢力のかなりの本音が反映されたもので、同氏はパシニャン氏の敗戦責任を口を究めて批判し、パシニャン政権は、まず露に詫びを入れた上で敗戦責任を取る形で退陣し、退陣後は軍政を敷くべきだと言い放った経緯がある。その軍政が敷かれた際の主犯候補は無論、マヌキャン氏になる。何よりマヌキャン氏が唱えた軍政への移行は、モノホンのクーデター宣言であり全くの言語道断。翌2021年には軍部によるクーデター計画が露見しており、仮にパシニャン氏が一見もっともらしい敗戦責任を受け入れていれば、クーデター計画は実現していた可能性が高い。そうなれば時代は30年逆戻りをしていたことなる😩
最も、軍政を敷き露に詫びを入れたところでナゴルノの強制平定が防げていたかは疑問だ。これは前回のエントリーでも触れたが、対するナゴルノ閥自身、2016年にプーチン自らが提示した「分割解決案」を潰した経緯がある。親分に恥をかかせた子分を助ける優しい親分など存在しない(笑)。
私がこの間一貫してパシニャン氏を評価している大きな理由がここで、氏が「辞めない勇気」を持ってくれたからこそ、ナゴルノ紛争敗北に乗じた民主化の後退を食い止めることができた。ナゴルノの強制平定がもたらす政治的な余波とアルメニア政局については、引き続き次のエントリーでも詳しく記して参ります、宜しくお願いします🙇♀️
わしゃあのぉ、ナゴルノの人たちの引き揚げ見てつくづくそう思ったんじゃ。何かこう、嫌な気持ちになってのぉ、もう殺る殺られんは飽いたわい、そう思わんや