【再燃するガザ紛争と、ハマースは3〜7年の間隔を置けば息を吹き返す】
前回、前々回に引き続き、ハング・パーラメントに陥ったイスラエル総選挙🇮🇱の余波と同国の安全保障政策について記して参ります。今回が4回目のエントリーになります。政局の流れが不透明な中、イスラエルと、パレスチナ自治区🇵🇸ガザを実効支配するイスラーム原理主義組織・ハマースの対立が再燃している。
事の発端は今月10日を境に、件のハマースがガザからロケット弾🚀の一大攻勢をかけたこと。ロケット攻勢は最初の2日間だけで実に1200発、過酷を極めたのが今月12日の攻勢で、この日だけでも850発ものロケット弾がイスラエル本土に向け発射されている。これを受けIDFは即座に反撃、その際の攻撃態勢は戦闘機だけで80機態勢、12日には攻撃を主導するイスラーム原理主義組織ハマース(英称はHamas.1987年創設.イスラーム抵抗運動の略称。構成員は2万人〜3万人)幹部16人を殺害。同日にはガザのハマース事務所を爆破した。屋上に複数のアンテナ📡が備え付けられていることからも、決して市政の住民の居住地でないことがおわかりいただける。
発端から2日経った12日についてはイスラエル側の反撃が目を引きますが、注目すべきはIDFの即応体制、その中でも一般に職を有している予備役軍人(Reserve)の招集と言えます。体制が整う時間的猶予が48時間になる。初期段階で9000人の予備役が緊急招集されていることに加え、これは過去の戦闘状況を一度お調べいただければわかりますが、キーワードはこの48時間になります。IDFの正規兵と言うのは僅か17万人(ちなみに自衛隊の正規兵は25万人です)でしかありませんが、予備役は何と46万人にも上ります。準臨戦体制の同国において国家を支えるのは正規兵だけではない、裏方で支える予備役軍人、彼らを含めたこの即応体制こそ真の強さなのです❗️



個人的に目を引いたのは、16日のIDFの空爆である。この日IDFが標的にしたのは、ヤヒヤ・アル=シンワールと言う最高幹部の邸宅で、このアル=シンワールと言う人物、日本では殆ど知られてはいないがハマースの政治部門(ハマースは軍事部門の統帥権が独立している。その代表格がイザッディーン・カッサム旅団になる)の実質トップ。実質トップと言うのは2017年に政治部門トップのイスマイール・ハニーヤがカタールに🇶🇦亡命している為、今のハマースを牛耳っているのはこの男と考えてくれて良い。何よりイスラエル側にとって、このアル=シンワールと言う男は、
「貴様だけはケジメだっ❗️」
と言うべき曰く付きの人物なのである。どう言うことか?!
ところで、皆さんはこの事件を覚えておられるだろうか?! 2011年に5年越しの解放が実現したギラード・シャリートIDF元曹長の拉致事件についてです。10年ほど前になりますがこの件についての記事を書いたことがあります。(元曹長を拉致したのはハマースではありません)その際に解放に向け間に入ったのがハマースだったが、元曹長解放に伴い突きつけられた条件は過酷でした。その交換条件としてパレスチナ人捕虜のおよそ1000人が釈放。しかも、解放を余儀なくされた大物の中に名を連ねていた人物、その男こそがアル=シンワール、いわば10年来の因縁を抱える仇敵を意味する。
同時に、1000人の猛獣を野に放ったとしても、1人の兵士を決して見捨てることなく救い出す。これがイスラエルと言う国の凄さなのですよ。この理念が顕示されているからこそ、いざ有事になれば一丸となれる。先のエントリーで、かつてのイルグンは維新の頃における「正義党」だと申し上げましたが、その意味でイスラエルと言う国は長州藩。もう1人の俺を見ることで、自国の姿がまた見えて来る。ザーパドを見れば必ずヴォストークが見えて来る👊

件のパレスチナ自治区・ガザ(英称はGaza Strip)は、総面積が365㎢(利尻島と小豆島を合わせた程の大きさ)、総人口は200万人を数える。日本のどの都道府県よりも小さい土地に200万人もの人口が密集しているため、人口密度は恐ろしく高い😲
前述したように、ガザはハマースの拠点。2005年にイスラエル国防軍(以下IDF)が全ての入植地を強制撤去し撤退した後、翌年のパレスチナ評議会選挙でハマースが第一党に躍進、過半数の74議席を獲得するに至るが、ハマースが穏健な勢力でない体質が露わになるのは議会選を経てから。支配体制を文字通り固めるべく2007年にはファタハ(Al-Fatah)と内ゲバを繰り広げ、これに勝利。
この世の中でかくも残酷だと痛感するのは、「お山の大将」とも言うべき勢力の立ち振る舞いで、この手の勢力は「少数派の中の多数派」、「弱者の中の強者」の立ち位置、これが脅かされると直感した時、潜在的に秘めている暴力性が露わになる。
ハマースが支配体制を固めることは闘争の拠点となることと同義語。IDFとハマースの大規模な戦闘はその後も2年から7年の間隔を置いて繰り返されており、代表的な例を挙げれば2008年〜2009年にかけてがまず一つ、次に2012年の「防御の柱作戦」が挙げられるが、これについては忘れられた感が大きいのは結果として1週間で収束している為。と言うのは、これにはエジプトが🇪🇬即座に仲介に乗り出した為で、当時のエジプトはモスレム同胞団政権、ハマースはここから派生した為、彼らはいわば兄弟分。その際には事なきを得るものの、2013年にモルシー政権がクーデターで政権の座を追われるや、ハマースは後ろ盾を失う。その翌年にはイスラエル側の一大攻勢に晒される「境界線防御作戦」。その際のパレスチナ側の死者は2200人を数えた。その後も散発的な戦闘はあったが、ハマース側の打撃は相当なもので大規模な戦闘としては7年ぶりと言うことになる。
ここで言う>「相当な打撃」と言うのは、IDFの攻勢と同時に対外的な要因がもう一つある。それは、ハマースの、暴力団関係で言うところの「ケツ持ち」これがどの国だったのかと言うこと?! それは“広義の意味でのアラブ”と、もう一つがシリアになる。
だが、ハマースのもう一つの雄-ハーレド・メシャルがかつて拠点としていたシリア、そのシリアとは2011年以来疎遠となっている。当のメシャルが、2011年当時、民主化を求めるデモ隊を武力で弾圧したアサード政権を嗜めたことがきっかけだ。この件に関しては無論如何なる理由があろうと弁解の余地はない。メシャルの諫言は全くの正論と言えるが、メシャルが読み違えたのは、アサードはシリアでは少数派のアッラーウィー派に属する為、アサードは早晩失脚すると見ていたこと、アサードと敵対していた反体制派の力量、これを過信していたことが挙げられる。
【では、ハマースの狙いとは何か?!】
それでは、ハマースがこのタイミングで攻撃に踏み切った、その意図ですが、理由は複数考えられます。同組織が攻撃を開始した5月10日は、第一次中東戦争が勃発した5月15日に(アラブ側はナクバと言う。アラブ側はイスラエル独立の翌日に全面戦争を布告、9ヶ国体制、約3倍の兵員を要しながら遅れをとる)差し掛かる時期であり、求心力を高めるには絶好の時期であること。もう一つが、トランプ政権末期に相次いだ湾岸諸国との一連の和解撃「アブラハム合意」を破棄はできないにせよ、衝突を起こすことで楔を打ち込みたい(少なくとも若君の国🇸🇦との正常化は阻止したい)等の理由が考えられます。しかもこれは、“広義の意味でのアラブ”の利害と全く一致する(笑)。一連の衝突を受け、緊急招集されたアラブ・リーグ(Arab league)はイスラエル非難で足並みを揃えてはいる…。
ハマースを巡っては、彼らにとって有利な状況が一つ生まれている。それは先のchapterで触れたアサード政権との関係修復が今年に入って進んでいること。ここで重要な意味を持つのが間に入った勢力が誰なのかと言うことだが、それはイランから🇮🇷支援を受ける立場にあるヒズバッラーです。イスラエルと湾岸諸国の改善が進むと言うことは、それと反比例するように“広義の意味でのアラブ”と「穏健ではないアラブ」が手を結ぶ契機にもなると言うこと。発火の前には必ず伏線が敷かれているもの。その一つがシリアとの関係改善であることを見落としてはなりません。
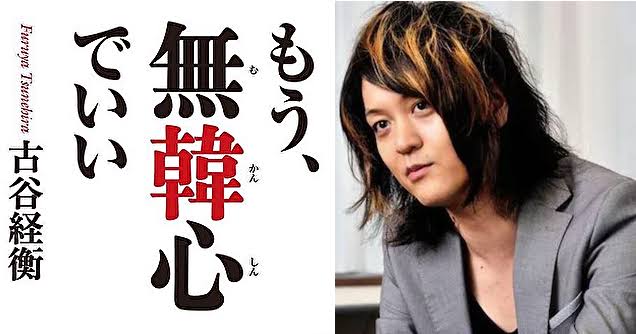
ハマース自身、イスラエルの防空網を単独で打ち破れない以上武力で打ち勝つなど不可能であることは認識している。そうではなく、彼らは犠牲が出ることなど織り込み済みで攻撃に踏み切っている。
何よりこの段階で3000発も発射されたロケット弾🚀は何処から発射されたものでしょう?! ハマースはこれを住宅密集地から発射している。反撃すれば住民を人間の盾として使える上、仮に犠牲者が出たとして、それは尚好都合なのです。この辺りが文明社会の弱さで、非がどちらにあるかを抜きに一度流血の事態になれば、その流された血が人々の目を「曇らせる」のですよ。
【ターバ協定-故・ラビン元首相を殉教者と言う枠から外し見えてくるもの】
先のchapterでは今月に入り再燃したガザ紛争について触れて参りましたが、ここからはイスラエルとPLOが過去に交わした和平合意について話して参りたいと思います。
先のエントリーで、歴史的和平合意と持て囃された1993年のパレスチナ暫定自治合意-世に言う「オスロ合意」は、実際には2国家併存を謳ったものではなく、イスラエル🇮🇱にとって致命傷になり得る部分、例えばユダヤ人国家の終焉を意味するパレスチナ難民の「帰還権」、イェルシャライムの帰属、(93年時点では)13万人に達していたユダヤ人入植者(Settler)の取り扱いは入り口部分で退けられていることを申し上げました。
ではオスロ合意、並びに翌94年にガザ・ジェリコでの先行自治が盛り込まれた「カイロ協定」(ちなみに、鳩山が尖閣の返還義務云々を口にしたのは、カイロ宣言です。当然この発言はデタラメ、そんな条文は全くないです)この2つの合意から確実に言えることは何か?! それはユダヤ人が多数派でない条件の悪い地域の切り離しになります。しかもガザは当時からハマースの拠点、安全保障政策を考える上で状況を左右するのは、ユダヤ人が多数派でない地域に駐留し続けることの利になります。当然、ユダヤ人が多数派でない地域に駐留し続けることは得策ではなく、ここでも「実利を取る力学」が働く、それが95年に締結された「ターバ協定」であり、同協定を巡ってはターバ協定という名称よりも「第2オスロ合意」という表現が広く用いられる。その理由は、IDFがイェフダー・ショムロン(英称はWestbank)のどの地域から具体的に撤退するか、その履行義務が定められているからです。
その意味では、ターバ協定は見出しの部分でイスラエル側の「譲歩」を意味する。国内の右派や宗教勢力は神経を尖らせるAgendaだが、これには2つの意味合いが含まれます。まず一つは、ユダヤ人が多数ではない地域、具体的には議長府のあるラマッラ、ナーブルス、ジェニーン、トゥルカレム、クァルキリア、ベツレヘムの6つの地域からIDFが順次撤退し自治政府に花を持たせる事。つまり「名」を相手に与える事。もう一つが、「実」の部分。つまり、イスラエル側が、安全保障や水資源の確保に重要な地域について決して譲らないことを文章として固定化させた、その契機になる。何故そうかは、下記の画像を見ていただければおわかりいただけます。これをご覧になれば、イェフダー・ショムロンが大きく3つの地区に分離されたことがおわかりいただけると思う。

↑件の画像を見て頂くと、イェフダー・ショムロンが大きく3つの地区に分けられていることがおわかりいただけると思う。まず、青く塗られている部分、自治政府側が治安維持と行政を執り行う「A地区(Area-A,全体の18%)」.次に茶色く塗られている部分が、自治政府側が行政を、イスラエル側が治安維持を担う「B地区(Area-B),全体の22%」,そしてグレーの部分、イスラエル側が治安維持と行政を維持する「C地区(Area-C),全体の60%」にそれぞれ分け、条件が整えばIDFはB地区,C地区からも順次撤退すると言うもの。
両者の紛争を巡り、よく反戦派の人たちが口にする、
「そもそも何でIDFが駐留してるんですかぁー、IDFがぁー」
と言う批判については、そもそも2つのオスロ合意でそうなっているからなんです。どちらに理があると考えるにせよ、10年後、20年後モノを言う継続性を伴う文書にはどう記されているか、これを知らない人があまりにも多い。
もう一つ申し添えておくと、全体の6割を占めるグレーの部分のC地区、ここからの撤退は絶対にありえないと断言して良い。いや、C地区からの撤退を巡っては与野党を問わず異論はない。何故なら、オスロ合意・ターバ協定の骨格が、1960年代、1967年の第3次中東戦争、世に言う「6日間戦争 Six Day War」直後に労働党政権が取りまとめた「アロン計画」に基づくものだからだ。ここで申し上げたアロン計画については、次のchapterで詳しく申し上げて参りますが、アロン計画の画像を見ていただければ、67年の段階で既に全域を手放すと言う選択肢は既にない他、行政というのはどの国も継続性があって成り立つ。その意味ではオスロ合意と言うのはアロン計画の延長線上であると共に、アロン計画における「許容範囲」が示された文書であったとも言えるのです。
ちなみに、宮沢りえさんがかつて出演されていた「ぼくらの七日間戦争」という映画がありましたが、タイトル名は恐らくここから拝借したものと思われます。
【オスロ合意の根幹である【アロン計画】。同計画こそ、今日に至るイスラエルの防衛政策指針である】


・「アロン計画」、これは先に挙げた6日間戦争でイスラエルが手にしたイェフダー・ショムロン、ゴラン高原、ガザに対する支配計画を取りまとめたもので、この計画は単純に領土を拡大させる入植者計画というより、安全保障上妥協できない一線が謳われた防衛政策指針と言うことができる。と言うのは同案が正式に閣議に諮られたのは戦勝から2ヶ月に満たない67年の7月26日。
同案は立案者であるイーガル・アロン元筆頭副首相の名を冠しアロン計画と呼ばれる。そのアロン計画の骨子は次の5点に集約される。
・「イェフダー・ショムロンをユダヤ人地区とパレスチナ人地区にの2つに分離する」
・「その『ユダヤ人地区』は将来において併合も視野とする」
・「上記の補足として『将来における国境線』は死海からヨルダン川。水資源確保の観点としてヨルダン渓谷は全域を保持する」
・「パレスチナ人地区は将来においてヨルダン🇯🇴本国への返還を視野に入れる(本来の当事国は67年までこの地を統治していたヨルダン本国)」
・「イェルシャライムは不可分の首都として統合を進める」
などと言うもので、↑ここで挙げた5つの原則については1つを除き全て2つのオスロ合意でも踏襲されていることがわかるのと、その内の1つである「パレスチナ人地区はヨルダンに返還」の項目は、ヨルダン本国が1987年に施政権を放棄したことでPLOに引き継がれることになる。
何より、オスロ合意をアロン計画がより深化したものと考える時、根底にあるのは6日間戦争以前、世に言う「グリーンライン(Green Line)」に撤退させることは現実的ではない、この認識が当時から外交・防衛当局者を含めた一致した認識だったことが触りだけでも伺えることと、件の6日間戦争はレヴィ・エシュコル首相-アロン筆頭副首相-ラビン参謀総長の3ラインが開戦を主導し戦勝に導いた経緯がある。アロン、ラビン両氏に認識の隔たりなどあるはずがない。
何より目を引くのはアロン、ラビン両氏の議会に身を投じる以前の前歴だ。両名とも1948年の建国以前は、軍隊に準ずる存在としてのハガナーに所属、そのハガナーがIDFに半ば発展する形になると、アロン、ラビン両氏が順を追ってIDFの南部管区の司令官を務めている経緯だ。かつてはエジプト🇪🇬を安全保障上の主敵としていた経緯から、参謀総長は南部管区司令官から輩出されることが多かった。しかも、年齢的にもアロン氏の方がラビン氏より4つ年長になる。
アロン計画を巡り目を引く点はもう一つあります。それは97年の議会採決で2つに分割されたヘブロン合意、そのヘブロン合意のアイデアも💡、アロン計画が出発点なのです。と言うのは、ヘブロンは宗教的背景からイスラエル側が保持し続けることが望ましいが、人口問題等で優位が保てないと判断した時は、事前の策として分割統治を模索すべきと言う考えが既に67年の段階で示されている。同時にこの考えは、翌68年にヘブロンを防護する形で最古参の入植地(Settlement)キリヤット・アルバが設けられたことからも明白、ではネタニヤフ政権が国論を2分する形で断行したヘブロン合意で何が可能になったか!? そのヘブロンのH2とキリヤット・アルバが隣り合わせになったではないですか。


ちなみに、イスラエル🇮🇱の入植地を考える際、国内法の枠内で設けられた合法入植地(Settlement),それに対し、法の枠外で共同体を設ける(Outpost)この2つの違いに留意する必要がある。後者は文字通り、法の枠外に活路を見出すモノホンの過激派。宗教的背景に支えられたユダヤ教の原理主義者、維新の頃における天狗党のような勢力だとご理解頂ければわかりやすい。
それに対し前者の、イスラエルの法の枠内で移住を果たした入植者(Settler)は過激派ではなく、こちらは正確には2つの入植者に分類できます。一つはより良い生活を求めて移り住んだ人たち。例えば、イェフダー・ショムロンには市(City)に扱われる大規模入植地(数万人規模。マアレ・アドゥミームやベイタル・イリットなど)が大きく4つありますが、この辺りの住民の宗教的背景はそれほどではない。
それに対し、人口が1万人以下で1960年代後半から70年代にかけて設けられた中小規模の入植地は、一種の「決死隊」と言えます。無論宗教的使命感に裏打ちされた入植者です。とりわけ前述のキリヤット・アルバなどはパレスチナ人が多数のヘブロンと隣接するわけですので、自分たちが「栄えある尖兵」と言う意識が非常に強く。時の政権や彼らを防護するIDFも彼らを半ば“阿吽の呼吸”と言う形で下支えしている。
彼らを過激派ではなく決死隊と申し上げたのは、(これは決して悪口ではなく)暴力団で言うところのあれです、
「うちの若いもんの中には、何をしでかすかわからんもんがいる。それをわしらが止めとるんですわ❗️」
その役割を暗黙の了解で演じていること。ちなみに正規軍に属さない荒くれ者を取り込むと言う考えは、イスラエル建国前夜からのアロン氏の考えが反映されたもので、先に私は委任統治下のイルグンについて触れたが、同組織を筆頭にハガナーに属さなかった過激派組織は枚挙に暇がない。これらの反体制組織を正規軍に組み入れると言うのが、アロン氏の一貫した考え。野に放つリスクを冒すより囲い込み利害を共有する方がはるかに合理的。何をしでかすかわからん若いもんを囲い込む。同じ考えは、安全保障政策の一環である入植地政策にも受け継がれているのです😲

イスラエルの政局、安全保障政策については次のエントリーでも詳しく説明して参ります。次のエントリーでは、シャス党の党首-アリイェ・デリー氏について説明して参ります。日本では全くその名を知られていない、このデリーと言う人物、この人物こそイスラエル政界における“怪物政治家”なのです。
You just follow me.