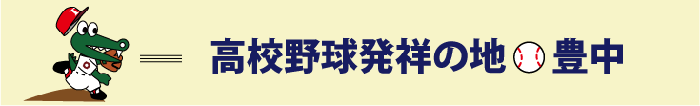
球史ここに始まる
毎年のようにドラマがある全国高等学校野球選手権大会(夏の全国高校野球大会)。高校野球といえば舞台は甲子園。
でも実は、大会の前身である全国中等学校優勝野球大会が初めて開催されたのは、現在の玉井町3丁目にあった豊中グラウンドです。
大正4年(1915年)、第1回大会が豊中で開催
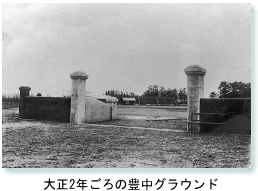
豊中グラウンドは、明治43年(1910年)に開通した箕面有馬電気軌道(現在の阪急電鉄)が、沿線の集客のため大正2年(1913年)5月に建設したものです。
赤レンガの外壁に囲まれたグラウンドは2万平方メートルと広く、当時としては日本一の設備を誇ったそうです。
第1回大会の参加校は10校。5日間の熱戦のすえ、京津地区代表の京都府立第二中学(現・鳥羽高校)が優勝しています。

第1回全国中等学校優勝野球大会
当時大阪では野球が大変な人気で、たくさんの観客が詰めかけました。しかし、観客があまりに多かったため収容しきれず、第3回大会からは、会場は西宮の鳴尾球場に移されることになりました。甲子園で行われるようになったのは、大正13年(1924年)の第10回大会からです。
豊中グラウンドは大正末期に取り壊され、跡地は住宅街に変わりました。今も近くの民家の塀に、豊中グラウンドの外壁の一部といわれる赤レンガが残っています。
「高校野球発祥の地記念公園」としてリニューアル
昭和63年(1988年)に、ちょうどグラウンドの正門の向かい側にあたる一角を高校野球メモリアルパークとして整備しました。これは、第70回大会を記念して豊中市と日本高等学校野球連盟が協力して建設したもので、レンガ塀には第1回大会始球式のレリーフがはめ込まれていました。
この高校野球メモリアルパークは、平成29年(2017年)「高校野球発祥の地記念公園」としてリニューアルオープンしました。
東エリアには、第1回大会からの歴代優勝校・準優勝校の名前が入ったプレートを掲載する壁が設置されています。このプレートは第200回大会まで設置可能です。
西エリアには、豊中グラウンドの門柱を再現したメインエントランスを設けたほか、バットの原料であるアオダモの木の植栽スペースや豊中グラウンドの解説板・平面図を設置しています。

西エリア(メインエントランス)

西エリア(レンガウォール)

東エリア(歴代優勝・準優勝校ウォール)

東エリア(歴代優勝・準優勝校ウォール)