今日は夕方まで、眠っていて、だいぶん疲れも取れた。
落ち込みも減ってきたように感じる。
食欲は相変わらず,ないが、少し食べておいた。
これ以上食べないとさすがにまずい。
-----
明日は朝早いのぞみで移動する。
10月もあと2週間で終了するが、確実にやるべきことを
こなして成果を残したいと思っている。
一番の悩みは、やはり体調が安定しないこと。
薬で無理やりコントロールしようとしても、限界がある。
薬源病を起こす可能性もある。
そして、これらは、治療を難しくしてしまう。
仕事の悩みは、やるべきことがすべて明確になっていないこと。
・タスクを明確化すること。
・ベースラインとの解離に意識的であること。
・リスク管理の視点を常にさしはさむこと。
これらをきっちりやっていこうと思う。
当たり前のことなのだが、最初からすべてが明確なプロジェクト
はない。
大切なのは成功のイメージを持てるかということ。そしてその
イメージと現実のギャップをできるだけ精緻に埋めていくということ。
これまでやってきたプロジェクトでも、そうやってきたのだから、
必要以上に心配することはない。
-----
プロ野球セ・リーグのクライマックスシリーズは、
第一ラウンドが昨日から始まった。
3位ヤクルトと2位中日の戦いは、
昨日はヤクルトが、今日は中日が勝って、タイブレーク
に持ち込んだ。
明日の試合結果によって、決勝への進出が決まる。
今年のヤクルトは相変わらず戦力不足が顕著だが、
若手の成長も著しく、なんとか3位に滑り込んだ。
短期決戦で、なんとしても勝ち抜いて日本シリーズ
へ進出して欲しい。
巨人対日本ハムみたいな日本シリーズだと、
なんか、つまんない。
それより断然、
ヤクルト対楽天のほうが盛り上がるような気がする。
-----
今日のNHKスペシャルでは、「自動車革命」と称したシリーズ
の1回目が放送された。
これまで、自動車は、ガソリンを中心とする化石燃料を動力源
としたエンジンを搭載してきた。
日米の自動車メーカーはそうした自動車を大量に設計・開発・
製造・販売に一貫して関わり、世界中で販売することで発展
してきた。
しかし、ここにきて、歴史的な転換点を迎えている。
ガソリンエンジンに変わり、電気自動車への移行に向け、
部品メーカーはこれまでとはまったく異なる製品を供給
する必要に迫られ、グローバル化と低コスト化が進むなか、
その設計・開発と実用化への取り組みは時間との戦いを
迫られている。
番組内では、モーターの開発に必要な「錆びない磁石」を新た
に部品として必要とする場面が描かれていた。
「まったく異なる部品の開発に取り組まなければ、生き残れないのだ。」
これからの自動車産業は、「核となる技術を自製化し、その
技術力を持って、設計・開発・製造・販売に一貫して関わり、
製品戦略の主導に立てなければ、ただのアセンブラー
(組み立て業者)になり下がってしまう。」
今の技術開発競争はまさにそういう競争のまっ最中にあるの
だということだ。
そして、そこで起こるのは、産業構造の組み換えだ。
例えば、電気自動車の技術の中核となるのは、いうまでも
なく、「バッテリー」であるが、これらは、今まで電機業界
が開発の主導を握ってきた分野だ。
番組では触れられていなかったが、
電池事業に強みを持つ三洋電機をパナソニックが買収し、
これから、自動車メーカー向けに電池を供給することだって
あるだろう。逆に自動車メーカーが電機業界再編を促す
ことになるかもしれない。
番組内で触れられていたシーンで衝撃的だったのは、
電気自動車のベンチャー企業にGoogleが出資していると
いうこと。しかもすでに試作車のテスト走行まで行っている。
モーターとバッテリーの技術そのものは比較的古くからある
もので、中国の内陸部などからもベンチャーが参画し始めて
いる。
自動車産業がその動力源をガソリンから電気に変えたと
しても、「移動手段」という目的は変わらない。
技術革新が起こるまさに今のタイミングで、Googleは何らか
の形で主導権を握ろうという戦略なのだろう。
今、自動車を開発するにあたって、必要とされるソフトウェアの
ボリュームはどんどん肥大化していて、単なる部品メーカー
だけでなく、ソフトウェアベンダーが関係性を持ち始めること
自体は、不思議ではない。
2050年ごろまでには、自動車・電機・ITの業界構造が完全に
変化を遂げ、Googleが、自動車を販売していたりするのかもしれない。。。
今日読んだ本。
- Amazon EC2/S3/EBS クラウドコンピューティングによる仮想サーバ構築/清水 正人
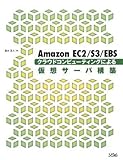
- Amazon.co.jp
- ここのところ、クラウドコンピューティングに関する
- Topicsが豊富に登場しているが、具体的に
- どのようなサービスをどのようにして使用すること
- ができるか、Amazonの提供しているEC2/S3/EBS
- それぞれに関して解説している。
- 詳しく読んでないし、実際に試してもいないが、表面的
- にはサーバーのホスティングとなんら変わらない。
しかし、クラウドコンピューティングが提供するサービス
は様々な仕様による制約と引き換えに、これからの
ビジネスインフラに求められる様々な要件を満たすこと
ができるようになっている。
例えば、負荷増大時にのみ、サーバーを増強したり
するなど、サーバーを借りるのではなく、サービスを提供
してもらう姿へと、少しずつ進化してきている。
まだ、H/W, S/W依存の部分も大きく、導入・運用の困難
さなどの課題は大きいだろう。
そして、導入のメリットは最も大きく検討されねばならない所。
なぜ、クラウドでなければならないのか、そこに
全社的な情報システム戦略の視点を欠いては、
「新し物好きの自己満足」の道具となってしまうだろう。
クラウドに関しては、まだ知識が全然ないので、
積極的に知識を蓄えたいが、優先度は低め。
今後しばらくは、
プロジェクト成功のために、
様々な本から学んだプロジェクト管理手法を十分に実効性
あるものとするための営みが優先度としては高くなる。
まあ、理想をすべて実現というのは難しいので、妥当な路線
で線引きして、そのレベルまでのことをきっちりとこなすことを
目指そうと思う。