「公共財」という日本の社会福祉や民主主義のあり方に対する指針にある程度の考察
を交えての「公正・公平」な立場で物申す姿勢に対して民衆が賛同して「商業として成
立」するものという「公共」のためになるはずのメディアだからこそ「公共の財産」と見て
のものだが、これが如何せん「言ってることと、やってること」の落差が、国民の目には
批判・非難の対象となってきているのだから、さてさてこんなものが「公共財」と名乗れ
るのか・・・。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
高校の日本史を必修にする検討を文科省がするという。そう聞いて14年前の1月を
思い出した。
時の小渕首相に「21世紀日本の構想」についての提言が出された。
英語を第2公用語にすると打ち出して話題になったから、ご記憶の方もいるだろう
▼義務教育を週3日に圧縮するという提案もあった。いわゆる読み書きそろばんは
徹底的にたたき込む。
その習得は国民の義務である。
それ以外は各自の自由な選択に任せる、という内容だ
▼実現性はともかく、教育のあり方を根源から考え直す姿勢が刺激的だった。
国民を守るためにも国家が強(し)いなければならない教育と、あくまでサービスとし
て個人を支援する教育。この二つを明確に分けよ。
週3日論の背後にある考え方である
▼提言の教育分野の座長は劇作家で文明批評家の山崎正和さんだ。
直前に発表した文章では、より踏み込んだ主張を述べている。
いわく〈国家は初中等学校における歴史教育を廃止すべきだ〉
▼史実の評価や歴史認識は、国家間だけでなく専門家の間にも対立がある。
そして、そうした異なる見解の数々は国民の間を自由に流通している。
その一つを国家が選んで学校で教えることは、学問的には不誠実だし財政的には
無駄だ、と。
異論もあるだろうが、一つの線引きの仕方ではある
▼日本史の必修化は「日本人としてのアイデンティティーを育てるため」と大臣はいう。
日本人は一色(ひといろ)でないし、日本史の理解も一様でないことを、くれぐれもお忘
れなきよ‥
http://www.asahi.com/paper/column.html?iref=com_top_tenjin
超党派の国会議員でつくる活字文化議員連盟(会長・山岡賢次前国家公安委員長)は
20日付で、消費税が引き上げられる場合、新聞・書籍には軽減税率を適用し、現行税
率を維持するよう求める声明を発表した。
国会で消費増税を含む社会保障と税の一体改革関連法案が議論されていることを踏
まえたものだ。
声明は「新聞・書籍の公共性は極めて高い。新聞・書籍に対する消費税率引き上げは、
国民の活字離れを加速させる」
危機感を示した上で、「日本の文化と民主主義の基盤を守るため、新聞および出版物
の消費税率引き上げには断固として反対し、現行税率の維持を求める」とした。
フランスなど欧州で新聞・書籍は食料品と同様、ゼロ税率としたり、低い税率を適用した
りしている例を挙げ、「新聞や出版物は民主主義のインフラとみなし、『知識課税は避け
る』との理念と伝統を大いに参考にするべきだ」とも主張している。
20日の議連総会には秋山耿太郎日本新聞協会長(朝日新聞社長)も出席し、
「新聞購読料に対する消費税率をこれ以上引き上げるのは、民主社会の健全な発展を
損なう懸念がある」との意見を発表した。
http://www.jiji.com/jc/c?g=pol_30&k=2012062100683
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
軽減税率は当然「公共財」には適用されるとかを申し出て、国民から顰蹙を買う「恥知ら
ず」ぶりは、国民から見れば「自分の思考のごり押し」だし、日本に反省を強いるが、自分
たちの「錯誤」に対しては、金輪際反省はないの傲慢な姿勢。
その中でもピカイチの民間会社は、素晴らしい公告宣伝費で成り立っているようである。
広告主にすれば「広告経費の費用対効果」に期待しているのだろうが、国民から辛辣な
批判を浴びる「報道機関」になにを期待しているのだろう。
その搾取される「広告費」が以下のような「記者天国」として浪費されると見ると・・・。
「騙されていますよ、お怒り下さい」とマスコミの「得意の告口」をしたくなるってものである。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
新聞記者 ハイヤーで合コンの女の子送って帰るのは当たり前
新聞記者の仕事は“激務”というイメージがあるが、最近はそうでもないらしい。彼らの
待遇は読者とはかけ離れている。
「給料は朝日と読売、日経がほぼ同水準で、毎日と産経がその半分。共同は8~9割
と言われています」(産経の若手記者)
世代にもよるが、”高収入組”の朝日などでは20代後半で年収1000万円の大台を超え、
30代半ばで1200万円、40代前半で1300万~1400万円もザラだ。
最近では若手の給料は減り、30代前半になって1000万円を超えるケースが多いようだが、
それでも同世代の平均年収の倍以上である。
縮小傾向だが、さらに社宅や家賃補助があるケースも。そんな中、最高の特権と言えば、
「ハイヤーでの送り迎え」だ。
「合コンで飲んでいる間、何時間も近くで待たせておいて、女の子を送って帰るのは当た
り前。運転手は原則的に守秘義務があるから、遊びで使ってもよほどのことがなければ
会社にチクられない」(全国紙政治部記者)
そのためか、完全な公私混同の事例も。
「ある記者は、ほぼ毎日ハイヤーで子供を保育園に送ってから職場に来ていた。自分の
結婚式で花嫁と移動するために社のハイヤーを使った強者もいます。
呼ばれたらすぐに駆け付けるためという建前ですが、その記者は普段から”呼んでもなか
なか来ない奴”として有名です(苦笑)」(同前)
黒塗りがあるのは”高収入組”の社の政治部、社会部が中心。産経や毎日は自家用車で
現場に駆けつけるなど、格差も大きくなっている。
http://www.news-postseven.com/archives/20140109_231466.html
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
「人の不幸を喰うマスコミ」という揶揄もある商業主義の「公共財」の使命は、さて「自分達
の幸福な生活か、公正・公平な情報の発信元か」となれば、表立っては後者で、裏の口
では前者に決まっているとなって来る・・・。
で、こういったマスコミを例えれば、映画の中にとんと「笑いだけは一丁前で、出来そのもの
は最低」というものに入ってくるのだから、「せせら笑いのジャーナリズム」となりそう。
そのせせら笑いの映画に「人喰いエイリアン」というトンデモ映画がある。
それも題名が同じでってものが二つある。
http://www.youtube.com/watch?v=yC4krbSmAkg
「人喰いエイリアン」 八十四年未公開作
低予算で「空想科学的宇宙人ものを撮りたい」意識は、大層ご立派だが何しろ予算も
また脚本も「なんちゃってエイリアン」だから、そこには危機感も皆無なトライアングル
の出演者のみで出来上がる。
何より「地球人に成りすました」エイリアンというものが、水にはとんと弱く膝下の水位
でも溺れてしまうだらしなさで、レズな二人だからそれなりのエロは任せて、展開が
広がって行くかと思えば、そんなことはなく変な三人組のホーム・ドラマと相成って
そろそろ「大変身」とばかりに本来の姿に戻って、ホラーらしい仕舞い方をするのか
思えば、これがブタ鼻の「忘年会変装セット」を取り付けてって、エイリアンの造形の
しょぼさは、犠牲になる女の血しぶきがなければ、石を投げられるレベル・・・。
と、エイリアン云々の外来の危機を安直に作れば、「こんなん、出来ました」という
笑うにも疲れきるという出来の凄まじさ・・・。
http://www.youtube.com/watch?v=bBbDPIHVos4
「人喰いエイリアン」 八十六年未公開作
同じ題名でもこちらは怖いと笑いが混ざり合うホラー・コメディーもの。
で、こちらの方が映画としては、しっかりしていてブラック・ジョークも程ほどに
ちりばめて、笑いを取りに来る姿勢は、主演のデブの容姿と相まって見ていられる。
最初の犠牲者はヒッチハイクのデブを乗せてやる田舎の人のいい爺さん。
それがイタリア人であったのが不幸で、トラック内でグチャグチャと喰われてしまう。
勿論コメディーであるから、そんな描写を取り入れるはずもなく音だけで、観客に
アピールする手法は終始一貫していて、次々イタリア人だけが犠牲になっていく。
捜査をする刑事や判事も登場するのだが、これらがすべてにおいて「一本神経が
抜けている人々」だから、デブエイリアンは犯罪で囚われても、無罪放免されて
「喰べることに勤しむ」が、最後はあっけなく宇宙にかえるでなく、傾注しすぎた
イタリア産によって、自らの命は不幸にも絶たれてしまう・・・。
とねコメディーとホラー、そこに空想科学のエイリアンとかをごった煮すれば、こんな
ものにもなるという一品だが、ここは主人公のエイリアンのキャラクターの特異さが
何より印象を強くする。
見るからに「食欲旺盛のデブ」それもつるっぱげとくれば、ジョーズの歯並びも笑えて
裏に隠されている制作側の「ちくりと刺す嫌味」にも及べば、どこかに差別したい人
のジレンマを笑い変えたと思える。
この下の作品は脚本も練られて映画としては、それなりの完成度わ見せているが、
上の作品は、日本のマスコミの程度と同じの最低なものと、同じ題名でもなんとも・・・。
- ぼくらの祖国/青山 繁晴
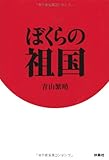
- ¥1,680
- Amazon.co.jp
といったところで、またのお越しを・・・。



